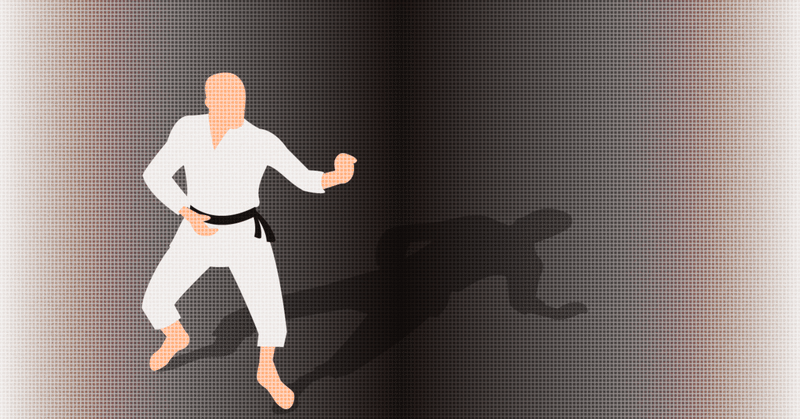
#104 医師が覗き見る「日本社会のイマ」
経済は調整局面。世界中で金融商品の価格が急落している模様。これで資産が目減りする人は多いはず。借金で投資をする所謂、先物を行っている方には更なる不安が渦巻いているはず。
金融バブルが崩壊したという人もいるのだが、それは老耄の囁きではないのかもしれない。
ここで思い出されるのが日本のバブル崩壊である。そんな昔を覗いてみる。
バブルの崩壊は1991年(平成3年)3月から1993年(平成5年)10月までの景気後退期を指す。
1986年から続いたバブル景気により、地価や株価は高騰し続けた。野口悠紀雄・一橋大学教授が、「バブルで膨らんだ地価」で「バブル」と表現してか「バブルとその崩壊」は日本人の口にのぼり始める。
地価や株価の異常な高騰を抑えるため、政府や日本銀行は1990年に本格的にバブル対策に踏み切った。
1990年3月に大蔵省銀行局「土地関連融資の抑制について」(総量規制)に加えて、日本銀行総裁三重野康による金融引き締めは急激なものとなり、信用収縮が一気に進んだ。信用崩壊のさなかにおいても金融引き締めは続けられ、日本の経済は悪化へのシナリヲを辿る。
1989年5月から1年3か月の間に5回の利上げが実施され、2.5%だった公定歩合は6%台まで引き上げられた。それでもマネーサプライがマイナスになる程の効果は見られなかったのである。
これと総量規制の効果に満足できなかったのか、1991年には、所有している土地に応じて課税される「地価税法」も施行され、土地神話は一気に崩壊した。
政府は、更に、固定資産税の課税強化、土地取引きの届け出制、特別土地保有税の見直し、譲渡所得の課税強化、土地取得金利分の損益通算繰り入れを認めないなどの対策を打ち出していった。
1989年に導入された消費税も加わり、大規模な金融引き締め策のオンパレードとなった。
土地や株は一気に売却され、地価や株価は大暴落。買い手が付かなくなったことで、資金を借りていた企業の多くが倒産した。それで返済が滞り、護送船団と言われた融資先の企業が経営悪化や倒産に陥ったために、回収困難になった所謂、不良債権により銀行の経営も悪化していった。社会が負のスパイラルに陥る。
日経平均株価はバブルの頂点、1989年12月末に3万8915円に達していたが、それは本来の価値に、まったく見合わない価格であるとしたのが、当時の政権と三重野日銀総裁であった。
彼らの取った政策は、過熱した資産価格の高騰を抑えるために行ったものであったのだが、予想をはるかに超えた急激な景気後退、バブル崩壊を招き、失われた20年へと突入したわけだ。当時を思い起こすと、痛手を被った銀行員の手が震え、証券会社の社員の悲鳴と、倒産した不動産業者のうめき声が聞こえてくる。
さて今回を金融バブルの崩壊と仮に定義すると、コロナ禍で市場に溢れたお札の為にインフレ加速、その加熱を嫌気して、量的緩和の縮小、政策金利の切り上げ、バランスシートの正常化というシナリオが報道されている。
ここは、日本のたどったバブルの崩壊から失われた20年、デフレスパイラルという所謂、日本化を背面教師とすべき局面ではないだろうか?
これを概念面で考えると、西村吉正の言う「資産価格の高騰で国民の間に格差ができた。だからバブル潰し・正常化が最大の課題だというのが当時の多くの人たちの認識だった」という見解は的を得ている。当時を思い起こすとバブルの崩壊に導いたのは政府や日銀の責任ではあるのだが、Mediaもこぞって財テクで労せずして儲けた人々を槍玉にあげていたし、金融正常化とバブル悪魂論を展開し、それを煽り続けた。体育会系で質素を美徳とする、偉丈夫な三重野総裁の心を世論が鼓舞したのだろう。
経済は九十九折を転げ落ちて奈落へ沈んでいったのだ。
世界中、FRBが急激な金融政策を取らない様に願っている。タカ派の意見にはその危険がいっぱいである。パウエル議長もハトからタカへ転換したと言われているのだが、日本化しないように、軟着陸する様に世界の経済を操縦してもらえると、安心感につながる。日本は当時の成金に対する嫌悪感、国民、政府、日銀の次から次へのバブル潰しは巨細にわたり日本経済に急ブレーキをかけ続けた。そんな徹底した金融引き締め策は想定しないのだが、格差社会の拡大など当時の日本と似た要素が世界に広がっている。格差弊害の責任をオブラートに包むかの如く、政権の責任逃れの為に、国際緊張を助長、戦争の危機が演出されるかもしれない。
現在はコロナ禍からの脱出が見える踊り場である。温故知新を尊び、その操縦を間違える事なく、デフレスパイラルの千尋を回避すべきである。
大切な時期に差し掛かっている。
コロナに密着して行きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
