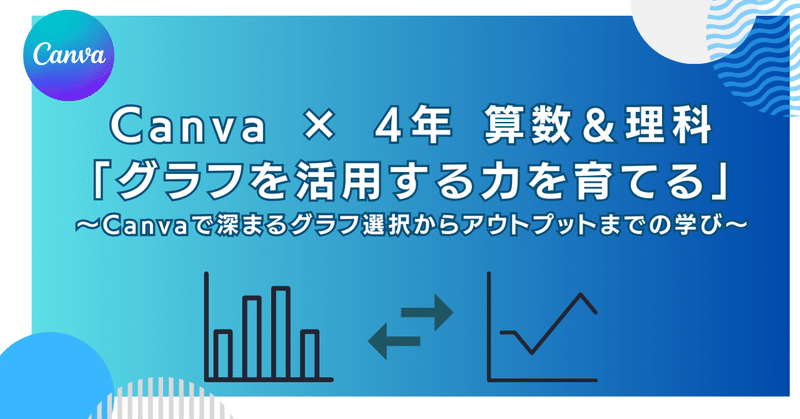
Canva × 4年 算数&理科 「グラフを活用する力を育てる」〜Canvaで深まるグラフ選択からアウトプットまでの学び〜
記事の概要 & はじめに
算数の統計領域で育てたいグラフを活用する力の一つとして、グラフを選択する力があると考えています。様々なグラフを学習するたびに、そのようなグラフ選択の場を繰り返し仕組んでいく必要があると考えています。
今年度、自分は教務主任となり3・4年の理科を担当しています。(・・・残念ながら今年は算数の授業をもてなくなりました。)算数で育てたいと取り組んできていたことをもとに、理科の中で関連して実践したことをまとめてみました。
「グラフを選択する力を育てる」「ICTとアナログを目的に応じて使い分ける」ということに関して考えながら実践した内容になります。なお、実際の子どもが作成したものを載せることはできないので、数値等や画像は架空のものを使用している部分もあることをご了承ください。
1. 4年 算数&理科「折れ線グラフ」についての学習
4年生では、算数と理科で折れ線グラフを扱う学習があります。
算数では、折れ線グラフの特徴や読み取り方・かき方、折れ線グラフからわかることを考察する等の学習をします。
理科では、実際に測定した気温を折れ線グラフに表して、晴れの日と曇りの日の気温の変化の特徴について考える学習をします。
2.活動のメインは「グラフをかく」こと?「グラフから考える」こと?
子どもたちがICTを活用してグラフをかくことはありでしょうか?なしでしょうか?
学習内容や授業のねらいに応じて、ここを明確にしておくのが大事です。それに応じて、子どもたちの活動が変わるからです。
ここでは、子どもたちの活動として、グラフを手がきでかくのか、ICTを活用してかくのかの判断の仕方についての考えを述べます。
まず、知識・技能として折れ線グラフを最初に学ぶ算数の学習の中では、グラフは手がきでかくことも大切です。最初からICTを活用してグラフが自動で出来上がってしまっては、子どもがグラフの仕組みをとらえきれないこともあります。インプットの場面では、手がきが有効であるともいわれます。グラフに習熟させたいときにも、手がきの方がよいと考えます。ただし、かくことに困難を抱えている子に関しては、最初の学習や習熟の際のICT活用もありだと思います。
次に、算数での思考・判断・表現について扱う授業や、理科で折れ線グラフを活用する授業では、ICTを活用してグラフをかくのもありだと考えています。限られた時間の中なので、グラフに表された結果をもとに考えることに重点を置きたいからです。手がきでグラフをかくことに時間をとられ、考察をしたり、結果の解釈について議論したりする時間がなく、結論を教師が出してしまうようでは授業のねらいは達成されません。かくことに困難をかかえている子がいる場合にはなおさらです。
また、ICTを活用することを積み重ねていった高学年であれば、「ここはICTの力を借りてグラフをさっと作り、考察をじっくり行うのがよい」と、子どもたち自身が判断できる力を身につけさせたいと考えています。
3.「絵をかく」のか「写真を撮る」のか
少し本題からそれますが、ICTの力を借りるのかどうかという点がグラフと共通する内容に、理科の観察で「絵をかく」のか「写真を撮る」のかといったことがあります。これについても、判断基準はグラフと同様だと考えています。
また、理科のヘチマの観察のような継続的に記録していく必要がある内容では、写真での記録も大いに活用すべきだと考えています。現在、定期的に写真などのICTを活用した記録を残し、要所でノートにも絵をかきながらじっくり観察する時間を設けるといった形で学習を進めています。
4.理科「ヘチマの観察」でのグラフとICT活用
理科のヘチマの観察では、ノートへの観察記録とは別に、毎週の記録を残すため、次のようなCanvaで作成した観察記録シートを使いました。

この観察シートは、グループで1つのものを共同編集しながら記録していくようにしました。フレーム部分には撮影した写真を入れ、その他の項目を入力して記録していく形です。
本校の環境では「①グループごとのCanvaのデータを作成 ②Google Classroomでリンクを共有 ③自分のグループのリンクを開く」という方法で共有しました。
入力後の完成イメージは次の通りです。

記録にあたっては、次のように役割分担をして入力をしました。

ここで、子どもたちはグラフ作成機能を初めて体験しました。一番左の表に数値を入力すると、右端に自動的にグラフが表示されます。最初にこの機能を使った子どもたちからは、歓声が上がりました。そこで、「便利だからただ使おうとするのではなく、しっかりグラフの仕組みを知った上で、グラフをもとに考えていきたいときにはこのような機能を活用していくとよい」ことを伝えました。
別の視点での話題になりますが、本校の今年度の校内研では、インクルーシブな視点を取り入れた「かかわり」のある授業づくりに取り組んでいこうとしています。それに関連して、このように分担して共同編集で作業ができることには、次のようなよさがあると考えています。
支援が必要な子は、作業が絞られることで参加がしやすくなる。(実態によっては毎回その役割専属としてあげるとよい)
毎回役割を変えることで、全担当の子が操作を教える場をつくることができ、かかわり合う場をつくることができる。
グラフ作成や写真の挿入が一つのアプリ内で完結し、それをクラウドベースの共同編集で行えるのはCanvaの強みであると感じます。
5.理科「天気と気温」で ICTを活用したグラフの選択を仕組む
統計領域では、目的に応じてグラフを活用できる力を育てたいと考えています。その力の一つがグラフを適切に選択できる力です。データの種類や考察したい内容に応じて、適切なグラフを選べるようになることが大切です。
この記事で取り上げている4年生の現段階では、子どもたちの選択の対象になるグラフは「棒グラフ」と「折れ線グラフ」です。この2つのグラフに関しては「どちらで表しても、伝わらないことはない」と子どもが考えがちな内容も多いです。だからこそ、変化に着目しやすいという折れ線グラフの特徴を、繰り返し考える機会をつくっていきたいと考えています。その積み重ねが、さらに多くの種類のグラフを学んだときにも、グラフを有効活用できる力につながると思います。
そこで、「天気と気温」に関して晴れの日と曇り・雨の日の比較をする学習では、次のような記録シートをCanvaで作成して活用しました。

ヘチマの観察と同様に、グループごとに1つのデータを共有し、共同編集、役割分担しながら記録を入力していきました。
ここで、もとのデータを共有する際に、自動的に作成されるグラフの設定をあえて「棒グラフ」のままにしておくことを仕掛けました。そのまま数値を入力すると、次のようなグラフが表示されます。(※これも数値は架空のものです。)

ここで、棒グラフで表された気温について疑問をもった子どもの声が上がりました。その声を全体に共有し、なぜ疑問に思うのかを問いました。そこで、既習の算数での学習を想起しながら、折れ線グラフで表すとよいことの理由を確認していきました。
理由が確認できたら、次のようにグラフを折れ線グラフに修正できることを伝えました。

ここで、子どもたちは初めてグラフを選択する機能があることを知ることになりました。入力するもとデータは同じものであっても、次のように様々なグラフを選択できることを伝え、実際の操作の仕方を伝えました。

ここでも、子どもたちからは歓声が上がりました。そこで、「それぞれのグラフの特徴を知った上で、考えたいことが考えやすいグラフを選んでいくとよい」ことを確認しました。
このような形でグラフ選択の学習ができるのは、ICTの強みです。
これは手がきではできません。従来の手がきだけの方法では、まずグラフをかく前にどのグラフにするかを決めて、その後にグラフをかくのがオーソドックスな方法だったかもしれません。しかし、その順序でグラフを決められるのは、グラフの形をイメージできて、ある程度の見通しをもてることが前提となります。
そのようなイメージが苦手な子にとっては、実際のグラフを見て、種類を変更しながらどのグラフにするかを決められることは大きな思考の助けになります。また、すべての子にとって、このような試行錯誤を可能とする場をつくることには大きな意味があると考えます。
このようなグラフ選択の場は、算数の統計領域の学習として、どの学年でも積極的に取り入れていくべきだと考えています。今回のように、理科等でもこうして関連した学習をどんどん設定していくことが大切です。
また、これらのグラフの選択を扱うことができ、他の素材等といっしょに一つのアプリ内で編集できるのは、Canvaの強みであると感じます。
6.単元のまとめは学びをアウトプットする活動で
晴れの日と曇り・雨の日の気温の変化を比較して、特徴を考察した後は、ノートにまとめました。そして、学習したことを表現する簡単な動画づくりを設定しました。作成した動画のイメージは次のものです。

動画は、上記イメージのようにグラフを背景として、その前に、子どもたちが登場して解説するものです。
次のような方法で作成しました。
背景とするグラフを共有
子どもたちは友達と撮影し合い、動画をCanva上にアップロード
Canvaの「動画の背景除去」の機能を使って背景を削除し、ちょうどよい位置に配置」
かくことが困難であっても、話すことなら得意な子がいます。その子は、ノートの記述やペーパーテストだけでは、評価ができなかったり評価が低くなってしまったりしかねません。しかし、このような多様なアウトプットの機会があることで、学んだことを表現することができ、教師もそれを見取って評価することができます。
折れ線グラフにした理由もふり返ってもらいたいので、気温の「変化」について考えたことを明確に入れるように指示しました。
なお、この解説動画をつくるというアウトプット方法のアイディアは、生井光治先生が5年理科の台風の学習でFlipを活用した実践で紹介していたものを参考にさせていただき考えたものです。本校ではFlipが使えないため、Canvaの中で作成しました。
5年理科の盛り上がらない単元『台風と防災』
— 生井光治(ナ・マイケル先生) (@backnamchildren) July 7, 2023
①天気予報士になって台風について解説
②ニュースキャスターになって台風の防災について紹介
を子供に選択させ
Flipを使って30秒から1分でoutputするというゴールを示す
前のめりに調べまくる子供たち
主体的に学ぶ仕掛け完了
あとは自走#全ギガ
7.おわりに〜Canvaの機能が大活躍〜
学校教育におけるCanva活用のメリットは、豊富な素材で見栄えがよいものが簡単にできることだけではないと考えています。
最大のメリットは、教科等の学習の本質的なところにおいて、オールインワンといわれるくらいの多機能さが有効に機能することだと改めて感じます。以前の算数の統計領域に関する記事に書いた内容も同様です。
自由自在につくれるグラフや豊富な素材の組み合わせ
画像や動画を撮影して編集
プレゼンテーションや動画などの多様なアウトプット
これらの機能を有効活用することで、子どもたちの学びを深めることにつながります。
Canvaは、豊富な素材を活用して掲示物などを作る簡単な活用から、教科の本質に迫る授業での活用まで、幅広く学校教育に貢献できる機能をもちあわせています。これからもしっかりとしたねらいをもって活用していきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
