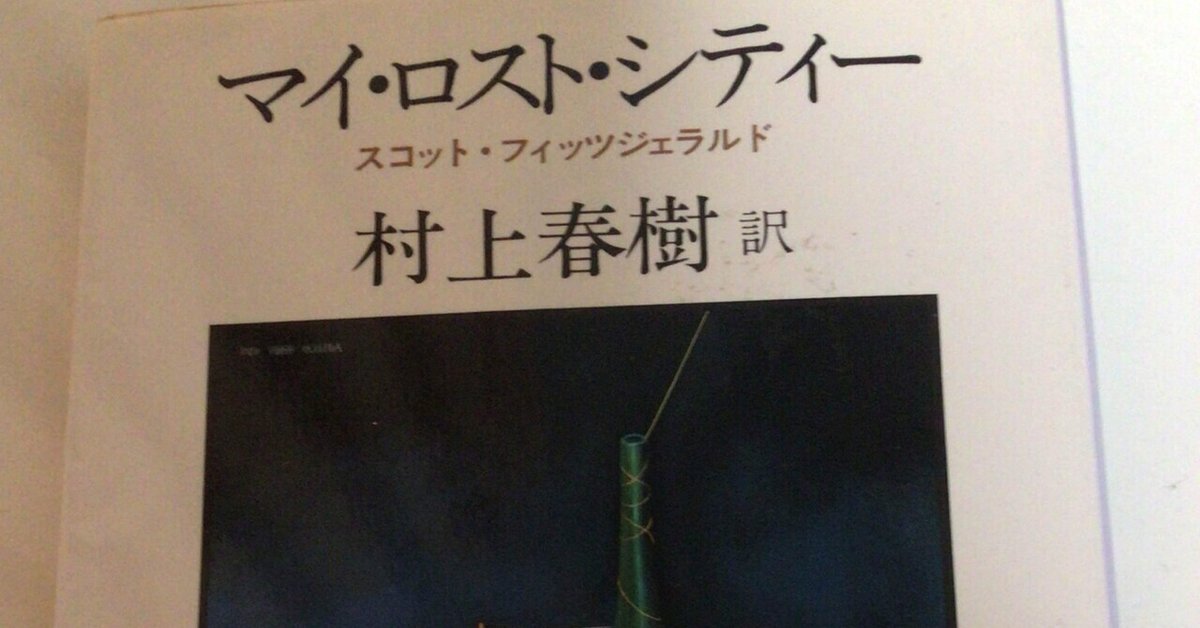
フィッツジェラルド「マイ・ロスト・シティー」
世の中には二種類の男の読書家がいる。一つは、モテる男が出てくる小説を好む人、もう一つは、モテる男が出てくる小説を毛嫌いする人だ。私は後者だったが、この真理を得て、前者を理解しようとつとめようとしたタイプに属する。
さて、モテる男をよく出す小説家として村上春樹がいる。実際に、統計をとったのかと言われると、もちろんとっているような暇はなくて、印象に過ぎない。いや、モテるという言葉に意味に語弊があるのもわかる。もう少し正確に言うと、異性と恋に落ちるにあたって、シームレスな印象を与える作家とでも言おうか。
登場人物と作家の距離というものを理解していれば、こうした曲解はいずれ解けそうなものだが、文体が大変にオシャレであったこともあいまって、モテる男が話しているかのように見えていたのかもしれない。作家には迷惑なことだが、作家としてのキャラが本人が登場せずとも大変に立っていたということの証左であろう。
そんな村上氏がフィッツジェラルドの小説+エッセイを訳しているというのだから、興味をひかぬわけがない。『マイ・ロスト・シティー』は昭和56年(1981)に単行本として刊行されたフィッツジェラルドの短編集だ。私はこのとき、まだ7歳ほどで、好きな音楽はクリスタルキングの『大都会』。フィッツジェラルドとはずいぶんな距離があったのだ。
この『マイ・ロスト・シティー』が文庫になったのは1984年。そして、おそらくは、90年代半ばに一度入手し、読んだはずである。いつまでもフィッツジェラルドとは距離が縮まらなかったし、それを訳す村上氏とも、距離は残念ながら縮まらなかった。
けれども、今、たまたま立ち寄ったブックオフにて入手した『マイ・ロスト・シティー』の表題作「マイ・ロスト・シティー」を読んで、エッセイじゃないかといまさらながら思いながら、それでも多少の共感を得ていることに自分の成長(ないしは崩壊)を感じ取ることができた。
エッセイのため(たぶん)、あらすじは割愛するが、「マイ・ロスト・シティー」の感想を書きとめておきたい。
感想
フィッツジェラルドが、いわゆるジャズエイジの時代のニューヨークについて回想しながら、幻影としてのニューヨークの喪失について語るというもの。
私は、知識でしか1910年代~1920年代のニューヨークを知らない。F.L.アレンの『オンリー・イエスタデイ』、海野弘『ジャズ・エイジの街角』で、部分的な記録が加えられている程度。ロスト・ジェネレイションの作家たちが、旧来の価値観の崩壊や社会秩序の混乱を背景に、作品を世に送り出していった時代。スコット・フィッツジェラルドもその一人であったことくらいまでは知っている。
フィッツジェラルド自身も、この社会変化の中、「勝利」と「夢の少女」の二つを手に入れ、それを失った。失ったというよりは、自らそれに幻滅し、崩壊の過程に身を置こうとしたのだろう。切々とした調子で、それらの気持ちが綴られていく。
個人的にフィッツジェラルドは、自ら距離を置いたと言いつつも、作品そのものの強度が失われていることも感じたのだと思う。自らの作品世界の欠如に対して、不安を抱きながら書いているように感じるのだ。
それに比して、村上春樹は前作を超えようという気持ちで作品を書き続けてきた。それはやはりフィッツジェラルドを愛好していると述べながらも、フィッツジェラルドとは異なる資質を持ち合わせている。いつまでも、『風の歌を聴け』を反復するのではなく『ねじまき鳥クロニクル』のような奥行きのある物語を書くようになっていった。
「マイ・ロスト・シティー」に限らず、『マイ・ロスト・シティー』という本の魅力は、その訳者・村上春樹の「フィッツジェラルド体験」という冒頭のエッセイにあると思う。
「そのような見地から見れば、一九二〇年代のアメリカ作家の中で、フィッツジェラルドほど感覚的にドストエフスキーに近づいた作家はいなかったのではないかとさえ思える時がある。もちろん質的にはその両者は比べるべくもない。ドストエフスキーがそのような対立、あるいは自己矛盾をバネにその世界を宇宙的なスケールにまで広げたのに対して、フィッツジェラルドの世界は最後まで狭いものに留まった。家庭の悲劇、報われぬ愛、裏切られた夢…極めてインティメートで個人的な世界である。そのような個人的な世界をより広大な世界に、そして宇宙へと敷衍していくことが一流作家の条件であるとすれば、彼は決して一流作家ではなかった。」(pp.16-17)
これはすでに80年代前半に書かれた文章なのだとすれば、すでに、現在の村上春樹は、フィッツジェラルドの方ではなく、ドストエフスキーの方にしっかりと歩みを進めていることがわかる。予言というか決意の文章とすれば、なるほど、恐ろしい。
「現代という様々な価値体系の交錯する世界にあっては、モラルは常に鋭い両刃の剣である。「信仰の告白」は既に文学の世界から忘れ去られようとしている。しかし人は、作家はいかなる形においてもモラルを持ち続けねばならない。もしそれが今日の文学の内包する重要なテーマのひとつであるとするなら、フィッツジェラルドを最も今日的な「近代」作家と呼ぶことも可能であるかもしれない。」(p.21)
フィッツジェラルド評でありながら、近年の村上春樹作品の自己言及であるかのように読める。この序文の三節「作品と生涯」も簡潔ながら、要を得た文章で伝記を書いてもきっと一流の作家なのだろうと、この時点で思わせるのは凄い。作品を読む村上春樹の凄みを十分に感じられる序文であり、若いときの自分に読ませてやりたいものである。
蛇足
『マイ・ロスト・シティー』、村上春樹の小説ファンはあまり読まないのかもしれないが、序文の「フィッツジェラルド体験」とフィッツジェラルドのエッセイ「マイ・ロスト・シティー」だけでも読んでみることをお勧めしたい。それを読めば、きっとほかの短編も読みたくなるように出来ている本だ。
浮気性でもなく「まず妻より始めよ。あとの世間は簡単だ」という村上さんは、やはり偉大な作家だと思います。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
