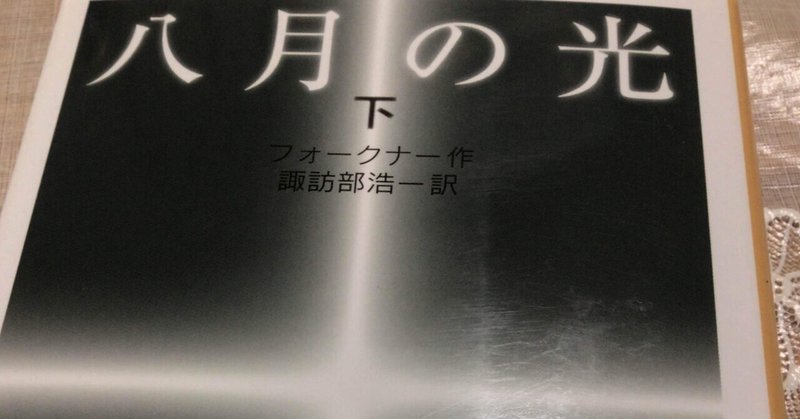
リーナの出産 ~フォークナー『八月の光』 17~
フォークナーに関する記憶といえば、私が大学に入った頃には新訳がなくて、冨山房の『フォークナー全集』と、岩波文庫と新潮文庫の数冊だけが手に入れられるものの全てだった。
もちろん、絶版ものや、世界文学全集などに入っているものとか、調べれば色々見つかったのだろうが、それをやれるほどの視野も知識もなかった。
世界は、その辺の本屋のラインナップとせいぜい図書館でアクセスできるものの幅によって、決められていた。
今、周囲を見渡すと、文庫の値段は高くなったものの、新訳はあるし、複数出ているし、文庫の中にもいろいろな種類が刊行されていて、アクセスしやすく、かつ、理解も進んでいるように見える。雑誌『フォークナー』という研究者向けの雑誌が案外と巻を重ねているのを見るにつけ、意外とフォークナーは日本に読まれているのだなという思いを持つ。
しかし、あの頃よりも出会う場は少ない。街の本屋は潰れているし、そもそも置くスペースがない。大きな書店すら、今は厳しい。以前よりも、理解可能性は高まっているのに、出会う場が縮小してしまっているのは、何の因果だろうか。
フォークナーを理解したところで何が起こるわけではないのだけれども、時代というのは少しづつ進んでいくのだなあ、という感を強くする。もともと全集が出ていたくらいだから、受容の厚みは私の入学前から当然あって、自分はそれをあの段階で触知できなかったわけだけれども、入手できる本に限りがあったのは、フォークナーの受容期と咀嚼期との狭間にいたのかもしれないと勝手に理解している。
私自身は、1992年に没した中上健次のリバイバルの中で、彼が参照したフォークナーという作家の紹介がなされて、興味を持った。しかし、翻訳ですら難解で、歯が立たなかった。『八月の光』でさえ、そうだった。1995年、せいぜい短編集の解説を読み、説明的な知識を得たに過ぎなかった。ただ、古本屋の格安ワゴンに置いてあることが多く、入手はしていた。
主著の一つである『響きと怒り』の新訳が講談社文芸文庫から出たのが1997年。それは購入して読んだ。面白かった。多少、勉強し、経験も積んでいたので、理解することができた。1998年には『アブサロム、アブサロム!』が同文芸文庫から刊行される。購入したが、あまりの厚みに積読した。どこかで読んだはずだが、覚えていない。
次にちゃんと読めたのが新潮文庫のリバイバル復刊『野生の棕櫚』だった。これは手頃な長さに感じた。しかし、交互に繰り返される物語の筋を追いきれず、イメージだけが残ったまま今に至る。いずれ読み返したい一冊だ。
2000年には『死の床に横たわりて』が文芸文庫で刊行された。これもお付き合いで購入。すでに関心は別の方向にあり、まともに読んだとは言えない。岩波文庫で刊行された『熊、他一編』に関しては、そっけないタイトルに、購入すらしなかった。
2002年ごろ、読んではいないくせに、好きな本はなんですかと問われるとフォークナーという癖がついていた。そんな発言をする中で、語学の達人みたいな女の人と知り合った。仕事上の付き合いだったが、彼女に同じような発言をして、「フォークナーいいよね、南部訛りの使い方が上手!」と言われ、恥ずかしくなり言うのをやめた。この女性はのちに友人にストーカーをしたという疑惑で、疎遠になるが、真実はどうだったのかわからない。その後、結婚して、子どももいると聞くが、どうなったのか。本当に語学の達人だったので、きっと立派になっているに違いない。
2006年前後、全集版の中の『自転車泥棒』という晩期の作品をつけ麺屋で読んだことが微かに記憶にある。むしろ、つけ麺屋が好きで、週3回通っていたら、どんどん太っていった。この頃は松本に住んでいた。
おそらくは2008年ごろに『サンクチュアリ』を読んだ。正直、もうこの手の内容に反応できなかった。『サートリス』や『行け、モーセ』、『寓話』などにチャレンジしたが、全く覚えていない。たぶん、背景にある宗教的バックグラウンドが、実感できなかったこともあるだろう。
2010年代にフォークナーは『八月の光』も含めて、何度もチャレンジした記憶はある。その都度、途中でやめた。理由は、闘病もあったし、仕事も忙しかったから。しかし、なぜチャレンジしていたのだろう。思い出せない時は仕方がない。ただ、幼いころサッカーのそれなりに強い学校の部活でしっかりやっていた人は、大人になってもその身のこなしをを忘れないように、文学部でそれなりに学んだことは、それなりに覚えているということではないか。
それにしても今日は暑い。
あらすじ
ハインズ夫妻と小屋に戻ると、リーナが陣痛でうめいていた。逃げてもいい、バイロンは思う。しかし、結局はハイタワーを呼びにいき、6時間前に談判して、疲れて寝ているハイタワーを叩き起こして、連れて来たのである。
そしてリーナは出産した。
手伝ったのはミセス・ハインズ、そして産婆役をしたのはハイタワー。
そもそもハイタワーは今まで二人の子どもを取り上げて、どちらも失敗している。その責任を追及されてもいた。
しかし、ここで取り上げることに成功したことで、ハイタワーの贖罪は終わった。当然、クリスマスのアリバイを証言する役割を断ったがゆえに、それを償うための産婆役だったかもしれない。
その後、医者が来て診察をする。ミセス・ハインズはジョー・クリスマスだと思って赤ん坊に呼びかける。男たちはぐったりしている。特にハイタワーは。
ハイタワーは思い出す。寝る前に、自分は役割を果たすだろうことを。そして、実際に果たした。関わってしまった。しかし、機嫌は悪くない。というよりも、老いた肉体に誇りと栄光が戻ってきたかのようにも感じる。
〈もっと機嫌が悪くてもいいはずなのだが〉と考える。しかし自分が不機嫌ではないと認めざるをえない。寂しく雑然とした台所で、昨日の古い油がわびしくこびりついている鉄のフライパンを持って立っている、背が高く不格好で孤独な男━その中を熱い勝利感のようなものが輝きとなり、波となり、うねりとなって流れてゆく。〈私は彼らに見せてやったな!〉と彼は思う。〈老人にもまだ生が戻ってくるのだ。一方、彼らは遅れて来る。彼らは老人の残り物をもらいに来る、とバイロンならば言うだろうな〉だが、これは虚栄であり、虚しい誇りだ。にもかかわらず、ゆっくりと薄れゆく輝きは譴責に耳を貸さず、それを無視する。〈だからどうだというのだ? 私がそれを感じたからといってどうだと? 勝利と誇りを? それを感じたからといってどうだというのだ?〉と彼は考える。しかし、彼の中の熱が、輝きが、支えてくれるものを何とも思っていなければ、必要ともしていないことは明らかだ。
そして、再度リーナのところに診察に行く。すると、「アンクル・ドック」がまず朝方どこかにこっそり出て行き、それを追いかけてミセス・ハインズが出て行った。さらに、バイロンもどこかに出掛けて行ったという。
リーナにねぎらいの言葉をかけた後、ハイタワーは、バイロンとどうするのかと聞いた。するとリーナは、結婚を申し込まれたが断ったといった。しかし、助けが必要であることは匂わせながら。ハイタワーは、複雑な立場を慮りながら、バイロンを解放してやってくれという。リーナも、私は特段引き留めているわけではないという。
ハイタワーは製材所にバイロンを訪ねにいく。すると、もう辞める言いに来たという。ハイタワーは思う。バイロンは、どこか遠くにいったのかもしれない、と。そして、自らは役割から解放されたのかもしれないと。
いや、まだ彼には役割があると、ナレーターは言う。
感想
ハインズおばさん、それはないよ、という感じ。それはクリスマスではなく、リーナの子どもだぞ。ハインズ夫妻の、おそらくは認知症的なありようが、文学的に昇華されると、このような聖性を帯びた感じになるのかもしれないけれども、周りにいたら困った老人だよなあ、と思ってしまう。そんな私もいずれ…ああ、ハイタワーのように生きるのが吉か。
リーナの出産は、これはこれで、クリスマスの死と新たな子どもの誕生とが重なるところに、犠牲と再生のモチーフが透けて見えるのだろう。ミセス・ハインズが「こんがらがる」のも、もう一度ジョー・クリスマスをやり直してみたいからだ。それにしても、それだとジョーがやりきれない。
マリアの懐胎とキリストの誕生、そして、ヨゼフ=バイロンで聖家族がそろうというわけである。逆に考えると、家族とはそもそもこうした偶然の関係性が織りなす奇蹟とでもいうほかないものではないか。血によって、犠牲となったジョー・クリスマスは、血によらない家族によって生まれ変わりを生きる。見ようによっては、これでいいのだ、とバカボンのパパならずとも断言したい気分になる。
懲罰感情や改心してほしいという素朴な感情は慰撫されないフォークナー作品だが、ヨーロッパの孤児として力強く生きようとするアメリカ的精神をそこかしこに感じさせる。そういう意味ではやはりアメリカ文学の系譜に連なるものなのだなあ、と実感した。
ちなみにこの章は、語りの中で時間が巻き戻ったりして、時間軸の取りづらい章です。こころして。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
