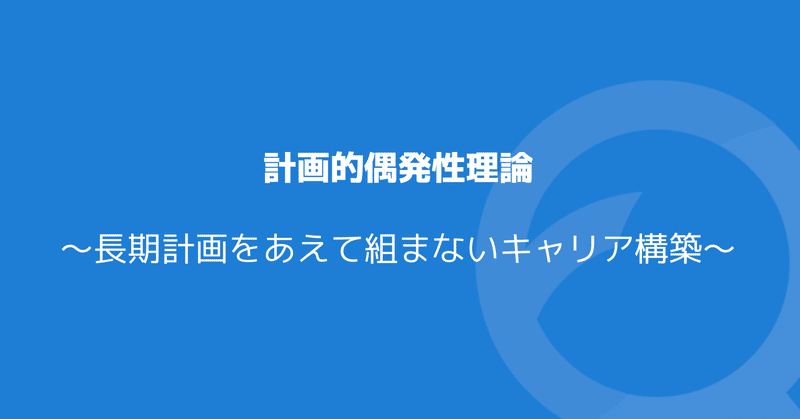
計画的偶発性理論 -長期計画をあえて組まないキャリア構築 -
ファインディというスタートアップで、CFO兼海外事業担当役員をしている河島です。事業・組織を大きくするため邁進しております。
自分の好きなキャリア構築の考え方である「計画的偶発性キャリア理論」について、掘り下げて書きたいと思います。
10年後のキャリアとかどうなっていたいか、など長期目線を聞かれたときに、きちっとした答えを持っていないといけないみたいな空気になったりしますが、この理論を知ってからは、おぼろげな方向性だけ見えていれば、あまりきちっと決めなくていいというように思えるようになりました。
あくまで一つのキャリア論なので、正解がない話です。
01. 計画的偶発性理論とは
・この考え方によると、個人のキャリアの8割は、偶然の出来事によって決定されるそう
・心理学者のジョン・D・クランボルツ教授によって1999年に発表
・クランボルツ教授がビジネスパーソンとして成功した人のキャリアを調査したところ、そのターニングポイントの8割が、本人の予想しない偶然の出来事による
計画的偶発性理論の骨子
1 予期せぬ出来事がキャリアを左右する
2 偶然の出来事が起きたとき、行動や努力で新たなキャリアにつながる
3 何か起きるのを待つのではなく、意図的に行動することでチャンスが増える
ゴールがなくても焦らなくていい
・これまでのキャリアプランの立て方は、将来の目標を決めて計画を立て、それに向かってキャリアを積み重ねていくというものがほとんどであった
・しかし、変化の激しい時代にあって、将来の社会や会社の状況は個人の意思でコントロールできるものではなく、従来のキャリアプランの立て方は効果的とはいえなくなっている
・そこで、あえて明確なゴールを定めず、現在に焦点を置いてキャリアを考える計画的偶発性理論が注目されている
目の前の仕事に向き合う
・将来のことは誰でも不安。新しいことは誰でもやってみたい。でも何ができるかはわからない。それなら、まず目の前の仕事に、そのもやもやしたエネルギーをぶつけてみる
・本気でやったことが、経験や結果に結びつき、自然とステップアップしていく
積極性が新しい機会を呼び込む
この理論の肝は、積極的にあり続けること
・もしやりたいことがおぼろげでもあるなら、声に出し、周りに発信する
発信し続けて、全力で取り組んでいると、ある日、転機が舞い込む。面白いと思ったら飛び込んでみる
・頑張れば誰しもなにかチャンスを得られるわけではないが、動いていないとチャンスは舞い降りてこない
02. 私なりのキャリアの考え方
基本3 - 5年ごとに、やる仕事もしくは役割を変えてきた。このブロックが3個目を超えたくらいで、色々繋がってきて、面白くなったのを感じた
変えることが正ではなく、尖らせるか、広げるかのキャリア感の違いであることは強調したい。どちらも正解であり、それは結果論でしかない
3 - 5年と置いてるのは、職務要件上、経験は3 - 5年求められることが多いから
結局は何を学んだか、成し遂げたかではあるが、リクルーターや採用担当者は、一定経験年数を見ている
スペシャリスト雇用の考えが強い アメリカの求人だと、10年経験者を求めるとかざらにある
このようなジョブ型雇用は、日本でも主流になりつつあるので、1つの職種を長く経験し、様々なフェーズを体験していくことは内部でも外部市場でも価値になる
振り返り
・3年前の夏までアメリカにいて、5月末に本帰国を言われるまで日本に帰ると思ってなかったし、なんなら年初に妻にあと2年はアメリカで頑張りたいと言ってた
・会社都合で帰国になり、その後、考えて転職して、今に至る(興味ある方は、こちらもぜひ
(河島 自己紹介)監査法人から事業会社。 大企業からスタートアップへのキャリア変更
・まさか五反田のスタートアップで働いてるとは、転職後一年前の自分は一ミリも想像してない
・そして今は海外事業の立ち上げをやっている。インド中心に事業を自分でつくっているとは夢にも思わなかった
1年後3年後どうなってるかはわからない。でも、今は、Findyに本気で取り組んでいる。読めないから人生面白い
03. 10年後何やりたい?と言われるの嫌いだった
・監査法人のときや、リクルートでもこの質問をされていた。ずっともやもやしてて、10年後とかわかんないと思っていた
・漠然と成功してたいとかはあっても、じゃあ今から数年何やってーとか描きづらい。なので初めて計画的偶発性キャリア理論のことを知ったとき、すごくしっくりきた
将来の自分をおぼろげに想像する
・今の組織に3年いた時、今の仕事で、どんな結果残せてて、どんな仕事できてたらいいか、なりたい自分を想像する
・まだ何もしてなくても、3年後の職務経歴書を想像して書いてみる
・その自分の市場価値を定期的に調べる(転職意欲がなくても周囲の友人・知り合い・エージェントと話してみる)
04. やりたいことは変わって良い
・意欲的にやりたいことを発信し続けて、目の前の仕事に向き合う。そして、やりたいことを考える。
・変わったならそれでいい。変わった新しい目標に向かって頑張ればいい
点と点はつながる
・スティーブジョブズも言ってたが、connected dotsという言葉がある。自分が頑張ってきたことは、インダストリーや職種を変えても、後でつながる
(ポジティブにつながると思い込む)
環境は変えたければ変えて良いが、大変なことを乗り越えた経験はプラスになる
・別に無理して我慢して仕事する必要はない。でもポジティブに、今の仕事で得られること、今の仕事に向き合うことは、次なる機会を産むので、新しいことをしたい情熱を、今の仕事にぶつけてみると、見えるものがある
・石の上にも三年という時代でもなくなっているが、大変なことを乗り越えてもがいて成果に繋げる経験に変えるものはない。とするとあまり超短期に考えすぎるとキャリアにとってはプラスにならないことも
05. 悩むのは普通。悩んだら周りに相談しよう
・キャリアについて、定期的に悩むことは、健全であり普通。それだけ本気で向き合っているという証拠
・20代中盤、30手前、30中盤と数年おきに自身も悩んでるし、周りにきくと40代でも50代でも何かしろ仕事について悩んでいる
・上手くいっていなくても悩むし、成功してるような方も悩みがある
せっかく長い人生を仕事するなら、自分が楽しめる仕事をしたいですよね。
楽しいの定義は人によるし、その楽しさを味わうためには苦労や辛いこともついてくる
ほとんどが苦しいか不安で、乗り越えた時の気持ちよさがドーパミンになってるので、そういった仕事をするように心がけてる。毎朝自分を鼓舞して動いてます。
— Sugu@Findy CFO(海外事業立ち上げ専任中) (@sugnchi) July 26, 2023
大変さも含めて、”楽しめる”が大事ですね〜 https://t.co/O5VjWqB2G5
大変さも含めて楽しんで、没頭できることを見つけ、自分らしい自分にしかないキャリアを築けるとより働くことが楽しくなるって思ってます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
