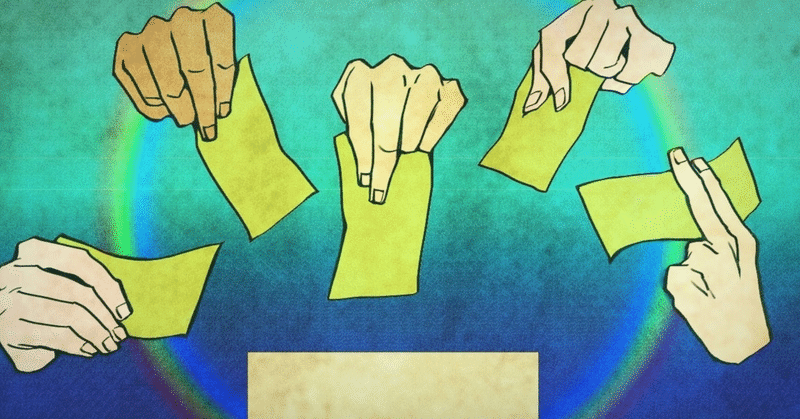
中国人は、西欧的な「民主」を求めていない
実業家の牛乳屋さんが、学生時代のレポート(の下書き)を公開されていました。中国村落部の自治について述べた内容で、とても興味深かったです。一読をおすすめします。
ものすごく乱暴に要約してしまうと、当時の中国の村落においては「生成的自治」(共同体参加者による自発的な自治)のようなものの萌芽が見られたものの、それは実質的には「構成的自治」(国家権力など外部者による自治)、つまり党による影響力を強化するように機能していた、というお話です。
僕はこの頃の中国についてはほとんど無知なのですが、習近平政権以前の中国にはたしかに「民主化」的な方向に社会が流れていくのでは、という空気があったようです。しかし現在の中国を見ればわかるように、その後そのような流れは大きく押し止められることになりました。
当時の空気の中で「生成的自治」、つまり民主化っぽい動きがあるものの、それは「構成的自治」のためのパーツでしかないだろう、と看破していた牛乳屋さん、結構すごいのでは。
+++++
ところで、中国においていわゆる「民主化」が進まないことを嘆く向きというか、中国は一党独裁でそこに暮らしている人は大変だねーなどという人がいます。しかし僕が現代の中国人と交流してきた中で感じる限りでは、中国人の「民主」に感じる重要性は高くありません。中国人は西欧的な「民主」など必要としていないのです。
西欧的な「民主」っぽいものの下で育ってきた日本人にとっては、「民主=よいもの」「民主じゃない=よくないもの、独裁、恐怖をともなうもの」という印象をどうしても持ってしまいます。「恐怖をともなう圧政によって民を苦しめる政府と、それに嫌々付き従うしかない、かわいそうな民衆」の構図を思い浮かべがち、とでも言いましょうか。
しかし中国人にとっては、そのような構図は必ずしも当てはまるものではありません。中国の人々はいわゆるそのような「圧政」と上手に距離をとりながら、それを蛇蝎の如く忌み嫌うでもなく、かといって過度に擦り寄るでもなく、時には利用しながら暮らしています。いまの体制に対する評価も、それほど低いものではありません。
それは近年の経済的な発展や、直近ではコロナウイルスの封じ込めの成功などからもたらされている面もあります。しかし、実はもっと根本的なこととして——中国人自身がいわゆる「民主」では中国を治められないということに気づいているからではないのか、と思うことがあります。
過去には天安門事件などもありましたが、その前も後も中国は「民主」に接近したり、離れたりを繰り返しながら、結局はわかりやすい「民主」の道を選ぶことなく国を発展させてきました。つまり、そういうことなんじゃないでしょうか。
そもそも人が多すぎる中国において、いわゆる「民主的」な方法による自治が唯一の正解とも限りません。むしろ共産党という大きな重しがなければたちまち分裂・瓦解してしまう可能性を冷静に見ているからこそ、中国人は消極的、あるいは積極的に今の体制を支持します。
もちろん今の体制に関して不便さや窮屈さを感じることもありますが、それよりもメリットの方が大きいと考えているわけです。
われわれのような西側的価値観(っぽいもの)のもとで生きる人々が「最適ではないかもしれないし非効率的な部分もあるが、少なくとも最もマシと思える制度」としていまの民主主義(っぽい)体制を選んでいるのと同じように、中国の人々も「最もマシ」なものとして、いまの体制のもとでの生活を享受しています。
この前提に立たないと、中国や中国人を見る目が曇ってしまうような気がするのです。
+++++
アメリカのアフガニスタン撤退などに代表されるように、コロナ禍以降は特に「西欧的民主」なるもののプレゼンスは大きく後退しています。「西欧的民主」が唯一の正解でないということに、みんな気づき始めているというか。
そんな中、「西欧的ではない」体制を持つ中国がどのように強いプレゼンスを発揮し、またそれを中国人たちはどのように捉えていくようになるのでしょうか。
無知無学なりに、中国と中国人の姿を見届けていきたいと思います。
いただいたサポートは貴重な日本円収入として、日本経済に還元する所存です。
