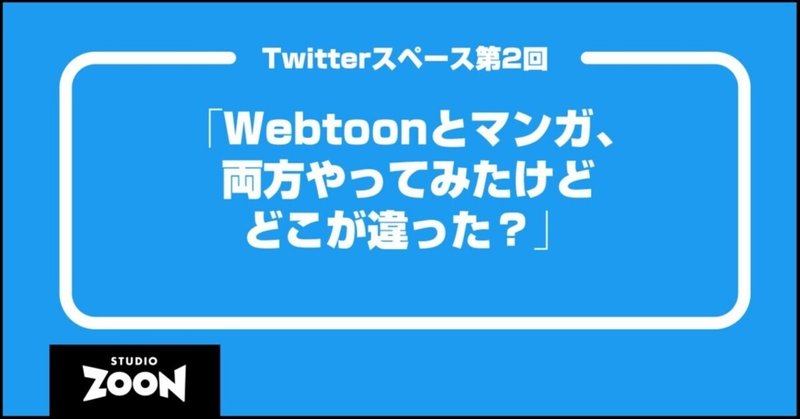
「Webtoon」の魅力を探る!Webtoonとマンガ、作り方や意識するポイントの違いはある?
編集者、アートディレクターの採用を進めるべく開始したコンテンツスタジオ「STUDIO ZOON」のTwitterスペース第2回を開催いたしました!
今回は「Webtoonとマンガ、両方やってみたけどどこが違ったのか」というテーマで、編集長の村松・鍛治の2名がWebtoonの特徴や魅力、マンガとの違いなどをお届けしました。
\スペースはこちらからいつでもご視聴いただけます/
— STUDIO ZOON (@zoon_studio) July 5, 2023
\編集長についてはこちらのインタビューをご覧ください/
\第1回の配信の内容はこちらにまとまっています/
Webtoonは「読む」よりも「見る」感覚が強い!
村松 Webtoonをやってみて、マンガとの違いを感じることはありますか?というテーマで今回は話していきたいと思うんですが、まず、ネームを作るときの違いはどうでしょう。
鍛治 ネームに限りませんが、トータルは「やってみればやってみるほどそんなにかわらないな」という印象です。ネームも見せ方や意識する部分は違うけど、やらなきゃいけないことや、意識しなきゃいけない部分は変わりません。たとえば、キャラクターをいかに魅力的に描くかとか。世界観がわかりやすく伝わるかっていう部分は変わらないと思います。
ただ、Webtoonはマンガのような横読みよりも見せ方に限りがある。Webtoonって「誰がどのくらいの距離感で、どこで話しているのか」といった見せ方が本当に難しいんですよね。横読みだとパーンと引きの絵が1つあれば、あとはキャラのアップの絵が続いても状況は伝わる。でもWebtoonを読むときって、スクロールして情報が上にどんどん上がっていっちゃうから、誰がどんなセリフを言っていたのか確認するのが難しい。だからこそ、セリフの使い方はネームの段階で見せ方を含めて作家さんと話し合いますね。
村松 マンガのセオリーからすると、状況を分かってもらうために引きや俯瞰の構図を入れてキャラクターの距離感を示しますよね。Webtoonの場合は、マンガよりも少なくてもいけるなという感覚があるので、マンガほど丁寧じゃなくても読めちゃうんですよね。
鍛治 横読みだったら「左ページの左下には次のページを開かせるための引きがある」とか、マンガを読ませるための構図はあんまり変わらないですよね。スクロールして読む手法でも、スクロールするための引きは常にないといけないし。そういう作り方や考え方は、全然変わらないなって思うんです。
村松 そうですね。結局あんまり変わらない。違いがあるから日々発見はあるんですけど、大きくは苦労してないんですよね。
鍛治 僕も苦労はあんまりないな。ただ、僕が作家さんとネームを作っているときに気を付けることが1個だけあるんです。Webtoonは、横読みよりも画面上のセリフの圧迫感があるなと思うんですよ。横読みだと「これくらいのテキスト量や、吹き出しの中に入る文字数は気にならないな」って量でも、Webtoonだと画面がすごく圧迫されて見える。
Webtoonは「読む」よりも「見る」って感覚が強いからだと思うんですけど、セリフの配置や量、テンポ感は意識しないといけない。なるべく絵で見せられるように、作家さんと話し合っています。
マンガよりも少ない情報量でディテールが充実するWebtoon
村松 Webtoonの「あるある」だと思うんですけど、マンガの1話目に入ると思って作ったシナリオが半分か、3分の2くらいしか入らないことってあるじゃないですか。だからシナリオを作っているときって、マンガだと「1話にこれだけ入っていないと満足感がないよね」という量を用意するんですけど、いざそれでWebtoonのネームを作ると3分の2くらいでお腹いっぱいになるというか(笑)。
鍛治 そうなんですよね。
村松 じゃあシナリオがそんなに入らないのになんでお腹いっぱいになるのかというと、Webtoonのほうがストーリーのディテールをリッチに描けるんです。でも、それは入る情報量が少ないってことでもあるんですよね。マンガほどセリフをたくさん入れられない、けれども、情報量が少なくても面白いと思える、という。
鍛治 横読みの場合、「こういう感じのプロットにしようかな」と考えていても、想像しているものよりもページ数がかさみますよね。Webtoonは、さらに入らないなと感じます。横読みの第1話を3分割してちょうどいいかなって感覚ですね。
村松 アニメは、どんなストーリーだったか思い出せなくても見ることの楽しみがすごく強いコンテンツだと思うんです。たとえば、宮崎駿さんの作品だと「キャラクターが動いているだけでおもしろい」「おいしそうな食べ物がひたすら並んでいるのがおもしろい」とか。そういった見ることの楽しみがアニメにはあると思うんですけど、Webtoonもマンガより見る楽しみが高いので、そこまでストーリーが入らなくても楽しめちゃうんじゃないかなと。
鍛治 確かにそうですね。
村松 ちなみに、途中でSTUDIO ZOONに参加した編集者の熊谷さんが「企画を読めば、どれが村松さんの担当で、どれが鍛治さんの担当したものなのか分かる」と言っていて(笑)。
鍛治 僕も言われたことがあります(笑)。
村松 おそらく鍛治さんのほうが、『見る楽しみ』に寄っているんですよね。鍛治さんは作家的な感覚でビジュアルの面白さを追求していて、僕の場合はもう少しストーリー性を意識しているところがあるのかなと思いました。
鍛治 もちろん作家さんの個性もあるけど、僕も村松さんが担当している作品が分かります。
村松 編集者の傾向って出るんだなと思いましたね。
Webtoonは「共感性」、マンガは「数の豊かさ」の表現に長けている!
村松 今Webtoonを描いてくれている作家さんって、初めてWebtoonを体験する方たちが多いじゃないですか。だからWebtoonとマンガの違いを確認しながら打ち合わせするんですけど、その度にWebtoonが優れているなと思える点をいくつか感じるんです。まず1つは、主人公への共感がすごくラクなんだよね。
主人公への共感って、マンガにとっては一番難しいことだと思うんですよ。特に新連載の1話目は、「どういう順番で主人公に光を当てていったらいいのか」と、いかに主人公に共感させるかに神経を使いますよね。でもWebtoonは、マンガでは絶対にダメな見せ方で主人公を紹介しても読めちゃうし、共感できちゃう。
鍛治 主人公もそうだし、Webtoonは全体的に「何を見ればいいのか」が分かりやすい媒体ですよね。でも、視線があっちこっち向けられる見せ方だと読みづらくなるから、できるだけセンターラインを意識しないといけない。
村松 マンガの画面は横に広くて、Webtoonは縦長で横に狭い。だから、僕のなかではWebtoonのほうが没入度が高くて、体験的にはVRとかに近い印象があります。その代わり、Webtoonは一覧性が低いんですよね。マンガのほうが、たくさんのものを同時に見せることができる。ここは違うなと思いますね。
Webtoonは没入度が深いので、主人公が登場したらどんなやつでも割と共感できるし、スラスラと読めちゃう。マンガの場合はページをめくるっていう労力を読者に強いる分、「こいつはどうなるんだ」と思わせないといけない。でも、没入度が高いWebtoonはスルスルと読める分、一覧性が低いので、マンガだと横長の1コマにモブキャラのリアクションの違いを小さく描けるのに、Webtoonでは難しい。たとえば「学校の先生がこう言いました」という1コマに対して、手前で驚いている主人公の裏でヒロインは違う反応していて、ライバルキャラはまた全然違ったリアクションしているといった状況が描かれていると、それぞれのキャラクターに少しずつ厚みが出てきますよね。
マンガには、たくさんの小さな「キャラクターの筋」を扱える豊かさがある。たくさんの筋を同時に扱えるし、それを一覧で見せられる部分があるんですけど、Webtoonは同時に情報を見せるのが得意ではないし、そういう細かさは描きづらいなと思います。
マンガとの最大の違いは「着彩」
村松 ネームについて、他に気になったことはありますか?
鍛治 Webtoonはアニメに近いっていう話があるじゃないですか。そういう印象を持たれる方も多いんですけど、さっき村松さんが言ったように、横読みは読者側が自分でページをめくるという、ある種のカロリーがあるわけで。そのカロリーを消費してもらうためにご褒美を用意して、「カロリーを消費する→ご褒美を提示する」という繰り返しの作り方があると思うんです。
Webtoonの場合はもう少し動的で、アニメに近い感じがします。勝手に流れていく感覚に近い。だから「読み込まないと理解できない」「情報量がたくさんあると理解しづらい」というデメリットが生じるのかなと。主人公の没入感とかもそうだと思うんですけど、動的な流れは相当意識しないといけないのかなと思います。
村松 なるほどです。ここまで色んな話が出ましたけど、ネームについては気を付けるポイントはあれどマンガを経験した身からするとなんとかなると思っていて。一方、一番気をつけなきゃいけないしマンガと最も違う部分は着彩だと思います。マンガ編集の立場から言うと、ネームが完成した時点で8割の仕事が終わった感覚があるんですけど、Webtoonだと「半分終わったかな、終わってないかな」という感じ。マンガの場合はネームが完成すれば線画を仕上げて、ネームに描かれていることがちゃんと表現されていたり、底上げされていたりしたらOK。
ところがWebtoonではネームが完成したら着彩での仕上げがあるから、マンガとの違いの大きさは日々感じています。衝撃的なくらい変わるんで(笑)。
鍛治 僕は着彩も見させてもらっていますが、1番意識して苦労するのは着彩です。作家さんと原稿を作っていくときは自分の中で「こういうカラーにしよう」と考えながらよく話すんですが。
たとえばさっきの学校のシーンで考えると、モノクロにしても全然気にならないじゃないですか。「主人公の奥にモブキャラの女子高生がいる」「先生がいる」「窓の外に鳥が飛んでいる」とか。モノクロだと気にならず読めるんです。
でもそこに着彩を入れると、鳥にも、空にも、教室にも色がつく。それぞれのモブキャラにも髪色がつくと、何を見ていいのか分からなくなる。だから、着彩チームはそういう画面作りをすごく意識しています。
作家さんが描いた作画で「何を汲み取らなきゃいけないのか」まで最大限話し合うんですけど、それでも汲み取れないものはあって。そういうときは、村松さんや担当の編集ともいろいろ話をしながら進めています。作家さんと話す機会を設けてもらいながら進められるので、着彩チームとして、スタジオとしてこれからもっともっとよくできるとは思っています。現状、胸を張って世の中に出せる色味を探せているのは、そこだなって。
村松 軽く補足すると、STUDIO ZOONは作家さんに合わせて体制を組んでいます。1人でネームから着彩まで仕上げる作家さんもいらっしゃって、そういう場合は普通のマンガ編集っぽい仕事だけをやっているんですけど、スタジオが着彩を担当するケースが8割以上です。その場合は、作家さんが描いてきたものをしっかり理解し、コミュニケーションをとりながら着彩を進めるところまでを担当します。
鍛治 補足の補足になっちゃいますけど、よく「着彩をお願いしたいんだけど、線画を仕上げたあとはどういう色味になるのか確認できないのか」と心配する作家さんもいます。
僕らの場合、線画をもらったら作家さんを含めて着彩チームの人間と何回か「こういう色味だったらどうか」と話し合ったり、「こういう見せ方ができている」と確認したりできます。着彩チームとコミュニケーションをとれるのは、僕が作家目線に立ってもすごくやりやすいし、安心できると思うんですよ。それが自分がイメージしていた着彩じゃなかったとしても、それがグレードアップしていればいいわけだし。逆に全くグレードアップしていなくて自分のイメージと違っても、何回も「一緒に色味を探したい」と言える体制になっています。着彩は、作品の意図をどれだけ汲み取れるかを意識しているので。
村松 僕、最近金髪にしたじゃないですか(笑)。金髪にしてみたら思ったような色に染まらなくて、ぶつくさ言っていたんですよね。「美容院を変えようかな」とか。僕の髪の色くらいどうでもいいことでも不満が溜まるのに、がんばって作った作品がイメージしていた色味と違った時の不満の大きさよ、と思って(笑)。これは気をつけねば、と感じたんですよ。
鍛治 村松さんの場合、自分がイメージした金髪の色って、どうすればその色になるのかが分からないから「違う!」っていう不満が出てくると思うんです。でも「こういう色なのか」ってやりとりができると、自分でやり方が分からなかったとしても安心できますよね。
Webtoonで大切なのは「スピード感」&「時間の一致」
村松 Webtoonは同時にたくさんの情報を提示しづらいよね、って話があったじゃないですか。1コマのなかで工夫の仕方はありますけど、マンガのように多くの情報を盛り込めない理由の一つには、色がついていることが挙げられるかなと思います。すべてに色がついているので、全部同じように塗ってしまうと「目がチカチカする」「どこを見ていいのか分からない」と感じてしまう。
着彩を仕上げる工程を日々見させてもらってますけど、最終的には「どこを見させるか」を絞っていく作業ですよね。たとえば「人を銃で撃っている場面だから銃口がうつっているべきだ」「逆にそこ以外はあまり見えないほうがいい」とか、見せ方を絞っていく。同時にたくさんのものが見えるのは、フルカラーだと相性がよくないのかなと感じます。
とはいえ、いろんなキャラクターがたくさん登場するマンガが日々アニメ化されているわけじゃないですか。アニメも、Webtoonも、同じ理屈だと思うんです。どちらも、1つの画面にたくさんの情報を入れないように意識されているので。見せ方を工夫するために、必ずなんらかのアダプテーションをやっている。アニメの場合、声優っていう見分けポイントがもう1つ加わりますけど、「たくさんの情報とキャラクターをどう扱っているのか」をちゃんと研究していけば、見え方が変わってくるのかなと思いました。
鍛治 小説、マンガ、アニメ、Webtoonと、媒体によって特徴は全然違うんですよね。小説は文字を読みながら「どんな顔をしてるんだろう」と想像する楽しみがあるし、マンガは「どんな声をしてるんだろう」と想像するのが楽しいのかもしれないし。それぞれ特徴が全然違うから、楽しみ方も違う。
村松 Webtoon作品のなかには「小説っぽい」「漫画っぽい」と感じるものもある。そこをちゃんとアジャストしていかないとってところはありますね。
鍛治 ちなみに、「小説っぽいな~」っていう部分はどういうところで感じるんですか?
村松 小説っぽさを1番感じるのは、キャラクターを眺めているように書いている作品ですね。たぶん、Webtoonだとキャラクターのなかに入って書かないといけない部分がある。たとえば、ある目的不明の主人公がいるとします。目的は開示されていないが、何かと戦っている。そして、その様子がかっこいい。そういうシーンを読んで「一体こいつは何者なんだ」と、冒頭で興味を引き続けることは小説ならできると思うんですよ。そして、数十ページ目くらいで「こういうやつが、こういう世界観で、こういう活躍をする話だったのか。ほうほう、これは面白い小説だな」となる。
でも、Webtoonでそれをやると「何を考えていて、何をしようとしているのか分からないキャラクターがずっとアクションをしている」「どこに共感していいのか分からない」と感じてしまう。読者をストーリーに引き込ませるには、アダプテーションが要るんですよね。
鍛治 横読みのマンガでもそうかもしれないけど、Webtoonでより意識しなければならないのは、ダラダラと話を進めないこと。「読んでもらって当たり前」っていう作り方は難しいし、しんどいですよね。もちろん、ゆったりと描くのもいいんだけど。
その点、小説は丁寧に作られているじゃないですか。「誰がどういう状況で話している」とか。マンガもそうですけど、どちらかというとWebtoonは「キャラクターそれぞれにどういう個性があるのか」を表現することに尺を使う。没入感と共感性を出す作り方をするんです。
特に分かりやすいのが、スポーツもの。サッカーをテーマにしたマンガだとしたら「なんのためにサッカーをやるのか」よりも「はやくサッカーの試合を見せてくれ」と思ってしまう。Webtoonでは、そこをより意識しないと読んでてつらいなと思う部分がある。
必要な設定やセリフだし、キャラクターのことが分かるセリフなのに、「そんなことよりも早く走り出してくれないか」と感じるところがあるんです。
Webtoonは期待させる部分をはっきり提示しやすいからこそ、読者に期待してもらってる部分にはやくご褒美をあげなきゃいけない。そういう意識を持つことは、Webtoonを作る上で大事だと思っています。村松さんは他にどういうところを意識してますか?
村松 そうですね、僕は読者が主人公に深く感情移入できていて、その運命から目が離せないっていう状況になっていれば、大体のエンタメは面白いと思っているんですけど、Webtoonの場合は特に感情移入させやすいし、やらないとダメな媒体だなと考えているんですよね。
でもアニメって、感情移入しなくても眺めるように楽しむことも可能な気はしていて。表現が極まってくれば、将来的には客観的な楽しみ方ができるようになるのかもと思ったりする。ただ現時点では、あるキャラクターにちゃんと感情移入して、そのキャラクターの運命を見届けてやるみたいな感じをしっかり表現できればいいなと思っていて。
そういう意味で、僕はキャラクターとのシンクロ率を上げることを考えています。そのキャラクターとのシンクロ率を高めて共感性を生むには、抽象的なんですけど、キャラクターの体感時間とネームの運びが一致していることが重要だと思っているんです。作品内の時間とWebtoon上に表現されている時間感覚が一致するように、気を付けるんですよね。
恋に落ちた瞬間に時が止まったように感じたり、ショックで頭が真っ白になってハッと気が付いたら数時間後に駅のホームに立っていた、みたいなことって現実にもありますよね。そういう作品内で人物が体感する時間感覚と、読者が作品を読んで体感する時間感覚を一致させることができればどんな感情にでも感情移入できる、と僕は思っていて、そのためにセリフの量を調整する感覚です。僕と打ち合わせしてる作家さんは「吹き出しの位置をもう少し上に、1cm上に」とか細かいことよく言われていると思うんですけど、それは作中内時間と読者の時間を一致させたいからなんですよね。
鍛治 その考え方は面白い。僕にはなかった感覚です。
村松 共感を得やすい人物や状況とか、共感されやすい運命を持っているキャラクターもいますけど、共感しづらい人でも共感していることがあるなと思って。たとえば、ヒッチコックが制作した映画に登場する主人公って、大体が殺人犯なんですよね。殺人犯が「やべえ、犯罪がバレる」っていうシーンを、僕は感情移入しながら見ていたりして。「なんで共感できるんだろうな」と考えたときに、キャラクターの体感時間とシナリオが進む時間が一致していればいいんじゃないかなと思ったんです。初めて言葉にしましたけど、そういう部分をWebtoonだと相当気を付けてるんだなと思いましたね。
鍛治 勉強になります。今まで僕はそういう考え方で作っていなかったので。
村松 僕もいい時間でした。
鍛治 自分の考えを言語化するのも大事ですね。
経験のあるマンガ編集者、ADを募集中!

現在『StudioZOON』では、経験のあるマンガ編集者を募集しています。この記事で興味を持った方は、ぜひ一度こちらをチェックしてみてください。
https://cyber-z.co.jp/recruit/entry/studiozoon_contents.html
お気軽にDMも受け付けております。
村松 充裕 (@yogoharu5535)
萩原 猛 (@yajin)
鍛治 健人 (@SE7EN_KENT)
StudioZOON(@zoon_studio)

不明点などがあれば以下までお気軽にお問い合わせください。
株式会社CyberZ 広報:城戸梨沙
press@cyber-z.co.jp
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
