
ユニットよもやま話
ガングリフォンをボードウォーゲームに落とし込むにあたり、さすがにTVゲームのままというわけにはいきませんでした。TVゲームでは主人公機のHPを極端に高くしないと無理ゲーになりますが、ウォーゲームではそも主人公機というものがおらず、どの機体も全体の中の1機でしかないので、より現実的なデザインにする必要があります。
以下HIGH-MACSに登場するユニットの中で、主にAWGSに絞ってどのようにデザインされたか等について、書いていきたいと思います。(AFTA軍は『HIGH-MACS Tactics』のセットに含まれていません)
日独HIGH-MACS対決①
まずは日本が誇るHIGH-MACS『12式装甲歩行戦闘車』と、ドイツのHIGH-MACS『ヤークトパンター』の当ゲームにおける個性の違いについてです。

12式の主武装について、当ゲームでは105mm砲装備の設定を採用しています。3次元機動のために重量を削るという意味合いと、何より地上では豆鉄砲でも空中からは脅威というバランスの方が、より「らしい」と思ったからです。
一方のヤークトパンターですが、主武装は30mm機関砲となっています。
本家ガングリフォンではどんなに火力の弱い兵器でも少しずつHPが削れるため、素早い敵からの機関砲は脅威でしかありません。しかしこのゲームには装甲の概念があるので、基本的に撃ち合いでヤークトパンターが勝つ見込みはゼロです。機関砲が12式の正面装甲を抜いて破壊するというのはおおよそ現実的ではないからです。
その代わり両腕30mm装備は対地攻撃における制圧能力においては12式以上となっています。
上記の理由から、このゲームにおける互いの関係は、地上部隊を狙うヤークトパンターと、それを迎え撃つ12式という図式です。
ただし地上にいる12式に対してならば、ヤークトパンターは上空から破壊しうるだけの力があります。戦車同様、AWGSの上面装甲も薄く設定されているためです。
ガングリ好きとしてはHIGH-MACS同士のドッグファイトのような戦いを期待すると思うのですが、このゲームでは戦闘機と攻撃機の関係に近いかもしれません。
しかしそんな不満を解消してくれるのが、ミハエル・ハルトマン仕様のヤークトパンターです。
日独HIGH-MACS対決②
みんな大好き黒いチューリップ。いわゆるライバル機的な位置づけでガングリフォン2に登場します。

ドイツのエース、ミハエル・ハルトマン(以下MH)仕様のヤークトパンターは、両腕に105mm砲が装備されています。それだけで12式に対して互角以上の戦いができるようになっているのですが、MH仕様はパイロットの能力も加味したパラメーターとなっており、高機動力に加えて、回避値も高く設定してあります。
当然重量の問題が出てくるはずなので、KEM(誘導弾)の弾薬指数(弾切れに影響)は低くして設計上のバランスを取っています。
要は完全なドッグファイト・カスタムというわけです。
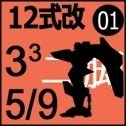
これに対抗するのが日本の12式装甲歩行戦闘車改です。
ヤークトパンターのように砲2門というわけにはいきませんが、120mm砲装備により火力が強化され、防御力もアップしています。
12式改で一番の特徴は飛行時間の向上です。12式やヤークトパンターが2ターンの滞空が限界なのに対し、12式改は3ターンの滞空が可能です。これは上空の占位が勝敗を分けるHIGH-MACS同士の戦いにおいて非常に有効ですが、その一方で連続でのジャンプ回数は12式やヤークトパンターの3回から2回に減っています。TVゲームにはない要素ですが、オリジナル設定にある行動時間の弱点を擬似的に再現しています。
また飛行時間は延びたものの高機動力はやや12式に劣るため、1ターンで移動できる範囲は若干狭くなります。
12式に比べて12式改は、パワフルだけどスタミナ不足。火力と防御力のアップにより、地上戦闘においては十分な汎用性を保持しているのが特徴。(当ゲームにおいては、飛行能力を失ったスエズ運河攻防戦で証明されます)
12式改とヤークトパンターMHカスタム。この両機体が単騎で戦うとどうなるかは、当ゲームの練習用シナリオ『兵棋演習』で確かめてみて下さい。
Autruche

ダチョウの名を冠するフランスのAWGS。ガングリフォンでは貴重な逆間接がなんともおしゃれな機体ですが、歩行形式のAWGSの中では最速の移動力7を誇ります。
その分装甲や耐久力は弱め。回避能力は高く、このゲームにおける位置づけは軽AWGSとしました。
通常火器が弱いものの、KEMを4基装備し、遠距離からの攻撃力は十分。
ただし火力支援に特化したロシアのBMX等と比べるとKEMの弾切れが起こりやすいです。
原作では比較的安価なAWGSとして、中東や北アフリカにも多く輸出されていると解説されています。実際このゲームでも通常歩行の移動力の高さやKEM主体の武装は、広大な砂漠での戦闘に最適です。
火力支援から偵察、或いはソフトターゲットへの強襲など、幅広い任務をこなせるAWGSと言えるでしょう。
ティーガー歩行戦闘車

ドイツが誇る四脚型重AWGS。
長年の開発実績の末、ようやく正式採用されたラインメタル社の140mm砲に加え、エレファントと並ぶ装甲値『4』はこのゲーム最強。装甲を抜くにはかなり肉薄する必要があるでしょう。
その代わり耐久値は低めに設定されているので、装甲さえ抜ければ意外と脆いです。
欠点は足の遅さと、行進間射撃ができないこと。そのため機動戦には向きません。それら欠点を補うローラータイプ(ストゥームティーガー)は原作でも脅威でしたが、このゲームでもそれは同じです。
KEMを装備していないのは欠点といえば欠点ですが、それも砲と装甲に自信があればこそ。無数のKEMを装甲で弾きながら、重たい体躯でゆっくり確実に接近して140mmをぶち込む。オットコ前な機体なのです。
レオパルト3
今回はAWGSではなく戦車ですが、恐らくガングリフォンという作品を越えて有名になってしまったセリフ「90式はブリキ缶だぜ」でお馴染みなので扱ってみました。

セリフからはまるで90式がダメ戦車であるかのような印象ですが、実はちょっと違います。なぜならガングリフォンに登場する戦車で唯一140mm砲を搭載しているのがこのレオパルト3であり、同じ状況ならM1であろうとメルカバであろうと「ブリキ缶」だったと思われるからです。
当ゲームのCRTにおいても、140mmなら戦車の装甲を抜けるけど120mmだと抜けないという距離が一部存在します。ガングリフォンのOPが正にその距離だったとすれば、あの結果は致し方なしと言えます。
勝利するには数で距離を詰めるしかありませんが、日本外人部隊という無理筋でハリコフくんだりに(中国の圧力で?)来させられている状況では難しかったのではないかと。
ちなみにガングリフォン世界においては、AWGSでさえ140mmを装備しているのは多脚型のみです。それだけ反動が強いということなのか、重量的なものなのかは分かりませんが、そんなものを戦車に載せて運用するドイツ。
ガングリ世界におけるドイツは現実以上にドイツなのがまた素敵なのです。
PT5

せっかくなのでもう一つ、実際にはない架空の戦車ということで取り上げておきます。
ただこれに関しては「スイス陸軍が予測して、発表したもの(ガングリフォン コンプリートファイルより)」ということですが、元ネタが見つからなかったので適当な戦車(具体的にはT-95)のデザインを元にでっち上げています。
これに限らずユニットのシルエットに関しては作り始めの頃に割と雑に作ったものが結局最後までそのままだったりしているものもあるので、造形にこだわる方のお叱りを受けてしまうかもしれません。ご勘弁を。
エレファント

アフリカでの運用を考えて開発された南アフリカの四脚型重AWGS。ドイツのティーガー歩行戦闘車と同様に140mm砲を装備していますが、南アフリカ製(機体設計はイギリスが協力)であること以外は詳しい解説がありません。
ただ見た目にもかなりの長砲身なので、CRTでもより長射程という設定でパラメーターを組んでいます。(その代わり取り回しの悪さを考慮し、近い距離での命中精度が少し劣ります)
何よりの魅力はティーガーと同じ装甲値4に加え、耐久力に至ってはこのゲーム最強の4。正に歩く要塞です。
移動力2という遅さは一見致命的に思えますが、砂漠での運用に絞って考えると、コストの関係で二脚型のパンター(移動力5)と1ターンに進めるヘクス数は変わりません。
アフリカでの長距離移動を想定し、倉庫スペースにかなり容量を割いているとのこと。そのためなのか、大型機体の割にKEMの本数が少ないのは難点。或いはKEM自体がアフリカでは貴重で、装備をケチっているのかもしれません。
リットリオ

イタリアの六脚型AWGSリットリオ。
当ゲームにおいては装甲が軽AWGS並となっていますが、耐久値は並なので、Autrucheよりは耐えてくれます。
移動力4は一見物足りなく思えるものの、多脚型で4はこのゲーム随一となっており、移動コストの大きい険しい地形もスイスイ歩くことができます。この辺りは山岳地での運用を想定しているイタリアのお国柄。改めて原作設定の素晴らしさを感じます。
多脚型でありながら基本武装が120mmと貧弱ではあるものの、それも軽快さの裏返し。足を生かして高所を陣取り、KEMで葬る。アルピーニの神出鬼没ぶりが体現できる機体なのです。
14式装甲歩行車
リットリオを紹介した流れで、続いてはそのコピー品と言われる中国軍の14式装甲歩行車です。

リットリオと違って足の遅さ(移動力2)が目立ちますが、防御力はどうにか同じレベルに仕上げています。しかしサイズが大型化してしまったため被弾率が高く、総じて防御力は低いです。
もっともコピー品といっても155mm榴弾砲装備によりリットリオとは役割がまるで異なり、当ゲームにおいては残念ながら突破シナリオの車列としてのみ登場。榴弾砲が火を噴くことはありません。
この機体を本来の用途として使うとなるとマップ外からの支援砲撃という形になりますが、そうなるとそもユニットとして登場させる必要もなくなるため、このような扱いになりました。
同じような用途で、PEU軍側にはパンツァーハウビッツェ2000が登場します。
BMX歩行戦闘車 VS 13式装甲歩行車
本家とデッドコピーその2。ロシアのBMX歩行戦闘車と中国の13式装甲歩行車です。

リットリオと14式の関係とは違い、こちらは機体の役割まで一緒。どちらもKEMを主体とした遠距離攻撃を得意とします。
ただしBMXの装甲値『3』に対して13式は『2』。移動力も『4』に対して『3』。またサイズ的にも車高を徹底的に抑えたBMXに比べて13式は全く収まっておらず、そもそもメイン武装のKEMからして13式のものは命中精度の面で劣ります。
このように、これでもかというぐらいの劣化版の仕上がりは、原作が90年代のゲームということで、中国軍にまだ可愛げがあったということ。更に言えばロシア軍を過大評価していたとも、今となっては言えるかもしれません。
BMX-30高射機関砲

BMXの対空バージョン『BMX-30高射機関砲』です。
リアクティブ・アーマーがない分防御力が落ちるものの、それでも13式と同レベル。KEMではなく、通常の対空ミサイルを装備しているためHIGH-MACSに対しては火力不足ですが、レーダー装備によりマップ外の攻撃ヘリに対して十分な防空能力が期待できます。
バリアント支援戦闘車両

このゲームでは貴重な対空用AWGSです。先のBMX-30も対空用ですが、そちらはミサイルと機関砲というオーソドックスなスタイルであるのに対し、このバリアントは機関砲の他に76mm高射砲を積んでいるのがミソ。
当ゲームにおいてHIGH-MACSは誘導兵器に対してはベラボーに強い上、機関砲程度ではビクともしません。つまり現代の対空兵器では対処が難しいのです。ところがこのバリアントの76mmなら、至近距離であればワンチャン可能性があるわけです。少なくとも博物館から高射砲を持ち出すよりはずっとマシでしょう。
このバリアントは対空に特化しているだけでなく、伝統的なスタイルという意味でも、バトル・オブ・ブリテンを経験した英国らしいAWGSと言えます。PEUの構想トライアルに敗れはしたものの、HIGH-MACSという異端の登場が再評価のきっかけとなるのかもしれません。
余談ですが、これらのことはドローンが活躍する今現在の戦争において、退役間際のゲパルト対空戦車が投入されていることをどこか思わせます。(追記:8月4日現在、ゲパルトはまだ前線には投入されていないようです。 →同月末に前線での動画が確認されました)
いったいガングリフォンはどこまで未来を予測すれば気が済むのか・・・
コラート戦闘歩行車

世界中の工場が集まるタイ。その工業力を生かしたパーツの寄せ集めのようなAWGS。実践配備テストの段階であることや、タイ自体が途中でAPCから離脱することもあり、活躍の場は正直あまりありません。
西側先進国の二脚型AWGSと比べて移動力が劣ることと、武装がデッドコピーのKEM頼みなのが難点。それでも中国製AWGSよりは頼りになります。
日独米 似たもの同士

最後に各陣営の二脚型AWGS3機体を紹介。
APCの9式装甲歩行戦闘車、PEUのパンター歩行戦闘車、AFTAのM16二脚歩行戦闘車です。(M16は今回のセットには含まれません)
当ゲームにおいてこの3機体はどれも性能が同じで、機体ごとの差別化がされていません。あまり細かい性能の違いを表現できないというデザイン上の都合もありますが、たとえば9式などはベースがアメリカの会社だったりするし、国を越えた企業統合が既に成されていた背景もあり、西側先進国が同時期に同じコンセプトで作るものにさほど差は出なかったのではというのもあります。
それでも当初は差別化を図るために9式だけ性能を落としていたのですが、改良を担当した小松製作所に敬意を表し、他2機体と同じ性能に引き上げています。(ただしパンターとM16にはローラー走行可能な高機動型が存在します)
メインの武装は120mmまたはKEMで、シナリオ毎に兵装が異なるのはこの3機体のみの特徴。140mmを載せられないのが欠点と言えば欠点ですが、あらゆる地形に対応できる汎用性に優れた機体となっています
さて、いかがだったでしょうか。
『HIGH-MACS Tactics』自体が(あまりのユニットの多さから)APC軍とPEU軍に絞ったという経緯があり、AFTA軍ユニットについてはほとんど触れていないのが個人的にも残念です。
M19-A1はかなり実用的で面白いAWGSだし、LOSAT(KEM装備の車両)など他の軍にはない個性もあるので、シナリオを作るのも楽しそうなのですが・・・
いつか『HIGH-MACS Tactics 2』が実現することがあったら、その時は「よもやま話2」でお目にかかりたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
