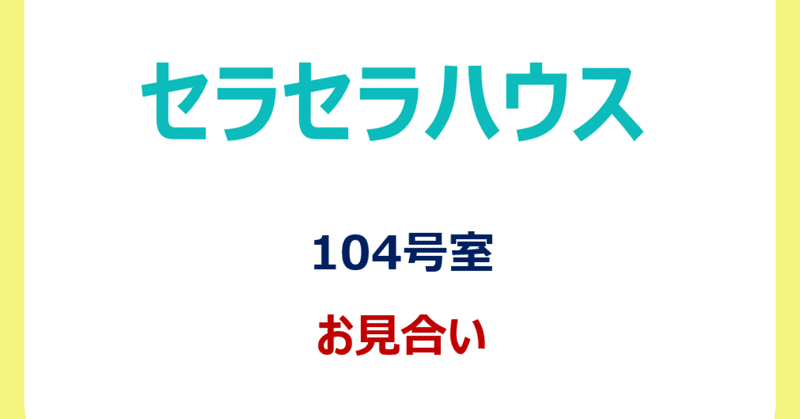
【短編小説シリーズ】セラセラハウス 104号室:お見合い
104号室
お見合い
鏡の中にスーツ姿の中年男性が立っている。紺色のスーツにグレーのストライプ柄のネクタイまでつけている。身体は54歳の割にすらっとしている。お腹も出ていない。どちらかというと、細身でしっかりと筋肉がついている方だ。それは、仕事柄、30年以上肉体労働を続けているからでもある。今着ているスーツも10年前のものだが、滅多に着る機会がないので新品のような状態だった。10年前と体格が変わっていないことに、平石正人はほっとした。
しかし、顔だけは10年分肌が黒くなっていた。皺が増えていることは言うまでもない。建設現場の仕事は、屋外にいることが多く、それが数十年も経つと、こんな濃い肌色になるのかと、正人は内心感心していた。正人の性格上、鏡の前にこんなに長い時間立っていること自体が珍しいことだが。
「スーツはやめようか」
独り言を言って、せっかくアイロンまでかけた上着を脱ごうとした時、電話がかかってきた。
『平石さん、出発しました?そろそろ出ないと間に合いませんよ。あ、そうだ。絶対スーツの方がいいわ』
正人は家に監視カメラでも回っているのかと、天井を見回した。何も見当たらない。さすが川原社長の奥様。70歳を超えても鋭い。タイミングまで分かっている。
しようがなく、「かしこまりました」と電話を切った。
「平石さん、一度だけでいいから、会ってみてほしいの」
紹介したい人がいると、連絡が来たのはもう3か月も前のことだった。ずっと断り続けてきたが、お正月に「もう帰る実家もないし、どうせ一人でテレビばかり見るやろ」と社長に呼び出され、人の家でお正月を迎えることになってしまった。今年はお年寄りに感染リスクがあるとかで、娘さんと孫たちも来ないことになったようだ。どうせテレビばかり見るのは社長の方だろうが、と思ったが本人には言わなかった。しかし、そこでまたこの話が上がってきたのだ。
「勘弁してくださいよ~ こっちもやること沢山あるんで」と何回言っても通じない。
家を出る時、廊下で108号室の水瀬さんに会った。住居歴の長い住民の一人だ。正人まではいかないが。
「あら~ 今日はどうしたんですか。珍しく~」
「う、打ち合わせが…」
正人はお見合いすることをばれた気がして逃げるように急いでマンションを出た。外に出て、マンションの方を振り向いてみた。この辺りも随分変ってきた。古い一軒家が並んでいた街に、ファミリー向けの高級マンションが次々と建てられ、正人が住んでいるマンションは古い方になっていた。
築34年のセラセラハウス。珍しい承和色(そがいろ)のタイルが地味に見えて地味ではない不思議な雰囲気を出している。今見ても、感無量になる。それもそうで、セラセラハウスは正人が初めて建設現場に入って、設計の段階から施工、そして竣工式まで参加した建物だった。
まだ時間に余裕があったので、正人は駅までいつもの街をゆっくり歩いて電車に乗った。あまりにも久しぶりに着るスーツが慣れなくて、席は空いているのに座る気にはならなかった。薄暗い地下を走る車両のドア窓にスーツ姿の中年男性が映っている。正人はそこに映っている自分の顔が他人のように思えた。実感がないまま長い歳月が経っていた。
上京して19歳に川原社長の会社に入った。現場でも雑務係だった正人に必要な資格を取るように時間と金を支援してくれたのも川原社長だった。今も事務職より現場で身体を使うのが好きだった。空白のような地面が人の身体と汗で少しずつ形になっていく。完成に近づいていく建物を見ると、正人は自分の子供が一人前になったかのような喜びを感じた。子供はいないので表現が合っているのかは分からないが。
初めての現場で、人が住む家というものを建てる楽しさを学んだ。無数の知らない誰かが毎日帰ってくる場所を作るのだ。それで、ついにセラセラハウスに入居した。34年間もあの家に住んでいることになる。その間、何回かリノベーション工事が入ったが、引っ越しはしなかった。
「お前、給料もそんなにけちってないから、もっと広い家に引っ越せばいいじゃないか」
社長に言われることも、ここ数年はなくなっていた。社長も諦めたようだ。一人暮らしには十分だし、家にいる時間もほとんどないので、無駄に広い家に住んでも意味がないと思った。自分には合わない服だ。このスーツのように。それは本音であり、本音ではないと、正人はふと気がついた。心のどこかで、ずっと待っていたかも知れない。それが、正人が突然気づいたことだった。
彼女が消えた。
あの家で、一時期一緒に住んでいた人がいた。平石ゆかり。家族ではない。苗字が一緒で、結婚しても苗字が変わらないのだと、22歳のまだ若い正人はなんだか嬉しく思っていた。そんなに沢山の時間を一緒に過ごしたわけでもなかった。短い恋だった。
心が締め付けられるほど好きで、家族のいないゆかりの家族になりたくて、出会ってすぐ一緒に住み始めた。夕方になると、二人が同じ家に帰ってきて、一緒に夕飯を食べて、テレビを見ながらげらげら笑ったり、週末には手を繋いで出かけたり、どうでもいい下らない話をしたり、世の中の恋人がみんなそうであるように、普通の恋をした。
「ただいまー」
彼女が家に帰ってくると、それだけで世界の照度が1,000ルクスは明るくなったかのように思えた。心の奥にずっと温かい宝石を抱いているような気分だった。そして、三つの季節を一緒に過ごして、ある日突然彼女は消えた。
事故にあったのではないかと色々調べたが、正人が分かったのは平石ゆかりが本名ではないという痛い事実だけだった。彼女はこの世から姿を消したかのようにどこにもいなかった。いつも呼んでいた名前が本名ではなかったので、事故にあっても分からないものだった。彼女は誰だったのだろう。その笑顔は嘘だっただろうか。そんなことを思いながら、心配は痛みに変わって、痛みは悲しみに変わって、悲しみは怒りに変わって、怒りはまた心配に変わって、最後はもう一度会いたいという気持ちも薄れて、会えなくてもいいからただ元気で生きていてほしいという祈りだけが残った。
昔の話だ。
当時は辛くて早く歳を取って認知症の爺になりたいと、若い正人は思っていた。まだ認知症の症状もないし、爺までにはいかないが、いつの間にかそれなりのオジサンになっていた。その後、また恋をしなかったわけでもない。だが、なぜか家族になるほど誰かと結ばれることはなかった。20代は彼女のことを忘れるためでもあって、仕事や資格取得に没頭していた。30代は仕事に、40代は親の介護やら趣味の週末畑に夢中になっていたら、いつの間にか50歳を過ぎていた。人生、束の間だ。
そして、今まで意識もしていなかったことに、正人は気づいたのだった。彼女の「ただいま」を待っていたのだと。
まさか。冗談じゃない。もう思い出すことすらないのに。
自分の心の底にある感情に戸惑う正人がいた。電車の窓に、目尻の皺が深い、肌の黒いオジサンが、似合わないスーツを着て揺れている。そして、自分ではないようなその中年男性がいきなり窓から消えた。電車のドアが開いて、世界の音とともにプラットフォームから人が入り込んできた。駅名を見て、正人は慌てて電車から降りた。
南青山の洒落た建物が目を引く道を歩きながら、正人は宝石について考えていた。指定された日本料理店は、裏道の建物の2階にあった。この階段を上がってドアを開けると、何かが変わるだろうか。ずっと温かかったあの宝石も歳を取るものだろうか。それとも… 正人はそのことを考えながら、2階に繋がる階段の踏面に足をのせた。
― お見合いはどうなりましたでしょうか ―
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
