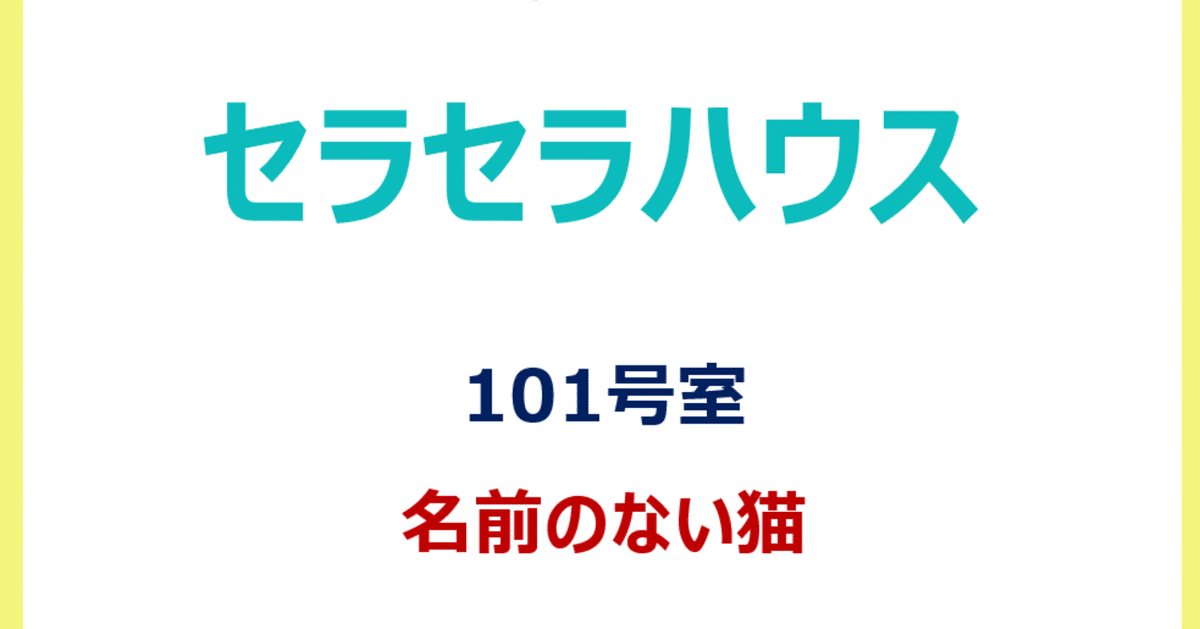
【短編小説シリーズ】セラセラハウス 101号室:名前のない猫
101号室
名前のない猫
ねーねー
彼女の声が聞こえて目を覚ました。昨夜飲みすぎたせいか頭が回らない。ここはどこだっけ。カーテンは見慣れた淡い青。ああ、お家だ。よかった。ちゃんと帰ってきたんだ。慌ててベッドの隣を確認した。見知らぬ女の子も連れてきていない。よかった。
ねー
また僕を呼ぶ声。1週間ぶりかな。先週は飲み屋を転々しているうちにどこかで出会った見知らぬ女の子を連れてきたのを彼女にばれてしまった。それから彼女は来てくれなかったのだ。ごめんね。
ねー
「はーい、いるよー」とベランダのドアを開けた。冬の朝の澄んだ空気が部屋に入り込んでくる。寒いけど、気持ちいい。彼女がベランダに来ていた。
「おはようー」
「…」
返事はなかった。僕は彼女の手を握って握手をした。ちゃんと手入れをしているのか、白くてきれい。前の彼女の手を思い出してしまう。彼女が手を引っ込める。やっぱり怒っていたのかな。なぜかちょっと嬉しい。
「今日も入ってこないの?」
彼女は無言のまま僕を見つめるだけだった。
「分かった。ちょっと待ってね。」
パジャマ姿でキッチンの方に行って、トーストが焼き上がるのを待ちながらコーヒーを入れた。その間、花柄のお皿に彼女の朝ご飯も用意した。
縁側ではないけど、1階だから、そのままベランダの敷居に座って、彼女と一緒に朝ご飯を食べた。少し肌寒くて肩に布団をかけたまま。目隠し用に植えられている木々が森の中だと想像しながら。小さな四角い青空も見える。
「おいしい?」
縁側に座って、彼女が聞いてきた。これは前の彼女との記憶である。僕たちは小さな縁側のある家に一緒に住んでいた。郊外にある、小さな川が流れる街だった。日曜日は二人ともたっぷり寝て、縁側に座って、日向ぼっこをしながらのんびり過ごしたりした。だるいくらい暖かくて、くすぐったいくらい甘い時間だった。子供の頃、お祭りで救った金魚のように、大切だった。
一緒に過ごし始めた頃、縁側の下で野良猫の子猫が見つかったことがあった。隙間に入り込んでしまった赤ちゃんを救えなかったのか、一匹の子猫だけが残されていた。
「ね、名前、どうする?」
と僕が尋ねると、彼女は「ふふふ」と笑って、
「蒼汰」と答えた。蒼汰は僕の名前。
「え~ 嫌だ。早く死んだら悲しすぎる」と僕。
「大丈夫。長生きするよ、きっと」と彼女。
「いや、無理!誰を呼んでるか分からなくなるし」
「猫の蒼汰を呼んでるのに、蒼汰が、はーいと答えたりとか?ふふふ」
なんとなく、そんな話をして、結局、名前を決めることができなかった。半分野良猫のように育てたから、家にいたりいなかったりしたけど、僕がその家を出る時、すでに大人になったあの猫には会えなかった。それから1年半が過ぎていた。
なぜ別れたかも忘れてしまった。大した理由はなかったかも知れない。その大した理由のなさが別れの原因になったかも知れない。大した理由がなかったから未だに思ってしまうのかも知れない。別れても別れなくてもよかったのかも知れない。でも、僕たちは別れる「選択」をした。お祭りで救った金魚はいつか死んでしまうことを、ある日突然悟ったかのように。
その時、僕の名前を付けていたら、彼女は今もあの猫を僕の名前で呼んでいたのだろうか。もしくは、名前を変えたのだろうか。僕の名前を付ければよかったと思う僕と、そうじゃなくてよかったと思う僕。二人の僕と、その間の無数の僕が、今も時々彼女を思い出している。会いたいと会いたくないの間の無数の選択肢を思い浮かべ、また消しながら。
その家を出て、ここに引っ越ししてきた。知らない街の、ありふれたマンションの一角。1階のこの部屋のベランダには、たまに野良猫が遊びに来た。名前のない猫。いつかこの部屋を出ると会えなくなるだろう。お互いにとって、今だけが光っている。
彼女は朝ご飯を食べ終えると満足げに伸びをして、去っていった。振り向くこともなく。軽い足取りで。微かな鼻歌が聞こえてきた。
にゃー
―101号室の蒼汰より―
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
