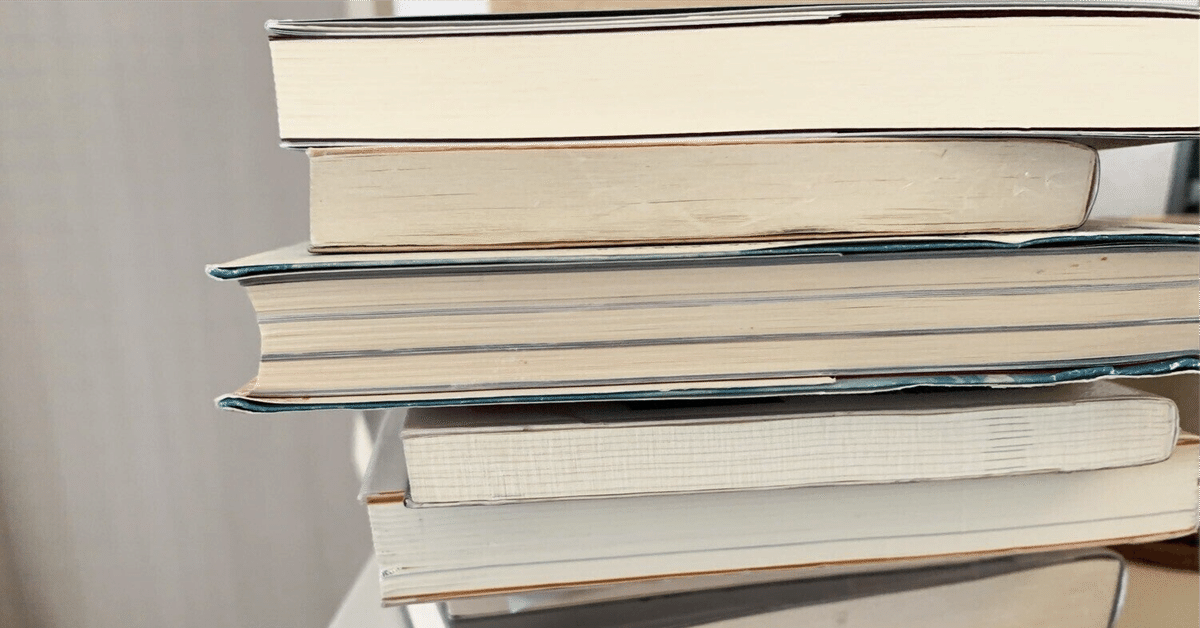
読書記録 スティーブン・ブラウン(2003)『ポストモダンマーケティング』
最近、ある物事を表現したときに、「内容は変えずとも、『ものの言い方、表現の仕方』を変えれば、聞き手から全く違う反応を引き出せたかもしれない」と考えさせられたことが、最近あった。「もちろん、良い内容の表現ができるのが一番良いのだけど、そうできなかったときの保険、またそうできたときに最大限伝えきるために、言い方、表現の仕方を考えねば…」、そういう気持ちになったその時、たまたま本書が目に留まり、読み返してみた。
もともとは社会人MBAで副読本として買った本だが、しばらく寝かせていた本である。
内容
原タイトルは"Forget the Customer. Develop Marketease", 邦訳サブタイトルは『「顧客志向」は捨ててしまえ!』という。「顧客第一」を前提とする旧来型のマーケティングの考え方に対し、様々な事例やマーケティングの歴史を踏まえながら批判を加え、”TEASE"という新しい枠組みを提唱する。
TEASEとは
Trickery(トリック):真実を誇張した仕掛けで売る *Trick Starを意識した表現
Exclusivity(限定):束の間と欠乏で供覧させて売る
Amplification(増幅):噂になっていることを噂にして売る
Secrecy(秘密):誘惑し追いかけさせて売る
Entertainment(エンタメ):想像を超えた驚きと変化の素早さで売る
の5つの要素を指している。要は顧客の役に立つことによってでなく、顧客を人間的な側面を刺激することで、モノを売ろうという考え方である。
作者がこのような考えを主張するのは、コトラーを中心とする従来型のマーケティングの考え方(4P, AIDMA etc)も、また当時浸透しつつあったEマーケティングも、次のような問題を露呈しつつあったためである。
社会に浸透しきったことで消費者には見抜かれ、かつ競合との差別化も難しくなり、有効性を失いつつあること
顧客に役に立とうとするあまり、顧客情報をひたすら収集し、顧客を「監視」するようになりつつあること
感想
正直な感想として、極端な事例を紹介しているように見え、これだけでモノを作れる・売れるという感想は持たなかった。ただし「モノを作るとき・売るとき、こういう顧客の人間的な側面に"も"配慮をしたほうがいいよ(これだけでは不十分なときもある)」という主張だと受け取った。その意味でTEASEには納得。私も表現をするときは、特にEntertaimentは取り入れたい。
おまけというか雑感
あとは、読んでいて印象に残った点をいくつか。
まず、訳者まえがきが面白かった。訳者は当時のEマーケティングの専門家であり、一見すると著者と対極の立場である。だが、その専門家が「Eマーケティングにも一定の限界があり、顧客の人間的な側面、マーケティングという行為の動的な側面を見ることも必要」と言っており、説得力がある。つまり、データ分析と仕組みだけでマーケティングのすべてを語ることはできない。そしてその語れない部分は大きいということである。この訳者前書きから約20年がたっているが(日本語訳は2005年)、個人的には、この指摘はいまも妥当すると思う。
また、Trickeryの事例であのD.Trumpが取り上げられている。顧客を幻惑させ交渉を妥結したり、場を盛り上げたりする天才ということである。そのTrump氏がその十数年後に米大統領になっているというのも、「選挙も一種のポストマーケティングなのですね」と痛感させられる。いやまあ、あの選挙ではSNSで投票者を誘導する等とかテクノロジーばかり注目されてましたが。
あとは、この本全体のスタイル。平たい会話風の文章になってはいたが、ともかく内容が頭に入ってきづらかった。一つには、取り上げられている事例が知らないものばかりだったという背景情報の問題もある。もう一つは、やや遠回しで、装飾が多い表現をしている印象がある。そうしたスタイルも、ポストモダン的ではないか…という感想を持った。そういうのは嫌いではないのですが、ちょっと鼻につくときもある。なんだったら、著者の提示する"TEASE"という枠組みすら、「顧客はそんな単純な存在ではないけど、ここはマーケ界隈の慣習に合わせ、読者の皆さんには、特別に分かりやすく説明してあげましょう…」という著者なりのTEASEな表現(今回だとExclusivelyだろうか)ではないかと感じでしまうのである。
感想よりも、雑感のほうに気合が入ってしまった。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
