
新しい言葉や概念を弄ぶ者等の罪
むやみに新語を作り出す人はとても罪深い人だ。
たいていの場合、その新語を使わなくても、今まで誰でも知っている言葉で説明できたりするのに、新語を使うと「何か違う概念が出てきたのか?」と、世の言説が混乱してしまうからだ。本当にやめてほしいなあと思う。
特に私の専門領域である組織や人事などは、正直言って、ほとんど新しい概念など必要なケースは少なく、既にある概念でいろいろな現象を説明できる領域の代表ではないか。この領域での新語はたいてい偽物だと思う(もちろん、まれに、本当に新しい価値ある新語・新概念はあるが)。
・・・
人類が発生して何万年たつのか分からないが、そもそもその悠久の年月の間に、ほとんどのことについては既に誰かが考えている。
長く生きれば生きるほど、今まで自分が発明したかと思っていたことが、知らぬ間に学んでいた誰かのアイデアの剽窃や看板の架け替えに過ぎないと分かり、何度絶望感を味わってきたか。残念ながら自分は天才などではなかった。
限りある僕らの短い一生と足りない能力で、先人たちが築き上げた知的資産に全く新しい何を付け加えられるだろうか。ニュートンですら「私が遠くを見渡せたのだとしたら、それは巨人の肩の上に乗っていたからだ」と言っている。
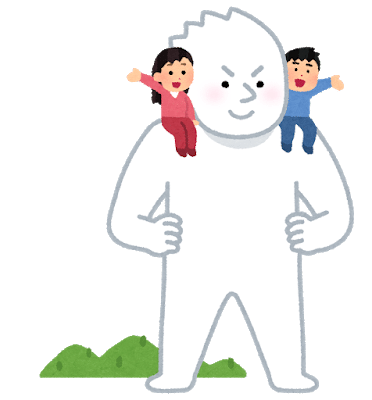
僕らができることは、過去からの知の巨人たちが積み上げて作ってきた知的資産に、ほんの少しだけ何か修正を加えたり、小さい積み石をしたりすることぐらいだろう。だからダメということではない。人類の知の営みというものの本質はそういうことではないかと言いたいだけだ。
一人ひとりの人間は、人類という大河の一滴である。別にそれでいいじゃないか。むしろ、大河の一部となり、大河に自分を同一視することができれば、永遠の命を手に入れることもできるのだから。
先人の知的資産を謙虚に学び、そこに自分で考えて価値があるのではないかと思うものを少しだけそっと付け足して、そしてそのことをきちんと晒して(どこを付け足したかとか)、衆目の評価、歴史の評価を受け、ダメなら忘れ去られ捨て去られ、良ければ生き残る。それでなければならない。
・・・
さて、ところが、この世の中にはすぐに「我、新発見を行えり」と言う輩が多い。自分が考えたことを、新しい概念や考え方だと称して、新しい言葉でパッケージングして、今までに無いものだと売り出す人々は山ほどいる。
世界は問題が山積みで、何か新しいことが出ると、画期的な解決ができるのではないかと期待するから「新しい」ということはもてはやされるから、売れたり、流行ったりする。お金も儲かるかもしれない。
それが本当に「新しいこと」ならいい。いい、というか、人類の知の進歩に貢献しているわけで、大変素晴らしい。本当に素晴らしい。
ただ、残念なことに、それはほとんどの場合、新しいことでもなんでもなく、もう既に考え尽くされたものを表面の飾りだけ変えたり、場合によっては換骨奪胎してより低レベルなものに改悪したものだったりする。「悪貨は良貨を駆逐する」の言葉通り、改悪された概念や言葉や解釈が流通すると、もともとの本当の概念の真意もそれに伴って誤解されてしまうことも多い。
例えば、ロイヤリティ(Loyaltyの方。ロイヤルティの方が正確らしい)とかコミットメントとかエンゲージメントとか、いろいろな人がいろいろ言っていて「ここが違う」「全然違う概念です」「全く新しい考え方です」とか言っている。それはそれでわかるし、確かに違うと言えば違うと思うが、いろいろ聞いてみての僕のイメージはこんな感じ。

いっしょやんけ!
あえて、取り立てて、新しさを騒ぎ立てるほどのことか・・・などと思う。
(このあたり、採用学研究所の伊達さんと共著を書いている最中なので、しばしお待ちください。適当に使われているいろいろな概念を整理しています。ちなみに、こんなすごい記事がありました)
逆に、同じ言葉を違う概念で勝手に使って、混乱させるケースもある。「自己実現」などは誤解されている概念の筆頭かもしれない(自分も完璧に理解しているか不安ですが)。
自己実現は、ユング(他にもマズローとかロジャーズとかあるが、僕はユングが好き)の原語では「self-realization」であり、個人の中で眠っていたり、あまり発揮されていない部分を自己の内に統合し、自分自身を完成させていくことを指す。別に「やりたいことをやろう」みたいな薄っぺらい意味ではない。
・・・
こういうのは無知や不勉強から来るものや、知っている癖にビジネスで新語を作ったものもあろう。どちらが罪悪かはわからない。
無知から来る場合、動機は善だろうから、その人に「それって新しくないですよ」と気づかせることは難しい。改善は行われない。地獄への道は善意で埋め尽くされている・・・。
意図的な場合は確かに詐欺のごとく憎むべき行為だと思うが、きちんと指摘すればそもそもその新概念・新語に忠誠心などないので、「てへぺろ」で逃げていくだろうから御し易いかもしれない。しかし、彼らはまた別の詐欺のネタを探し続けるだろう・・・。
・・・
結局、日々の態度としては、なにやら怪しげな新語・新概念が出てきた時には、知ったかぶりをせずにきちんとそれについて納得いくまで勉強するしかない。そして、それが「これまでの言葉や概念で容易に説明できる」&「付加された価値が少ない」という場合は、できる限りその言葉を使わないようにすることだろう。
新語・新概念のたぐいは結局いろいろ調べても提唱者すら曖昧な定義しかしていないこともあるので、その時は「わからないことがわかった」とする。知ったかぶりして、実はあまり意味のない新語・新概念の流行に乗ることは、最もやってはいけないことだ。不要な新語・新概念を作った者と同罪とも言える。
それぐらいしか対策が思い浮かばない。こんなnoteを書いている間にも、怪しい新語・新概念が続々と生まれているというのに・・・。
だから罪悪なのだと思うのだが。
嗚呼。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
