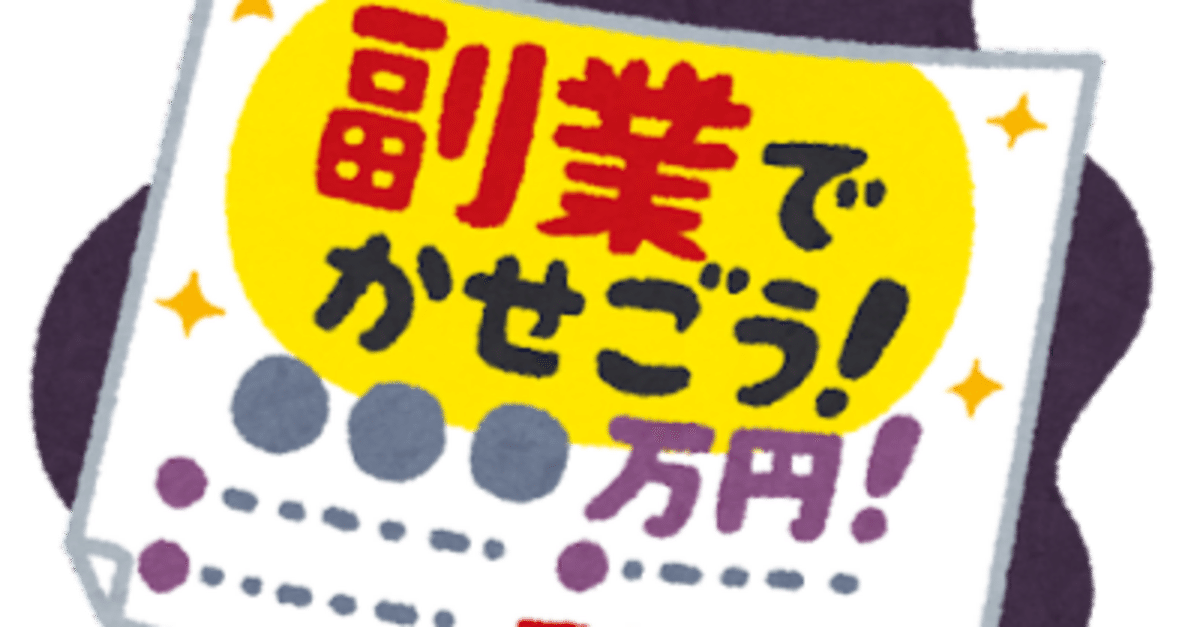
新しく副業・兼業制度導入企画を任された方向け:ざっくりガイドブック
こんにちわ。
本日は、
副業・兼業制度導入
について、Tips(?)的につらつらと書いてまいります。
終身雇用制度終了のお知らせから始まり、昨今では「人的資本経営」「エンゲージメント」「モザイクワーク」の流れを受け、市民権を得つつある「副業・兼業」
他方、実際の各企業に目を向けると、制度化しているのは、まだまだ一部であり、今後制度導入を検討しないといけない人事の方も多いのではないでしょうか?
また、副業・兼業制度導入については例外はあれど基本的には1社1導入と理解しており、直接的に本領域をご経験されていらっしゃる方は、あまり多くないという理解です。
その為、鶴の一声で
「オマエ、副業・兼業制度、ドウニュウ、キカク、シロ」
と指示命令を受けたまだ見ぬ同志の為に、参考になればと思い、本記事書き起こします。繰り返しになりますが参考になれば幸いの極み、です。

1.そもそも「副業・兼業」とは
色々な定義や解釈あろうかと思いますが、個人的にはざっくり以下の内容で概ね問題ないかと
副業・兼業は、二つ以上の仕事を掛け持つことをいいます。
副業・兼業は、企業に雇用される形で行うもの(正社員、パート・アルバイトなど)、自ら起業して事業主として行うもの、コンサルタントとして請負や委任といった形で行うものなど、さまざまな形態があります。
つまるところ「二つ以上の仕事を掛け持つ事」を指し、
・昼間は会社員
・夜はホスト
なんていうのも立派な副業・兼業になります。
2.副業・兼業の「労働者側」「企業側」のメリット・デメリット
新しいものを導入する際、何事においてもメリット・デメリットが存在します。
その為、副業・兼業における「労働者側」「企業側」のメリット・デメリットについても触れておきます。
■労働者側
・メリット
①離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、労働者が主体的にキャリアを形成することが出来る
②本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる。
③所得が増加する。
④本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。
・デメリット
①就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による 就業 時間や健康の管理も一定程度必要である。
②職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要である。
③1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の適用がない場合があることに留意が必要である。
■企業側
・メリット
①労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
②労働者の自律性・自主性を促すことができる。
③優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
④労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。
・デメリット
①必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応
②職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念
③副業・兼業先への人材流出
なげえ。長すぎる。
まあ端的に言えば、
労働者側:個の最大化、ネットワーク拡大、スキル向上
企業側:生産性向上、イノベーション・新規事業創出
等がメリットであるものの、ルール等をしっかり整備しないことには、
・従業員の健康棄損→レピュテーションリスク
・生産性低下
・人材流出
等にも繋がっちゃうよね☆ミ あたりの整理で良いかと。
3.副業・兼業制度 導入フロー
さて、前置きがやや長くなりましたが、本題の「副業・兼業制度」導入フローについて触れて参ります。
まず(身も蓋もないですが)、この書籍読めば上手くまとめられると思います。
※アフィリエイト連携等してないのでご安心を
副業兼業導入にあたり、数冊書籍に目を通しましたが、正直この1冊で十分!と言えるほど網羅的に分かりやすくまとまってます。
フローをまとめると以下のような図です。

①社内ポリシーの決定
②許可基準の決定
③管理方法の決定
④申請フローとルールの決定
⑤規定改定
この流れで一つ一つを自社の経営戦略/事業戦略、社内カルチャー等の要素と突合しながら検討の上まとめていけば導入まで至るかと。
③⑤についてはレギュレーション周りが関係して参りますので、この点は社会労務士の先生や法務と連携が必要になりますので、その点はご留意を。
また、これも身も蓋もないですが、副業兼業制度に「絶対の正解、ベストプラクティス」はありません。
副業兼業制度の目的や狙い(①社内ポリシー)や、雇用形態を有り無しとするか、在籍年数等の制限を設けるか(②許可基準)は、千差万別であり、各社によって本当に多種多様です。
この点は想定される影響等を勘案しながら、いくつかの選択肢を持ったうえで関係各位と調整していく必要があります。
また、忘れがちですが非常に重要なのは「ルール、FAQ」の明確化です。
この点を決めておかなければ待っているのはカオスワールドです。
聞いた話では副業兼業制度を導入した途端、社内にアイドルやYoutuberが増えた嘘みたいな話もあるみたいです。
体力尽きたので、ざっくりですがここまで。
気が向いたら加筆します。
何かの参考になれば幸いです!
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
