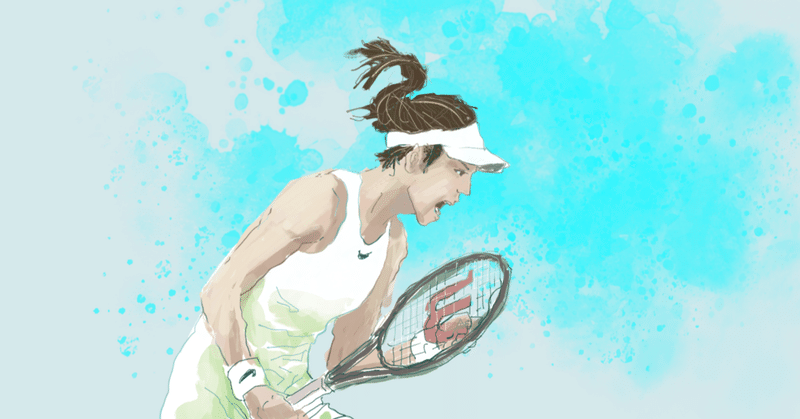
第5話:テニス
今年は久しぶりに夏合宿を行った。コロナで2年間は合宿も禁止、一昨年はインターハイも出来ず、昨年の夏は大会も練習も制限され、教員としては「楽」だったのですが、生徒は不完全燃焼だった。今年も危険かと思いつつ、でもやる時にやらねばいつできるかわからないと思い決行した。
合宿したところでテニスが格段にうまくなるわけでもない。「関係」が作れればそれでいいと考えている。初日の夜はみんなでカレーを作り、最終日にはスイカ割りをし、練習も合間に利き手と違う手でテニスさせたり。
もっとも、そんな細工をせずとも生徒は宿舎で、お風呂で、お互いを楽しんでいて、それは僕らが「関係」などと呼ぶより、もっと単純で純粋な「つながり」を作っているということになるのだと思う。
甲子園で優勝した仙台育英高校の須江監督の青春って、すごく密という言葉が話題になったが、コロナで直接的な接触が制限されてみると、人と人とが直に触れ合うことがいかに大切か教えられたような気がする。
合宿をやる前は、気の進まない感じの生徒もいたが、帰ってくると「冬合宿も春合宿もやろう」と言ったりしてきた。「セットするのがどんなに大変かわかってるか」と言ってやるのですが、「でも、やりたい」と駄々をこねる。孫の駄々をつい聞いてしまうおじいさんよろしく、やってみようかなどと気持ちが動いたりしないでもない。
僕は中学から大学まで軟式テニスをしていた。今で言うソフトテニス。教員になってからは硬式テニスの顧問をずっとしている。
ただ、僕が現役で経験したテニス生活は青春って、すごく密などという言葉とは全く違ったものだった。今の生徒が羨ましく思われるほど。もっと孤独で青春って、すごく苦しみ?だったような気がする。時代は変わったなあみたいな思い・・。
以下に主に高校時代のテニスの思い出を書こうと思うが、長文であり、個人的な思い出なので、皆さんと共有するのは難しいかもしれない。むしろ、部活で悩んでいる高校生に何かの参考になるかもしれないという意図で書いたものだとご承知いただきたい。
■テニスコート
僕が高校時代を過ごした学校のテニスコートは校庭に沿うようにしてある小さな山の上にあった。かつてこの山に北条氏の城があり、コートの位置は、その三ノ丸跡に当たる。コート3面が鬱蒼とした林に囲まれて、そこだけがぽっかりと平べったくなって存在していた。
素晴らしい環境ではあるが、僕らにとっては地獄のような場所で、すべての学校空間と切り離されていたため独特の雰囲気があった。神聖な場所などと言えば吹き出してしまう人がいるかもしれないが、コートと校庭をつなぐ数十段の階段を境として、聖域と下界とが分けられているということは部の伝統的な考えとして引き継がれてきていた。
コートに入る時は深々と挨拶をし、そこでは雑談をすることも笑うこともできなかった。指導してくれるコーチがいたわけでもなかったから、下級生の指導は技術面でも精神面でも上級生がすべて行った。
上下関係は厳しく、一種の封建体制ができあがっていたが、生徒同士がお互いの甘えを許さず、それ相応の厳しさを維持しようとすれば、それはそうならざるを得なかったのかもしれない。
■コート整備
一日の生活もテニス一色に染まっていた。朝早くからコート整備があり、昼休みも同様にコート整備に費やした。入学当時は15人いた1年生が、夏休みに入る前には3人になっていたからコート整備も楽ではない。大概は一人でローラーを引き、弁当を昼休みに食べられたためしもなかった。
夏は汗だくになればそれで済んだが、雨の日は小雨ならば傘を差してでもコート整備をした。スポンジとバケツを持って溜まった水を吸い取り、それからシ-トを敷きながらローラーをかけていく。
冬は冬で霜が降りるのを防ぐためにコートに筵を敷き詰めるので、それを畳んでからコート整備をしなければならない。筵は冬に入る前にリヤカーを引っ張って町内の農家をまわり、使えなくなったものをもらって来るのである。
最悪なのが冬の雨の翌朝。水たまりに張った氷を割って取り除き、スポンジで水を吸い取っていく。氷が張らずとも、朝、コートで水を扱うと、1時間目の授業が終わるまでは指が動かず、ノートを取ることもできなかった。
どんなことがあろうと、放課後は雨が降っていない限り、コートはボールが打てる状態にしておかなければならず、そうなっていない状態は許されなかった。
■練習
放課後もまた時間との戦いだった。授業が終わると、その20分後に練習が始まる。部室で着替え、山上まで駆け上がってネットを張り、ラインの汚れを整え、周辺の掃除をし、ボールの空調を確かめて、それから1キロほどのランニングコースを周って練習に間に合わなければならない。
20分しかないので、6時間目は時計とにらめっこをしながら、終業1分前になるとコソコソと授業道具を鞄に詰め、「起立」の号令とともに鞄を持って立ち上がり、「礼」の号令と同時に教室の扉を開けて廊下をダッシュする。
それでもそうしてバタバタとしているうちはまだよかったが、ランニングを終えて全員がコートを囲んで「体操」の号令を待つ瞬間は、何か異様な空気が漂う。「ああ、今日も始まるんだ」というどうしようもなく憂鬱な気分になった。それは本当にどうしようのない気持ちだった。
テニスが好きだ、などと思ったことも考えたこともなかった。そんなに憂鬱になりながらなぜ続けているのか、そんなことすら考えたことがなかった。ただそれは、そうしなければならない当然のこととして僕らの目の前にあったのである。
練習も厳しかった。くだらぬミスをしようものならクソミソに怒鳴られ、先輩と練習するときには、先輩がネットにかけたボールも、先輩がそれを拾う前にネットの向こうまでダッシュして拾いに行き、先輩に拾わせてはならなかった。練習ごとに相手をしてくれた先輩には挨拶に行き、アドバイスを受けた。
練習は日没まで続けられ、ボールが見えなくなるとトレーニングがあった。日の短い冬にはトレーニングの前に、グランドを20周ほど周り、家に帰るのは9時ころ。それから夕飯を食べ、ほとんど眠りながら翌日の予習を12時ころまでした。
入学当時は雨が降らないものかと考えたりしたが、待望の雨が降った日、トレーニングメニューが行われ、その激しさに1年生のほとんどが酸欠状態になり、吐いた。
休みの日の練習は基本的に午前練習だったが、8時半から2時頃まで行われ、その間、休憩は10分しかなかった。夏の練習はとりわけ悲惨で、3人しかいない1年生がすべての球拾いをしなければならない。
ボールは全部で30個程度しかないのに先輩の打つボールがカゴの中に用意されていない状態は許されず、「ファイトファイト」とか「ナイスボール」とか、声が一瞬でもとぎれる状態も許されなかった。したがって、練習の始めから終わりまで、休むことなくコートを走り回り、声を出し続けていなければならなかったのである。
休憩は6時間の練習で10分しかなく、その10分しか水を飲むことができなかった。今にして思えば非科学的なことだが、それを忠告してくれる指導者もいなかった。高校生がなんとか「テニスをする」ために必死でやっていた鍛錬の方法だったのである。しかし、乾ききってしまっては体が動かない。そこで練習前にタオルをビシャビシャにぬらしておき、練習の切れ目に、そのタオルの水を吸った。
■自主自立
ただ、こうした練習にそれでもついていけたのは、先輩も必死だったからだと思う。上級生だからといって気を抜くことはなく、下級生の面倒もよく見てくれた。部長は下級生を怒るように同級生を怒鳴りつけ容赦することはなかったし、怒鳴られた先輩も自分の非はきちっと認めた。
下級生を私用のために使うこともなく、時間に遅れることもなく、部長を盛り立てながら自分のすべきことを確実にやっていた。先輩が先輩らしく、一つ一つの行動や考え方は紳士的で大人びていた。あるいは大人になろうと努力していたのかもしれない。方法論はともかくとして自分達が自分達の部を作っているという誇りは確かにあったのだと思う。
夏休みのある日、ある学校が練習に来たことがあったが、昼休みにその学校の顧問の先生が、連れて来た生徒にビンタをくれていた。だらしがないということらしかった。その様子を見ながら、先生に怒られながらやっているなんてなんと情けない連中だと思った。
大袈裟な言い方だが、僕らにとって自分達の部は自分達の部であり、誰かの指図で動いているのではないという自覚はあった。今思えばそういう言い方自体に甘さがあるようにも思われるが、高校時代を振り返って唯一懐かしく思うことがあるとすれば、それはそういう一種の自主自立の気風の中に自分を置けたことである、などと思う。
■罰
かと言って、僕らが純粋に自主的に練習に取り組み、進んでつらい役目を引き受けていたかと言えば、決してそうでもなく、やはり罰は存在した。
声が出ていなければ声出しというものがあり、山の裏にある大きな池(運動場のトラックほどの大きさ)に連れて行かれ、その対岸に立たされて、練習中に出している掛け声やら自分の名前やら校歌や寮歌などを、声が潰れるまで怒鳴ったり歌ったりさせられた。
だらけていると先輩が判断したときは練習が終わってから1時間、コートに正座させられた。その間、先輩が一人一人説教をしてゆく。冬は土が冷たく足が凍え、夏は蚊にいいように刺された。1時間の正座は足にきつい。正座が終わり先輩が去ってしまうと僕らはヨロヨロと立ち上がって、やがてビリビリとしてくる足のシビレをベンチやフェンスにつかまって必死にこらえながら、笑っているのだか怒っているのだか分からない声で「チクショー」などと叫んでいた。
正座をさせられることについては確かに自分達の非を認めなければならないこともあったが、同時に納得の出来ないことも多かった。コートのラインが汚いとか、コートに葉っぱが落ちているとか、そんなことも理由になった。
手を抜いている訳ではなく、石灰を水にといてラインを引くわけで、どうしてもその雫が下に落ちてしまう。雨上がりの日には引いたラインが固まってくれず、流れて汚くなってしまうこともある。
また周りが木に囲まれたコートであったから木の葉などは掃除をするそばから落ちて来るのである。コートの入り口に生えている栃の木の実が練習中に落ちて来て地面でパカンと割れる、そんなコートなのであり、落ち葉一枚なくしておけというのは無理な注文であった。
しかしそういう言い訳を許してはくれなかった。そんなことが幾度あったか知れない。最初の正座の原因は入部して2、3日目、同じコートの隣で打ち合っていた先輩のボールが僕の方に逸れて来たので、ラケットでそのボールを先輩の方に送った、ただそれだけのためであった。しかしそれは正しくは、ボールを一度とめて「ボール行きます」と言って渡さなければならなかったのである。
また近眼の僕が廊下で先輩を見逃して挨拶をしなかったことや自転車がパンクしてコート整備に行けなかった時に偶然道で会った先輩ににこやかに挨拶したことなど、とにかく何でもが正座の原因となった。
■不合理への挑戦と挫折
僕らはそうしたことを不合理だと思った。そういう納得のいかないことを自分達はしないようにしなければならないと思った。
それで自分達の代になった時、話し合って罰則はなくそうと決めた。甘っちょろい理想であったのかもしれない。嫌なことばなのだが、水は低きに流れ、人は易きに流れると言う。後輩にもルーズな者も出始め、僕らはそれを合宿でOBに責められることになる。
その日、僕らは夜11時頃から正座をさせられコンコンと説教を聞かされた。最初は練習について、例えば日が暮れると練習を終えてしまうが自分達のころはボールが見えなくなればボールに石灰を塗って打ったものだとか、練習中に出している声が部室まで聞こえないから今日は練習は休みだと思って自分は帰ろうとした、など。
そのうち下級生のことに話が及び、「一年生がだらしがないが正座や声出しはやっているのか」と言う。僕が、こういう理由でやってはいない、と説明すると、そのことについてまたコンコンと説教が始まった。
そのうち同輩の一人がたまりかねて
「俺らの部なんだ。考えてやっているんだ。自分らで自分らの考えたようにやれないんなら俺はやめてやる」
とOBに盾ついて合宿所を飛び出して行ってしまった。
恰好良いと言えば恰好良いのだが、飛び出したと言っても正座をしていて足は既に感覚がない。一足踏み出しては転び、また一足踏み出しては転び、ほとんど這いずるようにして出て行ったのである。
もうOBなどそっちの気で、ヨロヨロした足で出て行ったそいつを、僕らもまたヨタヨタと転びながら追い掛けて合宿所を出た。
その時にはもうそいつの姿を見失っていたから僕らはそいつを捜して夜の街を走り回ることになる。駅へ走り、そいつの家へ走り、友達の家を回ったが、どこにも見当たらない。
仕方なくそいつの家まで戻り、だいぶ長いことしばらく黙ってそこに座り込んでいたが、結局会えぬまま合宿所に帰って来なければならなかった。何故こんなむなしいことをやっていなければならないのかとその時は思わずにはいられなかった。
高校のころを振り返ると、そこには何も楽しいことはなく、毎日何かに圧迫されているようなやり切れない気持ちが付きまとっている。苦しかったことも月日が経てば楽しい思い出になると言うが、僕にとっては嫌悪感ばかりが増して行くような気がする。
もっと違う在り方がなかったかと思い、あるいはまたそうするだけの勇気がなかったのかもしれない、とも思う。もっと単純にはいろいろなことに無知だったのだろう。どこをどう振り返ってみても後悔で頭がカッと熱くなる思いである。
■大学
だから引退するとき、やり終えたという解放感や充実感がまるでなかった。と同時にもうテニスはやりたくないと心から思った。
しかし不思議なことに、大学へ入学するとまず真っ先にテニスコートに足が向いてしまった。
何の気なしに練習の様子を見ていると、中から一人が出て来て「見に来たのなら打ってみろ」と言うので「何も持っていないから」と逃げようとすると「ラケットもウエアーも貸すから」と部室に連れて行かれ、それから2時間ほど乱打をしてもらった。その翌日にはもう入部が決まっていて、また4年間、テニスと付き合うことになってしまっていた。変なものだと思う。
大学時代についても触れておくと、これも悪戦苦闘の日々だった。
僕らの大学は決して強い方ではなく、関東のリーグの順位で真ん中ほどに位置しており、先輩の中には、4人のインハイ選手もいるが、また4人の初心者もいる、そんな構成の部であった。部員数は12人。軟式テニスの体育会なんかより硬式テニスの同好会に、という考え方が大学生では普通だったと言えるだろう。
ただ僕はここで初めて、テニス自体、勝つということの厳しさに気づかされた。入部して半年後、部内で一番うまい先輩とペアを組むことになるが、この先輩はむちゃくちゃ我侭放題の人だった。言うこととやることが余り一致せず、言いたいことを言い、やりたいことは頑としてやった。
関東大会ではベスト8、インハイも団体戦では決勝まで勝ち進み、さすがに技術面では素晴らしく、テニスの姿勢も厳しかった。
僕がミスをしようものなら、ボールを僕にぶつけ、ラケットをネットにたたきつけ、試合が終わってから正座をさせられた。殴られ蹴られ、僕は試合になると敵は対戦の相手ではなく、自分のペアだと思っていた。
恐ろしくて足がすくんで、ただそれだけのために負けた試合もあった。どんな試合でも負けることが許されない。先輩がミスをしても「俺のミスはお前が悪いからだ」というのが彼の理論だった。
しかしそんなことを2年間続けてゆくうちに、いろいろなことを彼から教わった。ゲームの組み立て方、カウントによる配球、ポイントの取り方…、そういうテニスに関するイロハを徹底的にたたきこまれた。
試合の反省はいつも将棋の棋士が対局後に棋譜を将棋盤で再現するように、3ゲーム目の4本目のこのカウントでお前の打ったこのコースに何の意味があるのか・・など、ゲームの最初から最後までを空で振り返らされた。恥ずかしながら高校時代には考えもしないことだった。
卒業後会って酒を飲むことがあっても余りお互い口もきかないが、僕は感謝している。勝つことの喜びを教えてもらい、インカレも2回戦で負けてしまったが、学生ランキングを持つ選手と最後まで勝敗のわからないいいゲームができた。テニスは面白いということを、僕はこの先輩を通して実感させてもらった。
■顧問として
こんな具合で、僕にとってテニスの経験は、振り返ればそれなりに意味のある経験であったが、決して「青春」という美しい冠詞を付け得るようなものではなかった。むしろ「苦難・困難」であり、「勝負」であり、「鍛錬」であったような気がする。
人間のやることは、楽しさだけでも成り立たない。一流の選手が「楽しさ」を言うことが多くなったが、それは血のにじむような努力をして、その競技の本質が「見えた」ときにそう言うのかもしれない。
でも、苦しさだけでも成り立たつはずもない。
若い頃は生徒にやはり厳しさを求めた。生徒が勝ちたいと思っているから厳しく練習をしている、と。
でもある時ふと思った。勝ちたいのは自分ではないか、と。すると、自分の目的のために生徒を使っていたのかもしれない、と。
そのときから自分がリードすることを抑え、「場」を作ることに専念するようにした。そこで「踊る」のは生徒だ、と。
探し求めるものが、楽しさの中にあるのか、苦しさの向こう側にあるのか、今もわからない。でも、笑顔が増え、人も増え、試合でも勝てるようになった。コロナで途絶えがちではあるが、卒業してからも一緒に酒を飲むことも多くなった。
敢えて言えば「こいつらと一緒に将来酒が飲めるか」という尺度が今の僕の顧問としての立ち位置と言えるかもしれない。それはひょっとしたら遅れて来た「青春って、密」ってことなのかもしれない、などと思ってみたりしている。
蛇足だが、この間も遊びに来るという卒業生に「お前のおごりで焼き肉行こう」と言ったら、「大学生におごらせて食べる焼肉なんか、おいしくないと思いますよ」と切り返された。多分、そのくらいの切り返しができる関係になると、酒を飲んでも楽しいんだろうと思う。
(土竜のひとりごと:第5話→2024加筆)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
