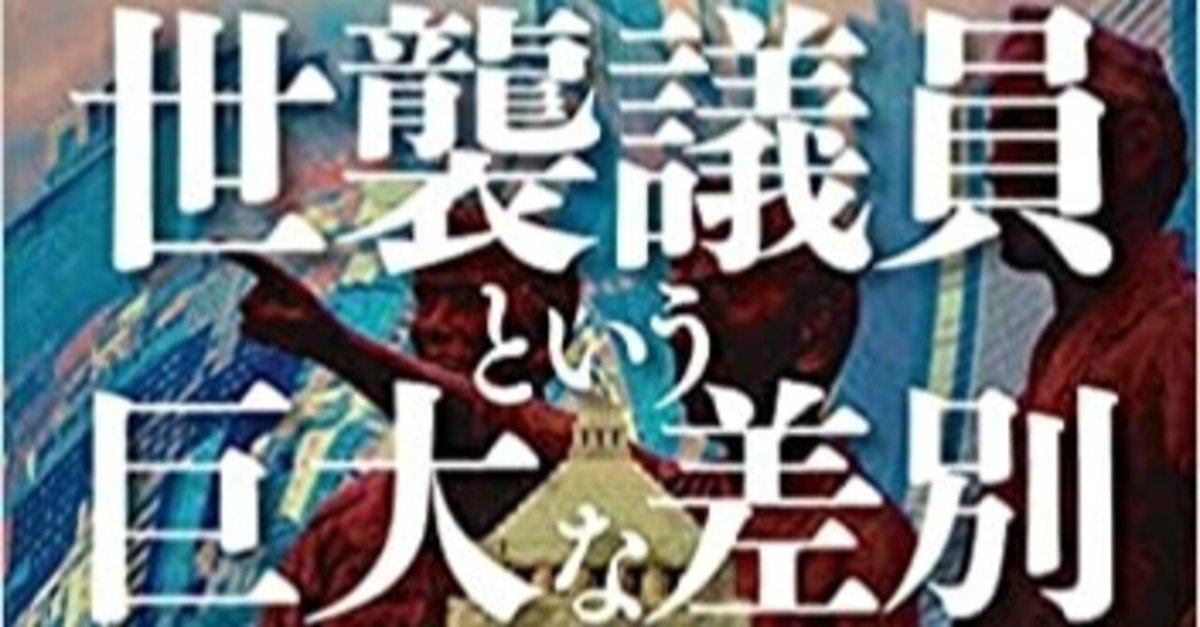
著書『世襲議員という巨大な差別』今だから読むべき!
中高生から読んでほしい、『世襲議員という巨大な差別』
今回は本の紹介です。紹介する本は、『世襲議員という巨大な差別』です。
実際の販売時期の前にも関わらず、Amazonのkindle unlimited(キンドルアンリミテッド:月額980円で、新刊を含む対象書籍が読み放題。登録時に「30日間の無料体験」、もしくは3カ月199円(通常3カ月2940円)で利用できる。)に著者が登録していることにも気合がうかがえます。
著者は、本noteの記事でもよく引用している、苫米地英人博士です。
苫米地博士のゴールは、「戦争と差別をなくす」ことがゴールであり、今回の書籍はその本気度が改めて感じさせられました。
選挙を前に是非一読をお勧めしたいと思います。
個人的には、中高生には必須のテキストにしてもらいたいと思うぐらいの本でした。
私の子どもがもうすぐ中学生なので、そろそろ本書を伝えたいなと思ったほどです。
一見選挙前に緊急で執筆された、文字数の少ない流行りものの本なのか!?という印象を、恥ずかしくも持ってしまった私は愚かでした・・・。
本書は、まず差別が何なのか、差別はどのようにして広がって行ったのか、というそもそも論を丁寧に解説してくれます。
内容が著者の個人的見解に偏りを持たせる印象を避けるため、昔の書籍の引用が多数ありますが、その分この本の信用度と価値があるということを示していると思えます。
そうして、我が日本国民は、差別が公然と行われていることに気がつかない状況下にあることを気づかせてくれます。
この本は人によっては、価値観180度ひっくり返るインパクトがあります。私はその中の一人でした。
本書を読んで、衝撃だった内容は、
・「士農工商」という概念についての新事実について 私は学校で「士農工商」という概念があるものだと習って生きてきたので、この真実を知って、愕然としました。
・四民平等が何故作られたのか 学校で習った印象では、旧幕府の世界は差別で窮屈な世界から、維新の志士たちが勇敢にも、その体制の風穴をあけ、人々を解放したというポジティブな印象を持っていました。その概念が180度、悲しくも覆りました。
・海外から見たら、日本は王朝に見える。 日本で生まれ育ったら全く気がつきませんが、世襲制の率を比べるとその割合の多さに驚きました。
<1995年~2016年までの各国の世襲議員率>
ドイツ:2%未満、アメリカ:6~8%、他の先進国:10%未満
・・・日本:25%
というように、海外から見ると日本という国家の仕組みは「支配層と非支配層に分けられている王朝」に見えるそうです。当然と言えば当然ですね。
・「親または祖父母が衆議院議員である(だった)人は、そうでない人の2300倍も当選しやすい」 この数値は聞いたことがありますが、著者がこの数値の計算式の根拠を示しています。
・世襲カースト制を国会から無くす案 シンプルに世襲議員に投票しないということがあげられています。また、他にも画期的な案があげられています。
他にも興味深い内容が詰め込まれています。
何故選挙に行きたくないのか。投票率が低い心理的理由について
個人的な感想ですが、この本を読んで、自分自身が昔から選挙というものに対して抱いている感情で、「選挙に行きたくない」という漠然とした理由のはっきりしない感情が氷解したような気がしました。
選挙に行くとは、個人的な思いとしてまるで、昔学校に行く時ような感覚に近い者がありました。
私は中学生や高校生の時に、一時期毎日学校に行くのが嫌で嫌で仕方がありませんでした。その時の感情は、理由もなく「無価値観、無気力、無感動、抑うつ感、悲壮感、気怠さ・・・」といったありとあらゆる感情に取りつかれていました。
高校生の時は、よく学校をさぼって海や山に一人出かけていたものでした。
その感情の背景は、「学習性無力感」に近いものがありました。
(※学習性無力感(がくしゅうせいむりょくかん)とは、長期にわたってストレスの回避困難な環境に置かれた人や動物は、その状況から逃れようとする努力すら行わなくなるという現象である。 有名な実験として、「逃げられないようにリードで犬をつなぎ、その犬の床に電極を流すと、最初は犬は痛みから必至で逃げようとする。しかし、いくらやっても逃げられないことを悟ると、犬は電極を抵抗なく受け続ける。つまり犬は「無力感」を学習したのだ」という残酷な実験があります。)
私は、中学校から懸命に勉強し、高校は進学校に進みました。中学校では勉強した分だけ成績が上がりましたが、高校に入ってから自分と同じかそれ以上の上位成績者と同じ集団に入ると、懸命に勉強しても殆ど成果があげられず、落ちこぼれました。やがて、ドロップアウトするという感じになったのです。
勉強をせず、学校に意味を見出せない言い訳として、一生懸命身を削って勉強して、偏差値の高い大学に入り、高給取りの仕事についても、その大人達がちっとも幸せに見えなかったことが大きな理由にありました。
頑張ってよいポジションを得ても、競争原理で常にせわしく働き、幸せではない。。。
しかし学校は偏差値を上げることをしきりに要求する。
学校をやめる勇気もなく、かといって勉強をする意味も分からない。意味もなくあてもなくぶらぶら日々を過ごしていました。気分は決して明るいわけではありません。日々、抑うつ状態は深刻化します。
そんな折に、同じ系列の進学校に通う友達が、勉強に意味を見出せず自ら死を選んでしまいました。
私はそいの友達の気持ちも理解できました。そうして、ますます学校に意味を見出せなく、日々を鬱々と過ごし続けていました。
そうした状況にいると、
何をしても変わらないし、自分の努力は無意味になる、という強い感覚。その感覚と同じような感覚が選挙に感じていると、自己分析しました。
つまり、本書で明かされた通り、私たちは見えない世襲制というカーストであり、差別という檻の中に知らない間に世代を渡って過ごしてきたので、
「何を期待しても無駄」「自分の一票が何の意味があるのだろうか…」「しょせん勝つ者がいつのものように決まる出来レース」という強い感覚が背景にあったように感じます。
その感覚を抑圧しながら、義務として毎回期待もせず投票に向かっていたという心境がありました。
個人的な回想をしてしまいましたが、この無力感は、程度の差はあれど多くの人々が抱いている一つの感覚なのではないかと思います。
この得体のしれない無力的な感覚が、全体の投票率が下がっているという理由の一つなのではと個人的には感じています。
つまり、私たち一人一人が「期待してもどうせ無駄」という「学習性無力感」を感じており、リードに繋がれて電極を流され続けている犬のように、その無力感を感じていること自体に気がついていないように思います。
実は、その「リード」などというものは、本書にあるように思い込みであり、巧妙に仕掛けられた見えないリードでしかない実体のない者なのだ、ということが本書で明らかになるのではないでしょうか。
それは自身が奴隷であったことに気がつくとも言え、目覚めのための、ショッキングな体験として人によっては感じるかもしれません。
世襲性は差別であり、現状維持
「世襲制は差別である」という著者の主張は、以前からよく聞いていたので、最初は新しく感じるものではなかったのですが、今回本書を読んで、その神髄が少し理解出来たような気がします。
本書を読み終わった後の感想は、「世襲制は差別だ」ということが分かり、そのことの重要性が垣間見えた気がします。
そして、世襲制は人間が最も好む現状維持という現象に結びついていることもわかります。
もちろん、本書が全て正しい主張であり、情報ではありませんが、日本に住んでいるのならば、本書はこの時期にこそ読むべき本の一冊で、一読の価値は必ずあるのではと思います。
このような本を書くとは、著者の高い抽象度の視点はもちろん、大きな勇気のいることだと感じました。
最後に本書からの引用で終わりたいと思います。
『よく、「人間が集団になれば必ず差別は発生する」と訳知り顔で言う人もいますが、それはウソです。歴史をよく見れば、差別は権力者が権力を維持するために意図して作っていることが分かってきます。 もちろん、自分と他人を比較して異質な物に対する戸惑いから彼我を分ける感情が湧く時もあるでしょう。しかし、それは好き嫌いの話であって、身分の上下の話には本来なりえません。 支配者はこの好き嫌いの感情、人ならば誰もが持つちょっとした嫌悪の感情に身分を張り付けて固定化することで人を縛るのです。
こんなものにいつまで従っているのですか?
権力者が作った自分勝手なルール、自らの支配の維持のためだけに他人を踏みつけにするルールに従う必要はもうありません。
中略
王は王のまま、平民は平民のまま、被差別民は被差別民の間mであれば支配層は未来永劫安泰です。つまり、差別の本質は現状維持なのです。』
本書には巻末付録に「明治から現在まで続く世襲家系図」があり、投票の参考になるのではないかと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
