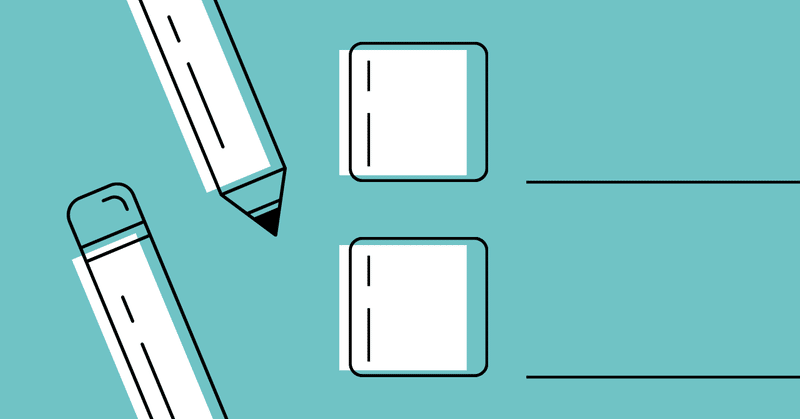
[方言の考え方(1)1960年代]
「方言ノイローゼの経験」
「標準語で話しましょう」とよびかけていたが、一朝一夕で改まるものではない。
うっかり鹿児島弁で返事して、同僚の笑いものにされる。
すっかり方言ノイローゼにかかってしまった。
「方言に対する認識」
1962年3月ごろの集団就職のシーズンでやってきた方の新聞記事である。
読んでみると当時の「方言」に対する認識をうかがえる。
まず、「標準語で話しましょう」と言った点である。当時の標準語は、地方から来た方々にとっては、難しいものであり、記事には、次のような話があった。
外からかかってきた電話もとらないし、話しかけられても短い返事をするだけだった。「生意気だ」「ぶあいそうだ」
[方言を話す人の気持ち]
標準語で話せない自分と方言を話す自分、そして、東京に就職した人たちは
次のような気持ちになっていたと書いてある。
地方に生まれたことをうらみたくなるものだ。
ここから、つまり、「集団就職」という時代から、標準語という言葉が出てきて、「方言ノイローゼ」、「方言コンプレックス」となっていたのかもしれない。
[外国人の日本語の発音について]
私は、外国語として日本語を勉強していて、日本語の発音には、人一倍気を使って生きてきた。今もそうではある。そして、「発音」と「個人性」、いわゆる、アイデンティティとの関連を考える必要がある。
[発音教育に関する認識]
どうしても新聞記事の内容と類似した「自分の発音は直すもの」と思っている人が多い。そして、自発的に、強い動機を持って、「発音をよくしたい」と思う人も多いだろう。そして、それに答えるために、教師は、
「一生懸命に直す」ことに集中することとなる。
しかし、それだけでは不十分であるだろう。
これからの発音教育は、必要なのか。必要でないのかを含めて、
どのようにしていくのが未来の教育の在り方であるか、考えていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
