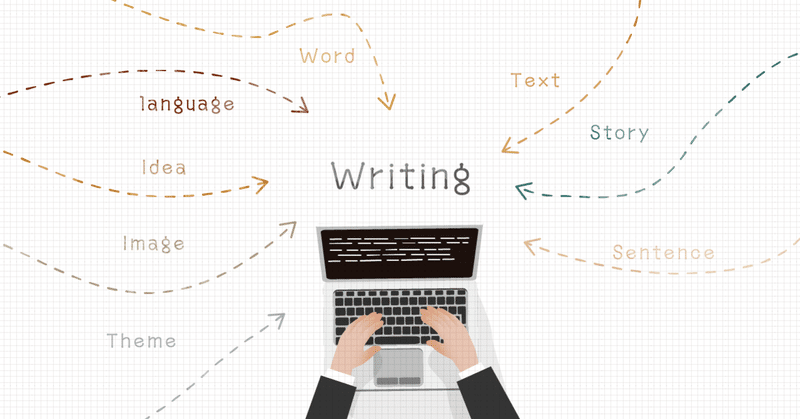
細部が9割。美しい原稿に仕上げる21の法則
編集者歴8年の池田園子と申します。「これさえ押さえておけば、美しく整った原稿に見える要素」をまとめてみました。原稿納品前や原稿確認時のチェックリストとしても使っていただけると思います。
■半角/全角
1.英数字を半角で統一する
同じ英語なのに半角と全角が混ざると整っていない印象に。数字も同様です。
例)WHO WHO
例)5月 5月
2.括弧を全角で統一する
例えば、全角の()と半角の()を混ぜると、ごちゃごちゃした印象を受けます。全角の「」よりも、半角の「」を書く方が手間かかりませんか? と思うことも。
括弧を使うならおすすめは全角です。全体が整って見えます。
■括弧
3.括弧内の括弧は慎重に選ぶ
例えば、鉤括弧「」内に同じ「」を入れてしまうと見づらいです。どこからどこまでが「」なのか? と戸惑います。「」内の括弧は二重鉤括弧『』にするのが一般的。
例)◯「父が回復したとき『よかったね』って、あなた泣いて喜んだよね」
× 「父が回復したとき「よかったね」って、あなた泣いて喜んだよね」
4.ダブルクォーテーションは対になる形で使う
引用を示すために存在するダブルクォーテーション(二重引用符)は、原稿内で「強調目的」で使われることが多いです。「“(左二重引用符)」で起こし、「”(右二重引用符)」で受けるのが本来の形です。なぜか下のように「”」で囲むケースを多く見かけます。
例)◯日本料理店で食べきれなかった炊き込みご飯を“おにぎり”にしてもらった。
× 日本料理店で食べきれなかった炊き込みご飯を”おにぎり”にしてもらった。
5.“”と""を区別する
ダブルクォーテーションと「ツーダッシュ(ダブルプライム/")」は似て非なるものです。
6.括弧内の最後に句点を使わない
句点は原則、文章の終わりにつけますが、括弧内の最後は例外です。ただし、感嘆符と疑問符はつけてもおかしくありません。
例)◯「顧客とのコミュニケーションが難しくなるのです」
× 「顧客とのコミュニケーションが難しくなるのです。」
例)◯「週末、鞍馬寺にお参りしてきました!」
◯「梅雨の時期でも川床料理を楽しめる宿を教えてもらえませんか?」
■辞書を引く/調べる
7.表記は正しく
一般的には小書き(平仮名/片仮名の小文字)を使わない言葉で、小書きを使っているケースをときどき目にします。迷ったときは辞書を引くことです。
例)◯新型コロナウイルス × 新型コロナウィルス
例)◯ウエストの位置に × ウェストの位置に
8.濁音がつく言葉を正しく書く
頭に英単語を思い浮かべると基本的には間違いません。
例)◯ベッド ×ベット →bed
例)◯バッグ ×バック →bag
9.会社名を正しく書く
下記のように英語+カタカナで構成される会社にときどきあるパターン。英語とカタカナの間が半角アキの場合があります。人名・社名をはじめとする固有名詞を誤るのは失礼です。間違いなく表記するために、公式サイトで確認するのを習慣にしたいところです。
例)株式会社PPP インターナショナル(存在しない会社です)
10.一般的ではない言葉に補足説明を添える
まだ普及しているとはいえない言葉や専門用語、英語の言葉などを原稿で使う際、気を遣う必要があります。浸透具合に応じて()で説明を補う方が親切なケースも。検索して、その言葉がどれくらい使われているか、他媒体の記事(公開年月も参照)では補足説明なしに使われているか否かを知り、都度対応を考えることが求められます。
「これはさすがに一般化したワードでしょう?」というものにまで()で説明を加えていると、“今”を捉えていない、少し遅れている印象を与えてしまいかねません。
例)DX IoT CRM SaaS ABM
■ケアレスミス
11.姓名を記載する際に表記ルールを守る
インタビュー原稿でインタビュイーの姓名を書くことがあります。姓と名の間に半角スペース、何も入れない(詰める)などの表記ルールは媒体によりさまざま。それを守っていなかったり、ふたり登場する際に表記がそれぞれ違ったりすると「推敲をしないのかな?」といった印象につながります。媒体の表記ルールまとめや過去記事のチェックで、このミスは防ぐことができます。
例)◯新垣 結衣さん 星野 源さん
例)× 新垣結衣さん 星野 源さん
12.句点のだぶりをなくす
時に、文末の句点がふたつ重なり、「。。」となっているのを見かけます。明らかな消し忘れなので「。」ひとつにすること。
13.疑問符と感嘆符の「後ろの表記ルール」を守る
媒体によって「?」や「!」の後は全角スペースを入れる、半角スペースを入れる、または何も入れない、といった表記ルールがあります。ある箇所では全角スペースを入れているのに、ある箇所では詰めているとなると、散漫な印象の原稿になります。
14.3点リーダーを統一する
文章の省略や文章に余韻を持たせたりする目的で使われる3点リーダー(…)。媒体によって「…」はふたつ重ねて「……」とする、「・・・」とする、などの表記ルールがあります。原稿内に「……」「・・・」など、違うタイプの3点リーダーが混じると、見た目の洗練度が下がります。
15.変換ミスを避ける
客観視しながら推敲を重ねることで防ぐことができます。同じ原稿をPCだとWordだけでなく、Google ドキュメントやテキストツールで見たり、もちろんスマホでも見たりと、媒体を変えながら見つめると気づきやすくなることも。
例)◯週刊文春 ×週間文春
例)◯不織布 ×腐食布
16.表記を統一する
「お客様」「お客さま」/「一人」「ひとり」/「友達」「友だち」など、同じ言葉でありながら表記が揺れている状態は避けたいです。ひとつの原稿内で表記は1種類にするのが原則です。
17.助詞の抜け漏れを防ぐ
助詞は文章を構成する必要な要素です。
例)◯弊社のサービスを利用していただくことが多かった。
例)× 弊社のサービス利用していただくことが多かった。
■さらに細やかな配慮
18.使う必要のある言葉だけを使う
原稿に頻出する言葉の代表格といえば、「ぜひ」「しっかり」「きちんと」「ちゃんと」などが思い当たります。
「ぜひ」は「どうあっても」「なにがなんでも」という強い勧めを意味する言葉ですが、そこまで圧強めに勧めなくても……? というシーンでも多々使われています。
「しっかり」「きちんと」「ちゃんと」は何かを言っているようで、たいしたことは言っていない、とてもふんわりした言葉です。政治家の方々が頻繁に口にする言葉でもありますね。
使わなくても意味が通じる言葉を削る方が、文章が整然として見えますし、スマートな印象を受けます。話し言葉にしても然りでしょう。
19.改行や見出しの下の幅を揃える
本来1行あけて改行するはずが、ときに2行あいている。ある見出しの下だけ、本文との間にやたらと大きなあきがある。そんな原稿を見ると「整っていないなあ」と感じます。本題ではなくても、「見直していないのかなあ」と気になる要素です(私がとても細かい性格なだけかもしれませんが)。
20.読点を使いすぎない
無闇に「、」を入れないことです。不自然なところで「、」が使われているとき、文章が「、」でやたらと細切れにされているとき、私は「この文章を声に出して読んでみてください。そこで息継ぎをしますか?」と指摘します。目で見るだけではなく、声に出して音としても考えることで、「、」の使い方はナチュラルになります。
21.文末表現を適宜変える
「〜します」が続いたり、隣接するパラグラフの各文末が「〜ます」になっていたりすると、原稿自体が単調に見えます。「〜です」を使ったり、体言止めを入れたり、変化をつけること。
■「神は細部に宿る」は原稿にもいえる
Webコンテンツの編集を8年ほどしていると、向き合ってきた原稿の量は相当なものです。
編プロからの受託業務、DRESS編集部での編集長業務、その他Webメディアの外部編集者業務など、いろいろな原稿と出会ってきました。
その過程で「もう少し細部にまで目が行き届いていれば、美しく整っていて、かつ誰(編集者・クライアント・読者)にとっても読みやすい原稿になるのに」と感じることが多々ありました。
「神は細部に宿る」という有名な言葉があります。原稿も細部にまで気を配ることで、「おお!」と感動するものになると私は考えています。そんな原稿が結局、「次」の仕事を運んでくるものだとも、思っています。
ここまで読んでくださった方にとって、少しでもお役に立てていれば幸いです。
***
編集・ライティング指導、承ります。
ご興味のある方はこちらまでご連絡ください。
オンラインでの打ち合わせをもとに、それぞれの方に合ったスタイルでの指導を考えます。
sono.ilangilang@gmail.com
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
