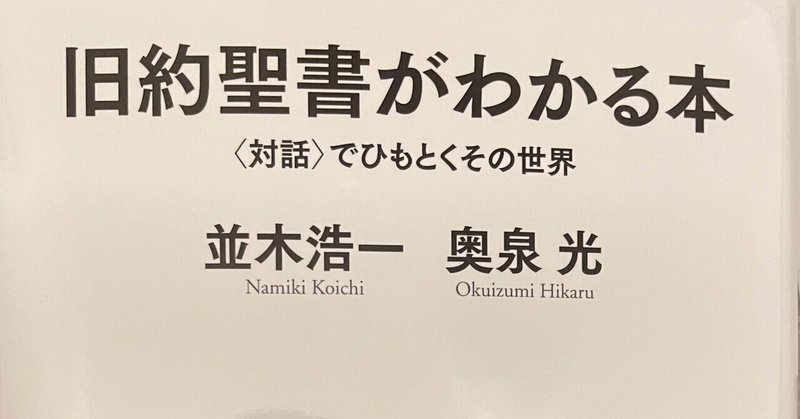
並木浩一・奥泉光『旧約聖書がわかる本 〈対話〉でひもとくその世界』
元・日本旧約学会会長の並木さんと小説家、奥泉光さんの対談形式による旧約聖書の入門書です。
西洋の思想を深く理解するには、ギリシアの思想とキリスト教の理解が重要であることは疑いを得ないことでしょう。しかし神々や英雄の物語として楽しめるギリシア神話や、イエスの生涯とその思想の伝播という大きな流れに貫かれている新約聖書と比べると、旧約聖書は格段に難解で近寄りにくい書物と思います。
この巨大な伽藍の内部を並木さんと奥泉さんは、分かりやすく、かつ刺激的にナビゲートしてくれます。例えば「創世記」冒頭。神が世界を創造する、有名なくだりですが、ここで奥泉さんが他の神話と比べて異なる雰囲気を感じとり「そもそもこれは神話と考えていいんでしょうか」と問いかけます。それを受けた並木さんの解釈を抜粋して引用します。
並木 そうじゃないですね。「神話」は起源を語るんですよ。…人間は「どのようにしてどうなったのか」ということに関心がある。神話はそのHowを語るのです。…ところが創世記にはHowの発想がない。「どのように」を関心の基本に置かない。これを書いた人も本当に6日間で天地が創造されたなんて考えてないと思います。彼の関心はこの世界、ことに人間をつくった存在者がいることにある。…
ギリシア神話や「古事記」のように混沌から神々や世界が生成されるのではなく、絶対的な外部にある神が世界を「つくる」という発想が旧約聖書の特異な点ですが、そこにはイスラエル民族の歴史的な経験が集約されている、と並木さんは述べます。
並木 …このテクストをつくったイスラエル民族は戦いに敗れて捕囚を経験し、その後も次々と諸大国によって支配されている。しかしこの民族は負けて強国の文明に巻き込まれても、それで終わりにはならないぞと踏ん張った。まず、彼らの神が大国の権力と神々の外に立ち、新しい民族を創造することに望みを託した。そのためには、神は諸民族の外に立たなくてはならない。
現代の我々の眼には荒唐無稽に映りかねない、天地創造の話にも、これだけの歴史的背景があったことに驚かされました。神は絶対的な外部の創造主として諸民族の上に立つ。だから人間同士には本質的な上下関係はない。これは当時の大国が取っていた、王権国家体制に対するアンチテーゼなのですが、基本的人権の考え方のベースでもあるでしょう。こうしたところからも西欧文明を理解するには、聖書の知識が不可欠であることが実感できます。
ユニークなのは、この絶対的外部存在である神は、単に人を力づくで支配のではなく、対話する存在であることです。本書の第3部では、ノアの方舟や、アブラハム、ヨナなどのエピソードから、神は行動を考え直すこともあり、人のとりなしに耳を傾ける存在であることが語られています。
旧約聖書は一見、非常に雑多な書物です。天地創設の神話であり、イスラエル国家とユダヤ人の歴史書であり、思想書であるばかりでなく、数々の詩篇や、官能の喜びを讃える雅歌もあります。こうした多種多様なテクスト群に接することで、読者一人ひとりがおのづから外的、内的対話を重ねることで神への理解を深めていく。その神と同様に旧約聖書も対話的存在であることが一連の対談を通して浮き彫りになっていくのは、非常にスリリングな読書体験でした。
そして「対話する神」への理解が深まったところでら本書のクライマックスである第4部「ヨブ記を読む」が読者の眼前に展開されていきます。ヨブ記を乱暴に要約すると、神からいきなり想像を絶するような苦難を与えられても信仰を捨てず、最後には神から以前に倍する栄誉と資産を与えられたヨブについての書、となるのですが、〈神は対話する存在である〉という前提で改めて読み解かれる「ヨブ記」は、突然神によって全てを奪われ、苦しめられ、しかもその理由については一切神から答えられることがないという、対話が理不尽に途絶した状態に投げ込まれた壮絶な不条理劇に他なりません。
そして、あくまで自分が高潔な存在であることを訴え、最後にはほとんど呪詛に近い言葉で神からの応答を望むヨブの言葉は、ドストエフスキーもかくやといわんばかりの迫力に満ちています。これまで本書での聖書の引用は主に新共同訳からだったのですが、第4部は全て並木さんが改めてテキストに向き合って、自ら訳しています。これまでの翻訳が話の流れをスムーズにするために、一見矛盾に見える表現を修正している箇所を、並木さんはそのまま原典通りに訳すことで、人間と神との関係性をくっきりとさせていることも見逃せません。
聖書の入門書はこれまでにも優れた本が多数出ていますが、これほど刺激的な入門書は読んだことがありません。随所に現在の社会に対する批評も織り込まれていて、単なる啓蒙書に終わっていないことも大切なポイントでしょう。旧約聖書は信仰の枠を超えて現在も息づいている書物であることを教えてくれた対談でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
