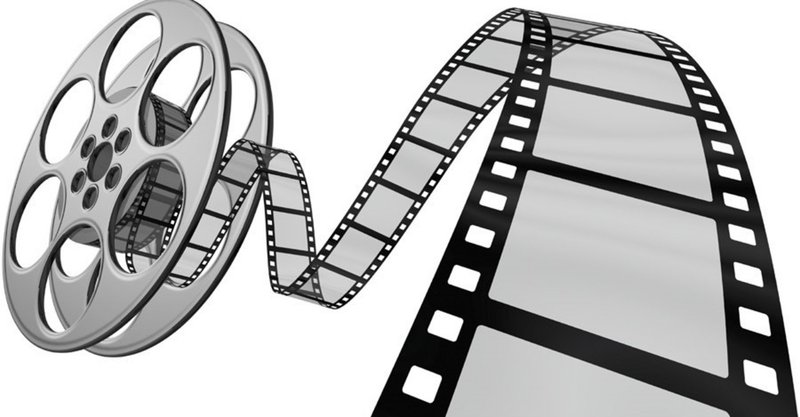
知っておいて損はない映画の基本6~ドキュメンタリー~
佐藤真監督のお言葉
「映像と録音テープに記録された事実の断片を批評的に再構成することで虚構を生み出し、その虚構によって、何らかの現実を批判的に受けとめようとする映像表現の総体である」
上の言葉は、早逝した日本のドキュメンタリー作家、佐藤真監督の言葉である。
ドキュメンタリー映画とはなんぞや?というクエスチョンに対して提示された彼なりの回答であり、今回の記事の内容をあっさりまとめてくれている言葉である。
以下の文章を読んでいただければ、その意味をはっきりと掴んでいただけるはずだ。
前提として
前回は「編集」そのものにどんな手法があるのかをタイプ別に紹介したが、今回はさらに発展させて、「編集」という行為はもちろん、映画をつくるという行為が「映画」というメディアにどのような性格を与えているかを考えていきたい。
結論から言ってしまえば映画製作の過程は、映画におけるドキュメンタリーとフィクションの境界線を亡きものにしてしまう、ということが言える。
これは決して小生の勝手な理論ではなく、これまで映画に貢献してきた数々の巨匠(特にドキュメンタリーを生業としていた監督)が言及してきた内容とも一致している。
丁度先日投稿した『ライク・サムワン・イン・ラブ』のアッバス・キアロスタミ監督もそのような映画の本質について深くまで探った監督である。
まず大前提として映画は誰かがつくった作品であり、そこにはその誰かの意図が多分に含まれていることは常に念頭に置いていただきたい。
「そんなの当たり前でい。馬鹿にしなさんな、若造」
という声が聞こえてきそうだが、では例えばあなたの好きな映画を誰が監督したかすぐに答えられるだろうか?
「そりゃ、すぐに分かるとも。いい加減に・・・」
という声がまたもや聞こえてきそうである。
では撮影は誰だろうか?
「撮影、、あの人だよ、えーっと」
では編集は?
「え?編集?」
役者は?脚本は?録音は?音楽は?プロデューサーは?
この手の質問は尽きることが無い。
エンドロールに名前が載っている人の数だけ問題が出せてしまうから。
もちろん、こういう質問に答えられない人に向けて
「君、本当はその映画好きじゃないでしょ?」
なんて嫌味ったらしく言うつもりは毛頭ない(現に小生だって役職のほとんどを答えられる映画など微々たる数しかないのだから)。
要は、映画をつくるという過程にはそれだけの人が関わっていて、それだけの人の意図が組み込まれている(もちろん監督の意図が最も強烈で強権的だが)ということを直感的に理解していただきたい。
そしてそれらの多くの意図の中でも、最も映画の印象に影響しやすく、クオリティに影響を及ぼす過程が「編集」なのである。
ポイント①「意図」
この意図という点が、フィクションとドキュメンタリーの差を極限まで埋める要因の一つである。
映画を撮るときは必ずカメラを構える。
カメラ無しに映画撮影をするのは無謀というかアホンダラである。
そしてカメラを置くということは非常に大きな意図をもってなされる。
普段何となく観ている映画の些細な一瞬の一カットであっても、それは監督の(あるいは他の誰かの)意図によってなされており、たとえ適当にカメラを置いたとしてもそこに映るものは限定されてしまう。
カメラによって四つの辺(フレーム)に区切られた「世界」=「我々の住んでいる世界から切り取った別の現実世界」を我々は見ているわけだ。
「世界」を所与のものとして受け取るならば映画を観ることは容易いが、なぜその「世界」を製作したのかを考え始めると映画は一気に不可解なものとなる。
分かりやすいのは会話の「切り返し」であろう。
例えば、A君とB君が話しているシーンを撮影するとき、普通はA君の顔がはっきり映っているショットとB君がはっきり映っているショットの2種類を使うだろう。
でも編集段階になると、残念ながら対面している2人の顔のショットを同時に一つの画面に映すことは、2画面で合成しない限りはできない。
だから編集ではどちらのショットを使うのか選択するわけだが、時にはA君が話しているショットを使い、時にはB君が話を聞いてうなづいているショットを使う。
つまり監督や編集がそこで何を映したいのか(A君の話している顔を見せたいのか、B君の反応を見せたいのか等)特権的に選んでいるわけだ。
選ばれなかったショットについては、つまりフレーム外の「世界」については観客が空想することはできても実際に観ることは不可能(フレーム外の「世界」を想像させようとするショットもあるが、話がややこしくなるから割愛)。
映画に映っているものには製作者の意図がふんだんに盛り込まれてることがお分かりいただけるかと思う。
そしてこの点は、フィクションでもドキュメンタリーでも同じことは言うまでもないだろう。
結局どちらも撮影と編集によってどこかが切り捨てられ、どこかが採用されているのだから。
ポイント②「記録性」
実写のフィクションもドキュメンタリーも、撮影対象にしているのは我々が生きているこの世界の、空間的かつ時間的な一部である。
どちらにせよ、この世界のいつか・どこかで本当に起こったことをカメラが記録したものを映画として構成している。
誰かが話している言葉が、脚本で予め決められた整ったセリフだとしても、その場でたまたま生まれたタジタジとした発話であったとしても大差はない。
その人がその時その場所でその言葉を発したという事実は変わらないのだから。
(お分かりだとは思うが、アニメは全く違う性格を持っている。いかんせんアニメは完全なる空想世界だからだ)
重要なのは、映画を構成している各ショットが「事実」であるということは、その集積である映画そのものが「真実」であることとは全くもって別の意味であるということだ。
この問題については、以前2本紹介しているマイケル・ムーアの記事でも触れているが、彼の映画こそそういう側面を備えている。
ド左翼のムーアが、アメリカのダメな部分とヨーロッパの素晴らしい部分を交互に編集することで、いかにもヨーロッパは凄いんだからアメリカも頑張ろうよと語りかけるような構造にしている。
それぞれのショットは確かに現実に即した事実なのだが、編集によって映る順番を組み替えるだけで如何にもアメリカが最悪な国のように見えてくる。
現実的には、もちろんアメリカにはダメな部分があれば素晴らしい部分もあるわけだが、ムーアの創った「世界」にはそれが映されていない。
完全なるムーアの主観によって形作られた「世界」がそこには映っているわけだ。
主観による真実や真理は、客観による真実や真理とは違う。
ある製作者の考える真実(世界はこうなのだと断定する思想)を押し付けられた「世界」を我々は観ているわけだ。
何度も言うが、この点でもフィクションとドキュメンタリーの差はないことが分かる。
ドキュメンタリー=本物と思いがちだが(部分的には確かにその通りだが)、編集され、構成された時点でそこには少なからぬ演出が入ることになってしまう。
どちらも現実の事実を集積して、製作者の主観による真実をつくろうとしているのだから。
まとめ
さて、それでは佐藤真監督のお言葉に回帰しよう。
「映像と録音テープに記録された事実の断片を批評的に再構成することで虚構を生み出し、その虚構によって、何らかの現実を批判的に受けとめようとする映像表現の総体である」
小生の説明が上手くいっていれば、彼の言葉がすんなりと頭に入って来たのではなかろうか?
ごく簡単にまとめれば、製作者の「意図」と「現実の記録」によって構成されているという点でドキュメンタリーとフィクションに差はない、ということだ。
佐藤真監督は早逝する直前まである本の執筆を進めていたらしい。
簡単な内容をまとめた自筆の文章が公開されているのだが、そこにはまさに「主観による世界しかありえないことを結論として導きたい」と書かれている。
さらに、昨今でさえ未だに騒がれることの多い、「やらせ問題」についても言及するつもりであったようだ。
一般的な人々はドキュメンタリー=現実であるという認識であろうが、彼はそこに疑問を投げかける。
現実信仰、事実主義に対して客観的事実の不在を武器に戦おうとしていたようである。
もしその本が完成していれば、少しは日本のメディアの現状も変わっていたのかもしれないと思うと歯がゆいばかりだ。
そんな金がありゃ映画館に映画を観に行って!
