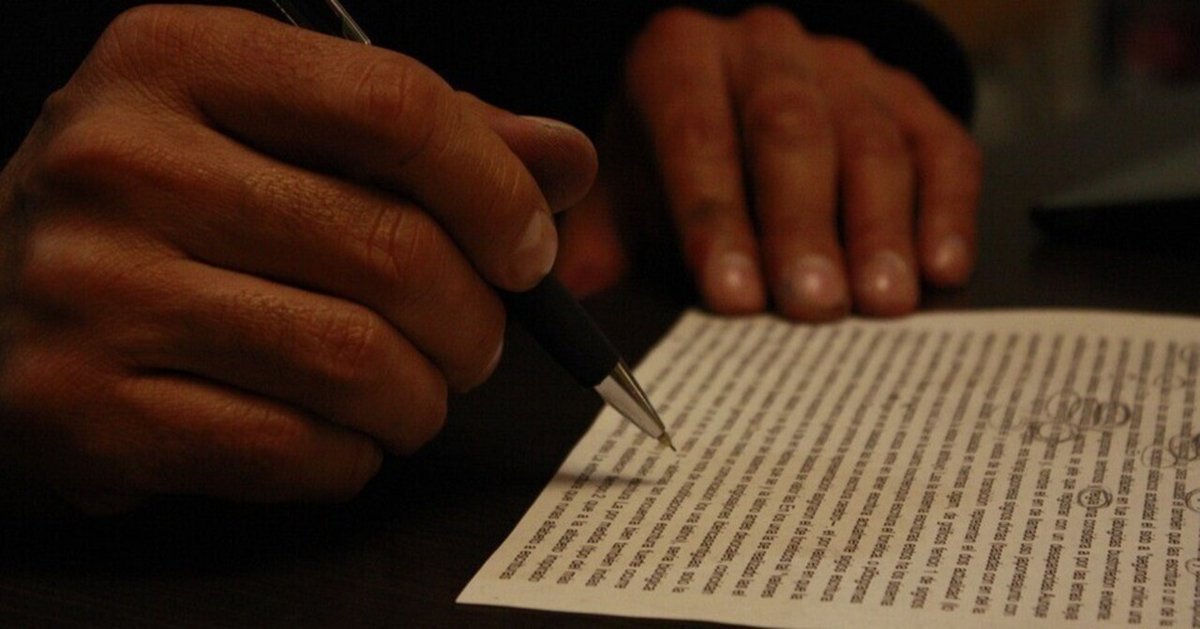
芸術行為とは何か?【Part4/8】
カフカ vs 父親
『逃避』
それは彼の父との確執に垣間見える。
実に有能な実務家であったまさに大人の世界に生きる彼の父親は彼のことを役立たずな存在として見ていた。
しかしカフカは父親の世界を否定したりそこから完全に逃避する事を考えてはおらず、幼年性の世界を理解してもらい、共存することを目指して努力した。
この親子の確執はまさに単なる親子喧嘩の次元を超越した文明の対立と呼べるだろう。
彼が父へ理解を促す為に書いた「父への手紙」の中で子供が夜に水を欲しがる場面がある。
父は水が欲しいと駄々をこねた子供に対して怒り、家から締め出してしまう場面がある。
しかしその実子供は喉が渇いていたのではなく、父との会話を求めていたのである。
子供は悪いことをしているという自覚はないために、水がほしいといえば締め出されるという条件付きの因果関係に陥ってしまい、「わからない、恐ろしい」という感情を抱くことになる。
ここにもみられるようにカフカの文学制作狙いは大人からの承認を受け、それぞれの世界を無意味化させて出会わせることであった。
カフカは自分の全作品に「父親の圏外への逃避の試み」と、このような願名をつけたいと思っていた。
彼にとって父親とは実の父親でありながら、当時の20世紀初頭の大変厳格な行動的な都市型社会、近代社会全体の体現者であった。
もともとユダヤ人は西欧の都市において、金融業、貿易などに関わって、財をなしていた。
更にこの時代のユダヤ人はユダヤ人の枠を超えて、西欧近代社会に同化することに活路を見出そうとしていたのである。
ナチスドイツはユダヤ教から離脱して西欧化する為、ドイツ社会のドイツ人への返還をめざし、こうしたユダヤ人をユダヤ人自身へ再度押し返す差別政策をとったのである。
いまだに封建的で旧弊な人種観を持つ当時のオーストリアではカフカの父親のようなユダヤ人は、ただ事業の成功にしか活路が見出せずにいたのである。
そのような時代において「幼年性」や「気まぐれ」などは到底許されるものではない。
子供らしさは子供時代に限定して肯定され、やがて克服されるべき対象なのである。
カフカの逃避とは父親の園内で、排除された者として生きることであった。
しかし逃避とは言えども彼の逃避は圏外へ完全に逃げて、作品も人格も逃避的存在として完結してしまう完全なる逃避とは異なっていた。
どのように生きても、どのように書いても、その結果に満足しえないのがカフカの逃避なのである。
「幼年性」とは大人の世界のように実体として完全なものにならない、つねに変化する気まぐれの世界である為、完結させることは文学への裏切り行為になってしまうのだ。
大人の世界に迎合する逃避は感傷的で表面的、大衆世界の共感を呼ぶ逃避であり、人間の根源の侵略という有罪性への明断な意識が欠落した逃避である。
カフカの逃避は文学を子供らしさの表出として打ち出しつつ、大人の制作品のように完結させないことを意味していた。
カフカのこの揺れ動く暖味さは自分を認めてくれそうにない権威から認めてもらうことを望んでいたが、彼にはこの権威を打ち倒す意志も、この権威に対抗する意志もなかった。
確固たる1つの個体として存在を認めさせるという主張的な態度ではなく、水がだんだんと染みていつの間にか少しずつ広がっていくような曖昧な態度を崩さないという方法で承認を得ようとしていた。
彼は近代人が忘れた根源的な存在の在り方を喚起する大切なものを提示してくれた。
『闘争』
マルクス主義的闘争観とは抑圧的な権威に対抗して、これを打ち倒す見方である。
これに対してバタイユは、「人間の本質は情熱的で気まぐれな欲望であるにも関わらず、共産主義はこれを拒否して生産活動に向かう欲求のみを重視した。」と批判している。
近代の後進性を克服するために共産主義は欲求中心主義に走った。
18世紀から20世紀にかけての政治革命が意味するものも、近代の生産活動の後進性克服の動きである。
資本主義と共産主義の対立は近代性への批判ではなく、近代化の先進性と後進性の対立でしかなかった。
共産主義の闘争とは欲求の充足度合が低い立場が充足度合の高い立場に対して挑んだ闘争であるが、カフカの闘争とは近代性そのものに対する闘争であった。
欲望に対する欲望の闘争である。
それを忠実に行なった為に気まぐれの闘争と呼んで良いだろう。
それは対象的ではないの闘争であり、父親にならない者と父親との闘争である。
父親になることは文学への、幼年性への、欲望への裏切りであったからである。
死と挫折
『死』
更に問題は死へと発展する。
カフカにとっての死は2つあった。
1つ目は個としての死、つまり肉体が死ぬことである。
カフカは1917年に結核にかかってから1924年に死ぬまでの7年間、自らの命を絶つ行為をせずに死の境地で文筆に専念した。
結核による病死、すなわち死と共に生きる日々を選択した。
個として自らを完結させる死は、完結しない生命の揺らぎへの裏切り行為である。
暖味状況としての死を、彼は限界体験としての死を生き続けた。
2つ目は死を生きるという死である。
彼にとっての「どのように存在しているか」という存在様態にとって大切なことは「曖昧さ」であった。
存在するものは何かしらの影響や関係の中にあり、物体それ自体として完結しているものは何もない。
自殺にも結び付けない、作品が作者とも結びつかない、常に曖昧に揺れ動き続ける態度が存在なのである。
自殺は近代的な死に方、個として完全に完結させる行為であり、完結しない文学(存在)というあり方への裏切り行為である。
死の瞬間を持続、死と生のはざまの中でこそ生の輝きを実感できるのだ。
人間の本質は気まぐれの欲求である。
自分らしさやキャラ、アイデンティティなどと言う固まった生の在り方などは幻想に過ぎなく、形の定まった大人としてではない、「生きている」という形のないままに存在する事が本質なのである。
人間の根底には曖昧な存在が常に流れている。
カフカは作品を作るという行為によってその存在に近づこうとしたが、それを達成するには挫折が必要であった。
完成されてしまっては「存在(揺らぎ)」とはならず、「存在者(作品)」として確立されてしまうからだ。
永遠に未完成であること、常に破壊されることこそが生きる事と重なるのである。
しかし作品へと結実できない「書く」という行為が彼にとっての二つ目の意味での死を生きることなのであった。
Part5へ
芸術行為とは何か?【Part5】|旅思想日記|note
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
