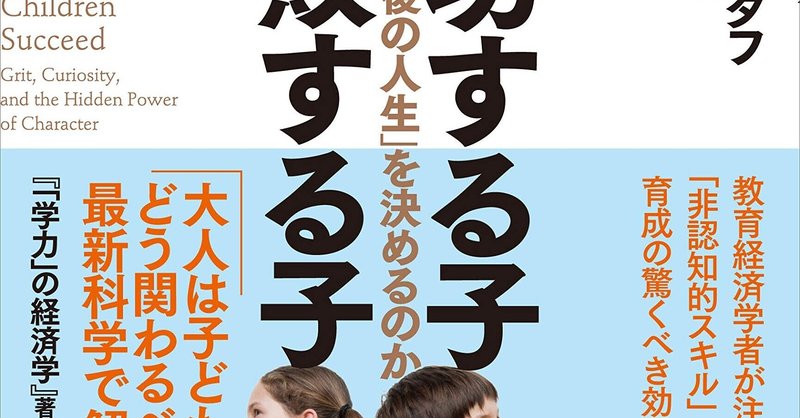
『成功する子 失敗する子-何が「その後の人生」を決めるのか』(ポール・タフ 著、高山真由美 訳、英治出版)
『成功する子 失敗する子――何が「その後の人生」を決めるのか』( ポール・タフ 著、英治出版、2013年)
https://www.amazon.co.jp/dp/4862761666
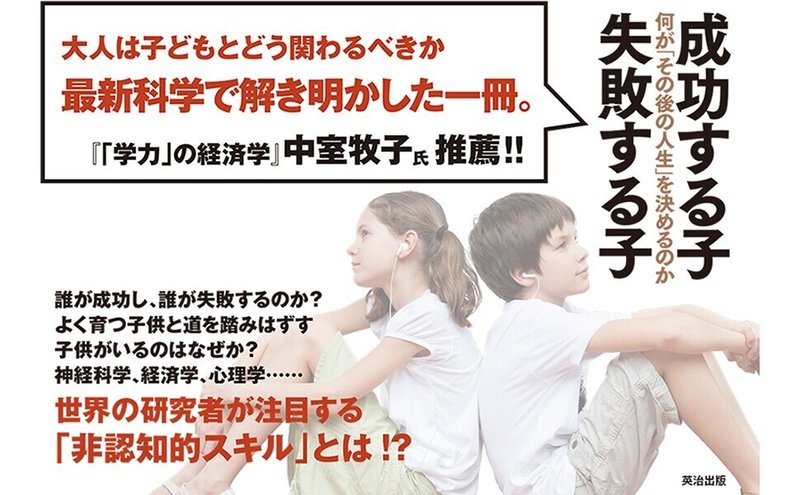
「人生はテストの点数では決まらない」という願いと裏腹に、子どもの試験点数に一喜一憂してしまうのが親心の本音である。
本書は、米国の最新の研究や実践事例を参照しながら、知能や試験点数のような目に見える能力よりも、(例えば学校を最後まで通い切る能力のような)目に見えにくい「非認知的スキル」が、その後の人生に大きな影響を与えることを明らかにする。
いわば「テストで決まらない人生」について科学的に検証しているのである。
例えば、米国で実施された「高校終了同等資格制度(General Educational Development: GED)」(高校中退者に高校終了と同等の資格を与え大学進学への道を開く制度。日本の高卒認定試験のようなもの。)は、マイノリティや低所得者の大学進学率を高め社会的地位向上に繋がると期待されていた。
しかし、ノーベル経済学賞を受賞したヘックマン教授らのその後の追跡調査で、所得、失業率、離婚率、犯罪率、違法薬物使用率などについて、知能や点数などの「認知能力」が低くないはずのGED取得者とその他高校中退者との間に、何ら統計的差異が見当たらないことが明らかになった。
(Heckman, J., and Rubinstein, Y. (2001) "The Importance of
Noncognitive Skills: Lessons from the GED Testing Program",
American Economic Review 91(2),pp145―149.)
ペーパーテストの点数が人生の成功につながらないということを計量分析を通して経済学者が実証した最たる例である。
※Heckman教授の日本で行った講演「能力の創造」は以下のURLを参照:
https://www.rieti.go.jp/jp/events/14100801/summary.html
それ以降、「非認知能力」と呼ばれるようになった、自制心や何事かをやり遂げる能力、それらを獲得・消耗していく能力とそのプロセスを科学的に明らかにしようとする試みが、世界中でなされている。
経済学で言えば、時間や予算などの限られた資源を投じて、人々が自身の非認知的能力を目的意識的に高め、獲得したその能力を様々な意志決定局面に配分しながら、人生をより豊かにしようとする行動メカニズムが明らかにされている。
自制心の欠如から、仕事を先延ばしたり、人間関係を粗悪にして後悔することは度々ある。
パフォーマンスの高い多忙なビジネスマンが、あえて時間を割いてマラソンや武道・座禅などを通して心身鍛錬する行動は、ただの趣味や息抜きを超えて、それが非認知的スキルを育てているのだということで説明できる。
認知能力に拘泥しがちな日本社会で、それ以外の能力の重要性を示した研究や実践を知っていくことは、20世紀型の古びた能力観から脱出し、21世紀型の人材像を考える上で必須である。
もちろん、非認知能力の高まりが本当に認知能力を向上させていくかどうかについても、多くの実証研究が必要になってくるだろう。
本書は、非認知能力を取り巻く研究と実践を知る上での「はじめの一歩」として、最も優れた啓蒙書の一つと言っていいだろう。
※参考になったら「スキ」をお願いします!更新の励みにさせて頂きますm(__)m
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
