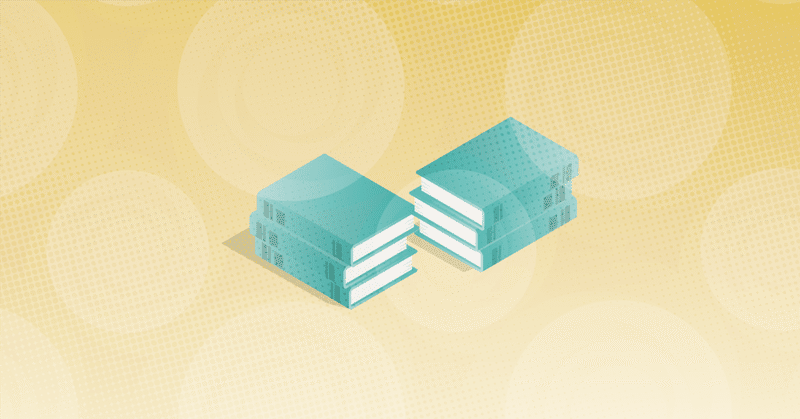
【読書記録】語彙力こそが教養である 齋藤孝
久しぶりに小説ではない本を。
語彙力こそが教養であるを読みました。
私が好きでよくSNSを拝見している方(いわゆる推しですね)がおすすめされており、いつか読みたいと思いつつ、なかなか読めずにいた本。
ようやく読みました。
全て読み終えての感想は
「もっと早く読んでおけば良かった」
自分は語彙力があるとは言えないにしても、
ない方ではないと思っていたのですが、こちらの本を読んで
私は語彙力がない人だ、と思いました。
同じ本を読み、同じ音楽を聴いた人が集まっているはずなのに、見方も価値観も表現も全く違う。「ものの見方」としても非常に勉強になるのです。
こうした視点でレビューを読んでいくなかで
「言葉の選び方によって、人間性がバレてしまう」ということも痛感するはずです。
(中略)
「短い文章のなかにも、人格は確実に表れる」
文章に人間性、人格が表われる。
これは本当にそうだよなと実感させられているのがX(旧Twitter)
同じ出来事や事実に対してもそれぞれ考えつくこと、思うことが違う。
それは当然として、その表現の仕方であったり、どのような言葉を使ってどのように表現するか、140字(今はそれ以上も可能ですが)という短い文の中にその人が表されている。
匿名性の高いSNSだからこそそのアカウントの方の人間性が見えてくると感じていました。
私がこの方好きだなと思い、フォローさせていただいている方々に共通するのは「言葉の使い方が好き」ということがあるなと気付きました。
言葉って本当に大切。
この本の中で語彙力を上げるための方法をいくつか紹介して下さっているのですが、その中の1つ「素読」があります。
素読とは、意味や内容を理解する前に、とりあえず声に出して本を読むことです。
現代日本ではこの素読がほとんど行われていない、と書かれていたのですが、思い返すと私学生時代に「素読」を授業でやっていました。
まずは小学生の時。
宮澤賢治の「雨ニモマケズ」を暗記させられたんです。
その時の先生は「このくらい覚えていないとダメだ」というようなことをおっしゃってた記憶があります。
今となっては全文暗記はしていませんが、有名なフレーズは当然のように覚えているし、聞けば思い出す、そんな存在です。
大人になった今、確かに「雨ニモマケズ」を知らないのって教養がないと思われても仕方ないよなと思うので、あの時の先生のおっしゃることは正しかったのだと思いました。
次は中学生か高校生の時。
古文の授業で著名な古文の一節を暗記してテストする、というものがあったのです。
あと百人一首も全部覚えました。
私が古文が苦手だったので(理系選択だし、得意にする必要もないよねと思ってた)なかなか面倒なと思っていたのですが、
こちらも今思えば・・・です。
枕草子の「春はあけぼの〜冬はつとめて〜」まで全部覚えたし、
今は全部言えないにしても知っている、だから会話の中にふと出てきてもすぐわかる、
平家物語の冒頭も覚えた、徒然草も竹取物語も覚えたな〜、、と。
当時は面倒だな覚えて何になると思ってましが、
今思えば感謝しかないです。
なお百人一首は記憶から無くなってはいますが、名探偵コナンで百人一首が取り上げられた時、あのとき全部覚えたな〜、確かに恋の歌多かったな〜くらいには思えたので、やっぱり教養として身についていたんだと思います。
余談ですが、一時期、今もたまに、道端に咲いている花の名前や歴史を調べるのが好きだったのですが、古来から日本に咲いているお花は当時の人にも可愛がられており、歌にもよく出てきているのだという発見がありました。
その時に当時の方々はその花の特徴、すぐに枯れてしまう儚さや、花の色が服にうつりやすい特徴から人の心の移り変わりやすさ、を表現していてその表現力に感動しました。
また、私がもう少し若い人だったら、SNSやメール、LINEなどのコミュニケーションツールで、「今読んでいる本の引用」を投稿したり送ったりしていたのではないかと思います。
気に入ったフレーズを見ながら画面に打ち込む。「いいね!」がついたり、「いい言葉だね」とメッセージが返ってきたりする。「私も読んだよ」「その本がと、この文章もいいよね」をコミュニケーションが深まる。
これはまさに読書記録のことではないかと思いました。
NOTEでたくさんの方の読書記録を拝見しておりますが、もっと交流できたら嬉しいなと思いました。
こちらの本、良いことがたくさん書いてあり、引用だらけにしたいくらいです。
本を読み終えてこの本読んでみたい!がたくさん増えたことと、文学部で学ぶということにも興味関心が湧きました。
これからは今まで読んでこなかったエッセイや、夏目漱石等の文豪の作品も読んでみたいです。
また花の名前から歴史を知る、という習慣また復活させたいなとも思いました。花の名前調べる→その花が歌われている歌を知る→時代背景を知る→歌を歌った人を知る、も教養の1つですよね。
これ本当に面白かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
