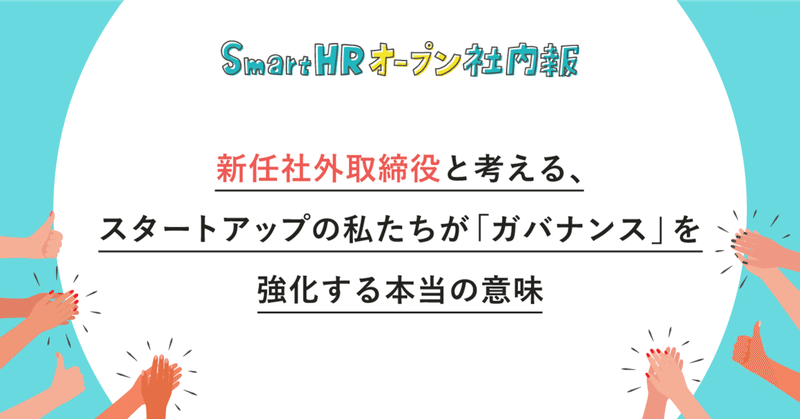
新任社外取締役と考える、スタートアップの私たちが「ガバナンス」を強化する本当の意味
お疲れさまです。ファイナンスグループ・財務企画ユニット 兼 カンパニーセクレタリーユニットの横溝(@Misopon)です。
今回は、主にコーポレート・ガバナンス業務を担当しているカンパニーセクレタリーユニットの Misopon として執筆しています。
さて、2021年7月2日に行われた下期キックオフでもCFOの玉木さんが語り、俄然、注目が集まる当社の「コーポレート・ガバナンス」。
この勢いに乗り、社外取締役に松﨑さん選任というイベントを通して、さらに当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方やこれから目指す体制について皆さんに周知できればと思い筆を走らせた次第です。
1. 松﨑さんを社外取締役として選任しました!松﨑さんてどんな人?
本日(2021年7月30日)開催の株主総会にて、松﨑 正年さんがあらたな社外取締役として選任されました。
プロフィールはプレスリリースに載せている通りですが、松﨑さんは「ミスターガバナンス」ともよばれていて、日本のコーポレート・ガバナンス改革を引っ張ってきた方です。
プレスリリースには載せきれなかった松﨑さんの略歴をご紹介すると、下記のように一貫して、コニカミノルタにてキャリアを磨いてこられ、2014年に取締役会議長に就任されてからは、活躍の場を社外に広げ、いくつも上場企業の社外取締役を務め、ガバナンス体制の構築を担ってきています。(すごい)
・1976年04月 小西六写真工業株式会社(後のコニカ株式会社)入社
・1998年05月 コニカ株式会社 情報機器事業本部システム開発統括部第一開発センター長
・2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
・2005年04月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
・2005年04月 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長
・2006年04月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役
・2006年06月 同社 取締役兼常務執行役
・2009年04月 同社 取締役兼代表執行役社長
・2014年04月 コニカミノルタ株式会社 取締役 兼 取締役会議長(現)
・2014年06月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)代表理事 会長
・2016年05月 一般社団法人日本取締役協会 副会長
・2016年05月 いちご株式会社 社外取締役 兼 指名委員 兼 報酬委員(現)
・2016年06月 株式会社野村総合研究所 社外取締役
・2016年08月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会委員(現)
・2018年05月 一般社団法人 日本取締役協会 理事・副会長(現)
・2019年06月 株式会社LIXIL 社外取締役 兼 取締役会議長 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 指名委員会委員(現)
・2021年07月 株式会社SmartHR 社外取締役(現) 👈 松﨑さんの歴史に当社が仲間入りしました!(すごすぎ)
※ 現任は太字としています。
松﨑さんの「経営者」としての活動
数々の上場企業等で役員を兼務している松﨑さんですが、「経営者」としても多彩な活動を行っています。その一部をご紹介。
● 2015年、東洋経済新報社からコニカミノルタ社長時代に行なってきた変革・改革を記した「傍流革命:変革をつくりだせ!」という本が出版されました。
● 「持続的成長を目指した経営の実践」、「企業変革を担うリーダーシップ」といったテーマでの講演会にスピーカーとして多数参加。最近では、野村マネジメントスクールの「トップのための経営戦略講座」という研修プログラムにて講演をしています。
● 現在、日本生産性本部主催「経営アカデミー経営戦略コース」の委員長を務めています。
2. なぜ、松﨑さんを選任したのか、その謎に迫る
前提 〜現状の課題と解決策〜
ここから社内でもあまり知られていない SmartHR のコーポレート・ガバナンスの話をさせていただきます。
● 現在、SmartHR では企業の持続的な成長を可能とするため、コーポレート・ガバナンス体制を強化するべく、いくつかのプロジェクトが動いています。
● そのひとつとして、取締役会の「経営」と「執行」の分離を行い、監督機能の強化を図っていくというものがあります。
● これまでの取締役会メンバーは、業務の執行面を担当する社内取締役(CxO)と、主要株主から派遣された社外取締役で構成されており、独立した第三者の立場で意見を言う方が不在でした。そのため、経営の監督機能が効いているとは言えない体制となっていました。
● そこで、その監督機能を強化するべく、社外取締役の経験が豊富かつ独立性が担保された立場の方をあらたに選任するべく、候補者探しをおこなってまいりました。
そこで白羽の矢が立ったのが、松﨑さんというわけです。
松﨑さん選任の理由
松﨑さんは、コニカミノルタにて2014年から取締役会議長を務めていることから、当社の取締役会により大局的な視点や判断軸をもたらすことが期待されます。
また、コニカミノルタ取締役会議長の他に、LIXIL など複数社の上場企業にて社外取締役を歴任されており、企業経営における多くの経験と知見を有しています。さらに、同年代かつ IT 関連企業出身者が大半を占める現在のボードメンバーに、多様性をもたらすことも期待されます。
これらの理由から、松﨑さんを取締役とすることが、監督機能の強化に繋がり、ひいては企業価値向上に資すると判断したため、社外取締役として選任しました。
3. 松﨑さん加入で、実際に何がどう変わる?
松﨑さんが入られることで変わることを、私 Misopon が大きく3つ予想してみます!
1. 独立した社外の立場であり、コニカミノルタにて、イノベーションの推進や大胆な事業転換を成し遂げてきた松﨑さんが入られることで、SmartHR の成長はもちろん、グループ会社も含めた、より、全体を大局的な視点で捉えた成長戦略の議論が活発になっていくことが予想されます。
2. 我が国を代表するコーポレート・ガバナンス体制を築き上げてきた松﨑さんが入られることで、取締役の選任や、報酬の決定、また投融資に関するプロセスなどがより明確で透明性の有るのものに変わっていくことが予想されます。
3. グローバル企業の経営者として培った高度な知識と経験を有している松﨑さんが入られることで、お客様、株主、従業員だけでなく、地域や社会、環境などにも配慮した、より、多くのステークホルダーを意識した議論が行われることが予想されます。
こうやって改めて書いてみると、松﨑さんの加入は本当に心強いですね。
ガバナンスの強化だけでなく、事業の成長戦略や ESG の観点まで幅広く SmartHR の成長を後押ししてくれるはずです!私も楽しみと同時に気が引き締まります。
4. 松﨑さんへのインタビュー
取締役就任に先立ち、2021年7月27日に松﨑さんにインタビューさせていただきました。
松﨑さんの今日に至るまでのエピソードや、最後にはメッセージをいただいていますのでぜひご一読ください!
Misopon:本日は朝の早い時間からありがとうございます。よろしくお願いいたします!
松﨑さん:こちらこそ、よろしくお願いします。

▲ 松﨑さんがスーツなのに対し、ゆるめのTシャツでインタビューに臨む Misopon
Misopon:まず最初の質問です。代表の宮田さんとの面談がきっかけで取締役のオファーを受けていただいたと思うのですが、宮田さんと初めて会った時の率直な印象を教えて下さい。
松﨑さん:宮田さんとのはじめての面会で、「どういう会社にしていきたい」という想いをしっかり持っている方だと感じました。そして、宮田さんご自身にも浮ついたところがなく、物事を落ち着いて客観的に見ている人だと。会社経営はイケイケドンドンだけではうまくいかないことを知っている人という印象をうけました。
未来を見据えて、今の会社に対し、どう手を打っていくかという考えを宮田さんなりにしっかり持っていました。
リーダーには必要な資質というものがあります。それは周りが応援したいと思えるような人かどうか。経営は必ずしも順風満帆とはいかないので、逆風にあった時に周りが助けたいと思えるかどうか。宮田さんはそんな人柄と資質を持っている人だと思います。
宮田さんの印象をまとめると
想いをしっかりもっている、浮ついたところのない、物事を客観的にみれる、周りが応援したいと思えるような人
Misopon:松﨑さんは日本の「ミスターガバナンス」と呼ばれていると聞いたことがあります。それほどまでにコーポレート・ガバナンスが重要だと感じた出来事はあったのでしょうか。
松﨑さん:「ミスターガバナンス」と呼ばれているというのは初めて知りました。笑
これは良い質問ですね。私が取締役会議長をしているコニカミノルタでは、何代か前の経営者からすでにコーポレート・ガバナンスの重要性を説き始めていました。常に「客観性のある意見を取り入れることが必要」だと考える経営者のもとで働いてきたということです。
そして、私が、2009年にコニカミノルタの社長を任された際、私の社長としての役割はなんだろうと考えた時に、長く歴史のあるこの会社を「持続的に成長させること」という結論に至りました。
社長に就任した頃は、リーマンショックがあったり、東日本大震災があったり、その他にもたくさんの経営に影響を与える社会事象がありました。そのような困難が降りかかるたびに、それでも経営を持続させないといけない、会社を守らないといけないと強く感じました。
その時に、コーポレート・ガバナンスは会社を守り、持続的な成長を支えるための機能なんだと、先代の社長の教えを身を以て実感しました。これがキッカケでしょうか。
私は経験から、会社の中の人の考えだけで意思決定をするのではなく、外部の目線を取り入れ、いろんな経験をしてきた人たちの様々な観点からの意見に耳を傾けることが大切だと学びました。
そうすることで、
● 社内の人だけでは気づけないリスクを発見できる
● 変化しなければいけない時に変化の必要性を認識することができる
● 会社の経営が軌道を外してしまいそうな時に、軌道を外す前に知ることができる
「会社がつまずく前に修正ができるようになっている」というのはとても重要なことです。自分のこの経験が活かせるならと、2014年に執行を離れ取締役会議長になってからは他の上場企業の取締役会議長などもやらせてもらっています。

Misopon:オファーを受けていただいた理由に、「あとに続くスタートアップ企業の模範になるようなコーポレート・ガバナンスの体制づくりをサポートして欲しい」との言葉に共感したというコメントをいただきました。上場企業でも体制づくりが二の次になってしまっている企業も少なくない中、スタートアップ企業がガバナンス体制を強化することの意味はどこにあるとお考えでしょうか。
松﨑さん:はい、まさに私の心が動いたのは宮田さんのその言葉でした。スタートアップ企業がガバナンス体制を強化することの意味はふたつあると考えています。
2015年に東京証券取引所が「コーポレートガバナンス・コード」を定めたきっかけは、海外の投資家が日本企業に投資しようとした時に、あまりにも不透明であることが課題になったからだと言われています。
たとえば、経営者がどのような判断で選任されたのか、経営の意思決定がどのようなプロセスでなされたのかもわからない。わからなければ、投資しようにも投資ができないといった状況でした。企業は、できるだけ透明性高く、きちっと説明するべき時には説明責任を果たそうということで「コーポレートガバナンス・コード」が制定されました。
しかし、会社が大きくなり、「出来上がってしまっている企業」が、急に2015年になって金融庁や東証から「コーポレート・ガバナンスが大事だから整備して」と言われてもなかなか変われない。「習慣」ができてしまっている企業はあたらしいことに対応できず抵抗してしまいます。
それならば、初めから健全な仕組みを作って「習慣化」することが大切だと私は考えていて、スタートアップ企業がガバナンス体制を強化することのひとつめの意味だと思っています。
ステークホルダーからみた時に、「納得感のある意思決定がされているな」と、あるいは「タイムリーな情報開示がされているな」と思える仕組みを最初から作った方がいいということです。
そして、ふたつめですが、スタートアップは成長のポテンシャルがありますが、それを実現するには正しい意思決定が必要です。会社の中の人は一生懸命考えて意思決定をしますが、それに加えて客観性のある意見をもらうことで間違いの少ない決定ができるようになります。
それは、スタートアップ企業がその高いポテンシャルを活かして持続的に成長できるようになるということです。
私の元々の想いとして、企業の経営執行から退いた人間の役目は、スタートアップ企業の成長を実現するため、組織を根幹から支えるコーポレート・ガバナンス体制の構築をサポートすることだと考えていました。ですので、宮田さんの言葉が刺さったというわけです。

Misopon:おそらくこの記事を読んでいる多くの SmartHR メンバーが、「コーポレートガバナンスの体制づくり」が進んでいくと実際に自分たちにどのような影響があるのかが気になっていると思います。その疑問について何かコメントいただけますでしょうか。
松﨑さん:これもいい質問ですね。従業員の皆さんにとってとても大事なことだと思うのでベストを尽くして回答します。
コーポレート・ガバナンスとは「ステークホルダーの立場で考えた意思決定をすること」だと理解しています。そして、ステークホルダーの中でもその会社の従業員は極めて重要だと思います。
ですので、健全なコーポレート・ガバナンス体制をつくるということは、経営の意思決定をする上で「従業員にとってプラスになるのか」を本気で考えることだと言えます。従業員にどんな影響が出るのかと、常に従業員を念頭に置いて意思決定を行なっていく必要があります。
SmartHR の取締役会をみていると、すでに経営陣は従業員のことを常に考えて意思決定しているなと感じていますが、外部の人間の目がはいることで、よりその精度は上がると思います。
もう一つは、コーポレート・ガバナンスを機能させることは会社全体にとってプラスになるということです。会社がつまずく確率を下げ、企業を持続的に成長させることは、従業員にとって様々なプラスの影響があるだろうと思っています。
ガバナンスが強化されるとチェックされることが増え、業務活動に制限がかかるのでは、と心配する方もいると思います。たしかに運用を誤るとそうなってしまう可能性があるので、注意を払う必要があります。
SmartHR 流のコーポレート・ガバナンス体制を作るときは、自由で型にハマらないやり方、圧倒的なスピード感やフレキシブルな行動、失敗が受け入れられるチャレンジ精神、そしてその失敗から学ぶことなど、元々 SmartHR が持つ強みがないといけない。
私自身もブレーキにならないように、むしろ安心して強みを発揮できるように、会社が大きくなっても維持できるようにサポートしていこうと思っています。
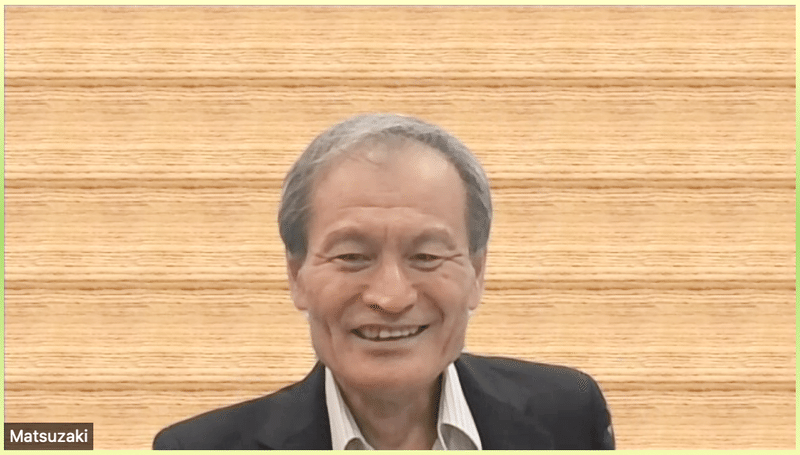
▲ 松﨑さんの落ち着きながらも熱のこもったお話は時間を忘れさせます
Misopon:最後に、この社内報を読んでいる SmartHR の役職員にメッセージをいただけますでしょうか。
松﨑さん:今、世の中では、D&I(Diversity & Inclusion)というのがバズワードのように取り上げられています。これは、多様性を積極的に取り入れていくということですが、それは、ジェンダーという考え方もあれば、国際経験のある方という考え方もある。その中のひとつとして、私は、「世代の多様性」というのが大切だと感じています。
一般的には、年齢を重ねた経営陣に対し、いかにして若い世代に経営に参加してもらい意見を汲み取れるかですが、私と SmartHR の場合は全くその逆で、スタートアップの中に、70歳を超えた人間が入っていく。そのことの良さ、新しい多様性をいかして、SmartHR に貢献できるよう精一杯やっていきたいと思っています。これからよろしくお願いします。
Misopon:本日は誠にありがとうございました。これから何卒よろしくお願いします。
5. 今後の SmartHR のガバナンスはどこへ向かうのか
「ガバナンスが効いている」とは下記の状態のことだと株主の方から教わりました。
「何度も大きなチャレンジができる組織」
ガバナンスが効いていると一度や二度の失敗でも会社が傾くことはありません。逆にガバナンスが効いていないと、適切なリスク評価ができず、一回の失敗で致命傷となりえます。
何度でも大きなチャレンジができる企業になるために、「経営」と「執行」の最適な分離を進めていきます!
ちなみに、「経営」と「執行」が分離していない or しているのイメージ(下記は私 Misopon の主観がふんだんに含まれています)
● 古田が監督 兼 選手のヤクルト or 古田がキャッチャーに集中し野村監督がいるヤクルト
● 藤真が監督 兼 選手の翔陽高校 or 藤真がポイントガードに集中し高頭みたいな監督がいる翔陽高校
上記の例ではどちらのチームの方が強そうと感じるでしょうか?
他の例でいえば、今年6月に100mで9秒95をマークした山縣亮太選手は10年以上つけずにいたコーチをつけたことで日本記録にたどり着きました。メジャー屈指の策士として知られるマドン監督が就任してから、大谷翔平選手の二刀流はさらなる進化を遂げ、今の大活躍に繋がっています。
名プレイヤーが名監督になるとは限らないですし、経営には経営の、執行には執行の専門家がそれぞれの課題に集中して取り組むことでチーム(会社)や個人としての完成度が格段に向上するということです。
今後は、具体的には「指名委員会等設置会社」という「監査等委員会設置会社」よりさらにガバナンスが効いているとされ、海外ではスタンダードな体制への移行を目指し準備をすすめてまいります!
松﨑さんと宮田さんが初めて面談した日から待つこと219日。一緒にお仕事ができることをずっと心待ちにしていました。
これからは、「あとに続くスタートアップ企業の模範になるようなコーポレート・ガバナンスの体制づくり」という目標に向かい色々とサポートいただきたいとともに、松﨑さんにとって SmartHR の取締役になってたくさんのことを得られたと言ってもらえるような関係を築いていければと思います。
