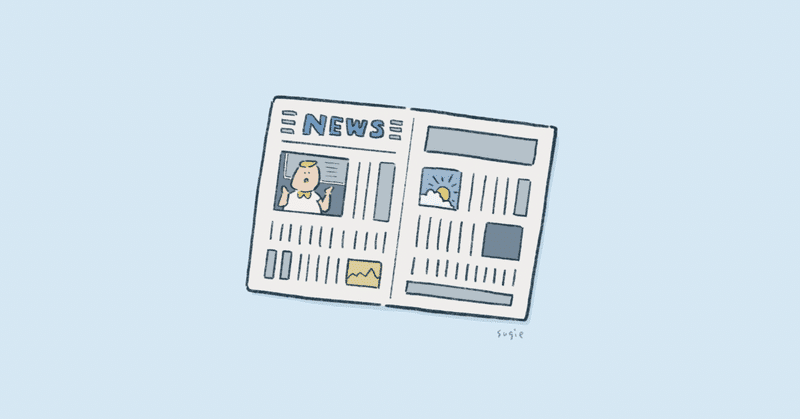
塾業界がいまだに新聞折り込み広告を辞めない理由【変化する広告の価値】
そろそろ冬休み。となると、塾業界は夏期講習に次いでのビックイベントとなる冬期講習が始まります。
夏期講習とは違い、期間も短く、受験生とそうでない学年では温度差がかなり違うこともあり、重要度は違うものの、
高校生の場合、
受験生は、共通テスト、私立大対策への追い込み
1~2年生は、休み明けの実力テストに備えつつ、これまでの復習
は、それぞれで重要な学びの期間になります。
特に高校2年生は、可能な限り受験生としての意識を高めてほしいところです。
冬期講習は言うまでもなく塾ビジネスとしての役割は大変重要で、当然年内最後の書き入れ時ということになります。
そこで重要となるのが、広告です。
これまで、塾業界は新聞折り込みチラシを重視しており、
塾業界の広告=新聞折り込みチラシだった時期がとても長かった。
しかし、昨今の新聞離れによって、塾業界も広告の多方面への展開が余儀なくされています。
ところが!
塾業界は、今もなお、この新聞折り込みチラシを重視しています。
また、HPやSNSには、手を出してもインターネット広告に手を出さない塾も多い。
それはなぜなのでしょうか?
福岡県の場合、新聞の配達部数は以下の通りになります。
県紙がない福岡県の場合、ブロック紙である西日本新聞がエリア最大の部数を誇ります。以下、読売、朝日、毎日、日経と全国的な平均と同じような順番になります。
新聞には今もなお、チラシを入れるメリットがあるボリュームはあるとみていいでしょう。
ただ、昨今の新聞離れは加速度的に進んでいます。
公益財団法人新聞通信調査会(以下、新聞通信調査会)が2020年に行った「第13回メディアに関する全国世論調査」※1によると、ここ10年程で購読率が約23%減少し、2020年では61.3%となっています。2011年度で若干の浮き上がったものの、右肩下がりで減少しているのは明らかです。
この記事を読むまでもなく、減り続ける新聞購読率は新聞業界的には大変深刻な傾向です。
それは、広告を打つメリットもしぼむということになります。
ところが、塾業界の目線では、新聞購読率が下がるのは、悪いことばかりではないのです。
それはなぜか?
塾業界には、新聞を購読しているご家庭は、良質の生徒の割合が高いという経験則があるからです。
なので、新聞購読率が下がる昨今の風潮にあっても、あえて新聞を取っているご家庭は、きわめて貴重で、良質の子息子女を抱えている可能性が高いともいえるからです。
つまり、下がる新聞購読率は、よりセグメントされた層を形成することになり、広告効果を高めているともいえるのです。
もちろん新聞を取っていない=ダメなご家庭というわけではありませんし、そのような実感もありません。
つまり、新聞を取っているご家庭には、正の相関はあるものの、取っていないご家庭には相関はないということです。
ただ、教育という観点から新聞を読むことで得られるメリットは、結構多いのは間違いありません。
高校生になると、在宅時間が減ることもあり、テレビでニュースを見る機会も限られます。社会問題を知る手がかりは、実は新聞になっている生徒は多いのです。
(大人と違って、ネットニュースをほとんど見ないこともあります)
なので、岸田文雄首相について、キシダさんと知っていても、フミオさんという下の名前を知っている生徒は新聞で活字を通して視認しているということが起こるのです。
また、昨今の共通テストは読解力を重視していることもあり、長い文章を読めない生徒が大変苦労しています。長い文章を読むことは、ある程度はトレーニングが必要です。結果として、新聞は普段から継続して文章を読む環境を担保していることになっていることが多い。
(このあたりは、新聞業界はスクラムを組んで調査してはどうでしょうか)
私自身が実感していますが、スマホやタブレット端末では、長い文章を読むのは目の疲労などもあり、あまり向いていません。その点は確実に紙で読むメリットがあります。
毎日、新聞を読む習慣のある人とない人では、大人でも知的リテラシーに差が出てしまうものだと普段から実感しているので、高校生ならばそれは顕著に出てしまうものではと思います。
あと、家庭教師時代、社会的地位の高い職業についておられるお父様が、突然新聞購読を辞めてしまい、生徒が苦労したことがあります。大人の中には、そのような判断に合理性があることは、理解できますが、まだお子さんが中高生であれば、お子さんのために新聞を読む機会を残してあげてほしいなとも思っています。
この点については、こちらで記事にしています。
混乱の続く共通テストですが、しばらくは長いリード文は続くと思われるので、新聞を購読するメリットは残してあげてほしいかなと思っています。
そして、いい塾との接点もあることも、メリットとなるように、私たちも努力をしたいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
