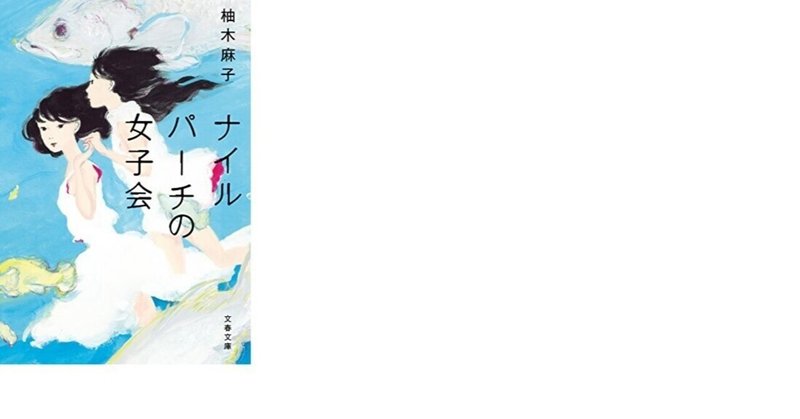
日曜日の本棚#9『ナイルパーチの女子会』柚木麻子(文春文庫)【ドラマが原作を圧倒する不都合な真実】
毎週日曜日は、読書感想をUPしています。
前回はこちら。
今回は、柚木麻子さんの『ナイルパーチの女子会』です。
変わったタイトルですが、ナイルパーチとは、食用に適した淡水魚です。とても繫殖力が強く、生態系の宝庫と言われた東アフリカ・ヴィクトリア湖に外来魚として放流されると、あっという間に在来種を駆逐し、生態系を破壊しました。そのナイルパーチの獰猛さを女同士の人間関係の象徴として表現しています。
デビュー以来、徹底してこの女同士の関係性にこだわってきた柚木さんの一つの到達点とも言うべき作品です。
しかし、この作品、まさかの展開を見せます。これが本稿のテーマです。
ちなみに、このナイルパーチのエピソードは、『ダーウィンの悪夢』という秀作のドキュメンタリー映画を生み出しています。
あらすじ
丸の内の大手商社に勤めるやり手のキャリアウーマン・志村栄利子(30歳)。実家から早朝出勤をし、日々ハードな仕事に勤しむ彼女の密やかな楽しみは、同い年の人気主婦ブログ『おひょうのダメ奥さん日記』を読むこと。決して焦らない「おひょう」独特の価値観と切り口で記される文章に、栄利子は癒されるのだ。
その「おひょう」こと丸尾翔子は、スーパーの店長の夫と二人で気ままに暮らしているが、実は家族を捨て出て行った母親と、実家で傲慢なほど「自分からは何もしない」でいる父親について深い屈託を抱えていた。
偶然にも近所に住んでいた栄利子と翔子はある日カフェで出会う。同性の友達がいないという共通のコンプレックスもあって、二人は急速に親しくなってゆく。ブロガーと愛読者……そこから理想の友人関係が始まるように互いに思えたが、翔子が数日間ブログの更新をしなかったことが原因で、二人の関係は思わぬ方向へ進んでゆく……。
女同士の関係の極北を描く、傑作長編小説。第28回山本周五郎賞受賞作。
(文春文庫の紹介文より)
実はドラマ化されていた本作。地味な枠で目立たない作品だったのだが・・・
本作はBSテレ東という、とても地味な枠でドラマ化されています。主人公・栄利子を水川あさみさん、「おひょう」こと、翔子を山田真歩さんが演じています。
このドラマ、とんでもない作品でした。知人に教えていただき、見始めたのですが、とてもよくできている。そのため原作を読んでみたいと思い、チェックしてみたのですが・・・。
本作、ドラマが原作を圧倒しています。何もかもがドラマの方が上だった。別の言い方をすれば、小説の問題点を上手く補ったドラマだということなんだろうと思います。
獰猛なナイルパーチがヴィクトリア湖の在来魚を食い荒らしたように、原作の存在価値を形骸化させたドラマだったのではと思っています。
原作は決して悪くない作品
本作は、山本周五郎賞を受賞し、直木賞の候補作品でもありました。直木賞本命とも見る向きもあった作品です。
柚木さんは、「時代が求める」とされる作家の一人でしょう。それだけ現代を正面から描く作家であると思います。その結果、エキセントリックなシーンや展開を織り込む傾向があり、これが生命線となっている場合が多い。本作は、さらにギアを入れた感のある作品でした。もしドラマという先入観がなければ、粗さもあるがそれが魅力な力感溢れる作品ということだったのだろうと思います。
ドラマはその上を行く
脚本は横田理恵さんで、代表作は何といっても『ごくせん』(日本テレビ)で、池井戸潤原作の『花咲舞が黙ってない』(同)も好きな作品でした。
ドラマが原作とは違った展開を見せたわけではありません。ストーリーは原作ベースに進みます。
ところが、ディテールをみると明らかに原作の問題点を掴んでいて、そこを綺麗に修復が施されていたように思います。後半はそれが楽しくて観ていた部分もあります。また、キャラクターの言動に謎な言動がある部分(翔子がカリスマ主婦ブロガーNORIにメールを連打するところなど)は、ほぼ原作通りに描いてすらいます。原作のマイナスをあえてニヒリスティックに演出として使うところも心憎い部分でもありました。
決定的に違った男性キャラクターの扱い
本作は、女性の友情がテーマ。同性とうまく関係を結べない成人女性を描くことで、ひとつの主張が生まれる作品です。そこでポイントとなるのが男性の存在。男性の存在及び男性が絡む人間関係、および思考は、テーマをぼんやりさせるものになる可能性をはらみ、慎重に扱うべきものだと思います。
そのため、ドラマでは翔子の夫・賢介以外は、デフォルメされたキャラクターになっています。男性キャラの存在感が大きくなるとテーマが見えなくなるという判断でしょう。象徴的なのは、栄利子の父の存在で、小説では存命、ドラマでは死亡設定になっています。小説では、栄利子の理想の男性像になっています。そのため、栄利子がテーマに向かって歩んでいかない足かせになっています。なので、ドラマは死んだことになっているのだと思います。
ラストはドラマと原作で異なる(ドラマの結末を書いています)
ドラマが明らかに小説を上回ったと決定的に思ったのは、ラストの扱いでした。小説では、主人公二人とも、評論家になってしまいます。自己分析し、自分を深掘りして終わり。二人はすれ違ったまま、二度と会うことなく終わります。このラストには強い違和感しかありませんでした。リアリティってこういうものでしょう?と言われたような感じがしました。
主人公は、そもそもの存在として、最後まで動いて、もがいて何かを掴むことが求められているのではないか。私はそう考えてしまうので、モヤモヤしたラストに違和感をもちつつ、ドラマの最終回を観ました。
ドラマでは二人を再開させるシーンを設けていました。紆余曲折があった二人ですが、「いつか街で偶然出会ったとき、立ち話ができればいいんじゃないか」という言葉に希望を持った栄利子が、最後に「声をかけてもいい?」と翔子に提案します。
翔子は、女友達ができない自分を受け入れ、自分とは形は違っても同志的な要素をもつ栄利子を理解し、「いいよ」と答えてドラマは幕を閉じます。そのようにいう翔子の言葉に、これまでの経緯から得た何かが凝縮されており、主人公らしい役割が付与されたいいエンディングになっています。このラストは、この物語存在した理由を見たように思いました。
原作の価値を増幅したようなドラマでしたが、だからと言って原作の価値が棄損されてもいけないとも思います。ただ、批評というのは残酷で、ここまでの決定的な差を認識してしまうこともあるのだなと感じた作品でもありました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
