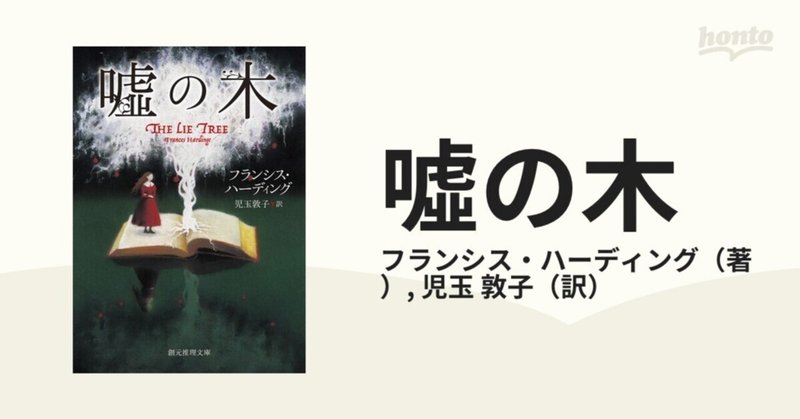
日曜日の本棚#32『噓の木』フランシス・ハーディング(東京創元社)【児童文学としてもエンターテインメントとしても最高水準の面白さ】
毎週日曜日は、読書感想をUPしています。
前回はこちら。
今回は、現在NHK-FMの『青春アドベンチャー』でラジオドラマが放送中のフランシス・ハーディングの『嘘の木』です。
たまたま聞き逃し配信でその存在を知り、面白さに惹かれてしまい、読書中だった本をペンディングして読みました。久々の一気本でした(^^)
作品紹介(東京創元社HPより)
高名な博物学者サンダリー師による世紀の発見、翼ある人類の化石。それが捏造だという噂が流れ、一家は世間の目を逃れるようにヴェイン島へ移住する。だが噂は島まで追いかけてきた。そんななかサンダリー師が死亡する。娘のフェイスは父の死因に疑問を抱くが…。謎めいた父の手記。嘘を養分に育ち、食べた者に真実を見せる実のなる不思議な木。フェイスはその木を利用して、父の死の真相を暴く決心をする。コスタ賞大賞・児童文学部門賞をダブル受賞した大作ファンタジー。
所感(ネタバレを含みます)
◆文学性とエンターテインメント性の高水準での両立
まず、理屈抜きに面白いですね。本作は、児童文学作品であり、ファンタジーと分類できるのでしょうが、それ以外にもミステリーやSF的な要素もある。そして、何より主人公・フェイスが魅力的でキャラクター劇としても申し分ない。高いレベルでのエンターテインメン性を備えています。
博物学者の父が証拠品を捏造したという汚名を着せられたこともあり、フェイスたち一家は、物語の舞台となるイギリスの離島ヴェイン島に移住します。前半はファンタジー要素はほぼゼロ。一方で、ミステリー的仕込みがあり、じっくり読むと面白さが増します。
そして、ほぼ真ん中あたりから急展開。
これまで描かれていた父・サンダリー師の言動が一つにつながります。
ミステリーの謎解きの爽快さが中盤に展開されます。
これが素晴らしい。予想外の展開に魅了された読者は、ここから一気に作品に引き込まれる。
作者の巧みな意図に操られる心地よさは、エンターテインメント小説の醍醐味だと感じます。
◆「噓の木」のリアリティの凄さ
ファンタジーは、大きく分けて幻想世界そのものをうまく構築するか、現実社会にファンタジーの設定をリアリティのあるものになじませるかの二つのやり方があるように思いますが、本作は後者。
リアリティを担保する設定がとても上手い。ぜひこれは本書の展開の中で味わってほしいところです。
人間の嘘を栄養源として成長する「嘘の木」。真実を知ることができることができるこの木を使って父の死の真相を知ろうとするフェイス。
そのため、島民たちは、フェイスがついた嘘に翻弄されていきます。もし、フェイスに嘘をつく必然性がなければ当然に狂ってしまうことでしょう。
なぜなら、嘘で何かを得た人間は、それをやめることができないからです。
そのフェイスの危うい均衡も上手く表現されています。
人間の嘘を栄養源とする嘘の木は信じられない速度で成長を遂げていきます。この荒唐無稽な設定に何ら無理がない。そう思わせるほど物語にうまく設定をなじませています。
これこそがリアリティの妙なのでしょう。
◆嘘の本質を突く鋭さと時代性
「噓の木」の機能を理解したフェイスは、どんどん嘘をつく能力を高めていきます。科学的視点での「嘘」のコツとして、
さしだすのは、嘘の一部だけでいい、あとは人々の想像力がすきまを埋めてくれるのだ
とフェイスは考えます。
これはとても現代をうまく風刺していると感じます。フェイクニュースは、それらしと思うところに広まる根っこがある。
現代人と嘘は実は大きな問題なのかなと読後に強く感じました。
四角四面に地道な努力をするよりも、嘘に乗じて何かを得る方が「コスパ」が良い。そう思う人が増えたように思います。
「切り取り」「レッテル貼り」などなどSNS時代によって登場したこれらの新しい言葉の意味は、巧みな嘘の存在のために生まれた使い方でもある。
ただ、そんな嘘の世界を生きることが何をもたらすのか。物語を通じて、この問題を客観視させ、そして、それを生み出させる想像力が起動する。これは、物語の良さでのひとつであり、それが結果として、人間に歯止めをかける抑止力に繋がっていくものなのでしょう。
最後に物語の結末は、本作が児童文学であることに存在意義があると感じます。児童文学であるからこその終着点に、説得力を強く感じるからでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
