
がん新薬誕生 第1回 万に一つの可能性にかける
取材・執筆:下山進
殺細胞性の第一世代の抗がん剤は、副作用で患者が死ぬこともあった。がん細胞が増殖するための血管の新生を止めれば「がん」はなおる、新しい理論のもと開発が始まる。
化学式のなかに、美しさがあるのだ。
これまでに存在していなかった分子式の物質を化合する。それが合成化学者の仕事だ。
1990年に千葉大学大学院薬学研究科からエーザイに入社した鶴岡明彦(つるおか・あきひこ)は、現在グローバルで年間1923億円、エーザイの全売上の4分の1を占めるがんの薬「レンビマ」の化学式を見るたびに美しいと思う。
ヒットする薬の化学式は抗アルツハイマー病薬のアリセプトにしても、レンビマにしても、シンプルで美しい。

鶴岡のチームが1999年12月に合成したこのレンビマは、血管新生阻害剤という新しいタイプの抗がん剤だ。
1990年代まで、がんの治療は、手術か、放射線治療か、殺細胞性の抗がん剤しかなかった。
「殺細胞性の抗がん剤」とは、分裂の激しい細胞をターゲットにして殺す薬だが、がん細胞だけでなく健康な細胞も殺してしまう。当然のことながら、副作用も強い。髪の毛がぬけてしまうのは、頭皮の毛母細胞が激しく細胞分裂をして、毛髪の育成をうながすからで、そこも叩いてしまうからだ。
「効果10パーセント、副作用100パーセント」
という笑えない冗談が、医療関係者の間にあったくらいなのだ。
それを、がん細胞だけを選択的にたたく方法のひとつとして考案されたのが、血管新生阻害剤の考えだ。
がんが分裂し増殖するためには、血管による血液の補給が必要だ。がん細胞は、シグナルを出して、健康細胞に血管をつくらせる。その血管から補給される栄養をもとに成長する。だから、それを叩けば、がん細胞は増えない。1971年11月にハーバード大学医学部教授のジューダ・フォークマンという医者が、「ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディスン」に発表したこの仮説を追って、世界中の研究者たちが、この新しいタイプの抗がん剤の開発にとりくんだ。
レンビマは現在、甲状腺がん(2015年)、腎細胞がん(2016年)、肝細胞がん(2018年)で承認を取得し、免疫チェックポイント阻害剤との併用では、子宮内膜がん、腎細胞がん(2021年)で承認を取得、その適用範囲を広げ続け、アリセプトの特許が切れたあと、神経領域で苦戦するエーザイの売上を支える存在になっている。
エーザイは、抗アルツハイマー病薬のアリセプトを97年に上市し、一気にグローバル化をはたし、次世代のアルツハイマー病根本治療薬の開発にとりくんできた。しかし、それはなかなかうまくいかず、2021年6月条件つきながら米国で承認されたアデュカヌマブも、後に欧州、日本で承認が見送られ、米国でも、実質上保険収載がされず、株価は下落、窮地におちいっている。そのエーザイを現在支えている存在でもある。
私は、前の本『アルツハイマー征服』の取材の過程で、エーザイの決算説明会にかならず出ていたが、アリセプト特許切れのあとの、エーザイの屋台骨を支えているのは、がんの分野、特にこのレンビマであることを知ったのだった。
低分子の血管新生阻害剤の中で、ナンバー1の売上をほこるレンビマ。このレンビマの承認によって、これまで手のほどこしようがなかったある種のがんに対処法が生まれつつある。たとえば、甲状腺がんで、放射線耐性をもつがんは、かつてであれば、対処法がなかった。しかし、現在は、レンビマという方法がある。
これは、その誕生までの50年の物語だ。

抗がん剤の副作用で死ぬ
「おふくろの仇(かたき)をとってくれないか」
父親にそう言われて、後にエーザイのがん研究をひっぱっていくことになる大和隆志(おおわ・たかし)は、東京大学で薬学部に進むことになった。2年の教養課程のあと、専門をきめる進路振分が東大にはある。大学2年生のとき、父親に、「理学部の化学科で、有機合成化学をやりたい」そう言ったらば、父親は、「その有機合成化学というのはどのくらい実学に近いんだ?」と聞いたあと、「仇をとってくれないか」と言ったのだった。
大和の祖母は胃がんで亡くなっていた。いや、がんで亡くなったとは言えない。投与された抗がん剤の副作用で亡くなったのだ。アドリアマイシンという第一世代の抗がん剤を投与されたが、殺細胞薬であるから、健康な細胞も殺してしまう。祖母はその薬の副作用である心筋梗塞で亡くなっていた。
父親の「仇をとってくれ」という一言で、理学部進学の希望を変えた大和は薬学部に進み、博士号は有機合成でとった。エーザイに入社したのは、1991年4月。
面接では、「がん研究しかやる気はない」。そう言っていたらば、がん研究のグループに配属された。
エーザイでがんをターゲットにした創薬の研究が始まったのは1987年、そのきっかけを、当時筑波の研究所の所長をしていた内藤晴夫(現CEO)はこう話す。
「最初は、薬もつくらないし、お金は使うし、そういうスモールグループが、5、6人はいました。彼らはなかなかやめないんですね。やめろやめろと言っても。アリセプトを開発した杉本八郎さんと似たところがあって。そのしつこさにほだされた。免疫の研究の延長上にがん研究というのはあるんだとうまくいいくるめられちゃったんですね。それで始まりました。えぐいやつががん研究にはごろごろいて、なかなか自説をまげないでつっぱしってきた」
大和の前年には、後にレンビマを生む原動力となる独特の化合物評価系をつくった船橋泰博(ふなはし・やすひろ)が入社しがん研究グループに配属されている。
ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院でMBAを取得し、1975年にエーザイに入社、1982年にできた筑波の研究所の研究開発本部長を務めた内藤晴夫は、1988年には社長に就任した。このときまだ40歳。エーザイは急速に変わろうとしていた。
80年代後半くらいまでは、エーザイの売上もまだ1000億円台(ちなみに2021年度決算では7562億円を売り上げている)。特許切れの薬のコピーをつくる「ジェネリック」あるいは少しだけ化学式を変えて同じ作用機序を狙う「ミーツー」。そうした薬をつくる物真似メーカーではなかったが、「ミーツーに毛が生えたような薬を、MR(営業)の力で押し込ん」(大和)で売っていた製薬会社だった。
が、内藤晴夫が社長になると、世界の20社入りを目標にかかげ、「その原点は自社の研究開発努力にあることは論を待たない」(1990年1月8日の内藤挨拶)と、研究開発に力をいれ、よりオリジナルなものを求めるようになっていた。
まだ何物も生み出していないがん研究グループも、「よそのミーツーはやらない。新しい作用機序のものを狙う」と決めていた。
その新しい作用機序が、血管新生阻害だったのである。
だが、「自説をまげないえぐい奴」が集まったがん研究グループは、当時はエーザイの中では隅っこも隅っこの存在だった。
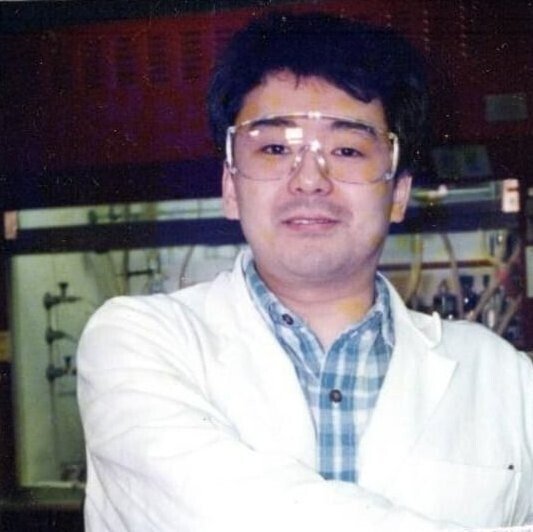
1971年の論文を起点に
フォークマンの1971年の論文では、がん細胞の増殖をうながす血管をつくる要素を「あるファクター」としていた。そのファクターが何なのかがわかってきたのが、1989年から1991年にかけてのことだ。
ナポレオーネ・フェラーラとウイリアム・ヘンゼルという研究者が、分泌物を特定精製し、VEGF(vascular endothelial growth factor:血管内皮細胞増殖因子)と名づけたのが、1989年。他にも、FGFやHGFなどの因子が見つかってきた時期に、エーザイのがん研究グループはできたことになる。
遺伝子工学の発展の時期ともかさなり、がん特有の遺伝子の変異からできる特定の分子をターゲットにした分子標的薬の開発が世界の研究室で始まった時期でもある。
たとえば乳がんにみられるHER2というたんぱく質とその遺伝子が特定されたのも1980年代後半だ。
大和や船橋らが、HER2といった特定のがんにみられる分子を標的としたものではなく、血管新生阻害を標的とした創薬をすることにしたのは、どのがんも、血管の新生がなくては生きていけないと考えたからだった。つまり、特定のがんではなく、さまざまながん種に効く薬であれば、それだけ市場が広いことになる(この仮説は後に正しかったことがわかる)。それともうひとつ、血管の新生は、傷口ができると、血管ができて治るように、人間にとってなくてはならないものだ。ということは、がんが薬に対して耐性をもつということが回避できるのではないかと考えた(しかし、これは後に間違っていたことがわかる)。
ともあれ、このふたつの理由から、エーザイのがんグループは、血管新生阻害薬の開発に着手したのだった。

多くの合成化学者はひとつも薬をだせず定年を迎える

冒頭の合成化学者鶴岡明彦が、がん研究に加わるのは、1995年。その鶴岡や船橋が入社した1990年4月2日に、内藤は、こんな話を全社にしている。
「研究開発活動はきわめてハイリスクな分野である。おそらくいかなる世の中のビジネス活動よりもリスクが高いであろう。何千、何万もの化合物のなかから薬になるものは、たった一つあるかないかで、生み出したものに関しては企業の全存在をかけて有効性と安全性を保証しなければならない」
また、1992年の社内報「週報」にはある大学の教授の話を引用する形で、こんな一文が掲載されている。
<新薬の研究開発には長い年月と莫大な経費、それに何人もの“つはもの”たちの労苦の積み重ねが必要とされる。しかもそれらの中に正当に評価を得られぬままに埋もれていく研究の数々もそれこそ数え切れぬほど多い。 そういう意味では“一将功なりて万骨枯る”という言い方が近いのかもしれないが、実は新薬の開発ではたとえ一将と言えども功名を認められることは殆どない。なぜならば新薬の評価は作り上げられたその時点では定まらないからだ。しかもその評価はその薬を作ったことに対して行われることは殆どない。即、薬が正しく用いられ、正当な治療効果を上げた時、大方はその医療行為全般に対して下されることが多い。たとえ治療に当たった医師は名医とたたえられることがあっても、そこで 使用された薬が名薬としてたたえられることはない。それどころか多くの薬は少しでも優れた薬効を持つ新薬が登場すれば、たちどころに置き換えられ、それを作った人たちの労苦とともに比較的短期間のうちに消えていく>
実際、合成化学者の鶴岡は、入社時に、先輩からこんなことを言われている。
「多くの合成化学者は、ひとつも上市しないで、定年をむかえるんだ」
何千、何万もの化合物のなかから薬になるものは、ひとつあるかないか――。
そのひとつを求めて、鶴岡の合成の日々が始まる。
つづく
証言者・主要参考文献
内藤晴夫、鶴岡明彦、大和隆志、船橋泰博
Tumor Angiogenesis :Therapeutic Implications, Judah Folkman, M.D., The New England Journal of Medicine, November 18, 1971
Pituitary follicular cells secrete a novel heparin-binding growth factor specific for vascular endothelial cells, N Ferrara, W J Henzel, Biochem Biophys Res Communication, June 15, 1989
