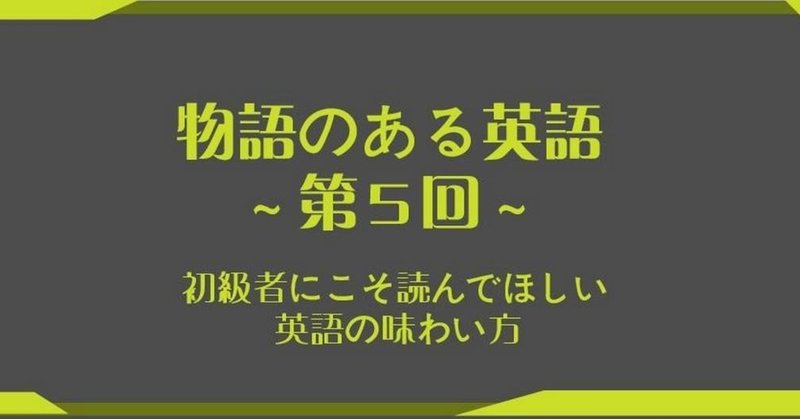
[物語のある英語]~第5回~too many irons in the fire,燃えるアイロンは警告する
-こんにちは!スロバールです。
言葉は人によって作られた。だからその過程には物語があって味がある。
単語帳では語られない物語を味わって味わい尽くそうというのが本シリーズの目当てです。
第5回目は「(have) too many irons in the fire」についてです。直訳すると(have) too many irons (アイロンが多すぎる) + in the fire (火の中に)で、火の中に多すぎるくらいのアイロンがある、という意味に見えます。

◆目次◆
・(have) too many irons in the fire の意味
・ironの発音
・鍛冶屋の仕事のお話
・too many irons in the fire の使い方
・スロバール流解釈~マルチタスクへの黄色信号~
・関連表現
-求婚者の多い娘は...
-2つの椅子の間に...
これもやはり単語だけ眺めていても、実際にコンロにアイロンを投げ入れても(危険ですのでおやめください)意味は分かりません。鍛冶屋の仕事ぶりに由来しているので今日はそれに迫っていきましょう。
◆(have) too many irons in the fireの意味◆
この表現の意味は「多くのことを一度にするな」という意味です。
まずこの意味を解説する前に、ironが洋服のシワをとるアイロンではなく、「鉄」という意味であることに触れておかなければなりません。
英語圏でもironはシワ取り用のアイロンを指しますが、意味を明確にするために「steam iron (蒸気アイロン)」と言います。
これで、炎の中に入れるのはアイロンではなく鉄の塊であるということが分かったのでより鍛冶屋のイメージに近づきましたね。
◆ironの発音◆
ここまで何回かironという単語が「アイロン」と読まれるかのごとく使われてきましたが、もし「アイロン」とカタカナ発音してしまったら伝わりません。読み方は完全に和製英語だからです。

読み方のイメージは「アイアン」で、最初のアが強く読まれます。
英語は日本語とは違ってスペルと読み方が一致しないので毎回発音をチェックしないといけないのですよね。
正しくironが読めるようになったところで、いよいよこの表現の由来についてです。
◆鍛冶屋の仕事のお話◆
今の鉄鋼業は恐らく自動化が進んでいて、一度に大量の金属を加工できるはずですが、昔の鍛冶屋さんはそういうわけにはいきませんでした。一つずつ手作業で金属を加工する必要があったのです。
どのようにかというと、
まず常温の鉄の塊を炉の中に入れるところから始まります。鉄が粘土みたいに常温で加工できれば楽なのですが、そうはいきません。
ある程度鉄を熱して柔らかくなり始めたところで炉から出し、冷めない内に叩いて加工します。
このタイミングが結構シビアで、早すぎるとまだ固くて叩いても形が変わらないし、遅すぎると鉄が完全に溶けて液体になってしまい加工できない…
だから鍛冶屋というのは常に集中力を要する仕事なのですが、もし炉の中に欲張ってたくさん鉄を入れたらどうなるでしょうか?

鉄の量が多すぎることから個々の鉄へ伝わる熱が減ってしまい、いつものタイミングで炉から鉄を出してしまうとまだ鉄は硬めの状態で、その状態で鉄を叩いて加工しようにもいつもの2倍激しく叩かなければいけないのです。
このように、一度に多くのことをしようとすると、かえって労力の無駄遣いになってしまうためhave too many irons in the fire は「多くのことを一度にするな」という意味になったのです。
◆have too many irons in the fire の使い方◆
現代では、火の中に鉄を詰め込みすぎることはありませんが、
日の中にスケジュールを詰め込みすぎることはあるので、
火=毎日
鉄=スケジュール
と読み替えると下の例文がしっくり来るでしょう。
・I had too many irons in the fire and missed some important deadlines.
(毎日スケジュールを詰め込みすぎたせいで、大事な締切をいくつか忘れて
しまっていた)
・So it's better not to have too many irons in the fire.
(だから毎日スケジュールを詰め込みすぎない方が良い)
◆スロバール流解釈~マルチタスクへの黄色信号~◆
そもそもどうして一度に複数のことをすると悪い結果に終わってしまうのでしょうか?
なぜあの鍛冶屋は、鉄がいつもより多いから熱の通りが悪いと知っていながらも、いつもと同じタイミングで鉄を炉から出してしまうのでしょうか?
ここまで読んでこられた読者の皆様なら簡単に想像できると思いますが、
判断力の低下でキャパオーバーの状態になるせいでしょう。
「あれも、これも、考えている内に何が何だか分からなくなってしまう」
「何がとこまで進んでいるかが把握できなくなってしまう」
ここまでなら想像するのは難しくないのですが、もう1歩深めて考えれば、
「マルチタスクをする→最悪の結果を進んで選ぶ可能性大」
と言えるのではないでしょうか。
マルチタスク中、何か決断を下さないといけないという時、判断力の低下から最悪の決断をしてしまう。
これは、たくさんの物から何かを選ぶときにも言えます。
・ 3つの中から1つを選ぶ。
・10個の中から1つを選ぶ。
・50個の中から1つを選ぶ。
3つめが一番脳への負荷が大きいのは明らかですね。
50個の物を比較する時、その比較はリアルタイムで進むので「同時進行」だと言えますね。
それはマルチタスクではないでしょうか?
えっ、そんな状況ありません!、、、、ですって?
・就活生が50社、100社を見比べる。
・婚活で50人も100人も「ちょっといいなぁ」と思う人がいる。
・ほしい洋服が50着も100着もある。
・近くのレストランを検索。検索結果は50個。
情報が溢れている今日、50個程度の中から1つを選ばないといけないなんて言う状況は実にザラにあります。
だから、have too many irons in the fireという表現は私にはどうも「情報社会で生きるマルチタスクの現代人に送る注意報」に思えて仕方ないのです。
◆関連表現◆
昔の人はエライ!ちゃんと分かっているんです。こんな諺があります。
・A maiden with many wooers chooses the worst.
(求婚者の多い娘は最悪の人を選ぶ)
日本語でいうと、「進んで滓(かす)を選ぶ」になります。

あれもこれもと査定している内に、時間だけが経ち結局、選択肢の中に悪いものしか残らなくなるという教訓ですね。
実際に有名な心理学者であるバリー・シュワルツも「選択肢の広がりは人を不幸にする」と言っています。
また、こんな表現もあります。
・Between two stools you fall to the ground.
(2つの椅子の間に座れば尻もちをつく)

どっちの椅子がいいかな?こっち?あっち?と迷って中途半端に、2つの椅子の間に座ればドカン!と地面にお尻をつく羽目に遭います。
ということでこの記事の締めはやはりこれでしょう。
One thing at a time.
(1回につき1つのことまで)
one thing (1つのこと)、at a time (1つのタイミングに)
いつも記事を読んでいただきありがとうございます。英語学習に苦しんでいる方、つまらなそうに嫌々語学を学んでいる方が周りに居ましたら、シェアしていただければと思います。楽しく、深く、語学に取り組める人が1人でも増えたら幸いです。
