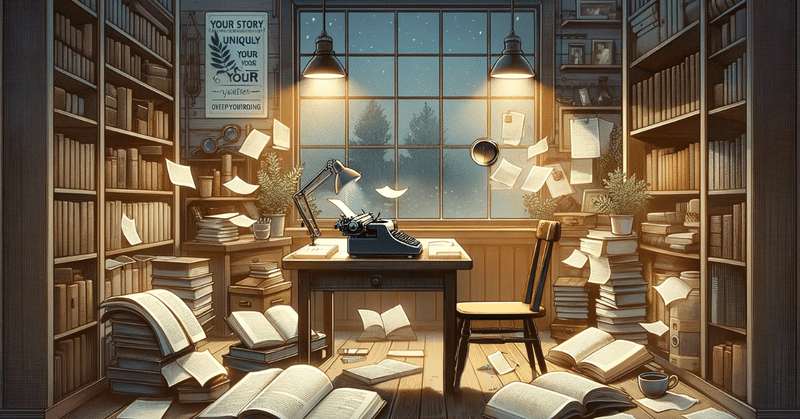
感想『君の物語が君らしく』
Google for Education認定トレーナー/コーチの笠原です。
本日は読書の記録と感想の共有です。
あすこま先生こと澤田先生が出版された『君の物語が君らしく』の感想をざっと書きます!
国語を教える人間としても、一人の読者としても、この一冊は多くの人に手に取って欲しいと願ってやまない一冊です。
上手く書けないので…
色々とお世話になっているあすこま先生の渾身の一冊なので、なんとか上手いこと紹介記事を書きたいなぁと思っていたのですが、一向にうまくアイデアがまとまりません。
色々なところにひっかかり、立ち止まって、その度に深くうなずきながら進んでいった読書体験を、上手く表現できるまとめ方が分かりませんでした。
だから、もう諦めて、何カ所か印象的な部分を引用しながら、ぽつりぽつりと感想を述べていこうと思います。
読者としてなのか、書き手としてなのか、国語科の教員としてなのか…どの立場で自分はこの本を読んでいるのだろう?そういうこともハッキリしないままに書き始めています。
とりとめもなく、感想
以下、引用と感想。たくさん引用したいのですが、厳選して。ページ順に。
他人との比較は、あなたを縛る呪文のようなもの。苦手な人は、いくら自分が頑張って言葉を紡ぎ出しても、常に「その上」がいるのだから苦手意識は消えない。逆に、得意な人だって、狭い教室を一歩出て自分よりも得意な人に出会った途端に、その自信は吹っ飛んでしまう。
比較するということを通じて、相対的に自分のことが分かる面は確かに多いのです。だから、何かをやってみようというときに「他の人と比べて」ということを無意識にやってしまいがちです。
教室の仕組みがどうしても他の人を気になるような仕組みになりがちなのも影響しているかも知れませんね。
だから、国語の授業をやっていても、「あなたの意見」を言えるようになるまでというのが非常に長い。そして、比較からではない言葉が出てくる瞬間って本当に少ないと思っています。その瞬間の言葉を見落とさないことがとても難しい。
他者を気にしないで、書く営みに一人で向き合ってみる。そうやって書くことを自分の手に取り戻した時、はじめてくっきりと見える書くことの魅力がある。
授業の枠の中だとどこまで出来るのでしょう。自分自身の授業を振り返って色々と考えてしまうところです。子どもたちの中にある他者への意識を授業という枠組みを使って、都合良くモチベーションにしていないだろうかと反省するところです。
自分の物語には価値がないなんて、勝手に思い込まずに。
こういう言葉を積み重ねていくことを大切にしたい。本書でも自己検閲の話が出てきていますが、生徒の自己検閲はとても強い。何でもかんでも開示しよう!という明るさは自分はありませんが、自分のことを言葉にできる場所で授業があって欲しいとは思っているのです。
でも、一歩踏みだして、あなたの書いた文章を実在の他者に開くと、それは直接外の世界とつながり始めます。(中略)書いたものを外に開くことは一種の賭けですが、その賭けがもたらす豊かなつながりの可能性を、どうか忘れずにいてください。
自分の世界に他者を招き入れることを子どもたちに伝えるということは、授業の経験年数が増えるほど、難しく、繊細に考えるべきことのようにおもうようになりました。まさに願うような気持ちだよなぁ…まさに祈りと言うべきか。
願わくば、書くこと、自分の物語を開くということが、国語の授業で一度でも体験できて欲しいなと思うのです。そういう体験が、自分の言葉が世界とつながったという体験が、おそらく学校の外に出て行く自分を強く勇気づけるでしょうから。
そういう体験が出来る国語ならば、楽しいのだろうなあ……。国語の授業は楽しくあって欲しい。
自分を支える言葉を探す
どうやら自分は書くことの授業を通じて、子どもたちが自分の言葉で自分を支えて生きていけるようになることを願っているようです。
世界は言葉に溢れているのだから、国語の授業は何を題材にしても国語の授業になると思っています。
だからこそ、その豊穣な言葉と上手く自分が折り合いをつける場所を見つけて、自分がはっきりと立ち上がれる場所としての言葉を、国語の授業で見つけて欲しいのだと思うのです。
言葉の力を経験できるような、そういう授業を考えていきたいですね。そのためには本書のタイトルの通り「君の物語を君らしく」と願うのでしょうか、自分も。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
