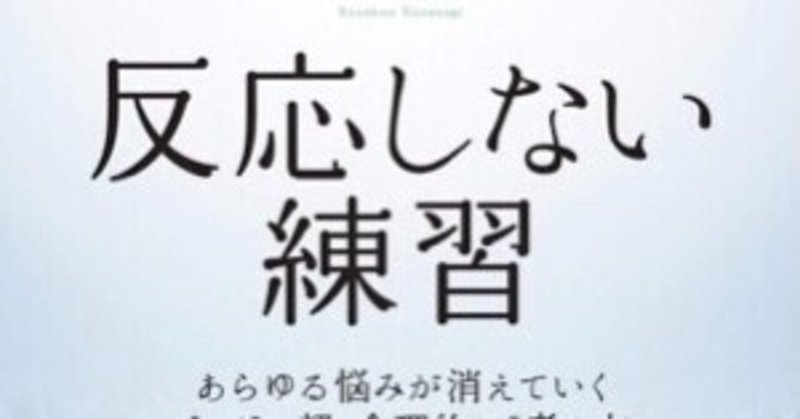
【書評】「反応しない練習」から学んだこと
今までやってみたいなって思ってたことが「書評をブログで書く」ということでした。自分なりに体得したい技術や、より学びたい内容、どこかで悩んでる人の助けになれそうな内容、そういったものを発信していきたいと思い書いてみました。今回書いた内容はマインドフルネスを実践化する際にも役に立った一冊、草薙龍瞬さんの書いた「反応しない練習」を自分なりに心の残った部分を中心に紹介しつつ、自分の経験など踏まえて綴っていきたいと思います。
悩みを作り出してるたった一つの原因とは?
それは「心が動いてしまうこと」と、根本的な解決方法は「無駄な反応をしない」。怒りや不安や「どうせ自分なんて」という思いが出てくるのは心が反応してる時。素早くリセットして解消することが悩みを無くす。反応を作り出してる真の理由は「喜びを求めてやまない心、求め続ける心」が原因。求める心が7つの欲求を生み出してる。①生存欲②睡眠欲③食欲④性欲⑤怠惰欲⑥歓楽欲⑦承認欲。この欲求に突き動かされて反応して悩みを作り出してる。
ふむふむ。悩みや不安は「心が反応した時」とのこと。不安な思いが生み出される時は7つの欲求に突き動かされ反応した時なんだな。自分の最近の悩みパターンは、「仕事で面倒なことに巻き込まれないかな?巻き込まれないで楽したいな。でも楽したいけど周りから仕事してないやつって思われたくないな」。こんな気持ちをよく抱くんですよ。これは「⑤怠惰欲」「⑦承認欲」この二つの欲に刈られてることが多いですかね。こんなモヤモヤをどう解消したら良いですか?草薙先生、教えてください!とそれは次の項目で。
悩みは無くそうとしない。「理解する」。
まず前提として「人生に悩み・問題は付きもの。人生に苦しみが伴うのは永久の真理」。まずは理解に徹する。自分には未解決な問題があると客観的に自覚する。その後が大事で「でもきっと解決できる」と考えよ。心の状態をきちんと見ること。きちんと見るには手順がある。
①言葉で確認
②体の感覚を意識
③その感情をラベリング(意識)する。
ラベリングは「貪欲」「怒り」「妄想」の3つの要素で分類しやすい。悩みを増やしたくないなら、反応・妄想を減らして「体の感覚を意識すること」
①「言葉で確認」は口に出して言うのも良いけど、僕のおすすめは時間に余裕があるなら「書く」ことです。一旦自分の中から取り出して実体化させて客観視できると今まで違った見方が出来たりします。
②「体の感覚を意識」は「体の感覚に意識を集中させると妄想から抜け出しやすくなる」とのこと。ここは正直言うとイマイチ腑に落ちてない・・・。本には「感覚に意識を集中させると妄想から抜け出しやすくなる」と書かれてました。これは瞑想時に呼吸から意識がそれたと「気付く」に近い感覚なんでしょうかね。そもそも最初の「反応した!」って言う気づきも瞑想で鍛えれらることなんじゃないかなとに思います。
③「ラベリング」は感情の整理ですよね。ここまで来て分類できると僕はスッキリした感覚になることが多かったです。上の仕事に対する思考にも「面倒なことが起きそうだなーっていう妄想」、「怠けたい・休みたい・周りから嫌われたくないと言う欲」。こう言った悩みが自分にはある、しょうがない、人間だもの、ぐらいに思うようにしてます。
自分を否定しない。どんな時も。
失敗したと思ってもそこで凹まず自分を否定しない。「自己否定の判断に打ち勝つ!」。日頃ネガティブな判断が心に浮かんだらそこでゲームオーバー。その先にあるのは自己否定という暗い妄想。自己否定に合理性はない。自己を否定するより「今を見据えて正しく理解して、ここからできることに専念する」。人が悩んでしまう理由の一つは「判断しすぎる心」。この仕事に意味はあるか?彼と私はどっちが優れてるか?「良い・悪い・好き・嫌い」という判断をやめる。人間わかったふりや、結論が出せると安心してしまうという習性があるそうです。自分自身どんな時も自己否定の判断をせず、あるがままを見つめる。そしてどんな時も「私は自分自身を肯定する!」と自分に言ってあげる。自己否定をしないという教育は今日の日本ではなされてない。でも苦しまずに生きていくことを念頭に入れた際に自己否定しない・自己否定に合理性はない、だから「自己否定をしない修行」を日々積んでくべしとのこと。
僕自身HSPなところもあり、比較的他人より物事に対しての「罪悪感」に苛まれることが多いように思えます。でも罪悪感って一種の自己否定ですよね。最近自分の身に起きた罪悪感を言うと、日曜日に「明日からの仕事がやだ。サボりたい。あ、不真面目な自分がいる。なんてダメなんだ」って思ってしまいました。この時自分自身を肯定してあげられてたら、「仕事に対して責任感持ってて偉いね」とか「人間楽したいし生き物だし、そう思うことが普通だよ」とか、今でもそう思うだけで心が楽になれる気がします。また本には「自分は自分を肯定する」と言いましょうってあるけど、自分が生きてきて「肯定」なんてあまり使わず、自分自身に語りかけてもピンとこないんですよね。恥ずかしい話最近まで「せいてい」って読んでたぐらいだしwだから少し言い換えて「自分は自分を認める、受け入れる、頑張ってるって認める」と言うようにしてます。このあたりは自分に響きやすくカスタマイズしても良いかも。ただ「自分は出来る」とか「日増しに良くなってる」と言ったような実態が伴わない言葉は自分自身の理解が追いつかない場合があるそうなので、あくまで「肯定」の延長線上の言葉で考えてみてください。
正しい動機を用意する
競争社会において、競争に乗るか、降りるか、別の競争の中で生きるか、という3つの選択肢がある。「別の動機」という新しいモチベーションにたった時、「競争の中にあって、競争に苦しまない生き方」は可能になるとのこと。それには4つの心構えが大事になるとのことです。
①慈【慈しみの心】相手の幸せを願う気持ち
②悲【悲の心】相手の悲しみに共感すること
③喜【喜びの心】相手の喜び・楽しさに共感すること
④捨【捨てる心】手放す心、捨て置く心、反応しない心
世間ではこれらをまとめて「愛」と呼ぶ。仏教ではこの「愛」という概念をこの4つの心の働きかけに分けて分類するとのこと。
僕の得意先にすぐキレ散らかす人がいます。機嫌が良いと問題ないのですが、機嫌が悪いと理不尽な高圧的な発言を連発。この時代にそんなこと言っちゃうの?いつか訴えてやる(帽子投げながら)!って心の中で何度も思いながら我慢して対応してました。この「反応しない練習」を意識してもまだその人に対しての嫌な思いは拭いきれないし、その人に会うと思うと憂鬱になります。それでもこの考えを学んで、「この人も自分と同じで悩んで反応してる、その人の仕事をその人なりに全うしようと抗ってるんだ」と思えたときに少しだけ許せるような、自分の気も落ち着くような感覚になれました。いざとなるとこの4つの考えがパッと出てこない時もありますけど、今後普段使い出来るようにクセ付けしていきたいと思ってます。
今日のまとめ
①結局瞑想最強説
僕自身、普段毎日瞑想することを心がけてますが、反応しない練習を実践する中で役に立つスキルを自然と身に付けることができると思います。瞑想についてはお金もかからず気軽にできるので興味がある方はやっといても損はないと思います。
②反応に気づいてからのサイクルを習慣化する
反応に気づく⇨言語化(口に出すor紙に書く)⇨ 10秒でも1分でも良いから体の感覚に集中⇨ 3つの要素にラベリング⇨ 自分には未解決の問題があると自覚⇨でも必ず解決できる・合理的に考えよう・今できる最善を尽くそう とこの一連の流れを習慣化出来ればいいですよね。こちらは今後私自身の身をもって習慣化を実践してみようと思います。この結果等は後日またこの場でご報告できればと思います。
③みんななんらかしらの悩みを抱えてる、そしてそれを解消すべく抗って生きてることを再度認識する
慈悲喜捨を意識することをクセ付けしたいですけど、その前に「人生に悩み・問題は付きもの。人生に苦しみが伴うのは永久の真理」っていう前提を思い出せば自然とそういう気持ちになれる気がします。YouTubeで大愚和尚の一問一答見るの好きなんですが、そこでよく使われてる「一切皆苦」と言うことですね。人生は苦しいことが前提、そこからいかに工夫して生きてくかが人間の目指す道、と和尚は言ってました。
この本にはもっと良いことや人生に役立つことが書かれてました。この本を読んだ方で「いやいやそこの解釈違う」とか「ポイントここでない」とか思う方いらっしゃるかもしれませんが、こういう受け取りかたをする人もいるんだぐらいの気持ちで見てもらえたら幸いです。書評って初めての試みで書いてみましたけど、この本が言いたいエッセンスをだいぶ凝縮しないとまとまらないもんですね。時間もかかったしまあまあ大変でしたけど、これからもぼちぼち書いてみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
