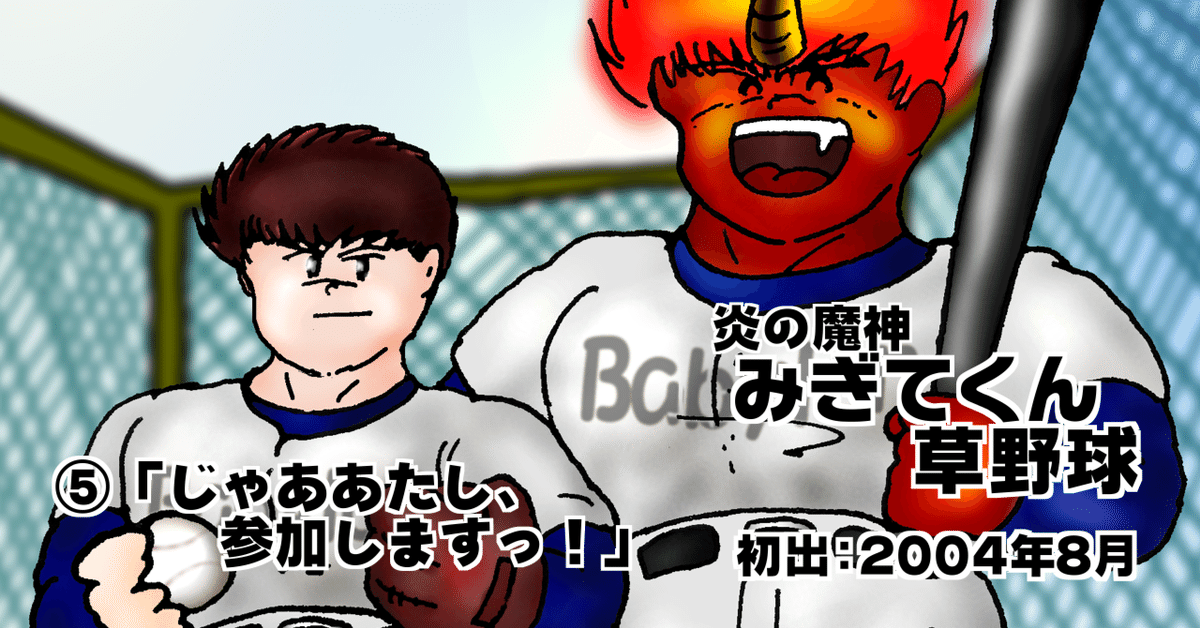
炎の魔神みぎてくん草野球⑤
5.「じゃああたし、参加しますっ!」
ところが…二回の表になって、いきなり状況は変わってしまった。そう、カーンという爽快な快音がグラウンドを響き渡ったのである。
「あ…打たれた」
『大きいっ!大きいっ!入った~』
自動実況中継マシンが興奮した声を上げる。二回表、経済学部チームはいきなりのホームランである。4番アラリックが見事な先制ソロを放ったのである。超軟投のロスマルク投法は、素人相手には非常に有効だが、さすがセミプロ級の野球部相手にはつらいものがあったのだろう。筋肉脱ぎ系ボディーから生み出されるパワーで、強引に持ってゆかれてしまったというわけである。
「先制されちゃったわね…」
「三回まで持つかなぁ…」
コージもセルティ先生も心配そうにロスマルク先生を見る。が、意外と先生のほうはショックではないらしく、飄々とした表情である。
「ほっほっほ、まだ大丈夫じゃよ」
ロスマルク先生は笑ってコージたちに手を振ってきた。まあ相手が野球部であるということで、ある程度覚悟は決めていたのであろう。この様子なら精神的には全然問題はなさそうである。が、身体のほうは判らない。
なんとか続く5、6、7番バッターをなんとか例のふにゃふにゃ球でしとめたロスマルク先生だったが、さすがにコージから見るとすこし球威が落ちてきたという気がする。五十過ぎのおっさんには二回まるまる投球するというのは、そんなたやすいことではない。プロの野球選手だって9回完投は大変なのである。この歳になれば2回だって一苦労なのは間違いない。
「コージ、ロスマルク先生、次の回が関の山かもしれませんよ。その後どうします?」
「そうだな…うーん」
はじめから予想していたことはいえ、こういう時の判断は難しい。ロスマルク先生が疲れきってしまってダウンする前に、リリーフでコージが出るしかないのは判る…が、「いつ」となると話は違う。思い切って次の回から出るべきなのか、それともあと一回はロスマルク先生に任せるべきか…
「ともかくみぎてが打ってくれないとつらい。みぎて、がんばるよーに」
「よしっ、任しとけって!」
前の回の蒼雷たちの惨憺たる有様など見ていなかったかのように、みぎては足取りも軽くバッターボックスに向かう。身体のでかいアラリックと同じくでかいみぎての対決は、まるでメジャーリーグの試合のようになかなか見ごたえがある。アラリックは大きくモーションをとって振りかぶった。ところが…
「あっ!」
「げっ!」
「みぎてさまっ!」
驚いたことにすっぽ抜けたボールはみぎての肩に見事に直撃したのである。これは痛い…完全にデッドボールである。わざとというわけではないだろうが、痛打であることには変わりない。
「大丈夫か?みぎてっ!」
「いててっ。平気平気」
こういう時は痛そうにアピールするのが戦術なのだろうが、そこで強がってしまうところがこの魔神のバカというかなんというかなところである。まあしかし実際のところ、みぎてはこの程度の打撲くらいならあっという間に治ってしまうのだから、あまり痛そうにするのも気が引けるのは理解できる。
「あ、ごめんごめん!平気?」
アラリックは気楽にいうが、相手がみぎてでなかったら骨折くらいしていたかもしれない。コージは思わずむっときてしまう。ひょっとするとビーンボールといったほうが正しいかもしれない。とはいえ、相手がとりあえず謝っている以上、危険投球だと審判に対してねじ込むのも難しい。隣に座っているポリーニもかんかんである。
「やっぱりあいつ汚いわっ!やっぱりユニフォームのクロスプレー戦闘システムを…」
「…だからポリーニ、それ反則」
「僕も散々言ってるんですけどねぇ…」
ポリーニの怒りももっともだが。「クロスプレー戦闘システム」となると殺人兵器になりかねない。ともかくあくまで反則技ではないところで勝負をするのが大事なのである。
* * *
さて、せっかくのみぎてのデッドボールだったが、残念なことに続く打線がダメだった。ディレル、セルティ先生、ポリーニと三者連続三振であっという間に2回の裏もおしまいである。コージとしてはもう少し粘って、ロスマルク先生を休ませたいと思っていたのだが、相手がそれを許してくれないというわけだった。
「先生、大丈夫ですか?後1回…」
「おお、当然じゃよ。どうせ下位打線じゃ。8番バッターなら歳もワシと変わらんよ」
ロスマルク先生は意気揚々と立ち上がるが、なんだか腰あたりが頼りない。が、本人がやりたいといっているものを無理に止めるというのも問題である。それにたしかに次のバッターは同じく老体イェーガー教授である。年寄り対決に水をさすというのも気が引ける。というわけでしかたなくコージたちは守備についたわけである。
ところが…
バッター二人を討ち取ってしまうと、打順は当然トップバッターに戻ってくる。野球の定石だが、トップバッターというのは打率が高い、とにかく塁に出る人がなるものである。つまり手ごわい巧打者というわけだった。ロスマルク先生もなめてかかるわけには行かない。
「ふんっ!」
掛け声と共に老先生は投げた…ふにゃふにゃとゆっくりした球がディレルのミットめがけて飛んでゆく。バッターはその球の遅さにつられて、中途半端なタイミングで軽くバットを振った。打たされたといったほうがいい。さすがはロスマルク軟投作戦である。
打球はごろごろとピッチャーのほうへと転がっていった。典型的ピッチャーゴロである。ロスマルク先生はそれを華麗にキャッチして、ファーストに投げようと身体をひねった。その時だった…
「うっ!」
「あっ!先生っ!」
突然ロスマルク先生は投球姿勢のまま動けなくなったのである。ボールをしっかり握り締めたままである。顔には苦痛の色が浮かんでいる。
「出たっ!ぎっくり腰…」
「ええっ!」

バッターは既にゆうゆう一塁についているが、ロスマルク先生はまったく動けない。完全にぎっくり腰状態で、動くに動けないのである。あわててコージはタイムを叫んで、そのまま老先生のところに駆け寄った。
「先生っ!」
「ううっ!ここで腰痛とは!無念…」
「みぎてっ!蒼雷っ!ちょっと頼む!」
外野から飛んできたみぎてと蒼雷の二人は、ロスマルク先生をそっと抱えてベンチへつれてゆく。とにかく後で医者に見せるのは当然として、今は休憩とみぎて得意の針治療しかない。(みぎては拳法をやっているので、この手のつぼ治療は得意なのである。)が、いずれにせよもはや野球が出来る状態ではない。
「コージ、どうします?控え選手っていっても…」
もともとぎりぎりの人数なのである。ロスマルク先生が退場するとなると、ピッチャーはコージがやるとしても人数がたりない。かといってこれで試合放棄というのはお互いにしこりが残る。みぎてがビーンボールを喰らい、ロスマルク先生まで腰痛となるとなんだか悔しすぎる。実際ロスマルク先生はよほど悔しいらしく、腰を抑えながらもコージに言った。
「コージ君、なんとか試合を最後までやりたまえ…ううっ」
「せんせ、しゃべると痛みが出るからダメだって…」
針治療担当のみぎてがあきれ返るくらい、ロスマルク先生は悔しがっている。それに比べて相手チームはもう勝ったつもりでいるのか、向こうのベンチでお茶を飲んだりおしゃべりをしたりしている。アラリックなどは楽しそうに頭の上から水をかけて、得意満々でさっきのホームランの話に興じているようである。やはりこれはあまりに悔しい。めんどくさがりのコージだってそれくらいの意地はある。
「おい、そっちのチームどうするんだ?メンバー足りるのか?」
アラリックが上半身水浸し状態でコージのところにやって来た。どうやら事情を悟り、引導を渡しにきたというわけだろう。コージは困惑と不満一杯の目で、周囲を見回す。コージ、みぎて、蒼雷、ディレル、シュリ、ポリーニ、セルティ先生、目玉…いくら数えても8人しか残っていない。これではもはや試合放棄しかないかもしれない。
ところがその時だった。
「じゃああたし、参加しますっ!」
「えっ!」
「氷沙ちゃんが?」
今までロスマルク先生を心配そうに看病していた氷沙は、意を決したようにそういったのである。どうやらさっきのみぎてに対するビーンボールに、彼女もかなり怒っていたのである。
「あたしだってボール投げるのできます。雪合戦なら得意です!」
「…雪合戦と野球は微妙に違うような気もするけど…」
思わずディレルは突っ込みを入れそうになるが、コージが横からわき腹をつついて止める。こうなったら氷沙ちゃんの雪合戦パワーにかけるしかないかもしれない。いや、他に選択肢は無いのだからそうするしかない。
コージは呆れ顔のアラリックに振り返って、さもわざとらしく申し訳なさそうに言った。
「ってこと。悪いけど試合続行できそう。」
「ふうん、まあいいや。その和服の娘かわいいから後で紹介してくれよな」
「なんですって?」
ポリーニがまたすごい顔をするのを見たコージは、苦笑しながら再びグローブを手に取ったのである。
* * *
というわけで、ごたごたの後ようやく試合は再開となった。ロスマルク先生の代わりに氷沙ちゃんが出場である。ピッチャーにコージが入り、ショートはセルティ先生、そしてサードに氷沙ちゃんという、女性たっぷりの内野陣である。悩殺ナインという言い方をすれば聞こえはいいが、ますます苦しい状況になっていることは間違いない。まあもっとも向こうのチームも、アラリックと他の二、三人を除けば教職員で、そろそろ疲れが出てきてもいいころである。それが吉と出るか凶と出るかについては、コージにも予想はつかない。が、普通に考えるとやはりセミプロ級のアラリックをどうにか討ち取らないと勝ち目が無いだろう。そして次の回にはいよいよアラリックの打順が回ってくるのである。高校野球経験者のロスマルク先生でも通用しなかったのに、はたしてコージで討ち取ることが出来るのだろうか?
いろいろ悩んでいるうちに、3回裏はあっさり終わってしまった。またしてもアラリックの剛速球に抑えられてしまったのである。コージは首を横に振り、マウンドへと向かおうとした。するとキャッチャーのディレルがコージを呼び止めた。
「どうします?アラリックさんは敬遠って手もありますよ」
「敬遠かぁ…」
たしかにホームランを打たれるよりは敬遠したほうがましである。が、さっきからのアラリックの挑発的な言動を聞くと、いくらコージでも少し腹が立ってくる。やはりできることなら正面切って対決したい気もする。
渋る表情を見せたコージにディレルは言った。
「アラリックさんのあれ、戦術かもしれませんよ。まあ自信があるからでしょうけど…」
「挑発してるってことか…」
コージはうめいて、それから一瞬外野へ向かうみぎてのほうを見た。みぎてはニコニコ笑ってコージに手を振った。「打たれてもいいから精一杯やろうぜ」という意味である。その笑顔を見ると、コージは今までの不安や迷いがうそのように消えるのを感じた。別にこの試合に勝って全国大会に行くとか、そういう目的があるわけではない…精一杯、野球を楽しむことが目的なのである。なら精一杯やればいい。
「ディレル、ホームラン打たれてもたかだか一点だって。かまうもんか」
「…うーん…まあそうか。そうだね」
吹っ切れたようなコージの表情に、ディレルも納得したらしい。思い切ってプレーした方があとくされがない。
コージはピッチャーマウンドに登って、ぐっとボールを握り締めた。バッターボックスに立つアラリックはひときわ大きく見える。威圧されているという言い方も出来るが、代わりにストライクゾーンが広いわけである。こういう考え方が出来るということも、後ろで守っている相棒や、講座の仲間、それに蒼雷や氷沙ちゃんのような友達のおかげかもしれない。そう思うとコージはなんだか自信が付いてきた。
コージは思い切り振りかぶると、ボールをミットに向かって投げた。
「あっ!」
「ファウルか」
コージの球はさすがにロスマルク先生よりもずっと速い。速球派というほどではないが、かなりの球威である。さっきまで超軟投のロスマルク先生を相手にしていたということもあって、さしものアラリックも驚いたようだった。なんとかバットをあわせたものの、振り遅れのファウルである。
「コージくん、いけるじゃないですか!」
「きゃーっ!頑張ってっ!」
声援がベンチではなく、後ろのナインから飛んでくる。というより既にベンチには誰もいないのだから当然だろう。が、今のコージにはそれがとても心強い。思い切って投げればいいのだという気持ちになってくる。
二球続けてファウルの後、今度は外角低めにボールを投げる。が、さすがにこれは手を出さない。相手もさすがにセミプロである。そこでコージはいよいよ決め球を出した。
「あっ」
「超軟投…」
見よう見真似だが、ロスマルク先生譲りの超軟投攻撃だった。これには完全に奇襲である。速球派だと見せかけてのふにゃふにゃ軟投を喰らうと、いくら強打者のアラリックだってタイミングが狂う。いや、強打者であればあるほど、こういうタイミングずらし作戦には弱いのである。一瞬びっくりした顔になったアラリックは、しかし強引にバットをあわせようとした。
「センターフライだ!」
バットが鈍い音を立てると、打球はふらふらとコージの頭上を飛び越える。が、さっきのホームランのような勢いは無かった。タイミングがずれてしまって、完全に振りぬくことが出来なかったのである。これなら楽々外野が取ってアウトのはずである。が…
その時コージはとんでもないことに気がついた。
「あっ!センター…『目玉』だっ!」
コージは大慌てで後ろを振り向いた。外野のみぎても蒼雷も仰天してダッシュを始めている…が、微妙な位置でとても間に合いそうに無い。これではツーベースヒットは確実である。コージはがっかりしてその場にへたり込みそうになった。
ところがその時、驚いたことにセカンドの後ろにいた大きな野球帽…つまり目玉が動き始めた。それもびっくりするくらいの速度である。八本の蛸足でまるで蜘蛛かなにかのようにがさがさとボールの落下位置に向かって走ってゆく…
「えっ?」
「うわっ!」
あれよあれよというまに、目玉は打球の真下に付くと、突然ころりとひっくり返った。実は目玉という生物は、蛸足の付け根にイソギンチャクのような大きな口があるのだが、それを上に向けたのである。
「あ…取った」
「やられた…」
すっぽりとボールは目玉の口に収まった。ちゃんとダイレクトでキャッチしているのだから、これは立派なアウトである。目の前で見ていたコージも、そして打ったアラリックも、あまりの珍事に呆然として見ているしかない。ゴルフボールをカラスに取られるよりもショックは大きいだろう。打球を食べられたバッターというのは、前代未聞である。
「……バッター、アウト!」
しばしの間沈黙が続いた後、審判は半分やけくそで高らかにアウトを宣言する。と、同時に目玉はプッっとボールを吐き出した。さすがに食べられないものだと理解したのだろう。またつまらなさそうにがさがさ守備位置に戻る。
「うーん、野球っていろいろあるなぁ」
「大丈夫、普通はうちの目玉みたいなモンスター、センター守ってないから…」
ボールを拾ってコージに手渡したみぎての感想は、実はコージの本音とまったく同じだった。
(⑥につづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
