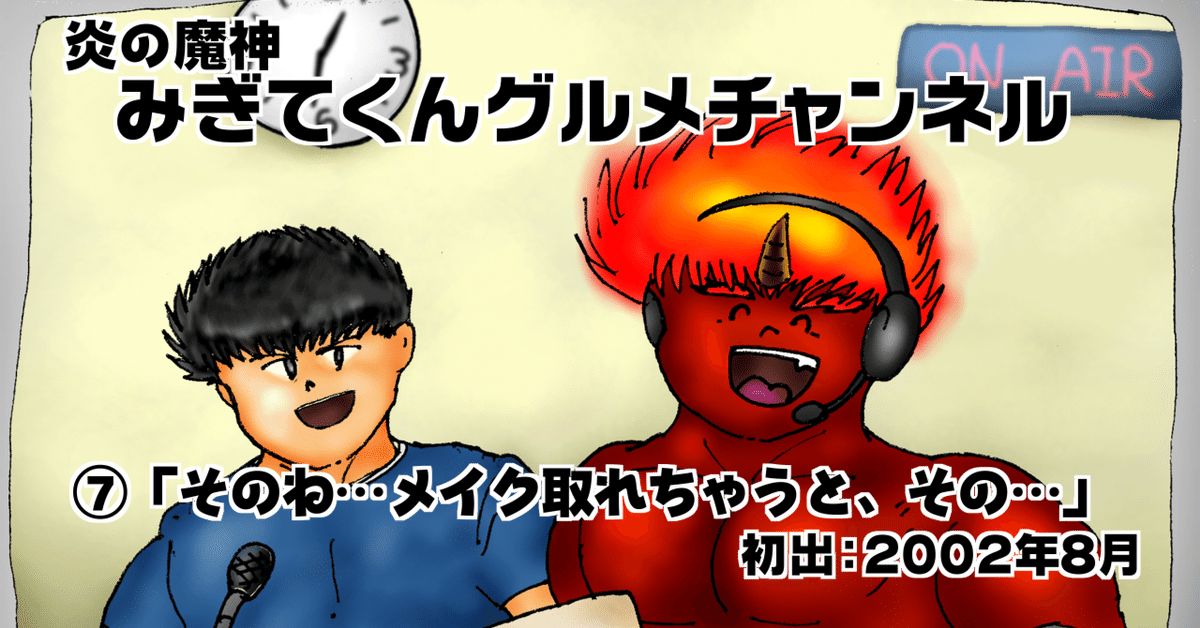
炎の魔神みぎてくん グルメチャンネル ⑦「そのね…メイク取れちゃうと、その…」
7.「そのね…メイク取れちゃうと、その…」
というわけで、「ミラージュ・ド・バビロン」の「お昼のランチコース」ロケは、みぎてにとっては酷寒の、それ以外のメンバーにとっては酷暑の中、とりあえず続行ということになってしまった。困ったことにコース料理というのは、目の前の料理を平らげてしまったとしても、適当な時間になるまでは次の料理が出てこないものなのである。ということは、たとえ室温が三十度を超えようが、最後のデザートが出てくる「決まった時間」まで、全員脱出不可能という恐ろしい事態になってしまう。これはまさしく我慢比べ大会の世界といっていい。
実際一番過酷な状況にあるのは、みぎての右隣に座ってしまったディレルである。彼はコージと違ってごく普通のブレザーを着ているせいで、既に体感気温は三十五℃くらいになっているようだった。さっきから水を何度も飲んで、とにかく暑さに耐えようと必死になっているのだが、いつまで持つかはかなり疑問である。
「メインディッシュのあとが長いですね…もうかなりきついですよ。あ、シュリさん何持ってるんですか!」
「そりゃパーソナル扇風機ですよ。こんなの発明でもなんでもないですが、さすがに妻が倒れるといけませんから。」
「ううっ、今まで見たシュリさんのアイテムで、それが一番まともに見えるんですけど…」
本音を言うと、太目で健康そうなシュリ夫人よりも、青びょうたんを地で行っているシュリ本人のほうが絶対先に倒れそうな気がするのだが、さすがにそれは心の叫びである。ディレルは仕方なくメニューをうちわ代わりにして、無駄な抵抗を試みる。
ところが反対側の席にいるポリーニは、ディレルのそんななさけない姿に手厳しい批判をぶつける。
「情けないわね。この程度暑いうちに入らないわよ。シンさんからも何か言ってやってよ。」
「…うーん、でも結構きついんじゃないかな。僕は意外と暑くても平気なんだけどね」
「やっぱりスポーツマンは違うのよね。ちょっとは見習いなさいよあんた達も」
やはりポリーニは筋肉系の人物にはとても弱い。それにシンの場合はタレントということでマスクまで格好いいのであるから言うこと無しである。思わずコージたちは肩をすくめるしかない。
しかし、このあまりの暑さに耐え切れなくなったディレルは、ついにトイレ休憩を宣言する。というよりさっきから水を飲みすぎて(ワインはあの一杯だけである。無駄な金をロケにかけるわけにはいかない)、トイレが近くなってしまったのだろう。ところが…
席を立ってトイレに行ってきたディレルは、テーブルをぐるりと回って…突然変な顔をする。
「あ…あれ?」
「どうしたんだ?ディレル」
ディレルはそれには答えず、もう一度今度はかなりゆっくりテーブルを回る。そして…おもむろにポリーニのそばに止まって言った。
「ポリーニ、反則ですよそれは」
「どういうこと?反則ってなによ」
「自分だけ涼しい思いって言うのはひどいじゃないですか。ここらへんは向こうとはぜんぜん気温が違いますよ」
「ええっ?」
驚いたコージはあわてて席を立ち、ポリーニのところに向かう。たしかに…たった数メートルしか移動していないにもかかわらず、あっという間に熱気が消えてしまう。汗をかいているディレルなどは寒いと感じるほどだろう。炎の魔神の熱をキャンセルできるほどの冷気が、彼女の周りにしっかりと停滞している。温度差で言えば十℃は軽くあるだろう。もしポリーニがはじめから「我慢比べ大会」を仕組んでいたとするならば、これはあきらかに反則である。
ところが今度は彼女が驚く番だった。どうやら彼女の周りに冷気があって、周囲の熱気が遮断されているとはまったく思っていなかったようである。
「ちょっと、あたしじゃないわよ。そんなにそっちは暑いの?あ…これひどいわ」
コージやディレルの予想とは反して、ポリーニが移動しても冷気はそのままである。それどころか彼女は冷気の外側のとんでもない灼熱に仰天してしまう。
「これじゃあひどすぎるわ。あんた達よくこれで我慢していたわね」
「だからさっきから暑い暑いってさんざん言ってるじゃないですか…」
「やれやれ…」
手のひらを返したように今度は暑さをなじる彼女だが、まあこれはいつものことである。が、この冷気塊がポリーニの仕業ではないとすれば…発生源は一人しかいない。
「…シンさん?もしかしてこの冷気ってシンさんですか?」
「…ばれちゃったか…」
シンは困ったように口ごもると、しぶしぶ事実を認めた。炎の魔神みぎてが排出した熱気を打ち消すほどの力で冷たい寒気を作り出していたのは、意外なことにこのスポーツマンの青年、シンだったのである。
しかしいくら考えても、コージたちのように専門の魔道士でもない限り、これだけの強い冷気の結界を作り出すことはできることではない。コージやディレルだってある程度のきちんとした準備をして、初めてどうにかできるという程度なのである。それをこんな簡単に作り出すことができるというのは絶対に普通の人間ではありえない。そう…それはまさしく魔神級の力だった。大魔神みぎての力にかなり匹敵する強い精霊力の持ち主だけが、これだけの結界をとっさに生み出すことができるのである。ということは…
「ひょっとして…シンさん、みぎてと同じ?魔神族?」
「…道理でみぎてくん並みによく食べるわけですねぇ…」
恥ずかしそうに頭をかくシンの腕には、さっきまではまったく気がつかなかったが、はっきりとした月光色のうろこのようなものが見えていた。そう、シンはトリトン族ではなく、海の魔神族だったのである。
* * *
最悪に近い高級欧風料理店でのロケがようやく終わって、一同は最後の店「居酒屋盤古幡」で締めくくりを行った。一応ここはコージお気に入りの多国籍屋台風居酒屋である。一応手短な番組収録のあと、そのまま反省会をかねた打ち上げ宴会となったのである。
「シンくんが魔神だったとはなぁ。意外と身近にいるものだな」
「すいません。今まで黙っていて…」
シンの正体がみぎてと同じ魔神族であるということは、どうやらコージたちがはじめて知った人間らしい。実際プロデューサーもスタッフも、本当に知らなかったらしくびっくり仰天している。が、それは魔神を怖がっているという感じでは決して無い。
ぺこりと頭を下げるシンに、プロデューサーは笑って手を振る。実際別に彼が魔神族であろうが何族であろうが、かっこいい人気スポーツキャスターであればまったく視聴率には関係の無いことである。むしろちょっと変わったキャラクターのほうが人気は上がるのだから、何も困ることは無い。
「…シンさんのことはじめから気がついていたのか?みぎて…」
「うーん、まあな。でもさ、悪いし、黙ってた」
「そうか…わかる気がする」
どうやらみぎては最初からシンの正体に気がついていて、それでも黙っていたのである。おそらく握手したときに感じた、強烈なエネルギーでわかったのだろう。言われてみればコージも確かに感じていた。単にアスリートだからエネルギッシュなのかと思っていたのだが、あれは魔神族の精霊力だったのだ。しかし…
たしかに…彼が魔神族であることはなにも悪いことではない。しかし今までそれを誰にも言わずに、トリトン族として人間界に住んでいたということがどういうことであるのか、それくらいは今のコージにはなんとなくわかる。みぎてに「魔神の学生」というだけで、テレビの取材がくるということがすべてを物語っている。やっぱり魔神が人間界で暮らすということはいろいろ大変なのであろう。
コージはさすがにいたたまれなくなって、思わず謝罪の言葉を口にした。
「シンさん、ごめん」
「いや、いつかはばれると思っていたし…みぎてくんの取材って聞かされたとき、ちょっとやばいとおもってたんだよ」
「特別な存在」であるということは、その分同じだけさびしさがついてくる…たしか前にそんなことを誰かがコージに言った。シンの少しさびしげな、透明すぎる笑顔に、コージは申し訳なさでいっぱいになる。いや、コージだけではなくディレルやポリーニだって同じ気持ちだろう。
しかしそのとき、みぎては笑顔で言った。
「大丈夫だって、シンさん。シンさんが魔神だからって誰も困るわけじゃねぇし。堂々とタレントやってりゃいいんだぜ」
「え…」
「それに人間族だって、コージみたいなやつもいるし。な、コージ」
みぎてはコージに笑いかける。たしかにこの魔神の言うとおりである。魔神族だからといって、別に人間界に住んではいけないという決まりなんて無い。多少の不自由はあるかもしれないが、人間達と一緒にわいわいやっていればいいのである。それに人間族にだっていろんな人がいる。下手をすると魔神族よりもたちの悪いやつもいるのだし、コージのように魔神にほれ込んでしまったバカ(自分で言うのもなんなのだが)もいるのである。それにこれからは、なにか困ったことがあればコージやみぎてが話し相手になれる。新しい友達ができたと思ったほうがずっといいに決まってる。
みぎてはその太陽みたいな笑顔を見せてシンの肩をたたいた。その笑顔は不思議なことに、今まで立ち込めていたネガティブな雰囲気を吹き飛ばす力を秘めていた。それにはじかれたように、ディレルやポリーニ、そしてプロデューサーやスタッフもいっせいにシンの手をとって声援する。
「そうですよ、シンさん。みぎてくんの言うとおりですよ。これで引退とかしちゃったら、うちの妹がぐれちゃいます」
「そうよ、シンさまファンがみんな首くくっちゃいかねないわ。それに筋肉素敵過ぎるし…」
「シンくん。君みたいなうちの番組向きの人気キャスターをはずすなんてもったいないよ。ありえないから安心して来週もよろしく」
思いもよらなかった暖かい声に囲まれて、シンは驚きながらも次第に笑顔に戻る。そう、魔神族だ何だという前に、彼はタレントでスポーツキャスターのシン・アル・カイトスで、今日新しい友達ができた…それは今までと何も変わらないことだし、むしろ「ちょっといいこと」だということにようやく気がついたのである。

さて、全員に笑顔と元気が戻ったところで、ふと思いついたようにディレルが言った。
「…でもひとつだけすごく不思議なことがあるんですけど…」
「?」
「シンさん、あの時どうして結界を張っちゃったんですか?もうすこし我慢すればなんとか正体ばれずに済んだ様な気もするんですけど…」
たしかにあの暑さはかなり強烈なものだったが、みぎての隣に座っていたディレルが倒れずに済んでいたのだから、無理して我慢できないものではなかったはずである。不用意に結界を張らなければ、シンの正体はばれずにすんだのではないかという気がしてくる。
するとシンは苦笑しながら答えた。
「いや…その…一応、僕、芸能人だし、こういう場面でさすがに汗だくになってカメラに写るわけにいかないんだよね。ほら、一応メイクしてるし…」
「メイク…あ、そうか…」
「メイクしてるんですねやっぱり」
「あんた達みたいに美を意識してないわけじゃないのね」
さすがに「イケメン系芸能人」ということで、眉毛とかそのへんはメイクしているのであろう。コージですら(めんどうなので忘れることも多いが)眉毛くらいはととのえることもあるのだから当然である。ところが…
「いや、そのね…メイク取れちゃうと、その…ちょっとうろこがみえちゃうんだよね。ここらへんとか…」
「…え?」
「…うろこですか?あ、首のところ…」
どうやらシンの普段の姿は、実は人間やトリトン族そっくりというわけにはいかないらしい。みぎてがいくら人間らしい姿をしていても角があったりするのと同じなのである。さっきコージがちらりと見た、青銀色のうろこがあるのだろう。顔全部とかそういうわけではないようなのだが…
しかしうろこを隠してしまうほどのメイクとなると、それはもはや普通の「化粧」などではない。そう…それは明らかにSF映画に使われる「特殊メイク」の世界だった。
「…魔神って大変なんですねいろいろ…みぎてくんもいつも貧乏だし」
「…ちょっとまてディレル」
いきなり話が変なところに波及して、みぎては思わず悶死しそうになる。あまりに不満そうなみぎての表情に、思わずその場の全員は腹を抱えて笑い出したのは言うまでも無い。しかしその明るい笑い声は、新しい魔神の友達ができた喜びがはじけとんだ音そのものだった。
(炎の魔神みぎてくんグルメチャンネル 了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
