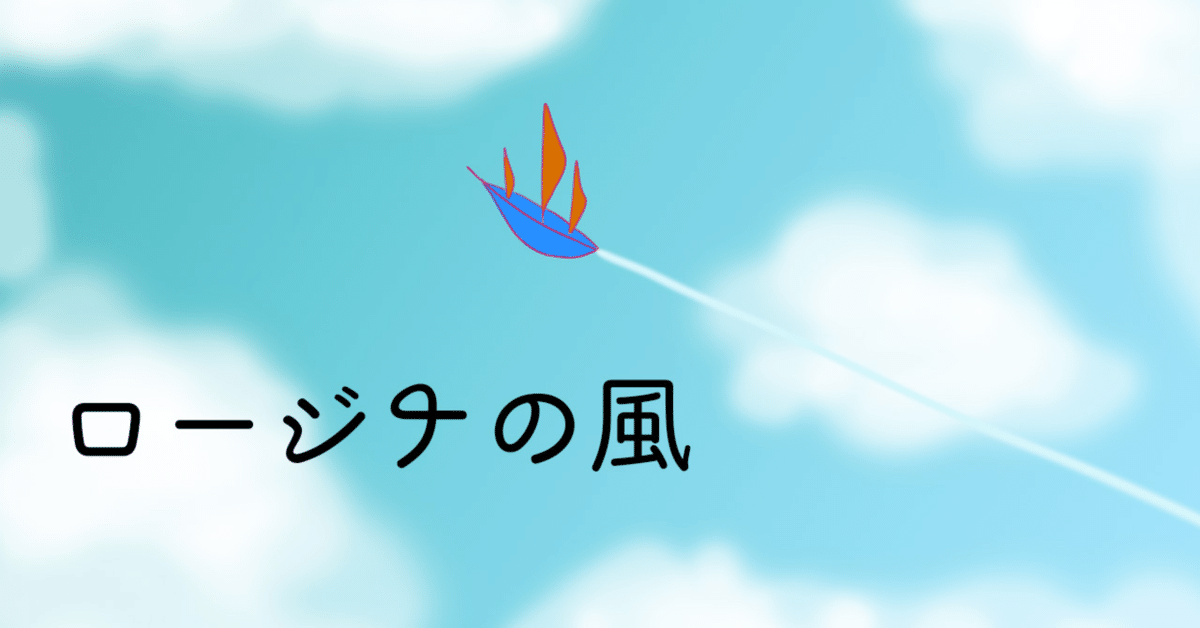
ロージナの風:武装行儀見習いアリアズナの冒険 #106
第八章 思惑:9
ロープや滑車のたてる音が風音に軽快なリズムを与える。
思考とは切り離して、観測に集中を強いている両の目に、青く澄んだ海原が痛い程に眩しい。
「二時方向に船影。
分かりますか?」
突然、ヨナイ兵曹長のきびきびした声がタケオの耳朶を打った。
それまでの多分に趣味的な会話の流れや、平時めいたまったり感を断ち切る。
いきなりの状況発生だった。
「後部甲板!
二時方向に船影!
距離一万四千。
船種、所属共に現在不明。
アンノウンと呼称」
次の瞬間、メガホンを取り上げたヨナイ兵曹は、後部甲板に向かって声を張り上げた。
ついうっかり、放課後のクラブハウス的ノリでタケオはヨナイ兵曹との当直時間を過ごしていた。
考えるまでもなく今は戦時であり、自分たちは日々戦闘任務に就いているのだ。
タケオは自分が海軍士官の端くれであることを思い出し、卒業試験間際のできの悪い学生じみた焦燥感に襲われた。
「引き続き監視を怠るな。
逐次報告を入れろ!」
間髪を入れずにバイロン副長の甲高い声が返ってきた。
双眼鏡を構え慌てて二時方向を伺うタケオの脳裏に、ふとディアナの面影が浮かんだ。
すると以前と全く変わらない副長の声がどこか遠く、しかし妙に愛らしく聞こえたのは不思議なことだった。
甲板長の号笛が響き、当直士官の総員準戦闘待機を命ずる怒声が飛ぶ。
トップ台を包み込むある種の静謐とは正反対の活気と慌ただしさが、後部甲板を発火点にして艦全体に行き渡るのが感じられた。
「カナリス候補生!
記録をお願いします」
タケオと同様双眼鏡を目に当て、食い入るように観測を行っていたヨナイ兵曹長は、アンノウンに意識を集中したまま微動だにしなかった。
タケオとしては水平線上にちらっとアンノウンのトゲルンスルが見えた様な気がするだけだった。
はっきりと船影の確認はできていなかった。
師匠は弟子にまだ現場を任せるつもりが無い。
タケオは双眼鏡からすぐ手を放し、マストに取りつけたメモリーボードに向かった。
タケオはクレヨンを使って現在時刻と、ヨナイ兵曹長が口頭で伝えるアンノウンまでの距離、方角を素早く記録した。
このメモリーボードはつい最近二人で考えた新しい設備で、“カナリスの落書”を具体化する為の第一歩でもあった。
五十センチ四方の黒板に丁寧にニスを塗っただけの代物だったが、思った以上の使い勝手の良さだった。
日々の当直に当たり、更に用法を改良すべく色々と試行錯誤を重ねているところでもあった。
甲板の慌ただしさを余所に、インディアナポリス号の軽快な航走はアンノウンとの相対距離を確実に縮めて行った。
やがて、ヨナイ兵曹が双眼鏡に目を当てたままポツリと言葉を紡いだ。
「カナリス候補生。
アンノウンの種別と船籍、分かりますか?」
タケオは、記録係を務めながら二時方向以外への警戒観測に当たっていた。
慌てて双眼鏡を目に当てると、改めて二時方向に目を向けた。
「ガレオン型のシップ。
商船ですね。
所属はえーと、アトランティス諸島」
メインマストの天辺で流れる長旗は、海を利用する地域行政団体ごとに取り決めた所属旗だった。
今双眼鏡の向こうで鮮やかに翻るのは“黄緑に白い縦縞”、アトランティス諸島生活共同組合の旗だった。
生活協同組合と言っても、それは赤道直下に広がる大小の島々が代表を出し合って運営する立派な行政組織だった。
アトランティス諸島は、乾留すると高純度の揮発性燃料と軽量で高熱源となる炭が採れるマングローブの一種、炭油樹の一大産地としてよく知られていた。
アトランティス諸島生活協同組合は常備軍こそ持たなかったが、炭油樹から得られる収益で経済的に豊かだった。
組合員と称する数十万に上る人々を抱え込んでいたものの、暮らし向きが楽なせいもあるのか、政治的に安定した地域行政団体だった。
「報告をお願いします」
ヨナイ兵曹長がタケオにはまだ分からないアンノウンの詳細情報を淀みなく口にすると、穏やかな声でタケオを促した。
アトランティス諸島生活協同組合の商船であれば少なくとも今のところは元老院暫定統治機構と敵対関係にあるとは言えない。
そうではあっても、この世界で元老院暫定統治機構は明らかに不人気だった。
先の大戦の時にも、アトランティス諸島は中立を宣言したが、都市連合に肩入れしていたことに疑いは無かった。
船乗りの間では、赤道海域で組合の密許を受けた私掠船が、元老院暫定統治機構所属の商船を襲っていたという事実は、公然の秘密だった。
「宛て後甲板!
アンノウンは三本マスト、ガレオン型シップ。
アトランティス諸島生活協同組合所属。
母港は極楽市極楽港、泰平丸もしくはその姉妹船」
タケオはメガホンを取ると、ヨナイ兵曹長からもたらされた情報を後甲板に向け叫んだ。
兵曹長の能力と知識が、カウンターパートに当たるピグレット号のシンクレアに匹敵するのは明らかだった。
数時間の後にインディアナポリス号は、アトランティス諸島のガレオンに追いついた。
薄緑に塗装された船体の喫水は深い。
恐らくは積み荷を満載しているのだろう。
張り切った横帆の力強さの割に船足は遅かった。
現在位置と速度から考えて、元老院暫定統治機構が都市連合に宣戦布告した事実は、ガレオンのクルーにまだ知られていないはずだった。
しかし、ガレオンの反応は、大海原で出会った海の仲間同士と考えれば冷たくそっけなかった。
素早く掲げられたこちらの信号旗に対して遅れること数分。
のろのろとハリヤードに掲げられた信号旗は通り一遍の確認答礼のみだった。
船上で働く水夫達もこちらに手を振る者は皆無で、戦闘態勢を取っていないのがせめてもの好意と言う感じだった。
「僕たちは嫌われていますね」
ガレオンの様子はトップ台の上からだと手に取るように分かった。
タケオは相手が不意打ちで戦端を開くことが無いか、双眼鏡で舐めるように船体と人員の観察を続けていたのだ。
レンズを通してもひしひしと伝わってくる冷ややかな敵意には、身が竦むような思いだった。
それはまるで、のけ者にされている街の鼻つまみ者を尻目に懸けるような、冷淡で悪意のこもった反感だった。
「こちらが準戦闘待機を取っていることを悟られていますね。
向こうは恐らくまだ開戦の事実を知らないでしょう。
当艦は商船相手に面白半分で戦闘訓練を仕掛ける傲岸不遜な軍艦という訳です。
我々は元老院暫定統治機構の軍人っていう、謂わば凶状持ちですからね。
カナリス候補生の仰る通り、何処へ行ったって誰と会ったって好かれちゃいないことだけは確かです」
ヨナイ兵曹長は笑いながら肩を竦めて見せたが、その顔は遣り切れなさでいっぱいだった。
先の大戦の原因や凄惨な殲滅戦に至る経緯を問われても、弁解できる言葉がない。
戦後世代の者にとっては、父祖の世代がやらかした歴史的不始末は、心に刻印されたスティグマのようなものだった。
彼らにとり、それが理不尽で息苦しい罪科であることは、紛れもない共通認識だった。
ジェノサイドの加害記憶は、遺伝性の先天疾患が殆どすべて克服された社会において、元老院暫定統治機構の市民が背負った業病、宿痾(しゅくあ)とも言えたろう。
それは、例え額を地面に擦り付けて世界中の人々に謝って回ったところで、本当の意味で決して治癒することがない病だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
