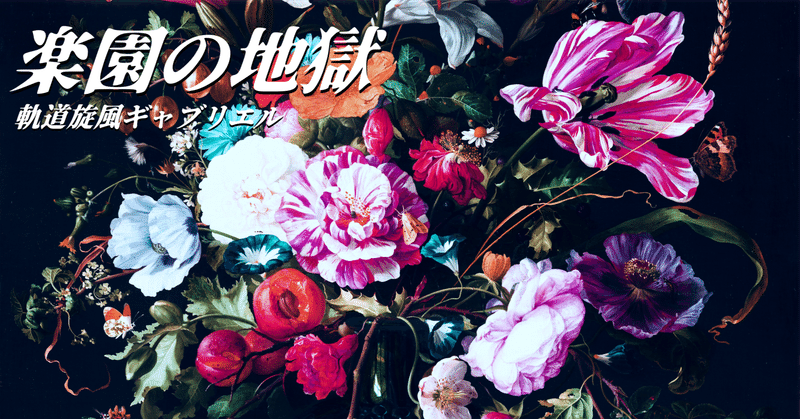
軌道旋風ギャブリエル 『楽園の地獄』 第四話 「マキシムの楽園」
【前回】
登場人物たち
デミル
この物語の主人公。アルドリア連邦の切り札、超人部隊〈屍衆〉のひとりであり、アルドリア連邦にとって起死回生の作戦となる〈楽園の地獄〉の要。盲目だが、超感覚・超計算能力の持ち主である。
マキシム・デュカン
エクサゴナル共和国の〈指導者〉。若きカリスマ。マキシムの台頭後、エクサゴナル共和国はアルドリア連邦に侵攻。その国土を焦土に変えた。
ルウルウ
〈屍衆〉最年少の少女。小柄ながら鋼鉄のような肉体と、尋常ではない膂力を誇る。デミルの護衛役。
セレン
〈屍衆〉のひとり。デミルの幼馴染。作戦決行前に何者かによって殺害された。
ユヌス
〈屍衆〉の長。眼光鋭い老戦士。
スライマン
〈屍衆〉のひとり。超人的な聴力の持ち主。
赤いコートの女
エクサゴナル共和国と覇権を争う東方の強国、ガルトゥ人民国のエージェント。
最強の人類
〈最強の人類〉とはコードネームであり、そのコードネームが指し示す個人は不明である。
ギャブリエル
〈軌道旋風〉の異名を持つ、この物語のもうひとりの主人公。
プロフェッサー・ガエタン
天才的頭脳を持つとされる科学者。マキシムやギャブリエル、そして〈屍衆〉の誕生にも関与しているようだ。
◆
それは陽が落ち始めた夕刻。人びとが一日の終わりを感じはじめた、その時だった。エクサゴナル共和国の首都パリスと周辺都市で、次々と火の手があがりはじめたのは──。
まず手始めに交通機関、南部の浄水施設、港湾都市ポールドペ……各地で自動車爆弾がさく裂し、建物が倒壊。凄まじい数の死傷者がうみだされた。そして直後。国際空港と各地の治安施設を武装集団が強襲。治安組織との間で激しい銃撃戦がはじまった。それはさながら内戦だった。
国営放送はジャックされている。国営機関のウェブサイトもまた改竄されていた……流されているのは反政府組織〈エクサゴナル解放戦線〉によるマキシム打倒宣言だ。
そして今ここに、夕闇と争乱とに紛れるようにして〈指導者〉公邸へと向かう一群の姿がある。
それこそがエクサゴナル共和国、終わりのはじまりである。
軌道旋風ギャブリエル
『楽園の地獄』
第四話
「マキシムの楽園」
夕闇のなか〈指導者〉公邸へと向かう六名の男女。彼らは瓦礫をものともせず、パリス中枢を凄まじい速度で駆け抜けていく。風が轟々と音をたて、遠くからは爆発と銃撃戦の音が木霊する。
先頭を走るのは、軍用コートに身を包んだ眼光鋭い老人。
彼の名はユヌス。
アルドリア連邦が誇る超人部隊〈屍衆〉の長だ。
そしてその背後。付き従うように駆けるのは男が三名、女が二名。いずれもただならぬ雰囲気をその身にまとっている。
ユヌスは前を向いたまま、彼らに語りかけた。
「よいか。これが〈楽園の地獄〉最終段階ぞ。死して屍拾う者なし……己の身命を、決して惜しむでないぞ」
ユヌスの右後方を走る女が笑った。
「ははは、当然」
女の瞳は大きく、丸く見開かれている。そしてその瞳が閉じられることはない……まるで深海魚のように。彼女の名はバスマという。当然〈屍衆〉のひとりだ。
続いてバスマの背後。ローブ状の上着をまとった小柄な醜男が口を開いた。
「陽動とはいえ、敵の本拠地に殴り込む……心がたぎりますなぁ」
男の名はヌール。
その左隣、女が口を開く。
「ヌール……お前ぇ、調子に乗ってあたしらまで巻き添えにしたら……」
女の喉が、蛇のようにシャーっと音をたてた。
「殺すぞ……?」
ひぃっ、とヌールは首をすぼめる。
その時、女を咎めるように口を開いたのは殿の男……岩のような巨魁だった。
「マイイ、やめろ……」
マイイ。それが蛇のごとき音をたてた女の名だ。マイイは舌打ちし、その様子を見てヌールはローブを揺らしながら、ひひ、と笑う。
巨魁は低く、唸るような声で続けた。
「ヌールもだ……これは祖国の命運がかかった作戦ぞ。長の言うとおり、己の命を捨てる覚悟が必要ぞ……」
巨魁の名はワジド。ユヌスに次ぐ〈屍衆〉のナンバーツーだ。
その言葉にバスマの隣、年若い男が神妙にうなずく。男の名はイーサー。まだ十代半ばの少年だった。
彼らの纏う空気が徐々に緊張を帯び、やがて目的地が見えてくる。
ユヌスは立ちどまった。
ユヌスたちが辿り着いたのは木に覆われた小高い丘であり、眼下には〈指導者〉公邸が見えている。
ユヌスは木々の闇に身を潜めた。
付き従う面々もそれに続く。
「よいか……」
ユヌスは静かに、威厳のある声音で告げた。
「これが、最後の作戦だ」
そして面々の顔を見回し、静かに続ける。
「覚悟を決めよ。我ら〈屍衆〉もとより死人も同じ」
その言葉にワジドが、バスマが、ヌールが、マイイが、イーサーがうなずき、唱和で応える。
「「「我ら〈屍衆〉、もとより死人も同じ!」」」
◆
時は遡り、その前日。
薄暗い〈屍衆〉アジトのなかでユヌスは椅子に腰かけたまま、電灯に透かすように右手をかかげていた。その見つめる先。親指と人差し指の間には小型の記憶素子が挟まれている。
「これを、その女が渡してきたと?」
ユヌスの問いに眼前の青年は黙ってうなずく。ユヌスは記憶素子から視線を外し青年を……デミルをゆっくりと眺めた。
くせのある灰色の髪。繊細さすら感じさせる芸術家のようなたたずまい。そして、盲いた目……そのデミルの背後では、息を呑むように少女ルウルウが、ふたりの様子を見つめている。
ユヌスは左手を顎にあて、沈思黙考した。
ユヌスはデミルがその記憶素子について語った言葉を思いだしていた──。
セレンの亡骸を探すためにアジトを抜けだした俺は、マキシムの直属部隊〈シヤン・ドゥ・ギャハルドゥ〉の襲撃をうけた。だがその時、空から奇妙な女が降りたった。「ギャブリエル」と名乗る女は一瞬にして〈シヤン・ドゥ・ギャハルドゥ〉を撃破し、記憶素子を残して去った……。
「にわかには信じられん話だが……」
フン、とユヌスは鼻を鳴らした。
「そもそも貴様が」
その眼光が鋭く、デミルを射抜くように見つめる。
「軍規を破って勝手に動いたこと、許すわけにはいかんな」
ごくっ、とルウルウが唾を飲みこんだ。デミルは無言のままだった。デミルにとって、もとより覚悟のうえでの行動だったからだ。
「しかし……」と、ユヌスは遠くを見つめるように続けた。
「セレンの亡骸を持ち帰ってくれたこと、私としても思うところはある……」
それは悲しみとも、憧憬がまじった追憶とも言える複雑な感情をたたえた眼差しだった。
その瞬間、デミルとルウルウ、ふたりはユヌスの想いを理解していた。
かつて故国で過ごした日々。セレンも含めた四人で、まるで家族のように過ごした日々──もう二度とは戻ってこない、過去への憧憬。
その美しく暖かな日々は、エクサゴナルによって焼き尽くされたのだ。そして今やセレンも死に、四人は三人となり……残された者は、より大きな喪失を抱えることとなった。
悲しみと、憎しみと、後悔、祖国を救わなければならないという使命感。三人のなかで、それらがないまぜになった感情が渦巻いていた。
「デミル……」
ユヌスはその眼差しのまま、デミルを見つめた。
「貴様への処分は〈楽園の地獄〉作戦完遂後とする……この意味は、わかるな?」
デミルはうなずき、胸に手を当てた。
「わかっている。我ら〈屍衆〉、もとより死人も同じ。祖国アルドリアに報恩忠国し、一身をもって悪辣なるエクサゴナルに鉄槌を下すのみ」
それは重く、力強い言葉だった。その声音に偽りの感情は見いだせない。
ユヌスもまたうなずき、
「もうよい……下がれ」
とふたりに促した。デミルは一礼し、きびすを返す。その背後、はしゃいだようにルウルウがまとわりつき、小声で「よかったね」と言ったのがユヌスにも聞こえた。
ユヌスは苦笑とともに鼻を鳴らす。
ふたりは退出し、ドアは閉められた。
それとほぼ同時。
「いやはや、ご老人は実にお優しい……」
ユヌスの背後。にわかに人の気配が生じ、影が浮かぶように静かに、もうひとつのドアから何者かが入ってきた。赤いコートをまとった黒髪の女だった。
ユヌスは首を回し女を一瞥。無言のまま指で記憶素子を弾いた。記憶素子は女に向けて飛んだ。
「おっととと」
女は記憶素子を慌ててキャッチする。
ユヌスは女に向き直り、言った。
「聞いていただろう……その記憶素子、本当に〈指導者〉公邸の詳細データであるのか、あなたがたに調べていただきたい」
くく、と女は笑った。言われるまでもなかった。すでに懐から取り出したハンドヘルド端末に、素子をセットするところだった。
「当然、調べるに決まっている。ああ、そうそう……」
女はハンドヘルド端末をかかげ、ユヌスに振ってみせた。
「念のため説明をしておこうか。このコは実に優れものでね。秘匿回線を通じて、我らガルトゥ人民国の中枢コンピュータへとつながっている……世界最高峰の量子コンピュータ群によるクラスターにね。そして、あらゆるデータを即座に解析するのさ……」
女は端末を見つめた。
「ほら、言ってるそばからさっそく結果が出たようだ。ほうほう、実に興味深い……」
顔をあげ、ユヌスを喜色に満ちた顔で見た。
そして、人差し指をユヌスに向けた。
「ビンゴだよ、ご老人! これは間違いなく正真正銘〈指導者〉公邸の機密データだ。これはすごい……」
そこまで言って女はユヌスの顔を見た。「ご老人……?」そして戦慄したように息を呑む。ユヌスが、かつてない表情を浮かべていたからだ。ふっ、ふっ、ふっ、と肩を震わせ笑う……獰猛な笑みだった。
これは、僥倖である。
当然、罠である可能性は否定できない。ギャブリエルと名乗った女の素性も気になる。あまりにも不確定要素が多すぎる。だが古の軍略家もこう言ったではないか。
「兵は拙速を尊ぶ」と。
それは真理だ。我々が情報を掴んだことを気取られる前に、作戦を決行する……。
ユヌスはそう考えた。かくして〈楽園の地獄〉最終段階、最後のピースが埋まり、賽は投げられたのだ。
◆
地上が戦火につつまれていく。
そのさなか、パリス地下に張り巡らされた下水道では、暗闇のなかをカツ、カツ、と白杖を鳴らし進む青年がいた。
デミルだ。
デミルだけではない。その背後には明かりすらない闇のなかを、迷うことなく進む男女がいた。ひとりはルウルウ。そしてもうひとりは大柄なドレッドヘアの男……スライマンだ。
同時多発の攻撃も、ユヌスたちの公邸襲撃も、すべては陽動に過ぎない。〈楽園の地獄〉は徹頭徹尾、デミルを要とした作戦だからだ。
つまり真の攻撃は、この地下下水道から行われる。その結果もたらされるのはパリスの完全破壊であり、エクサゴナル共和国の終焉だ。
だが……。
デミルは立ちどまった。
「デミル……?」
ルウルウが怪訝そうに尋ねる。デミルは背を向けたまま、押し黙っている。デミルは光のない盲いた闇のなかで、ひとり考えていた。
〈楽園の地獄〉完遂前に、ここで決着を付けなければならない。
セレン。
君の死について、俺は決着をつける……。
君を死に追いやったそいつと、俺は、ここで。
その盲いた目がゆっくりと、だが、力強く見開かれていった。
◆
パリスの闇は深まり、いつしか夜に包まれていた。周囲の騒乱をよそに無数の警備車両と装甲車によって護られた〈指導者〉公邸は静けさにつつまれていた。まさにネズミ一匹通さぬ万全の体制だ。
だが。
「……!?」
若い警備兵は、声をあげる間もなく死んでいた。倒れゆく警備兵を冷ややかに見つめながら、マイイは蛇のように喉を鳴らす。
「これで六人目」
音もなくマイイの傍らに人影が立つ。ユヌス、深海魚のような瞳のバヌス、若きイーサー。バヌスの目が不気味に輝き、告げる。
「このブロックの無力化は完了」
イーサーがハンドヘルド端末を操作しながら続けた。
「監視カメラ、セキュリティ設備、すべて無効化してあります」
ユヌスがうなずいた。
「よろしい」
その傍らに新しい影がふたつ。小柄な影と巨大な影。ヌールとワジドだ。ワジドは言った。
「警備兵どもの定時連絡までは、あと五分」
ユヌスが再びうなずく。
「よろしい」
そして右手を挙げた。
ここからマキシムがいる執務室まで、最短距離を突っ切る。
これは陽動作戦に過ぎない……だが。
フン、とユヌスは鼻を鳴らした。
マキシムを殺せるならば自らの手で殺したい。それは、ここにいる誰もが思っていることだ。故に……ここで、確実に殺る。当然だ。それは私情でもあり、使命でもあり、この場にいる全員の総意でもある。
「……ゆくぞ」
静かに、挙げた右手を降ろした。
その時だった。
「!?」
五人を、強烈なサーチライトが照らしだした。
瞬間、〈屍衆〉の面々に動揺が走る。
ユヌスはまばゆい光に手をかざし、顔をしかめた。
やはり、罠であったのか……!?
「あれを!」
バヌスが巨大な目をさらに見開き、指さした。
その先。公邸中央の庭園に、巨大な舞台状の装置が置かれていた。入手したデータには存在しないものだった。そして壇上。スポットライトを浴びながら、ひとりの男が浮かびあがる。
栗色の美しい髪を揺らめかせ、男は尊大に腕を広げていた。そして六人を歓迎するように言った。
「ようこそ」
威厳がありながらも、美しく、澄み渡るような声だった。
「……ッ」
ユヌスは憎しみとともに奥歯を噛みしめながら男を睨んだ。
不倶戴天の敵である!
彼こそはまさしく〈指導者〉マキシム・デュカンその人であった。
◆
パリス片隅にある貧民街。
市内で戦火が広がるなかでも、重要施設のないこの一画は静かだった。明かりの少ない路地にはすえた臭いが漂い、アルコールの呼気を放つ男たちが、路地のいたるところでうずくまっている。
そのなかを、颯爽と闊歩するひとりの女がいた。
女は赤いコートを身にまとい、長い黒髪をなびかせて、顔には気味の悪い笑みを浮かべている。
女はとある集合住宅の前で立ちどまった。年季のある……いや、率直に言うならば、ボロくて汚らしいアパルトマンだった。
「ここか……」
女は玄関ドアを開け、なかへと入る。
薄暗い共同空間を抜け、奥の一室へと向かう。
そしてドアの前で首を傾げた。伝統的にエクサゴナルの家屋には表札がない。ゆえに、家主について確信を持てずにいたのだ。
「この部屋でいいのか? やれやれ、表札をつけないとはね。エクサゴナルの文化は理解しがたいものがある……」
女はノブに手をかけ、
「失礼するよ」
と言うやいなや、ドアを開けた。
部屋のなかは薄明かりがともり、アパルトマンの古さとは対称的に、きれいに整えられていた。
玄関のすぐ先にはリビングがあり、小さなテーブルが置かれている。
その傍らには初老の男が座っていた。
男は読んでいた本から顔をあげ、女を見た。
女は恭しくお辞儀をする。
「やあ、お会いできて光栄だ……プロフェッサー・ガエタン」
お辞儀から顔をあげた女の顔は、ますます不気味に歪んでいる。
男は……ガエタンは、ふぅ、とため息をついた。
「私を追う者は大勢いる。だが、黒髪のお嬢さんには心当たりがないのだが」
「おっと、失礼」
女は再びお辞儀をして言った。
「わたしはガルトゥ人民国から来た……いわば職業斡旋のエージェントだ。名前はそうだな、ひとまず赤月と名乗っておこうか」
ガエタンは片眉をあげた。
「そのガルトゥのエージェントどのが、私にいったい何の用だね……」
と、その言葉を言い終える前に、
「何の用も、クソもなぁい!」
と、チィユェは猛烈な勢いで話しはじめていた。
「なぁぜ。なぁぜだ! あなたほどの天才……世界における最高峰の天才が、このような場所に身を潜め、不遇のなかにあらねばならないのかッ! そんなことはあってはならない! 断じてあってはならない! そうは思わないかね、プロフェッサー・ガエタン!」
鼻白むガエタンをよそに、チィユェはなおも続けた。
「これは人類にとって大きな損失ではなかろうか……いや、なかろうかではない、間違いなく損失である! いいかね、我らガルトゥは常にあなたに注目し続けてきたのだ。あなたの才能は偉大であり、まさに人類の宝と言えるからだ!」
チィユェの独演はさらに熱を帯びていく。
「あなたは研究がお好きでしょう? どのような犠牲を払おうとも、研究を続けることこそあなたの存在理由でしょう? 違いますか? そんなあなたがいま、マキシムに追われて身を潜め、大好きな研究すらできずにいる! なぁんてことだ! だがしかし、我らガルトゥのもとに来ればこのような境遇も終わるのだ! 我々の庇護のもとであれば、どのような研究も可能となり、資金も青天井で提供され、どのような手段も、どのような設備も、どのような資源でも……入手して、提供できる!」
ガエタンは眉をしかめ、咳払いをした。
チィユェは独演をやめ、ガエタンをニヤニヤと見つめた。
ガエタンはうながした。
「つまり?」
「要するにだ。我々とともに来て欲しい。我がガルトゥは、あなたを熱烈歓迎する!」
ふふ、とガエタンは静かに笑った。
「いきなりだな、お嬢さん。もし、あなた方の申し出を断ったとしたら?」
くくく、チィユェは不気味な笑いで応えた。
「超並列体の実験に失敗し、エクサゴナルに居場所を無くした後……あなたはアルドリア連邦に渡ったね」
ほう、とガエタンは感心したように目を見開いた。
「もちろん調べさせていただいた。いかに偽装しようとも、我らガルトゥの目はごまかせない。あなたがあの超人集団〈屍衆〉の産みの親だ。違うかね?」
沈黙。ガエタンは顎に手をあて、何ごとかを考える仕草を見せた。
チィユェは続けた。
「かのマキシムはこう考えているはずだ。わたしのような超人は、わたしひとりで十分だとね。だからあなたの命は狙われている。そしてもしあなたが〈屍衆〉の産みの親だとわかれば、マキシムはいままで以上にあなたの命を狙うに違いない。くくく、違うかね?」
ガエタンはやれやれ、と首を振った。
「脅しか」
「いやいやいやいや」
チィユェは手を広げた。大げさに、いかにも困惑してます、といった風情だった。
「それは違う。断じて違う! 我らガルトゥであれば、あなたの不幸な境遇を救うことができる……そういうことだと理解いただきたい! 我らガルトゥ人民国はあなたの才能を最大限に生かすことができる。いやめんどうだ、もっと直截に言おう! 我らガルトゥは、あなたが望むだけ、望むように、お好きなだけ、資金も、設備も、時間も、なにより被験者も用意できる。男でも、女でも、子どもでも、老人でも、赤ん坊でも! あなたが望むならば、いくらでも用意できるのだ。もちろんいくらでも使い潰していただいて構わない! 人道がぁ、なぁんてばかげたことは言うことはない! そしていずれは、あなたの最高傑作である〈最強の人類〉をも上回る結果を出していただきたい!」
ガエタンは呆れたようにチィユェを見た。そして、
はははははは!
と笑いだした。チィユェはきょとんとガエタンを見つめた。
ガエタンは腹を抱えんばかりに笑っている。
「最高傑作?」
笑いすぎて目に涙をためながらガエタンは続ける。
「あれが? あんなものが? ははは! あんなものは、最高傑作とは言えんのだが!」
「バカな!」
チィユェは知っている。〈最強の人類〉とは一国を滅ぼすことすら可能な文字通り最強の兵士なのだと。チィユェは色をなして反論した。
「われわれの掴んだ情報では〈最強の人類〉とはまさに空前絶後の存在だ。あなたにはそれを上回る成果があるとでも? いやいやそんなバカな! ではいったいなにが、あなたの最高傑作だと言うのか!」
はは……ガエタンは笑いを止め、チィユェの目をじっと見つめた。
「最高傑作……それはね」
ガエタンは手を重ねて組み、その上に顎をのせて静かに続けた。
「私の手を離れ、なおも自己進化していく存在」
その顔には、穏やかな笑みが浮かんでいる。
「それこそが、我が最高傑作さ」
◆
「ようこそ、諸君」
庭園中央の壇上から、ユヌスたち〈屍衆〉に向けてマキシムは言い放った。その時だった。ワジドの巨大な手がマイイを持ちあげ、砲丸のように投げた……一切の躊躇なく、マキシムへと向かって。
「シィャハハハ!」
宙を切り裂き飛びながら、マイイの獰猛な哄笑が轟く。同時。ユヌス、バヌスとイーサー、ヌールが駆けだす。ユヌスの目は、憎しみとともに見開かれていた。彼は雷撃のように考える。
そちらから出てくるとは……手間が省けることだなッ!
シャーッ!
蛇のような音を鳴らし、その時すでにマイイはマキシムの眼前にあった。超人集団〈屍衆〉にあって、マイイもまた当然、尋常の人間ではない。その体はさながら流体のように歪み、稲妻のような軌道を描いて、
「死ねッ!」
マキシムの喉元めがけて手刀を繰りだしていた。仮に手刀がかわされてもかまわない。なぜなら、マイイは蛇のごとき超軟体の持ち主。そのままマキシムに絡みつき、締めあげ、一瞬にしてその全身を砕くことが可能だからだ。
マイイは勝利を確信した。
いっぽうマキシムは……微笑んでいた。
コンマミリ秒の世界のなかで、マキシムは、必要最小限の動きのみで手刀をかわす。続けて迫りくるマイイの超軟体をしゃがんでやりすごし、即座に立ちあがった。かわされて勢いあまり、マイイは壇上にしたたかに叩きつけられていた。
「な……」
起きあがろうとしたマイイの前には微笑むマキシムがあった。
「きれいなお嬢さん」
小バカにしたように、マキシムはマイイの両頬を鷲掴みにした。そして、
「さよなら」
そう言いながらマキシムはマイイに口づけをした。マイイは屈辱に目を見開いた。その視線の先でマキシムの体が離れていく。直後、マイイの体を貫いたのは無数の銃弾だった。
「!」
そしてその時、ユヌスたちは聞いたのだ。大地を揺るがす地鳴りのごとき音を。そして見た。アサルトライフルを手に、公邸へと津波のように押し寄せる群衆の姿を。その顔は一様に瞳孔が開き、無表情だ。まるで機械人形じみている……。マキシムはスポットライトの下で、酔いしれたように演説を始めていた。
「エクサゴナルの市民よ、私たちの家族よ! いまこそ立ちあがる時だ! 今、この危機の時こそが目覚めの時である! 恐れるな。使命を胸に抱け! いかな困難があろうとも、いかに敵が卑劣であろうとも、高らかに言おうではないか……私たちの歩みを止めることなど、お前たちにできはしないのだと!」
ユヌスは奥歯を噛み、顔を歪めた。
これは、大衆煽動なんて生易しいものではない。
殺到する銃弾のなかで、ユヌスたちはマキシムの築きあげた楽園の、真の姿を目撃していた。
【終】
【次回予告】
極限の死地のなか戦う〈屍衆〉たち。その時、地下下水道でデミルは……。
軌道旋風ギャブリエル『楽園の地獄』
第五話「死して屍拾う者なし」
デミルは覚悟を決め、そして物語は終焉へと向かう。
この続きは2023年1月31日に発売される『無数の銃弾:VOL.6』で読めま……
……せん! 読めません!
実は『無数の銃弾:VOL.6』では諸事情によりギャブリエルの連載を休載しちゃいました。しかしその代わりに、ちょっとしたサプライズ掌編を掲載しています。お楽しみに。
きっと励みになります。
