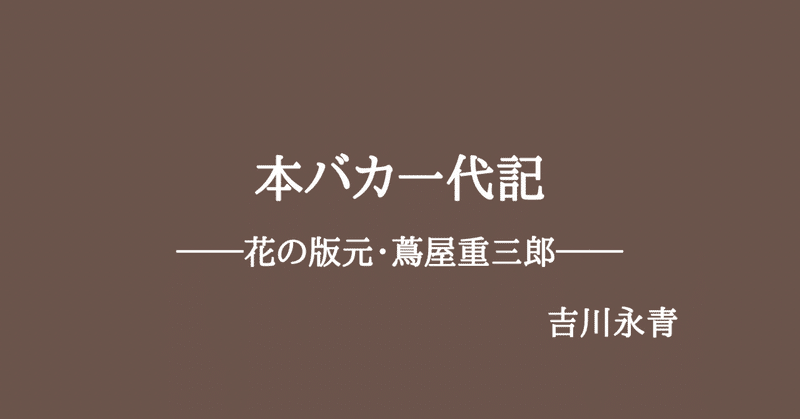
本バカ一代記 ――花の版元・蔦屋重三郎―― 第五話(下)
*
安永八年の秋、重三郎は丸屋から地本問屋の株を譲り受けた。
通油町にある丸屋の見世も買い取っていたが、その受け渡しには少しばかり時を食うことになった。丸屋小兵衛は他へ居を移すのだが、長きに亘って暮らしてきた場所だけに荷物が多い。それらを全て運び出した上で、重三郎が望む形に建物を造り直すためであった。
それに当たって、まず重三郎は自分だけの見世を持った。吉原の五十間道、次郎兵衛の引手茶屋から五軒右手の向かいであった。何しろ丸屋の奉公人のうち、手代が二人に小僧ひとり、下女ひとりが引き続いて重三郎の下で働くことになっている。奉公人を抱えて商売を拡げる以上、弟の見世に間借りしたままでは話にならない。
「うん。ちっと狭いが、中々いいじゃないか」
見上げる軒先には、真新しい白木の看板が掲げられていた。間口はたったの一間半(一間は約一・八メートル)しかない。丸屋の見世の引き渡しまで、長くて二年ほどの仮住まいではある。それでも、墨痕鮮やかな「蔦屋耕書堂」の文字を見ると、ついつい面持ちが緩んだ。
「どうだい。これからは女将だぜ」
共に看板を見上げるお甲に言うと、くすぐったそうな笑みが返された。
「商売のことは、あたしには分かんないけどね」
「でも、おまえなら奉公人を守ってやれるさ」
掛け値なしの本音であった。女郎として十年の年季を勤め上げた女である。世の中の裏側を知り、酸いも甘いも嚙み分けてきた経験は、きっと「ここぞ」で活きてくるはずであった。
株を手にした重三郎は、以後、手代と手分けして黄表紙本作りに奔走した。
少しして年が改まり、安永九年(一七八〇)の一月を迎える――。
「さあさあ皆様お待ちかね、黄表紙の新刊だ! 耕書堂、初の黄表紙ですよ」
見世先に本を山と積み、重三郎は大声を張り上げた。五十間道を行き来する人々が「何ごと」と目を向ける。遊里に来る以上、誰もが本は二の次、三の次であろう。それでも足を止め、立ち寄ってくれる人はいた。
「へえ、喜三二かい。いや……おい、こっちも喜三二かよ」
「ええ。どうです?」
にこやかに応じると、その客は「いいねえ」と懐に手を入れた。
「鱗形屋がおかしくなって、喜三二の本はしばらく見なかったからな。一冊ずつもらうよ」
「はいはい。ありがとうございます」
耕書堂はこの正月、喜三二の黄表紙を二作同時に売り出した。他にも王子風車で一作、四方屋本太郎――大田南畝の変名である――で一作を取り揃えた。
「二冊で四十文です。はい……確かに」
代金を受け取って本を渡す。客はぺらぺらと捲って軽く中を眺めると、軒先に掲げられた看板を見上げた。
「耕書堂ってえと、こないだまで引手で商売してた見世かい」
「ええ。去年の終わりくらいに地本の株を買いましてね。これからは色々と作って売りますよ」
「へえ。あの見世、鱗形屋と一緒におっ死ん……」
鱗形屋と一緒におっ死んだとばかり思っていた。その言葉を中途で呑み込み、客は幾らかばつが悪そうである。対して重三郎は軽やかに「ははっ」と笑った。
「ところがどっこい、こうして生きておりますよ」
「いや、すまねえ。参ったな」
苦笑の面持ちで軽く会釈し、客は吉原大門へと歩いて行った。
かつて西村屋与八に言われたとおり、重三郎と鱗形屋の繋がりは世に広く知られていた。それゆえであろう、鱗形屋が躓いた折に何も売り出さなかったことで「蔦重も終わり」と囁かれていたものだ。この先も細見だけの本屋のままだろう、と。
それが一転、この安永九年には一月の黄表紙に加え、七月にも喜三二の新作を売り出した。同年に売り出したのは、二度の吉原細見を含む十五作である。そのうち人気の黄表紙は計八作、しかも当代一の朋誠堂喜三二が三つも書いているとあって、世間はこれに驚嘆した。
人は世の中の流れや、話題になっているものに弱い。死んだふりからの、一気の仕掛け――重三郎の立ち回りも人々の口の端に上り、日を追うごとに蔦屋耕書堂の名は巷間に知られてゆく。さらに、喜三二の三作が揃って大当たりを取ると、世間が勝手に「黄表紙なら耕書堂」と騒ぐようになっていった。
いざ、この流れを手放してはならじ。明けて安永十年(一七八一)正月、耕書堂はまたも多くの黄表紙を売り出した。
その中の一冊に、朋誠堂喜三二の『見徳一炊夢』があったのだが――。
「よし! やったぞ」
重三郎は一冊の本を見て大声を上げた。一月末のとある日、見世を閉めて夕餉を取った後である。端で茶を含んでいたお甲が、ぎょっとした目を向けてきた。
「何だい、いきなり」
「おう、これだよ。これ見てくれよ」
差し出した本は大田南畝の『菊寿草』である。新しく世に出た本の中から、優れたものを取り上げて紹介する一冊であった。
「ほら見ろ。喜三二先生のが極上の上吉に挙げられてんだ」
南畝は昨年、耕書堂から黄表紙を一冊刊行している。その縁という訳でもあるまいが、高名な随筆家が最も優れた一冊と評してくれたのだ。それは『見徳一炊夢』の大当たりが約束されたに等しいできごとであった。
「へえ。さすが喜三二先生だねえ。今度、お礼しないとね」
満足そうなお甲の声に、しかし重三郎は「いやいや」と頭を振った。
「お礼をする相手は南畝先生の方さ」
如何に良い本を世に送り出しても、必ず当たるとは限らない。時には箸にも棒にも掛からない本が大当たりを取ることもある。そう言って、重三郎は「でもさ」と続けた。
「売り出す方としちゃあ、そんなの嫌じゃねえか。だから本当の本物を流行らせようって気張ってんだ。いいものに触れてるうちに、読む人の目も肥えていくもんだからね」
「こういうのに取り上げられると、黙ってても世の中が騒いでくれて、皆して読んでくれるって訳か。だから南畝先生にお礼すんだね」
「そういう理由だけじゃないよ」
南畝は昨今、京で流行りの狂歌に興じていると聞いた。狂歌は宴席の座興で詠み捨てにされる歌だが、南畝の作風は独特である。国学や漢学の知識を下敷きにした歌は、同じく知識に富む戯作者や絵師を引き付けているらしい。
「南畝先生と昵懇になれたら、物書きの先生や絵師さんとの繋がりが広がるってもんだろ?」
「分かっちゃいたけど、あんた逞しいねえ」
重三郎は「うは」と笑った。
「とは言え、南畝先生ほどのお人を梃子に使うだけじゃ申し訳ない。だから先生お得意の狂歌でも、ひとつ考えてることがあるんだよ」
「どんなの?」
「それは先々のお楽しみ」
この先は、その「お楽しみ」のために奔り回ることになる。黄表紙その他の本は手代に任せれば大丈夫だが、見世の切り盛りはお甲に頼むところが大きい。
「てな訳でさ。頼りにしてるよ」
*
十日ばかり過ぎて、重三郎は牛込中御徒町に出向いた。内藤新宿より少し東、神楽坂のやや南である。大田南畝は下級ながら武士の家柄で、ここに小さな屋敷を構えていた。
「ようこそ、お出でくだされた。四方屋本太郎の時以来ですな」
南畝は三十三歳、重三郎よりひとつ上である。もっとも既に髪は薄い。頭の後ろ辺りに結った申し訳程度の髷が、五十路も間近かと思わせるような貫禄である。
「ご無沙汰、申し訳ありませんでした」
平伏するように一礼して顔を上げる。重三郎が再び口を開く前から、南畝はにこやかに語りかけてきた。
「この間頂戴した文では、喜三二さんの本のお礼ということでしたが」
「その節は、ありがとうございました。これ、つまらないものですが」
手土産の菓子折を差し出す。南畝は「これはどうも」と目を細めた。
「もっとも『見徳一炊夢』は、誰が見ても分かる良作でしたからな。喜三二さんは元々が筆の立つ人ながら、蔦屋さんで書くようになって脂が乗ってきたようだ」
「そう思われますか」
「喜三二さんは蔦屋さんとご昵懇ゆえ、気分良く書けておるのでしょう」
通り一遍のやり取りではある。しかし重三郎は、南畝の今の言葉を聞き逃さなかった。この人は、気心の知れた相手と仕事をすることに喜びを感じるらしい。
「気分良く仕事をする、それが一番ですよね」
「まさに、まさに」
顔を見れば分かる。心の底からの同意だ。ならば、これこそ足掛かりになる。
「ねえ先生。実は手前も、気分の良くなるようなことを始めたいと思ってんですよ。こう……仕事で疲れた時なんかに、そういうのがあると気の張りが戻るじゃないですか」
そう切り出した。重三郎の仕掛けた勝負であった。
「どうでしょう。先生は狂歌をお好みと聞いておりますけど、手前もそのお仲間に入れていただけませんか」
「ほう? 蔦屋さんも、ご興味があると」
即座に「もちろんです」と頷いた。
「最近、妓楼連も狂歌を齧るようになってきたんですよ。どうにも面白そうなことをしているなって、思ってたとこでして。ところが手前は本屋ですから、妓楼連には入れないんです」
「なるほど、ならば是非ご一緒しましょう。集まりがある時にはお報せしますゆえ、暇があればお越しになるといい」
思うとおりに話を進められた。始めの一歩は、これにて「勝った」と言えた。
それから四ヵ月余り。天明元年――安永十年四月二日を以て改元――の夏六月を迎えた。
ある晩、重三郎は夜半を過ぎて自らの見世に戻った。
「今、帰ったよ」
声をかけるも、間口を閉めきった見世の中から返答はない。重三郎は右端の戸板にある小さな木戸を開けた。この木戸には閂が掛けられていない。夜中でも引手茶屋が見世を開けている五十間道ゆえ、常に人目がある。盗人に荒らされる気遣いはなかった。
ごそごそと木戸を閉め、本の積まれた台の脇を擦り抜けると、板張りの狭い帳場に腰を下ろして独りごちた。
「いやいや、参ったね」
大田南畝の狂歌仲間に食い込んでからというもの、頻繁に狂歌の宴に赴いている。南畝の催す席ばかりではない。南畝を中心に集った面々――いわゆる「山手連」の中、他の誰かが設けた歌会でも、できる限り顔を出すことにしていた。
「まさに三日に上げず、だからなあ」
言いつつ、背を丸める。
「ここんとこ、女房も抱いてねえ」
お甲は女郎上がりで、男に抱かれるのが商売だった女である。嫌な客の相手を繰り返すと、そういう営みが嫌いになる女も多い。もっとも、お甲には重三郎に寄せる思いがある。ゆえにこそ三十を数えても女たり得るのだし、そういう女を放ったらかしにしているのは少しばかり恐い。
「そろそろ……三ヵ月もご無沙汰になんのか。あいつ、怒ってねえかな」
「ええ怒ってますよ。もっとも、それ以上の不満もあるけどね」
独り言の囁きに、後ろから囁き声を寄越されて背筋が伸びた。振り向けば、いつの間にやらお甲が来ていて、目を吊り上げていた。
「お、おお……。おまえ。まだ起きてたのかい」
「寝てなんかいられるかってんだ」
この上ない仏頂面、忌々しそうな声で吐き捨てると、お甲は一枚の絵を突き付けてきた。
「これ。今日、西村屋から届けられたんだよ」
「え? 来たのか、あの野郎」
「届けたのは飛脚さ。さすがに当人は来やしないだろ。それより」
この絵を描いた絵師が問題なのだ、と溜息をつく。渡された絵に目を落とせば、左下に「清長画」とあった。
鳥居清長は名が示すとおり鳥居派の絵師だが、重三郎と懇意の北尾重政や、勝川春章の画風も学んでいる。その縁で北尾から紹介されたのだが、西村屋と共に絵を売り出すという話の折に引き剥がされたひとりであった。
「ああ……清長さんか」
「何が『ああ』なのさ。こりゃ西村屋が、あんたを馬鹿にしてんだよ。あたしゃ、もう悔しくて悔しくて」
なのに重三郎は今日も狂歌、明日も狂歌でふらふらしている。お甲にとっては、それが何よりもどかしいところらしい。
夫が見くびられて怒るとは、何ともかわいい女である。重三郎は「ふふ」と苦笑して、二度三度と頷きながら返した。
「西村屋が清長さんを担いでんのなんて、とっくに知ってるよ」
「だったら何で黙ってんのさ」
「違うな。だからこそ、今は黙ってんだ」
黄表紙では西村屋に迫る勢いだが、絵では未だ足許にも及ばない。さすがの大版元、一朝一夕に勝てる相手ではないのだ。
しかし――重三郎の目に、確かな力が籠もった。
「今、必死で種を蒔いてんだよ。狂歌の集まりに顔を出すのも絵で勝つためさ。それに最近じゃあ、町人の間でも狂歌は流行ってきてるだろ?」
「あんた、いつも『自分が流行りを作る』って言ってんじゃない。世の中の流れに乗るなんて蔦重の仕事じゃないだろ。そもそも歌と絵に何の関わりがあんのさ」
なお不服そうな女房に、にやりと笑みを向けた。
「それも違うよ。関わりがあるかどうか、じゃあない。関わりを作ってやるんだ」
絵と歌、全く畑の違う二つに関わりを作る。それが重三郎の思い描く次の一手であった。
もっともお甲には、雲を摑むような話らしい。
「あんたが何考えてんのか、あたしにゃ分かんないよ」
「明後日、人を招いてある。おまえも一緒に会うといい。そうすりゃ分かるよ」
重三郎は、にやりと笑った。我に策あり――自信の面持ちを受けて、お甲の目が軽く見開かれた。
〈第六話に続く〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
