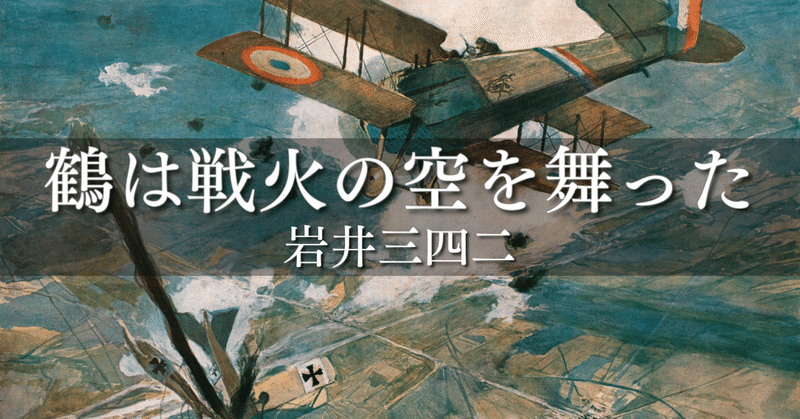
【刊行直前特別連載!】鶴は戦火の空を舞った 第三章 2/岩井三四二
(第三章 フランスの青い空)
二
初夏の日射しに灼かれながら、英彦は演習場を見渡していた。
遠景には、蒼くそびえる富士山。頂上には白いものが見える。
裾野には暗緑色の樹海がひろがり、目先一キロほどまでつづいている。そこから足許まで、黒い土に岩と草がまじる原野になっていた。
「中尉どの!」
兵のひとりが駆け寄ってきて報告する。
「第二区画の掘り方が終わりました。検分を願います」
「おう」
カーキ色の軍服に制帽、膝から下を革ゲートルでかためた英彦は、兵の案内で作業場に向かった。
第一師団工兵第一大隊は、ここ富士の裾野にある駒門に野営演習にきていた。原野に建てられたバラックに一週間ほど寝泊まりして、毎日朝から晩まで実戦を想定した演習をするのだ。
今日の演習は、築城である。といっても本格的な要塞を築くのではなく、司令本部の野戦陣地を築け、と命じられていた。
掘り下げた穴の中では兵たちが、円匙(シャベル)をつかって地面をならしている。地上にはバラックを建て、土囊で防護し、ついで砲撃されたときに避難するための地下壕を掘る、という手順だ。英彦は穴の中におりてゆき、図面を手に、兵たちが掘り下げた深さと奥行きを検分していった。
「よし。図面どおりだ。支柱設置にかかれ」
兵たちに指示しておいて穴から出ると、
「よお、錦織よ。久しぶりだな」
と大隊本部付の小山大尉が歩み寄ってきた。英彦は敬礼した。
「ご無沙汰しております。先日、もどってまいりました」
「おう、聞いてる。どうだ、鳥からモグラにもどった気分は」
小山大尉は悪い人ではない。親しみを込めて言っているのはわかっているが、それでも胸に痛みが走る。
二月末の所沢大阪間の長距離飛行は、予定どおりに実施されて成功裡におわった。新聞にも大々的にとりあげられ、操縦者の四人は一躍ヒーローとなった。
英彦は陸上の支援部隊にまわされ、静岡でひかえていた。そして成功の熱狂が去った三月、研究会員を解職し、原隊にもどすという辞令をもらった。
「後進に道をゆずるということだな。また戦争がはじまって、操縦者が必要になったら呼び返すから、そのつもりでいてくれ」
と徳川大尉に言われたが、だまって敬礼をしただけで踵を返した。人員整理のうわさは本当だった。
辞令とあれば拒否はできない。赤羽の工兵隊に帰るのだ。
──邪魔者あつかいされたか。
徳川大尉にとって英彦は、うるさくてあつかいにくい部下だったのだろう。
考えてみればこれまでも、研究会の立ち上げ時に期待された博識の日野大尉が、たいした理由もなく福岡に飛ばされている。昨年には滋野男爵もいなくなった。
徳川大尉と対立したり並び立ったりすると、研究会から消えるようだ。徳川大尉は、ここまで実直に飛行機と作戦に向き合っていたのでそうは見えないが、実はたいした政治力の持ち主なのだと、いまさらながらに気づいた。
赤羽の工兵大隊にもどると、三日とたたぬうちに野営演習に出された。もちろん以前から決まっていた予定どおりで、別に英彦の原隊復帰とは関係ないのだが。
「やはりモグラは暑いですね。鳥のときは、逆に寒さに震えて飛んでましたが」
上空二千メートルまであがると、夏でも寒いのだ。だがその寒さが、いまではなつかしく感じられる。
「軍人は要領を本分とすべし、だ。上に逆らって意見具申などしたら、よく思われるわけがない。ま、おまえらしいがな」
小山大尉は、みなわかっている、という表情をしてみせた。せまい世界だけに、いろいろうわさが飛んでいるのだろう。同情されていると思うと、英彦は切ない気持ちになった。
夕方になると作業を切りあげ、バラックにもどる。中央に土間があり、左右に板敷きの床がもうけられた粗末な住居は、将校といえど兵とかわらない。
野営演習のあいだは新聞も読めず、世間から切り離される。飲み屋はもちろん酒保もないから、夕飯を食べたあとは静かに寝るしかない。日課の腕立て伏せや懸垂をいつもの二倍やってみても、時間はあまる。
それが英彦には苦痛だった。どうしても飛行機のことを思い出してしまうのだ。
自力で操縦して空に舞いあがったときの爽快さは、忘れられるものではない。気がつくと布団の上で、そこにはないスロットルと操縦桿を操作しているのだった。
──徳川大尉がいるかぎり、飛行隊にはもどれないだろうな。
目を閉じてから、そんなことを考える。
気球研究会はそろそろ発展的に解消され、正式な飛行隊になる──青島に出征したのは「臨時」飛行隊だった──とうわさされていた。一期生で古株の英彦も初代飛行隊長の候補にあげられていたはずだが、いなくなってしまえば、隊長は徳川大尉で決まりだろう。
ヨーロッパではいまだに戦争がつづいているが、アジアは静かなものだった。今後しばらくは、戦争が起きて飛行隊に呼びもどされるとも思えない。
つまり当分のあいだ、自分は空を飛べないのだ。いや、もう一生飛べないかもしれない。
となれば工兵将校として一生を送るのか。
その人生を想像してみた。
陣地を造り、戦場で橋を架け、あるいは敵の要塞を爆破する。
一般のサラリーマンや商売人にくらべれば、十分に刺激的な仕事だ。世間体もよい。
だがそれでも、と思う。
「退屈すぎる。とても耐えられん」
空を飛ぶ面白さを知ってしまった以上、ほかのどんな仕事も刺激がなさすぎて、色褪せて見える。地面の上で、ただ意味もなくのたうちまわっているとしか感じられない。
空を飛びたい。
といっても、飛行隊からはじき出されてしまった以上、飛びたくても飛べない。
英彦はため息をつくしかなかった。
野営演習からもどると、また赤羽の本部での勤務となった。近くの官舎から毎朝、出勤する。
仕事は多かったが、どれもこれも退屈なものばかりだった。
兵たちの教育と作業の監督、勤務評価、つぎの演習計画の策定、自分自身に出される演習課題の回答作成。そして将校仲間での銃剣術や柔道の稽古、それが終わったあとの飲み会……。生ぬるくよどんだ川の中に浮いていて、ただ流れに身をまかせている、という感じがした。
英彦と対照的に、妻の亜希子は実家が近くなって喜んでいた。いまや頻繁に実家に帰っているが、そのせいか亜希子は機嫌がよく、夫婦のあいだがいくらか円満になってきたように思える。
一方、ヨーロッパでは戦争がつづいていた。
昨年八月、開戦と同時に怒濤のごとくフランスに攻め込んだドイツ軍は、ひと月もしないうちにパリの近くまで迫ったが、マルヌの会戦で敗れて快進撃はとまった。いまやドイツと英仏両軍は、互いに長大な塹壕陣地を築いてにらみあっている。
ドイツの東部ではロシアと戦いがはじまっており、そこにトルコも加わって複雑な様相を見せるなど、昨年八月の開戦当初、年末には終わるとみられていたヨーロッパでの戦争は、いまやいつ終わるとも知れない消耗戦に突入していた。
青島での戦いのあと、アジアでは戦乱の芽はどこにもなかった。日本が中国に対して二十一箇条の要求を出して紛糾していたが、それもそろそろ解決しそうだ。
こうした動きは新聞で毎日のように報道されていたが、その中で英彦はとくに飛行機の記事をさがしては丹念に読んでいた。
今年にはいってから、ドイツのツェッペリン飛行船がイギリス本土を爆撃した、という記事が目につくようになっていた。
──飛行船など、飛行機から機関銃を撃ちこめば、簡単に落とせるのではないか。
と思っていたが、どうやら飛行機が上昇できないほど高い空を飛んでくるらしい。ドイツの手にかかると、飛行船も高度な兵器になるのだと感心するばかりだった。
五月の末には、フランスの飛行機十八機が戦線から二百キロも後方のドイツの都市を爆撃した、との記事が出た。
「てえことは、往復で四百キロもの距離を一気に飛んだのか。しかも爆弾を抱えて!」
英彦はうなっていた。やはり飛行機の技術は日進月歩なのだ。とくにヨーロッパは戦争の必要に駆られて、飛行機がどんどん進化している。偵察だけでよしとする日本は、技術進歩から置いていかれてしまうのではないか。
心配したところで、工兵にもどった英彦にはどうすることもできない。
もどかしい思いを抱えたまま、英彦は勤務をつづけていた。それでも、やはり空を飛びたいという思いは消えない。思いあまって、
──いっそ軍をやめて、民間の飛行家になろうか。
とも考えた。操縦者として雇ってくれるところがないだろうか。
しかしいまのところ民間では金持ちの個人がヨーロッパから飛行機を輸入して乗っているばかりで、飛行機の用途は道楽の域を出ていない。
帝国飛行協会というものができて、懸賞飛行競技大会などを開いていたが、出場者はみな個人で飛行機をもっている者ばかりだった。念のため調べてみたが、日本には英彦を雇ってくれるような民間の飛行会社はない。
「航空思想は、いまだ世間に普及していないようだな」
と嘆くしかなかったが、そこでふと思い出した。
「待てよ。だれだったか、民間の飛行会社を作ると言ってた人がいたな」
だれだったか。たしかにそんな話を聞いたはずだ。
しばし頭をひねってから、思い出した。
「滋野男爵だ!」
たしか気球研究会をやめたあと、大阪で飛行会社を作ろうとした、と聞いた。しかし、飛行機を買い付けにいったフランスで、何を思ったのか従軍してしまったのだ。
だから、滋野男爵はいまフランスにいて、やはり日本に民間の飛行会社はないのだ。
がっかりしたが、そこで思わず、
「おっ」
と声をあげてしまった。
閃いたのだ。
「だったら、真似をすればいいんじゃねえか」
フランスへ渡って、滋野男爵とおなじように陸軍に志願する。
飛行時間が百五十時間以上あると申告すれば、飛行隊にまわしてくれるにちがいない。
そうなれば、また空を飛べる。
英彦自身も、いまでは昔の滋野男爵とおなじほどの腕前になっている。十分にフランスで通用するのではないか。
フランスで従軍するとなれば真っ先に必要になるのはフランス語だが、さいわい幼年学校と士官学校で勉強している。会話もそこそこできる。フランスでも、なんとか意志を通じさせることくらいできるだろう。
道が見えた、と思った。
だがつぎの瞬間、さまざまな障害があることに気づいた。
そもそも、日本陸軍をやめてフランス陸軍に入るなど、できるのか?
軍の将校は終身官とされ、一度将校となったら死ぬまで軍籍を離れることはできない。あるのは現役と予備役の別だけだ。現役を離れて民間人になっても予備役とされ、必要となれば呼び返されて軍に復帰しなければならない。
そんな日本軍の予備役将校が、フランス陸軍に入隊できるのか。
滋野男爵はもともと民間人だったから、そのへんはもう少し単純だっただろうが、自分の場合は?
そして妻はどうする? 日本においてゆくのか? また父や母は何と言うだろうか。
問題は山積している。
しかしそれで、と英彦は自問した。
困難だからやめるのか。飛ぶことをあきらめるのか?
答は明らかだった。
「あきらめられるわきゃあねえ。何としても飛びたい。いや、飛んでやる!」
もしあきらめてしまったら、いま胸にくすぶっている熾火が燃えあがり、いずれこの身は焦がれて死ぬだろう。自分はじっとしていられない性格だ、とわかっていた。どうしても冒険を求めてしまうのだ。
いま行動に出るしかない。
「よし。腹は決まったぞ」
道は見えている。あとは進んでゆくのみだった。
(次話に続く)
プロフィール
岩井三四二(いわい・みよじ)
1958年岐阜県生まれ。96年「一所懸命」で第64回小説現代新人賞を受賞し、デビュー。98年「簒奪者」で第5回歴史群像大賞、2003年『月ノ浦惣庄公事置書』で第10回松本清張賞、04年「村を助くは誰ぞ」で第28回歴史文学賞、08年『清佑、ただいま在庄』で第14回中山義秀文学賞、14年『異国合戦 蒙古襲来異聞』で第4回本屋が選ぶ時代小説大賞を受賞。他に『鹿王丸、翔ぶ』『あるじは信長』『むつかしきこと承り候 公事指南控帳』、『絢爛たる奔流』、『天命』『室町もののけ草紙』『「タ」は夜明けの空を飛んだ』など著書多数。
岩井三四二さん『鶴は戦火の空を舞った』は
5月21日に集英社文庫より発売!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
