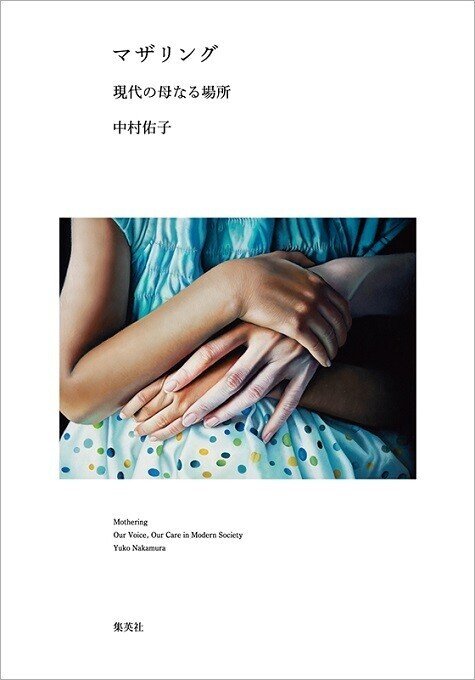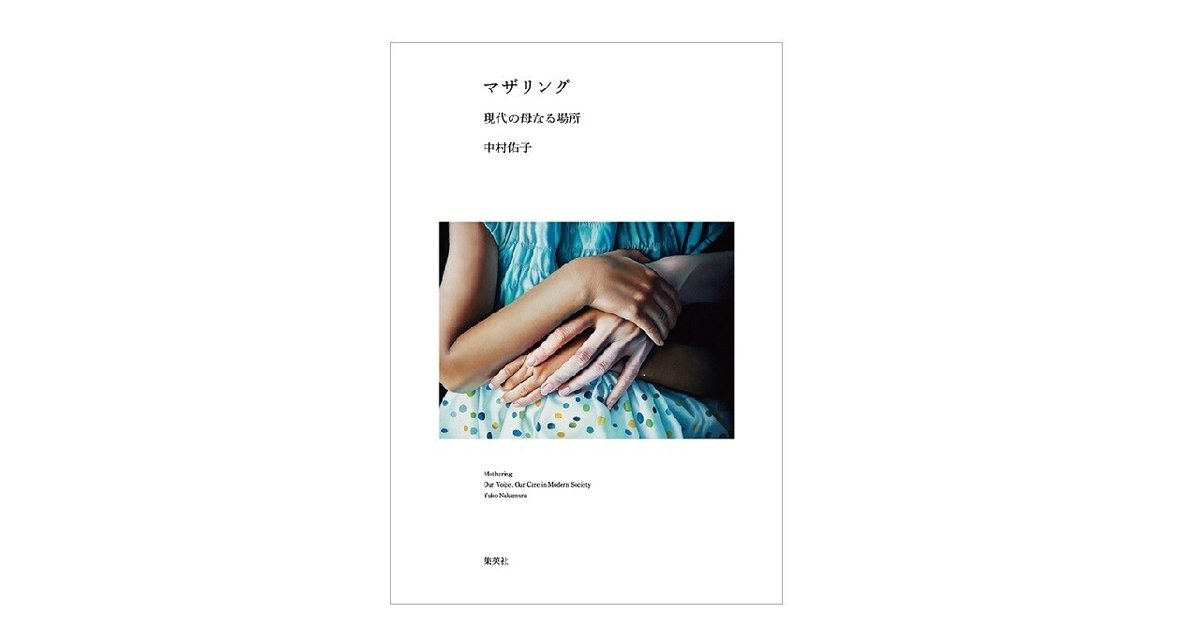
【試し読み】『マザリング 現代の母なる場所』(中村佑子・著)まえがき
映画『はじまりの記憶 杉本博司』や『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』などで知られる、気鋭のドキュメンタリー監督、中村佑子さんによる初の単著『マザリング 現代の母なる場所』が発売されました。
中村さんはご自身の妊娠出産をきっかけに、「母」とは何なのか、母になる体験というのは人にとってどういうことなのか、それを言葉にしたいという切実な想いに駆られ、同時代を生きる様々な人への取材を開始。
産後うつにおちいった人、流産を経験した人、仕事と育児の両立を綱渡りでこなす人、産まないと決めた人、養子を迎えた人、介護者、父親……。インタビューの対象はみるみる拡がり、さらに過去に書かれた「母」をめぐる文学・哲学のテキストも交えながら、性別を超えた「ケア」をめぐる普遍的な思考が紡がれていきました。
「哲学エッセイ」とでもいうべき、新しいジャンルを切り拓く一冊です。
本書の「まえがき」を、このたび試し読みとしてまるごとnoteに掲載いたします。ぜひご一読ください!
中村佑子『マザリング 現代の母なる場所』(集英社)
2020年12月16日発売
定価:本体2,200円+税
まえがき
なぜいま母なのか? 「母」という言葉を聞いて、抵抗感をもつ人もいると思う。産まない選択肢を選んでいた可能性も高かった私もまた、「母」という言葉に身構えるような感覚をもつ一人だった。そんな私がいま、手垢にまみれた「母」という言葉を、解体したいと思っている。そこから何か別の意味を抽出したいと願っている。なぜか? その思考のプロセスが本書そのものだと思うのだが、どうして母たちを取材して行こうと思ったのか、その端緒となったいきさつをここに書きおこしてみたい。
妊娠中の私におとずれたのは、霞がかった世界のなかで、小さな息一つ、一陣の風のひと吹きにも、触覚を寄り添わせるような微細な感覚だった。あのときほど、病をかかえながら仕事をしている人、なんらかの痛みをもってこの社会で生きている人のことを近くに感じたことはない。そして生まれてきた赤ちゃんは、それにも増して「弱い」存在だった。うつぶせになるたびに息をしているかたしかめた。その弱い存在と呼吸をあわせるように全身をなげうつことから、母親であることがはじまった。
自然と自分の存在は赤ちゃんの方に投げ出され、それは身体の一部がごっそり奪われるような経験だったが、奪われていることにさえ気づかなかった。目を閉じて見知らぬ水流のなかへ身をひたすようなおぼつかない日々のなか、自分が引き裂かれていくような、「私」が乖離していくような感覚にとらわれていた。これまで築きあげてきた自己という表現ではとらえきれない者に、自分が変容していた。
かつて母だった者たちも、こうした感覚をもったのだろうか? しばらくすると、自分と赤ちゃんの自他未分の状態の、この圧倒的な体験を言語化したい、そして他の人の言葉を読みたいと、切実に欲するようになった。しかし、合致する言葉に出会えないまま、あっというまに半年あまりが経った。
そうして一つのことに思い当たった。妊娠出産期の女性たちの言葉、その数が絶対的に少ないということに。当事者ならではの体験談や苦労話、ワンオペ育児や保活がどれだけ大変か、社会的につらい立場に置かれる女性たちに警告を発し、鼓舞する文章には出会った。そうした言葉にはとても勇気づけられたが、私が感じたような、子どもを身ごもり育てる女性たちが直面する存在論的な不安というべきものに当てはまる言葉に、なかなか出会えなかった。
当初は、この時期の女性は現実的なタスクに追われ、抽象的な思考ができなくなっていくのかもしれないと思った。産後の傷も癒えぬまま命をあずかる責任感のなかで、授乳に抱っこ、おむつ替えと、やらなくてはいけないことが多すぎる。核家族化した社会のなかで、先行世代からの学びの場が少なく、孤立しがちな現代の母親たちが出産を経て突然ほうり出される、このカオスな名づけ得ぬ状況に、いつか適切な名前がつけられる日がくるのではないか。思考もまとまらず自分が何を感じているのかもわからなくなっていくなかで、それでも目の前で起こるのは、毎日が「初めて」に満ちあふれた赤ちゃんの、喜びや恐れとともにある時間だ。その体験の総量を言葉にしないまま、これまで女性たちは黙って子育てをこなして来たのかもしれない。記録されていない言葉がある。私は切実に、母になった人の言葉が聞きたいと感じはじめた。そして、本書のもとになる連載がはじまった。
産後うつに陥った人、流産を経験した人、仕事のキャリアを捨てずに綱渡りで子育てをしている人……さまざまな事情を抱えた現代の母親たちと、膝をつきあわせて言葉を探る日々のなかで、ここにはある本質的な問いが潜んでいることが次第にはっきりしてきた。それは、言葉を失うということが、ある種の必然なのではないかということだ。この本質的に言語では形容不能な「母」の発見の詳細は、ぜひ本書をお読みいただけたらと思う。
取材し、書いていくなかで実感としてつかんだ「母」とは何かといえば、それは生命が躍動し「生」の方に振れたり、生命が動きを止め「死」の気配に振れたりする、その振り子の繊細な挙動に応え、揺らぎつづける存在、とでもいえようか。母なる体験には、生と死、その両義的なもののはざまにあるグラデーションの、全てが詰まっているように感じた。
次第に取材対象者は母になった人だけではなく、母にならなかった人、母にならないと決心している人、養子の子どもを迎えた人、父親……産む/産まないの差や、性差を超えて広がっていった。この論考を通して考えていた「母」とは、旧時代から続くイメージである、自己犠牲を伴う包容力を喚起する母とは異質な概念だ。
現代社会のなかで「母」という言葉には、家父長制に由来するある種の烙印が押されている。自己犠牲、生産性、社会への貢献、安定感、保護膜……「母」と言った途端、社会的な構造の問題にからめとられてしまう危険を、連載時も、そして連載を終えたいまも感じている。
しかし、母になってみて何よりも実感するのは、大きな虚無に触れるような境界性や、自分のなかに他者が流入してくる、言葉にならない空白の感覚、痛みから世界を見るという、被傷的で過敏な感覚だった。何一つ合理化できるものがない生の起源の場所なのに、母を科学的にアウトソーシングすれば良い、個人としての母を最大限尊重し、母親業は徹底的に合理化できると考える現代主義的な母像もまた、生命自体を合理化しすぎていると、私には感じられた。そんなに物事をはっきりと線引きし、合理化できないものの総体が「母」であるとも思っていた。
「母」が忌避されるような時代のなかで、母を再発見し、あらためてその孤独や虚無や喜びの総量を、この社会のなかに位置づけたい。それは母のなかに、いまだ語られていない無尽蔵の謎が潜んでいると実感したからだった。母を考えることは、自然と人間との関係をとらえ直すことでもある。子どもや、他者からの要請に人間はどう応え得るか。ケアとは何か、その問いに向き合うことでもある。取材に応じてくださった多様な「母」のうちに、この世界にあふれる問いの多くが象徴的に潜んでいると感じていた。しかし、それを語るのに、手垢にまみれた母や母性という言葉を使って本当に良いのだろうか……?
私は「母」に代わる言葉をずっと探していた。そして、出会った言葉に「マザリング」があった。「マザリング」とは、オックスフォード現代英英辞典によれば、「the act of caring for and protecting children or other people」つまり「子どもやその他の人々をケアし守る行為」という意味である。「マザリング」は性別を超えて、ケアが必要な存在を守り育てるもの、生得的に女性でないものや自然をも指すという。取材を重ねながら考えてきたことと、奇妙に符合する偶然を感じながら、二年に及んだ連載のタイトル「私たちはここにいる――現代の母なる場所」を、書籍化にあたって「マザリング 現代の母なる場所」に変更した。
さらに、こうした守るべき他者を助けようとする感性のことを、介護の現場で「母性」と呼んでいるということを、最近知った。
介護研究家の三好春樹は、「〈介護的人間の誕生〉」という文章のなかで、「何とかしなきゃ」という「健全な倫理主義」が介護の現場にあふれていることを指摘する。就職で介護業界に入ってくる若者には、「何とかしなきゃ」という偽らざる思いがある。それを三好は、「「母性」をその根拠としたい」と書いていた。彼が監修した『実用介護事典』にはこう記述がある。
「母性【ぼせい】/弱い立場の人、困っている人を目の前にするとなんとかしてあげたいと思う、人間が本来持っている性質のこと。(略)介護の世界では、女性にかぎらず広く定義するほうがよい。(略)母性をこのようにとらえると、専門的知識や技術は「母性をより適切に発揮するための手段」といえるだろう」
驚くほど「マザリング」の定義に似ていることがわかる。介護の現場では人が痛み、苦しんでいるときに「何かしなきゃ」と手を差しのべる。それは人間の本来性にかかわる性質で、その力を「母性」と呼んでしまおうというのだ。それは「母性」が持っている、「他者を生かしたい」という力を、性差を超えて、この現代社会に使い果たそうと宣言しているようでもある。介護事典に書かれているこの意思を、私も深く共有している。
連載を読んでくれた同僚の男性が、こんな感想を漏らしてくれた。「〝傷ついた身体に空いた穴こそが、他者の痛みを感じとるセンシティビティになる〟というのは、共感するということでもあるのかな。それを〝母性〟と呼ぶのなら、確かに性差も年齢も関係ないし、僕の中にも〝母性〟はある」。
母なる体験とは、自己のなかの空隙が、他者の生命の微細な変化を感じとる体験のすべてだったといえるが、そこに彼は自分自身の共感の力、感受力とでも呼ぶべきものとの呼応を感じてくれた。
地縁も、人とのつながりも希薄な現代社会において、他者へのセンシティビティに「母」という言葉を使うなら、それはもはや生物学的な女性や、子どもを産んだ人だけではなく、多くの人がもつべき力のようなものとして、とらえられるだろう。
連載を終え、書籍化のための改稿に取り組む半年あまりのうちに、世界の状況は大きく変化した。「コロナ」という単語を発すれば、そこに落胆と不安が入り混じった感情までも付随する、圧倒的な世界共通語が生まれたと言えるだろう。私たちは、よりあいまいで複雑になった新しい世界線のフロンティアに立ちすくんでいる。
個々人の権利と自由を守り、尊重しなければいけないことは変わらず疑いもないが、人間という「種」にとっての自由の意味は変革を迫られている。文明が追いやってきたウィルスや病原菌、不潔なもの、死の影を帯びたものたちが、ひたひたと私たちの背後から迫っているような今、人類は文明が謳歌してきた自由の意味を問い直し、自然や環境との新たな紐帯を創造する必要に駆られている。
「マザリング」とは、自分や他者の痛みに鋭敏になり、いつ終わるとも知れない計画できない時間を待ちながら過ごすという、文明が退化させてしまった他者に寄り添う感覚を取り戻すプロセスであったと感じている。それは、私たちの文明を問い直す力でもあると言えるだろう。
生の起源を忘れることで成り立つような現代社会のなかで、本書を手にとっていただいたことが、この本来人間が豊かに持っていたはずの感覚を思い出し、文明の矛盾とオルタナティブを考える上での問いの共有となるなら、この本を書いた者のよろこびとなります。
プロフィール 中村 佑子 (なかむら・ゆうこ)
1977年東京都生まれ。映像作家。慶應義塾大学文学部哲学科卒業。哲学書房にて編集者を経たのち、2005年よりテレビマンユニオンに参加。映画作品に『はじまりの記憶 杉本博司』(2012年)、『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』(2015年)がある。主なテレビ演出作に、「幻の東京計画 ~首都にありえた3つの夢~」(NHK BSプレミアム、2014年)、「地球タクシー レイキャビク編」(NHK BS1、2018年)など。本書が初の著書となる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?