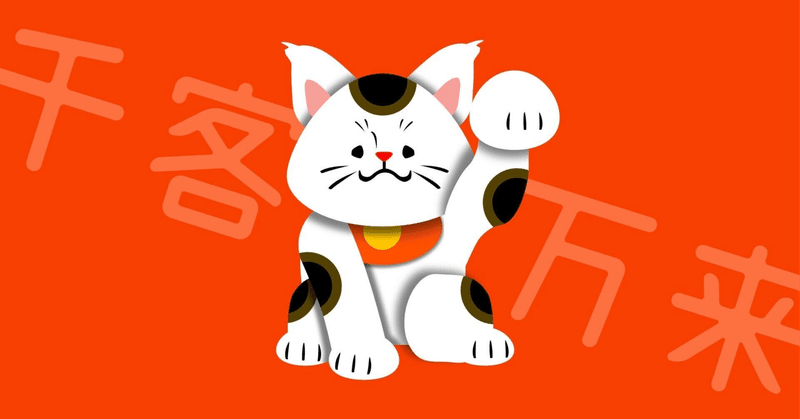
「安いことは良いこと」幻想(1)〜経営者は値上げの「論理」と「心理」をコントロールしよう
事業において「プライシング」は最も重要な要素です。
大抵、失敗する地域事業で間違えるのは、値付けなのです。これは口酸っぱく言ってきてて、特に人手不足の地方では安くたくさんを処理する人員確保が困難なので、絶対に息詰まるので、しっかり単価を引き上げてサービスを改善するサイクルを作るほうが良いと考え、私もプロジェクトに関わっています。
基本的に事業に関するアドバイス求められても常に値上げをして、サービス改善するという視点で話をします。安くして、たくさんもっと売っていきましょう、ということは言わない。特にインバウンドなど海外勢に向けた商売確実に値上げが大切で、安すぎると怪しまれるだけで良い客はきません。
ただ当事者の方に言われて「なるほどなぁ」と思ったのは、私の狂犬ツアーなどに何度か参加して心から値上げをすることの必要性を感じ、それを少しトライしたらやはり非常に客筋がよくなり、事業性も高まったという実感から「勇気をもらえた」というわけです。
そうか、なんで値上げをしないのかと思ったら、それは「論理的な納得感」だけでなく「心理的抵抗感」を乗り越えなくてはならないところです。ということで、論理と心理の2点から今回は解説したいと思います。
○ ガラパゴス・プライシングに陥るな
今は海外と日本との価格差はダイナミックに変化していて、対象国でも違いますが、基本的には「インフレ率」は日本より海外のほうが高く、さらに「円安」によって相対的に日本円の値付けは値下げをしているのと同じ為替上の圧力がかかっています。米国なんか7%とかあがっていることを考えれば、その分値上げできるし、さらにドル円相場もものすごく動いて、一時期1ドル150円程度まで円安になり、今は131円あたりの円高になったりしています。このあたり海外からみて日本のプライシングがどうなのか、は常にインバウンド事業とかやっているところは重要になりますね。

ここから先は
サポートいただければ、さらに地域での取り組みを加速させ、各地の情報をアップできるようになります! よろしくお願いいたします。

