
現役大学生が映画「聲の形」を見た感想
ネタバレなしの感想をご覧になりたい方はこちらから!
あらすじ
いつもクラスの中心にいるやんちゃな小学6年生の石田将也。退屈な毎日の中で突然現れたのは耳の聞こえない少女だった。
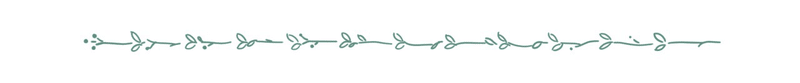
初めは好奇心から耳の聞こえない少女西宮硝子にちょっかいをかけていた将也だが次第にエスカレートしいじめに発展してしまう。
いじめに加担する人、ただ見て笑っているだけの人、何もしない人。その中にいじめを止めようとするものはいなかった。
しかし、いじめが表面化して問題になった時、クラスのみんなは将也一人に責任を押し付け、彼は孤立してしまう。それから5年後、別々の道に進んでいた将也と硝子は新たに再会するのだった。2人だけではない、誰もが抱えている自身の問題とどのようにして向き合っていくのか。

映画「聲の形」の情報
映画「聲の形」は大今良時原作の漫画「聲の形」を「映画 けいおん!」などの作品で知られる山田尚子監督でアニメ映画化したものです。
当時大きな話題を呼んだ「君の名は」と同じ2016年上映の作品だったため当初の知名度は低かったものの、第40回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞を受賞するなど確かな評価を得ている作品でもあります。

映画「聲の形」を見た感想
では早速、現役大学生が映画「聲の形」を視聴した感想をいくつかのポイントに分けて紹介します。

それぞれが抱える問題
いじめの主犯だった将也と聴覚障害でいじめの被害者だった祥子の2人はどちらも「自分が悪い」と考えてしまう癖があります。しかし、それは結局どうしようもない事と向き合うのが怖くて逃げているだけなんですよね。そんな2人だからこそ互いを思い合えるし、クライマックスの「生きるのを手伝って欲しい」という将也の言葉に繋がるのだと思います。

そして、将也への行き過ぎた恋心を抱える植野と自分を可愛いと思っており被害者意識が強い川井。この2人は本作でもかなり重要な役割を担っていました。
思ったことを口走りすぐ相手を攻撃してしまう植野ですが、実は一番硝子と正面から向き合っていたのは彼女だったと思います。障害者だからという理由で硝子をいじめたり、反対に優しく接したりする人もいた中、彼女は徹底して祥子を恋敵、もしくは将也の邪魔をする存在として見ていました。

そこに“障害者だから”ということは全く関係ないんですよね。そんな彼女ですが、映画終盤では硝子に対して“ばか”という言葉を手話で伝えるなど、不器用な彼女なりに祥子の個性とも向き合おうとする姿勢が感じられました。
そして、よくネットでも話題になっている川井。彼女も直接ではないにしろ、いじめに加担していた人物でしたが、その罪を将也一人になすり付けて自分はまるで被害者であるかのように振る舞います。その結果、彼女は多くの視聴者の反感を買いました。しかし、彼女のような一面は誰しもが持っているようにも思えます。
ネットの中で見られる行き過ぎた彼女への批判は、安全圏から人を攻撃し、優位な位置に立ちとうとする川井の行動と似ています。というよりも#川井を許すな を見ていると彼らはこの作品から何を学んだのだろうと感じます。

そんな彼女ですが、自殺未遂を行った祥子に対して「自分のダメなところも愛して進んでいかなくちゃ」と涙ながらに伝えるシーンや、将也のために千羽鶴を集めた行動は本心であり彼女なりの伝え方なのだと感じました。なにより、多数派に紛れて行動する自分が可愛いだけの人間というのは実は一番多いような気もします。

光はあるのか
主人公である将也と祥子が最も避けていのが“人の声を聞くこと”と“気持ちを伝えること”でした。将也は周りの人の顔にバツ印を張りつけてその顔を見ようとせず、他人と向き合うことから逃げます。そして、西宮もまた「自分が悪い」と決めつけて植野からの強い言葉や自分の過去から逃げていたのです。なにより聴覚障害を待つ彼女は人とのコミュニケーションが容易ではなく、その事にも苦しんできたでしょう。

そんな2人にも光が差し込みます。自殺未遂を行った彼女はその後、一人一人に「壊したものを取り戻したい」と伝えて向き合う覚悟を決めます。将也もまた、橋での出来事で彼らとの関係が悪化してしまったももの、その後も変わらず自分と接してくれたことで全ての人の顔を見る決意を決めます。
結局2人は他人との関わりから逃げ続けるのではなく、自分のダメなところや他人の個性と向き合うことで救いを得ることができました。

まとめ
映画「聲の形」は社会や個人が抱える様々な問題に焦点を当てた作品でした。私は、この作品を通して“自分の声を聞くこと”が何よりも大切だと感じました。自分を救うきっかけを与えてくれるのは周囲の人かもしれませんが、最終的に自分と向き合うことができなければ彼らのように苦しみ続けることになります。
また、この作品はもうひとつ“赦す”ということを教えてくれました。それは“自分の声を聞くこと”の延長線上にあるものだと思います。人をいじめていた過去に苦しみ続けた将也ですが、その過去は決して無かったことにはできません。それは、いじめを受けたものの消えることのない苦しみと同様です。しかし、他人を赦さない限り自分を肯定することはできないのだと思います。本作ではそれぞれが他人を赦し、自分を赦すことでやっとお互いに認め合うことができました。それがこの作品の伝えたかったことなのではないかと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
