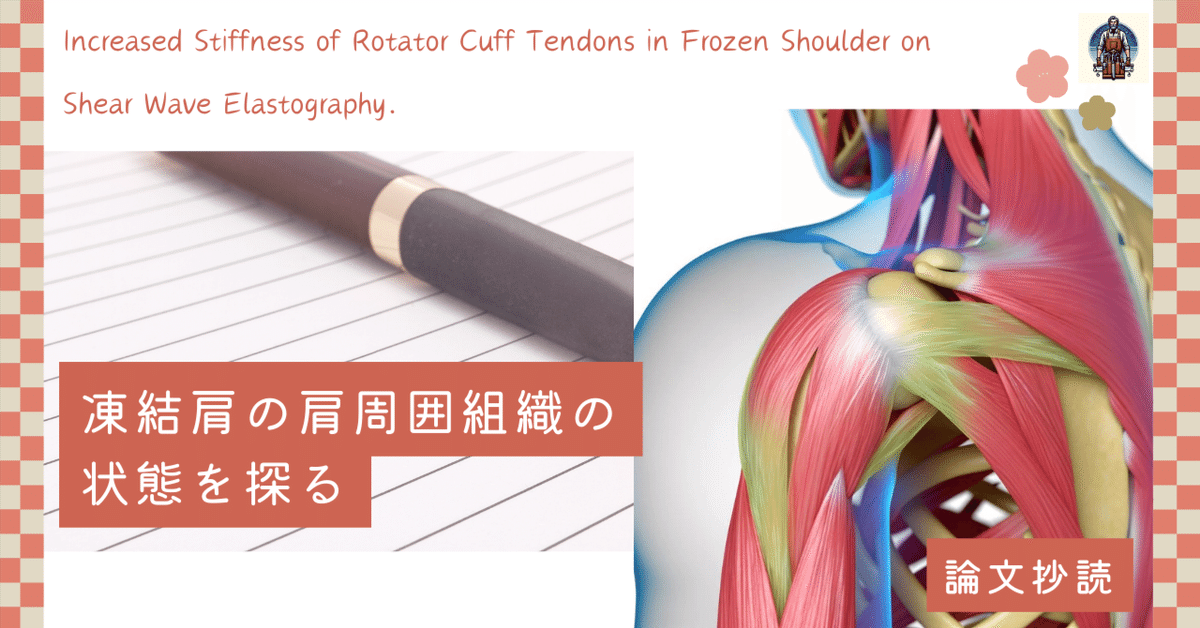
凍結肩の患者さんの肩周囲組織はどうなっている?
抄読論文
Wada T, Itoigawa Y, et al.
Increased Stiffness of Rotator Cuff Tendons in Frozen Shoulder on Shear Wave Elastography.
J Ultrasound Med. 2020 Jan;39(1):89-97.
PMID: 31218712. PubMed. DOI: 10.1002/jum.15078.
ー剪断波エラストグラフィーにおける凍結肩の回旋筋腱の硬さの増加ー
要旨
目的
凍結肩の患者において、肩関節包、回旋筋腱および筋肉、烏口上腕靭帯(CHL)、上腕二頭筋長頭を剪断波エラストグラフィー(SWE)およびBモード超音波を用いて、その硬さおよび形態学的特徴を評価する。
方法
凍結肩の患者32名を炎症期と拘縮期に分けた。全患者は、回旋筋腱の断裂なしに運動範囲の制限があった。棘上筋腱、棘下筋腱、棘上筋、棘下筋、小円筋、上部および下部僧帽筋、後方関節包、CHL、および上腕二頭筋長頭の硬さはSWEによって測定された。後方関節包とCHLの厚さもBモード超音波で調べられた。すべての値は、各期において障害肩と非障害肩で比較された。
結果
炎症期の棘上筋腱および棘下筋腱と凍結期のCHLのSWE値は、障害側が非障害側よりも有意に大きかった(平均±SD、280.4±125.3対178.1±73.3、318.4±110.7対240.8±91.5、および287.2±135.3対214.1±91.1 kPa、それぞれ;P < .05)。炎症期と拘縮期の両方で後方関節包と拘縮期のCHLは、障害側が非障害側よりも有意に厚かった(1.3±0.2対0.9±0.3、1.2±0.4対0.9±0.3、および4.4±1.4対3.3±1.1 mm;P < .01)。
結論
炎症期には棘上筋腱および棘下筋腱のSWE値が増加し、拘縮期にはCHLのそれも増加した。後方関節包の厚さの変化だけでなく、回旋筋の硬さの変化も凍結肩と関連している可能性がある。
要点
Frozen shoulder(凍結肩)は整形外科における臨床場面で多く出会う状態及び疾患の一つだと思われる。
現状、凍結肩は3つの段階に分けられていることが多く、炎症期、拘縮期、回復期、といった表現が用いられている。
本研究では、凍結肩の肩関節周囲組織の硬度及び厚みを超音波エコーを用いて定量的に評価し、比較することを目的としている。

剪断波エラストグラフィーとBモードを用いて、それぞれ硬度と厚みを評価した。
対象のうち、疼痛評価であるVASの状態によって、炎症期と拘縮期の対象者に分類した。
→ ここは注意点であり、疼痛の度合いで判断しており、疼痛発生からの時期と言った、時期要因は考慮されていない。そして、記載もない。
ただ、この点に関してはリミテーションで述べられている。
→ もう一点、時期要因が考慮されていない、つまり炎症期から拘縮期に移行した段階で同一患者を評価するといった、対応のある要因にはなっていない。
あくまでも横断的にVASによって分類した患者群で評価しているところも理解しておくべき点になる。これもリミテーションに記載あり。

炎症期と拘縮期に分けて理解する。
炎症期の患者では、棘上筋腱と棘下筋腱の硬度が高くなっていた。
また、後方関節包の厚みが拡大し、肥厚している様子が見られた。
一方、拘縮期の患者では、CHLにのみ硬度の高さが見られた。
また、厚みに関しては、後方関節包に加え、CHLも肥厚していた。
その他の部位には患側と健側で差がみられなかった。
CHLは凍結肩による可動域制限の大きな要因とされており、過去の報告でも多く見られる。しかし、時期によってその違いがあることの報告はなされておらず、本研究では、その点に着目し、炎症期ではCHLの肥厚や硬度化が生じていないことを報告する最初の論文になったと考察で述べている。
CHLと棘上筋、棘下筋などは解剖学的に連結している。
本研究の結果から、炎症期に回旋筋の炎症、硬度化が生じ、それを一つの起因として、拘縮期にかけてCHLの硬度化、肥厚と変性していくということが想像される。また、その変化は可逆的であり、拘縮期になると回旋筋腱の硬度化は寛解してくるということも明らかになった。
どのように活用するか
本研究の考察でも述べてあるように、時期的な変化によって可逆的変化が生じているという可能性を示したことは非常に興味深い。
それを踏まえると、炎症期に回旋筋の活動を過剰に生じることは、さらなる炎症を惹起し、より硬度化へとつながる。
そのため、炎症期には回旋筋腱の滑走を控える、つまり筋活動を控えるとともに、肩の関節運動でも滑走が生じる可能性はあり、それ自体抑制しておく必要があるものと考える。
そして、その時期を乗り越え、拘縮期に入ったら、CHLは一定度合い硬さも生じるし、肥厚もしてくるが、回旋筋腱自体の炎症は軽減し、硬度化も軽減してくる。
従来からその方針ではあると思うが、炎症期の活動をしっかり抑制した上で、拘縮期に入ったら、回旋筋の活動は促しつつ、CHLへの負荷を軽減する形での可動域練習、モビライゼーションが必要になってくるだろう。
本研究では、そのことに改めて確実性を覚える重要な所見となった。
↓ 関連記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
