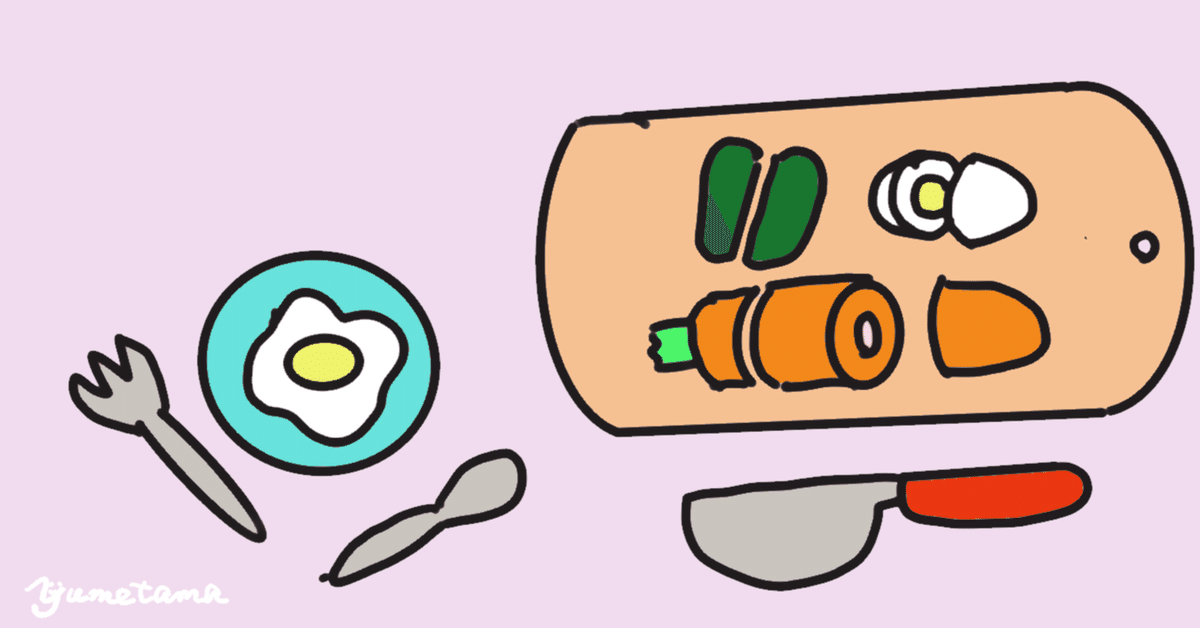
「料理で偏差値を上げる」的な食育メソッドを開発した学習塾がある。
この2年ものあいだ、日本を含む多くの国で子供たちが学校に行く機会が減りました。
その結果、親が家庭で子供に教える場面が増えているように思われます。
親が子に勉強を教える際、テーブルに教科書やドリルなどを並べ、親が教師となって子供が勉強する、という形が一般的でしょう。
いわゆる家庭教師のスタイルです。
しかし家庭教師スタイルではなく、料理スタイル、すなわち
料理を作り、そのプロセスで勉強を教える
という考えかたもあるようです。
そうした「料理を通じた学び方」には実際に学力を高める効果があるという研究結果もあります。
今回は、
学習の手法、勉強の手段としての「料理」の可能性
について考察してみます。
単に料理を一緒に作って楽しむだけではない、料理の新しい価値を見出せるかもしれません。
ニューヨークに本当にあったキッチン学習塾
もう10年以上も昔の話になりますが、
「クリエイティブ・キッチン」
という名前の、子供むけ料理教室がニューヨークにありました。
この料理教室は、料理を通じて「国語」「算数」「理科」「社会」を教えることを旨としていました。
いわば学習塾でもありました。
子供は、聞く・読む・書くといった通常の学習スタイルよりも、嗅覚・味覚・触覚を含めた五感でもっと多くを学べるかもしれない…
そういう可能性を追求しようとする料理教室でした。
指導者は、調理を教えながら、「国語」「算数」「理科」「社会」をその中に盛りこんでいました。
子供たちは料理を通じて学習し、仲間と交流しながら創造性を育んでいました。
国語
「クリエイティブ・キッチン」はアメリカの料理教室ですので、ここでいう「国語」とは「英語」ということになります。
日本語でいう「漢字の学習」は、英語では「綴り(つづり)の学習」に該当します。
たとえばブロッコリを見せながら「ブロッコリの綴りが分かる人、言ってみて?」といった質問を投げかけます。
料理には食材、調味料、調理器具、食器、料理の種類など、覚えたい単語は山のようにあり、教材に不自由しません。
また、日本語もそうですが、英語にも
食にまつわる慣用句
食にまつわる諺(ことわざ)
がたくさんありますので、料理をしながらそうした慣用句やことわざを学ぶことができます。
算数
低学年の子供の場合、
食材を数える、足し算・引き算をする
塩や砂糖などの重さを測る
酢や水などの量(体積)を測る
加熱する時間を測る
といったことを、料理で体験することになります。
もうすこし高学年になってくると、たとえば野菜を立方体に切りながら
「サイコロはいくつ面がありますか?」
と数えさせることで、幾何学の授業になります。
理科
料理がもっとも授業になりやすい科目は理科かもしれません。
料理には、
加熱する
冷やす
水に溶かす
といったプロセスがあるため、料理を「科学の実験」に見立てることができるからです。
また、肉・魚・野菜・果物といった食材は、もともとは生物に由来しています。
したがって食材を題材にした生物学の授業も行うことができます。
社会科
たとえば、以下のような授業を行っていたようです。
地理:アボカド料理の「ワカモレ」をみんなで作りながら、「この料理はメキシコ」と説明しながら「メキシコはどこですか?」と世界地図を見せる
歴史:作った料理をみんなで食べる際にコショウを見せ、「昔はコショウが貴重品で、ヨーロッパの人はコショウを探し求めて冒険をした結果、世界一周をしたり、アメリカ大陸にたどりついたりした」という話をする

さらなる可能性
「クリエイティブ・キッチン」の授業は、全盛期は全米で引っぱりだこでした。
しかし残念ながら、現在はやっていないようです。
日本から遠いニューヨークでの話でもあり、その後どうなったかの情報も筆者は持っていません。
とはいえ、料理を通じてさまざまな科目の授業をするというアイデアは、今でもじゅうぶんに使えるのではないかと思います。
「料理を通じた授業」には効果がある?
料理を通じて「国語」「算数」「理科」「社会」を教えると成績は上がるのか?
という研究がアメリカの大学で行われています。
それによると、理系の科目は成績が上がるという結果が出ているようです。
(文系の科目については研究対象に含まれていなかったようですので、どうなのかは不明)
「ExploringtheAssociationsAmongNutrition,Science,andMathematicsKnowledgeforanIntegrative,Food-BasedCurriculum」
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29224221/
「料理」で得られるのは学力だけではない
「料理」で得られるもの、その1つは「健康」
かつて一度、「クリエイティブ・キッチン」主催者のインタビュー記事を目にしたことがありますが、主催者の方はこんなことを語っていました。
* 料理教室、学習塾、どっちなのかについては、あくまでも料理教室だと考えている。
* 授業はするけれど、詰めこみ教育にするつもりはない。
* 食に関心を持ち、早くから料理の楽しみを知れば、食材に関する知識も深まり、健康な食生活につながる。
発想力や自発性も、「料理」で得られる
料理には、自発的に行動するネタが豊富に考えられます。
「カレーにチョコレートを入れたら美味しくなる?」
「チーズをおでんに入れたら美味しくなる?」
など、子供のアイデアや好奇心を尊重する形で料理を進めることができます。
結果がすぐに出て分かりやすいところも良いですね。
どのように応用するか
この2年間、世界のあちこちで学校が閉鎖されたと聞きます。
閉鎖にならなくても、時間短縮や登校日が限られたケースも多いことでしょう。
そうなると、子供たちはもっぱら自宅で学ぶことになります。
せっかくそういう機会が増えているなら、親子で料理を作りながら、「国語」「算数」「理科」「社会」を教えることができると良いですね。
ただ、そのためには、ある程度のマニュアルが欲しいところです。
ここでいうマニュアルとは、
体系的なカリキュラム
それにもとづく教本・教材
を指します。
地理を教えたければ、さまざまな国や地域の食材を準備したいところだし、子供たちに見せる地図も用意したい。
食材を切りながら幾何学の話をするなら、親にもそれなりの予習がいるでしょう。
そんなあれこれを、親が自分でゼロからすべて考えるのは無理があります。
そんなときに、
どんな食材を準備するか
どんな料理を作るか
どの科目の話をどのように教えるか
どんな教材(地図など)を用意するか
などが書かれたガイドブックがあると助かるのではないでしょうか。
ようするに「授業の準備と進め方」的なことが書かれているものです。
学校の教師が使う「指導要領」に似ているかもしれません。
まとめ
10年前にニューヨークにあった「クリエイティブ・キッチン」という料理教室は、料理を通じて国語・算数・理科・社会を教えるという、料理教室と学習塾が融合したようなスタイルで人気を博していました。
自宅学習が増えた子供たちのために、かつて「クリエイティブ・キッチン」がやっていたことを、家庭でやってみるのも良いかもしれません。
「料理を通じた学び方」には実際に学力を高める効果がありそうだという研究結果もあります。
料理は「美味しい」ものです。
料理を通じて国語・算数・理科・社会を学ぶ体験をすれば、
「勉強=美味しい」
というイメージが心の中に育つでしょう。
これが子供の学力向上にとって、何よりの力になるのではないかと筆者は考えます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
