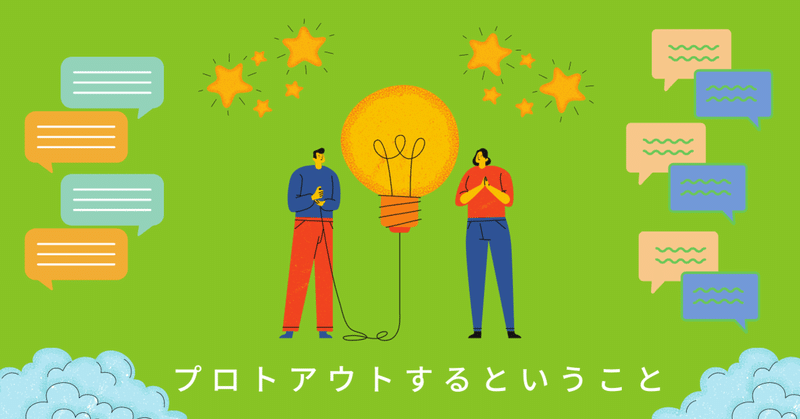
ここ2か月で学んだ「プロトアウト」するということ
この4月からプロトアウトスタジオというスクールに通っています。(リモートですが)
プロトアウトスタジオというのはプログラミング(モノづくり)とプランニング(企画)、両方のスキルを兼ね備えた人材の輩出を目的とした日本初のプロトタイピング専門スクールです。
(詳しくはリンク先を覗いてみてください)
通い出して2か月が経過し、カリキュラム的にも終わりが見えてきましたので、ここで学んできたことの振り返りをしたいなと思います。
事の経緯
プロトアウトスタジオには仕事の一環という形で通っています。
私は某システム会社のSEとして仕事をしていたのですが、この春から社内の人材育成を担当することになっていました。
そして、異動直前にこの研修に参加することを告げられたのです。
目的はプロトアウトスタジオのカリキュラムを受講してその内容を社内に持ち帰ること。変化の早い今の時代だからこそ、自身で素早くアウトプットして発信するスキルを持った人材が会社には必要だという判断です。
そんな経緯で、私はプロトアウトスタジオに通うことになりました。
プロトアウトするということ(こんな事してきました)
プロトアウトって私自身初めて聞いた言葉だったのですが、企画して作って発信するという一連の流れを指します。
(入学式で見せていただいたスライドの内容が分かりやすかったので↓に載せておきます。)
・技術 -> プログラミング
・技術+企画 -> プロトタイピング
・技術+企画+発信 -> プロトアウト
なので、プロトアウトスタジオでは基本的に以下のサイクルでカリキュラムが組まれています。
①授業(プロトタイピングに関する技術や企画の仕方について学ぶ)
↓
②企画(授業で学んだ技術を使用した企画を立てる)
↓
③モノづくり(企画したものを作る※完成しなくても良い)
↓
④発信(作ったものをQiitaやnote,twitterなどで世の中に発信する)
↓
⑤FB(発信した内容についてレビューしてもらう)
これを1週間に1サイクル回していきます。カリキュラムの最後には卒業制作として、自身が一番作りたいものをクラウドファンディングという形で発信することになります。
もう言わなくても分かると思いますが、このサイクルがめちゃくちゃきつかったです。
基本的に平日の昼間は仕事をしているので使える時間は仕事が終わった夜と土日です。(最終的には仕事中も空き時間を見つけて少しずつ進めるというスタイルに落ち着きましたが・・・)
また、授業で学んだものを使ってただモノを作れば良い訳ではなく、しっかりとした企画の上にモノが無いといけません。(「何故、自分がそれを作るのか が大事だということ」)
更に更に、作って終わりではなく、それを世の中の人に伝わるように発信しないといけないのが非常に大変でした。(入学式で、「いくら素晴らしいものをつくっても、伝えなければ、ないのと同じ」という言葉を頂戴しました。まさにその通りだと思います)
一応これでも大学時代を合わせて10年以上プログラムを書いてきた人間ですので、作るというのはそれほど苦になりませんでした。
(というか、仕事ではあんまりプログラム書かなくなってきたので久しぶりのモノづくりは凄く楽しく感じました)
問題は企画する部分と発信する部分で、最初の1か月くらいは毎週のように「あ、自分はこんなに企画力無かったんだ」、「こんなに発信するのヘタなんだ」って感じに凹んでました・・・orz
それでも2か月経てば企画から発信までをそれなりに自信を持って回せるようになってきました。多少なり記事が盛り上がったりもしました。
(かなり嬉しかったので勝手ながらリンクを貼っておきます。)
結局何を学べたのか
ここからは企画・発信力皆無だった私が、この2か月を振り返ってみて、私自身が考える気づきや学びについて書きたいと思います。
■企画~発信までの間に「分析」するという流れ
前述したように単にモノづくりをするだけでは、「何故それを作ったの?」「何故それが必要なの?」と言われておしまいです。
※単純に技術の調査・研究・学習が目的ならこの限りではないと思います。今回は主旨がプロトアウト(技術+企画+発信)なのでこういう書き方になります。
大事なのはこの「何故」という部分で、自分の作った企画に対してどんな「何故」が来ても耐えられることが理想だと思います。
そして、この何故の部分を考える上で大事なのが「分析」という行為です。企画が課題に根差したものであれば、その課題を(それが何故課題であるかを含めて)深く分析することが必要ですし、企画自体が課題ではなく自身の作りたい欲求から出るものであれば、その欲求がどこから来るものなのかを分析しなければいけません。
ただ、別に最初から深い分析をする必要はありません。というか1週間という短いサイクルで分析に時間をかけていてはとても間に合いません。
大事なのは企画を発信する段階でどんな「何故」にも耐えられること。
なので、私の場合は最初に企画を考えてからそれを形にして発信する過程で「分析」をしながら企画自体をシャープにしていくという流れが良いんじゃないかと思いました。(実際、この流れで考えるようになってからは発信までのサイクルを結構余裕を持って回せるようになりました。)
■発信することの大切さ
次に「発信」についてです。前述したようにどんなに良い企画を立てても、どんなに素晴らしいプロダクトを作っても、それを「発信」しなければ意味がありません。
と、いうか「発信」していないのにそれが「良い企画」なのか、「素晴らしいプロダクト」なのか、判断できないと思うのです。
何故なら企画・プロダクトというのは、それを欲している人たちの手に触れて、評価されて初めて価値があるかどうかが分かるからです。
(なので、自分自身のためだけに作ったものはこの限りではないかも知れませんが。)
私は元々発信という行為が苦手で、出来れば作ったものは自分の心の中にしまっておきたいタイプでしたが、プロトアウトスタジオで学ぶうちに、「発信しなければその企画・プロダクトはそこで止まる(成長しなくなる)」ことを知りました。
※なので、プロトアウトスタジオではたとえ未完成でも発信することを絶対としています。
実際、作っている途中のものでもTwitterに載せたりすると色んな人からコメントをもらえて、それが前に進むきっかけになったりしました。
最後に ~卒業制作に向けて~
先ほど発信の大切さについて書きましたが、卒業制作ではクラウドファンディングという形で世の中に発信していくことになります。
クラウドファンディングというといきなりハードルが上がった気がします(私も最初はそう感じていました)が結局は自分が作りたいもの、作ったものについて、それを届けたい人たちに発信してその是非を問うというものですので、今までのサイクルでやってきたことと本質的にはあまり変わらないのかなと考えています。
(noteのスキやTwitterのいいね、QiitaのLGTMがクラファンで言うところの支援にあたるのかなと。)
勿論、支援という行為には金銭のやり取りが含まれますので、スキやいいねのように手軽にできるものではありません。なので、自分の企画・プロダクトの価値がより明確に分かるのかなとは思います。
発信もより明確に届けたい人に明瞭なメッセージを持って行っていく必要があります。
その辺りはこの2か月で学んできたことをフルに活かしながら、最後まで楽しんでやりたいと考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
