
摩擦にも似た優しい熱
「愛はどこにも行かない」
そんなセリフをどこかで聞いた。
フィクションの世界か、友人の言葉だったか。
もしくは、かつての恋人の声だったか。
あるいは、すべてが夢の中だったのかもしれない。
道中、川端に座って風鈴のように足を揺らすと脈打つ生水の冷たさに走る胸の痛みが今も鮮明に懐かしかった。
私は、目を閉じて真っ黒な川に白昼夢を浮かべた。
夢路
アルコール混じりの冷水が喉を伝う。
唇に触れる氷が痛いほどに冷たい。グラスの中の氷塔が小さく崩壊し甲高い音が鳴ると、一枚板の木目が氷塊の中心で大袈裟に揺らいだ。
水滴を纏ったグラスから目線を少し上のほうへ逸らすと、カウンターの隅でひっそりと回旋する換気扇の羽の隙間を、断続的に射し込む光が埃と踊っていた。
換気扇の稼働音に、アルコールに浸した意識を向けてみると、音の粒が空間を満たしているようだった。僕は、目を閉じてしばらく音に身を委ねた。
心地いい静寂を破るようにして、背後の木製のドアがゆっくりと、唸るように開いた。床をなぞる軋む音が、ギィ、ギィと近づく。背に迫る足音は陽気な感情が漏れだしているようだった。
背後で足音が止まる。息遣いと香りが一人歩きして僕の感覚と重なった。
「はい、バーガー、L」
抑揚のない透き通った女の声に、濡れた衣服が背中に張りつく錯覚を起こし、吊り上がる胸に居住まいを正してしまいたくなった。同時に妄想を見透かされたような恥じらいが沈黙へと変わった。
「ここ、おいとくね」
うん、と頷くと、慎重にグラスと密着する紙袋を伏し目で追った。彼女の左手の薬指と小指の爪が紺色に染まっている。海の底のような色をした爪の中で褐色の光が白く泳いでいた。
彼女は隣のカウンターの端のイスに腰をおろすと、一頻り品書きを睨み、「梅酒をロックで」と注文した。
両の指を組んで待つ彼女の、右の親指から中指までの紺色の爪が僕を覗いていた。
僕もまた、片羽を失った蝶のような、非対称な儚さに見とれていた。きっと、この時の僕は、瞬きさえ忘れていただろう。
またひとつ、甲高い音が緊張を突き刺した。
目線を戻すと、グラスの結露が燃え広がるように紙袋に侵食していた。
微睡み
「どうも....」
最低限の一言を済ませると、紙袋に手をのばし枯葉の上を歩くような音を鳴らし封を開けた。中身はなんでもよかった。
淡い灯りに照らされた塊に一口大を頬張り、甘辛い海が舌を包んだ。咀嚼をするたび、遠い記憶に触れるようで、皮膜に包まれていた懐かしさが口の中で広がっているような気がした。口の端に付着した液体に構わず二口目を頬張ると、噛みきれない滑らかな感覚が前歯に伝わる。慣れない不快感に口を離すと、パン生地についた歯型の隙間からポリエチレン袋に包装された1.5cm四方の紙片が顔を覗かせていた。
僕は、ようやく口の端の冷えた液体を拭き取った。
「300μg」
そう言うと彼女は眼前に広がる暗闇の一点をみつめたまま、グラスを口に運んだ。
「こんなやりとりしないで、普通に渡してくれていいのに」
君が勝手に食べ始めたんじゃないか、と言い、呆れた表情でこちらを見つめる彼女は、なにかを察したかのように表情が緩んだ。
「それに私は伝えたよLって、緊張してるの?」
「それで....いくらなの?」
平静を装った僕の質問に彼女は、いらないよと笑う。
「そのかわり、私の前で摂取してよ、それだけでいいよ」
とろけた瞼の狭間で、悪戯めいた黒い瞳がにやりとこちらを見つめる。
目頭に吸い込まれる二重瞼の線は、どこまでも続く飛行機雲みたいで、僕の後ろのずっと遠くを見透かしているような虚しさが突きぬける。
「それは構わないんだけど......」
言っていることが理解してもらえないだとか、軽蔑されるだとか、そんなことばかりが口をついて溢れ出ている最中、僕は僕のことすら受け入れられない狭量な人間なのだろうと知った。次第に、彼女の瞳からは、先ほどまで感じていた虚しい奥行きが失われていく。
「まぁ....それを理由にやらないならいいけど、表現するのに誰の理解も必要なんてしなくていいよ」
彼女は舌を上に反らせると、ふやけた紙を見せた。
「それに、一人遠くへ旅立ってしまいそうな君だけの言葉を、私だけが抱きしめたいだけだよ」
ただのエゴだよ、と言う彼女の瞳には、同情を誘ってしまったのではないかという不安と罪悪感に胸を掠める僕が映っている。優越感に浸っているようにも見えた。
「....変わってるね、あなたも食べてたんだ」
喜色を抑え、今度は透明の包装を一枚一枚、丁寧に剥がして、冷たい液体に包まれた指先のまま紙を舌の上に乗せた。
彼女も追加で、舌の裏に紙を忍ばせた。
「君はどうやってここに彷徨ってきたの?」
彼女はアルコール混じりの冷水を飲み干すと、唇の先を軽く噛んだ。
「ノスタルジックな気持ちに酔って夜の街を歩くなんてよくある話なんだけど....」
舌の上の紙を動かさないように言葉を吐いた。相変わらずつまんない冒頭だね、と言う彼女の表情は笑みを取り戻し、遠くを眺める瞳の中心で喜色が大袈裟に揺らいでいた。
「なんとなく、夜明けから逃げたくなる時があって....」
普段なら見向きすらしない裏路地の隙間が、その一瞬、深夜に目立つ自動販売機のように輝いて見えた。
頭上で揺らめく褐色の光を眺めながら話を続ける。
グラスの氷が、溶けた身体に溺れていた。
湿気の街
蝶になった僕は導かれるようにして、裏路地の暗闇に溶けた。歩くほどに自動車の走行音は希薄になり、息遣いと鼓動音が耳鳴りの内側で反響した。
道すがら、生ごみを詰めた黒い袋に足が接触して、内側で反響する唯一の音を掻き乱した。静止した身体は蛍光灯の途切れる音で正気を取り戻した。心臓が落ち着きを取り戻し、夕焼けのような色に錆びた産廃コンテナを抜けると一層と眼前の景色の色が失われた。僕は僕の形さえ失う自由に浸ったような気がした。
「案外、自由って感覚の一部が麻痺したことを言うのかもしれないね」
突然の、芸術家然とした彼女の言葉に懐かしさが胸を走る。
いつの日か、僕は、君と会っていたような錯覚、いつものデジャヴに過ぎない。
自身の自由を奪うという相反する自由を理解することは容易ではないが、それもまた、人間経験の一部なのだろうと、漠然と思い流した。
エスカレーターを逆走しているような感覚に陥る頃、宙に揺蕩う灯りが網膜に張りついた。目を擦るも灯りは依然として張りついたままで、永遠から抜け出してしまったような咀嚼できない矛盾が心に残ったまま、僕の輪郭は露わになった。わかってはいたけど、やっぱり、僕はどうしようもなく人間の形をしてた。
灯りの下では、斜視の犬が灰色の体毛を揺らしながら、半壊した馬の頭部に腰を振り生殖を行っている。その足元からは、いくつもの花が芽吹いては枯れていた。吸い込まれる奥の暗闇からは、能面を張りつけた半透明の人面魚が灯りに群がるように宙を泳いでいた。
「怖くはなかった?」
怖かったよ。でも新奇な体験ではあったけど、いずれもこの住人のような生き物たちが、僕に反応を示さない未知の美しさに畏敬の念を抱いたよ。
その様子を横目に歩くと再び、暗闇が身体を包んだ。奥には網膜に張りつく灯りが見える。
灯りに向き合うようにして、粗悪な歯並びのように不揃いに並んだ三つの影が仄かに照らされていた。
人の形をした影に否定しても拭いきれない恐怖が頭の中を駆け巡り、気付いた時には背を向ける恐怖に突き動かされ、身体は形而上的な恐怖に突き進まされていた。
鍋の中で沸騰する心臓を力いっぱいに抑えて歩いた。蓋の隙間から泡は吹きこぼれ、炭酸をかけられたような鳥肌が波のように押し寄せる。
....生きているのか?
無理矢理に絞り出して生まれた疑問に一縷の希望を見出して、おそるおそる顔を覗いたが、彼女たちもまた、僕に反応を示さなかった。項垂れる彼女らの虚ろな瞳には、深い緑のグレーチングが映っている。まつ毛には霧を纏ったような微細な水滴が、光の帯を纏い絡みついていた。息を呑んでしまう美しさに、沸騰していた恐怖は粘度を増し、遠い過去のように黒く冷えていた。安堵から、彼女らの目線の先に腰を下ろし、液体のような静寂に身を浸した。
浮世離れした瞳に映る僕の表情は、ひどく虚しかった。
その後も、蛍のような新奇な灯りは次々に人間らしさを増して変容を繰り返した。
半開きになった引き戸から人の温かさのような灯りが漏れ出しているのが見えた。心の隅の寂しさを埋めるように隙間から、煙で白濁した店内を凝視すると、網の上で人間のものであるかのような腕が焼かれていた。肘関節と思われる部位の切断面を網に押しあて、滲み出た血液が網と断面を黒く接着させていた。心臓が沸騰する前に足早にその場を去ると、後方で、こりゃ交換だなという会話が薄らと聞こえてきた。
はぁ、とため息を吐いた。俯き気味で歩いていると、赤と青の粒が両側の壁に不規則に連続した窓ガラスの結露を泳いでいた。歩みを進めるほどに、視界の端で一粒一粒が色味を増して混ざりあった。意図せずして、妖しい灯りの元を辿ることになった。
甘い夢のような人工的な灯りはアスファルトにまで色を投影させた。目線を上に向けると、壁一面に"胔"のネオンサインが打ちつけられた、鉄筋コンクリート造の重厚な建物がそびえ立っていた。
水滴に反射していたのはこれか。ホテルの類いだろうか。
僕にはそれが、ひどく滑稽なものに映った。
入口の透き通ったガラス越しから、奥のエントランスが丸見えだった。
受付のカウンター端に設置されたピアノを、ネイルハンマーを腰にぶら下げた黒い熊の着ぐるみが、深遠な"亡き王女のためのパヴァーヌ"を弾いていた。
この裏路地にはそぐわない異質さに額を流れる汗にすら気付かず、目頭から汗の侵入を許し熱く滲みた。
目を閉じてしまう恐怖に、瞬きを挟み半ば強引に瞼を持ちあげると、ネオンの灯りが万華鏡のように乱反射した。もう、11月になるというのにこの一帯は妙にじめじめしている。圧迫されるような苛立ちを、胸いっぱいに溜めこんで緩く開けた口からゆっくりと細く吐き出した。
極彩色が明滅する手首を呆然と眺めながら、奥深く進むにつれて、ピアノの音とともに灯りは薄くなり、木製の開き戸に突き当たると、幻想が閉じようとしていることを感じさせた。
"瘡" 営業時間 00:00~03:00
一際目立たないどこにでもあるような普遍に満ちたスタンド看板だ。
木製のドアを手前に引くと、歯ぎしりのような異音が閑散とした裏路地に響いた。更に力を加えると、さらさらと落ちる砂が鼓膜を撫でた。
長年使われていなかったのだろうか、それとも、誰かが来るのを待ち続けていたような、そんな感覚に陥る。
店内は暗く静まり返っており、黴の臭いが漂っている。踏みしめる床板の軋む音は、まるで、この空間が僕の不安すらも見透かしているようだった。
空調の効いた冷えた店内は、額の汗をなぞり、より一層、心の動揺を掻き乱した。
カウンター席の端から二つめの席に座ると、歯車が摩擦する音が響き渡り、緞帳があがるようにして、頭上にぶら下がる電球が微かにオレンジ色の光を灯した。
「あの、一人です」
聞かれたわけではなかったが、無言に耐えかねて口をついて出た一言だった。それに対する返事は特になかった。
眼前の暗闇から傷んだメニュー表を持った影が伸びる。すぐに、水が入ったグラスが二つ、そっと置かれた。
一人って言ったのにな....と言葉は喉の奥に、なにか不思議な予感に包まれていた。
「それからは、疑ってしまいそうな不自然な事象に、そうすることが自然だと騙してお酒を飲んでたら、あなたのきまぐれで会話してるって感じ」
「きまぐれ、か、どうして今の状況を疑わなかったの?」
「さぁね、僕は、僕自身のこと、僕が思っている以上にどうでもいいのかもしれない」
そう、どうでもよかった。なんの疑問も持たず、バーガーを口にして、致死量の毒が盛られていたとしても、あぁ終わりか、と思うだけだった。眠剤を過剰摂取して救急搬送された日も不思議と温かかった。いつか見た、緑のホースの中を泳いで全国一周する夢にいけるとすら思った。
「そのわりに君の見ている世界や比喩は、執着する痛みの中でばかり推敲しているよね」
彼女は両の人差し指をピンと立てて左右に揺らした。
「痛みを介して獲得する普通が唯一生きてるって感じるだけだよ」
大半の人が言う普通というのは、数式が存在しない回答のように感じる。砂上の楼閣に過ぎないけれど、その曖昧さに依存してる。普通を獲得するにも、痛みが付き添うことは知っていた。
痛みとは、どうでもいいなりの確かな、小さな現実だった。
「君は死の要因となり得る痛みと、死そのものの不安をそれぞれを抱える二つの自分を俯瞰して、俯瞰するもう一人の自己さえも俯瞰してる」
なるほど、彼女が言うには、裏路地で見たものは、生存することの"不可能性の可能性"が形になったというのだ。
どこまで僕のことを見抜いてるのだろうか。
「君は痛みに慣れすぎているのに、死ぬことは怖いみたい」
乾いた口の中の紙片を飲みこんだ。
「僕に反応を示さなかったのは、その生存の不可能性の可能性、死の恐怖だけが鮮明だったからなんだね」
ということは、つまりあれは....僕自身ってことになるんじゃないのか。
尋ねると、彼女は顎をつまんで考える。
「捉え方によってはそうだけど、君が命の形を与えたと言うほうが適切かな」
表れた、ではなく、与えたという消化不良な表現が引っかかる。この人は僕の思考を試しているのか?
「到底生きてるとは思えないよ」
吐いた言葉は僕自身に返ってきた。
彼女は僕の言葉に、そうだね、とやけに肯定的だった。
「命は魂にしがみつく肉塊に過ぎなくて、いつか限界を迎えて形を手放すという前提でなら、君の見たものは生きてると言えるんじゃないかな」
根拠もないような言葉だけれど、不思議と腑に落ちた。
生の副作用が死であるなら、生きてると定義づけられるのかもしれない。むしろ、不老不死というものがあるとするなら、それは同時に生きてるとすら言えないなと思った。
死というものがもたらす生の価値の喪失、それを考える個人の価値観によって異なるのだろうが。
「現存在である僕に取り巻く死の可能性なら、僕の存在すらも誰かの狂った一部の形だったりするのかな」
乖離的に自身を眺めると、この感性は僕のものではないような窒息に現実が遠のく。だんだんと自分が小さくなっていくのを感じた。
「さぁね....でも、例えば、吐いた言葉はもはや誰のものでもないように思えるよ」
以前にも似たようなことを耳にしたことがあった。 どこで聴いたのか、顔も声も思い出せないけれど、なんとなく、彼女の伝えたいことは理解できた。
吐き出された僕の存在は誰かに強制されるものではない。それは、路地裏の湿気に塗れた住人たちにも言えることだ。
同時に、僕の吐いた言葉ですら、もう僕のものではないのかもしれない。
「君の痛みは欠けているけれど、ふと存在している小動物と変わりないよ」
君は美しいよ、と笑う彼女の言葉に再び、胸のあたりが熱くなる。
渦になる
彼女の言葉が壁を走る。
いや、正確には彼女の言葉だった、ものだ。
変容する景色に、現実が目の端に追いやられていく。底知れぬ苦しみから脱皮し続けるかのように、溶けゆく砂糖の身体を新たに創り出した砂糖で塗り固めていくように、自我を支えていた自我は瞬く間に過去となった。僕は今、細胞分裂の最中にいるのだと悟った。
目まぐるしく入れ替わる赤と橙の砂は互いに干渉することはなく、映る景色にだけ溶けた。真昼に空を見上げたなら夕焼けが見えただろう。きっと、十三時の夕焼けは綺麗に違いない。モンシロチョウすらも赤く染まっているだろうか。
「それと、君の想像力は海みたいで、痛みや憎しみも虚しく泡に還るけれど、弾ける泡すら綺麗だと思えてしまったよ」
窒息にもがいてるようにも見えるし、口から溢れる泡を楽しんでいるようにも見えると彼女は話す。
「詩的だね、詩とは程遠い僕の薄汚れた言葉が詩以上に綺麗であっていいはずがないのに」
初めは興味本位だった。
感情の底に触れようと潜った海に、底なんてなかった。いつか愛したなにかがそこにいると信じていただけに、愛した人達すらを否定してたことに気付くのが遅かった。悲しみの総量など量れるものではなかった。陽の光はもう届かない。
「僕の想像力なんて、狂うほどのエゴを必要とした飢えに過ぎないよ、それに、海は涙を映してくれない」
もう今更なにを吐いたって許されるわけでも、汚れが落ちるわけでもない。狂気性を秘めたアイデンティティを幸福以上に信じてしまった自身の醜さに笑ってしまいたくなった。
「なんか、少しわかっちゃうな」
彼女の手元を飛ぶ蝶は僕の声を背負い、鼓膜に変容した換気扇の隙間へと羽ばたいた。手首の傷跡が、飛び立つ蝶によって広がる水面の波紋のように揺らいでいる。
「私もね、以前そんなことを言う恋人がいたよ」
思い出の皮膜を一枚一枚、丁寧にめくるように。人がまず声から忘れていくように、記憶が崩れていく。
「あれ、ごめん....なんの話してたんだっけ」
僕達は、浜辺に座っている。繰り返し押し寄せる波に攫われる砂を何度も積んだ。月の傾きを時計にしよう。
すべてを忘れてしまっても、僕達はそうしているような気がした。
今は、この幻だけを信じさせてほしい。
摩擦にも似た優しい熱
彼女はおそらく、僕のことを知っているし、僕は君のことを忘れているらしい。
「僕は、君のことさえ忘れてしまうんだね、もう既に忘れてるのかな、ごめんね」
時々、この胸の痛みについて考える。馴染むことのない痛み。あなたとはもう会えないのだと本能的にわかった。
「謝ってばかりだね。またすぐに会えるよ、夢の続きみたいな今もいつかは忘れて夢の中へと還るけど、終わるわけじゃない」
この世界の全ては形を手にして、いずれは消えていくの、誰も意識していないだけで当たり前に起こっていることだよ、と言う。
「この喪失はどうしたらいいの」
「泣いていいんだよ、泣き疲れたら自己防衛を脱いで喪失と向き合ってあげてよ」
いつまでも許しを待っているような、何にも靡くことのなかった草木が彼女の言葉に散っていくような気がした。
「苦しむのは自然な事象に逆らっているから、一度捨ててみたらその感情の変容だと分かるよ」
「その先に、新しい景色はあるのかな。君はどうして僕と話そうなんて思ったの?」
彼女は呆気にとられていた。
「さぁね、私はあす....」
不自然に途切れた言葉の、その瞬間の不穏な感覚、声の響き、体温、空気に漂う香り。
どうして、この記憶から目を背けていたのだろう。
車内ですすり泣く声が頭の中を反響した。
どうして、僕に幸せが許されると勘違いしていたのだろう。堰き止めていた感情が、崩壊したダムのように次々に溢れる。
歪み、移り変わる幻覚に垣間見える現実が思ったよりずっと、悲しかった。
「明日、死ぬには残しすぎた痛みを詩で消化してるだけだよ」
僕は、今日まで忘れていたことすら忘れていたのか。
気がつけば、自然に身体が動いていた。
彼女を、影の中に隠すように唇を重ねた。
重なる影はどちらのものだろうかと頭を過ぎったが、その思考はすぐに消えて、今はただ、唇の冷たい感覚に君を感じていたかった。
固く閉じた瞼を緩めると、彼女は驚きに目を見張り、次第に悲しみで縁どられた笑顔に変わっていくのが見えた。
彼女も優しく瞼を閉じた。慣れたような落ち着いた浅い呼吸を感じる。彼女の手首の傷跡が哀れみを込めて、見下すように僕を見ていた。この快楽は、甘美な蜜となり歯の隙間からじわじわと溢れだしているようだった。
あぁ、こんな瞬間も夢の中へと還るのか。
夢から醒めるようにゆっくりと瞼を開き、乾いた唇を離した。
「今、すごく胸が痛いよ」
大切な人や、愛する人がいつかは死ぬという事実から目を背けてきた。二度とは来ない今という今に目を背けながら生きてきた。その全てはやはり、常に移り変わるという。
生きることは痛いらしい。愛は痛むらしい。
「遅いよ、少し移動しよ」
そう言うと彼女は、後ろのソファーを指さした。
「幻覚がひどくてさ、うまく歩けないよ」
「私もだよ」そう言って彼女は右手の親指から中指の三本を優しく開いて差し伸べた。
僕らは頼りない指を交差させて歩いた。
劇薬に蝕まれていく二人の身体は、灯りに群がる蝶になった。
「フタゴムシみたいだね、そんな映画があったよ」
二人の歩いた後には誰の瞳にも映ることはない水の跡が残っていた。
「それ、ほんとは君と見たかったんだけどな」
不揃いな足音は、永い想像に囚われ、目の前のソファーすら遠いものに感じた。一つ、足を前に踏み出すと、遠い過去の夏休みに囚われる。また一歩、人の優しさを踏みにじったような痛みが襲った。足音に歪む景色の懐かしさは隣を歩く彼女を否定しているようで嫌気がさした。
目まぐるしく入れ替わる幻覚に、心は擦り減り、"助けて"なんて口からこぼれそうになった。彼女なら僕のすべてを肯定してくれるだろうから、尚更そんなことは言えなかった。
永い想像の果てに、ソファーに座ると、沈むクッションに意識だけが沈み続けた。目を閉じて、呼吸を整える。
「ねぇ、また、膝の上で寝ていい?」
僕は目を閉じたまま、緊張する暗闇の中、声を発した。
「最後だよ、あの時の君も体調不良だったね」
彼女は笑う。思えば、そうだった。
身体の力を抜いて彼女の太ももにゆったりと横たわった。彼女は紫色のパーカーの裾を摘んで引き上げ、僕の頭を腹の中で抱きしめた。
影の中に呑まれた僕は、僕以外のなにかになってしまったように思えた。この身体に流れている血液が温かいのか冷たいのかすら分からない。僕という人間が本当に、ここに存在しているのかも分からない。それでも腹の中は、当時の鮮度のまま、感覚的にあたたかいものだと理解できた。
「ねぇ...私の血液はどんな音がするの?」
歪む暗闇の中、小さく、くぐもった声がきこえる。
生ぬるいような腹の中で流れる血液の音は、蝉の声みたいだった。思い出す、むせ返る夏、ビルとビルの隙間で瞬きをした太陽、乾いたプールサイドの隅で息絶えた蝉の儚さが流れている。
「蝉の声、夏の木漏れ日みたいに温かいよ」
呼吸をするほどに湿気を帯びる腹の中は、瞬間に腐る夏の記憶を保存しているように温かい。
「あの時、あなたが言ってくれた、本当は死にたくないんでしょ、って、その通りだった。幸せになることを拒んだのも僕だったよ」
自死を選択することでしか払拭できない痛みがあった。
「その痛みが愛だって知らなかったんでしょ、私も、死期が近付いてそのことに気づいたよ」
過去に触れるのは、夢の続きを歩むような感覚だった。
「あなたのことを忘れても、抜け殻になった痛みだけが今日まで僕を生かし続けてきたんだね」
肉体は同じところにあれど、心が別々にあった夜。
僕たちは今、肉体こそ遠いけれど、心だけは傍にいた。
温度のない手が頭を撫でているような気がした。
「あの時、私たちに足りなかったのは生きてる実感だったね」
湿度のない雨が窓を叩く。
「今日まで痛みを大事に抱えてくれていたから、この瞬間に、私の命は輝いてるんだよ」
だから、もう、手放して幸せになっていいよ。
そう聴こえた。
僕の幸せは......いや、よそう。
口にしてしまおうとしているこの愛は、暴力と同義な気がした。
「覚えているか分からないけど、前に言ってた小説が書けたんだ。やっぱり、初めにあなたに見せたかった」
ジャケットの胸ポケットから携帯を取り出してあなたに手渡した。情けないほど不格好な姿だったろう。
「もう必要ないから、持っていってよ」
こうやって、携帯を渡したのは四年前に書いた遺書以来だった。
「覚えてるよ、最初に見せてほしいと言ったのも私だったから」
彼女の言葉が暗闇の中で二足歩行を始める。歩くほどに枯れる姿に、この空間に流れる時間の全てが愛おしくなった。
「君と出会うまで退屈してたから。大事に読むね。これだけは覚えていて、この愛はどこにも行かないよ。......ずっと愛してる」
「信じるよ、僕も愛してる」
ずっと、そうだった。愛を口にしてしまうのが怖かった。こんな瞬間もいずれは胸を苦しくさせるだけなんじゃないかと、形にしてしまうことさえ僕には憚られた。それでも、そんな理由で取り繕えるほど愛は合理的にできていなかった。
あぁ、やっとだ。伝えることができた。
「僕もすぐそっちにいくから、感想、聴かせてね」
彼女はなにも言わなかった。胎児を抱えるように僕の頭を抱きしめた。
死とは、ゆっくり訪れるものだと思った。
死を目前にしても、酒を囲む余裕さえ残されている。僕には、それだけで十分すぎるほどだった。
この痛みは、いつの間にか捨てられなくなってた。 でも、不思議と嬉しかったんだ。君から唯一貰ったものは目には見えないけど一番近くにいたから。
消えていくあなたの熱の中、まだ伝えたいことがあった。
僕はやっぱり、死にたいほどに、君と生きたかった。
現実以上
美しい夢を見た。
地球にうつ伏せになった僕の心臓は黒く煮詰まり、呼吸と呼応するように赤い海がほとばしり、その身を蝕んだ。焼べ続け、灰が積もる。私は何かを失ってしまったのかもしれない。でも、何が失われたのかわからない。私の心臓はまだ動いているし。自分自身に囚われた心臓は暗闇の中にいるように感じていた。時々、顔が見えない誰かがやってきて薪を焼べる。
それは少しだけ、光に見えたような気がした。
「ねぇ、見て」
頭の隅で人の声がぼんやりと聴こえた。
新芽が芽吹くように顔をあげると、僕だけの海が見えた。身体からこぼれ落ちたように広がる白い砂浜のすぐ傍には、さっきまで遊んでいたような友人が、積み木に変容していた。作りかけと思われる、貝殻の道が夜明けの太陽に照らされている。
ただただ美しいばかりの、この灯りに、後悔はなかった。
......。
......。
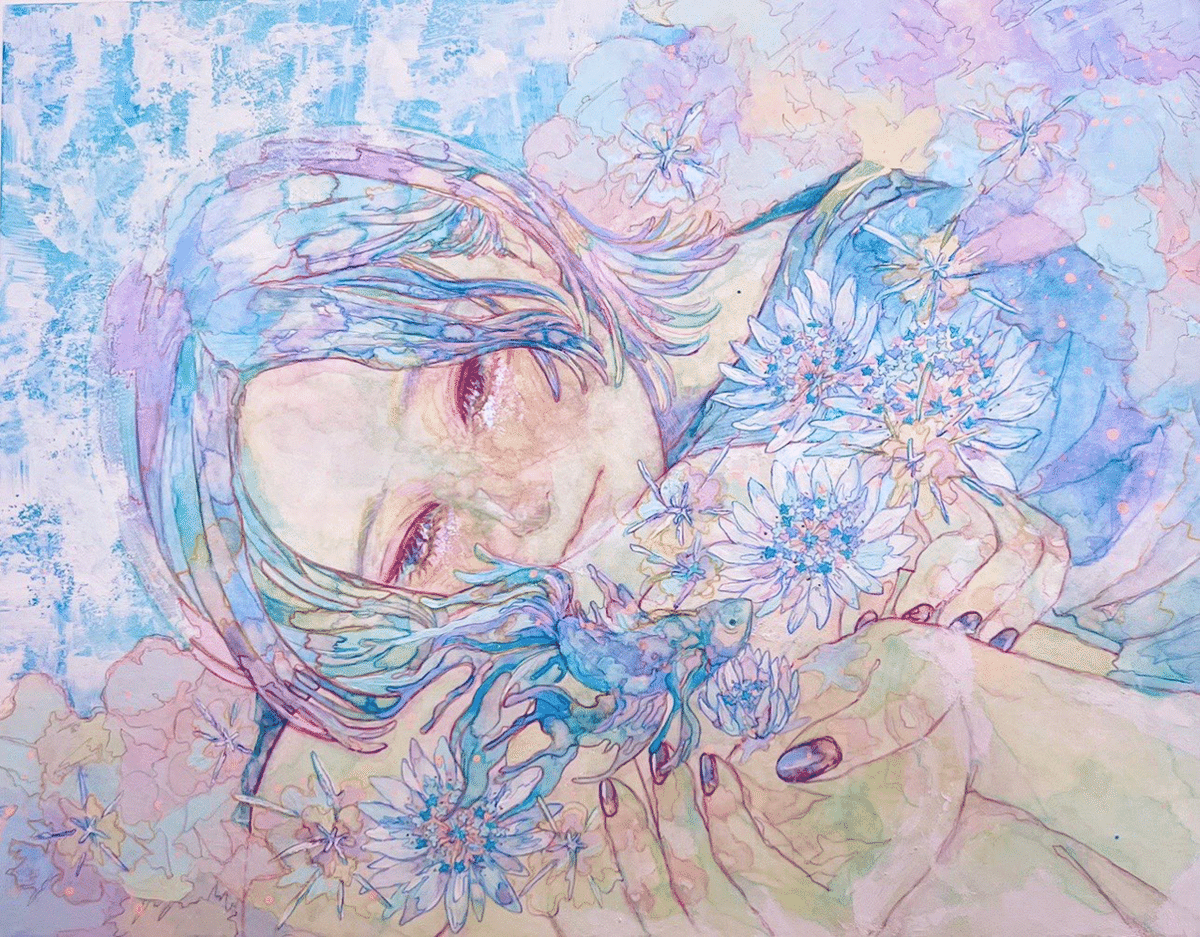
薄膜のような瞼を透かして映る淡い柑橘色の朝日に、瞼を開かずとも、夢から醒めたのだと気付いた。水槽の中を漂う魚になった気分だ。
瞼を開くと、朧気な輪郭を保ちながら、朽ち果てた木製のテーブルに蛍の乾いた死骸が横たわっていた。ひどく重い身体を起こすとほんの少しの吐き気が込み上げた。息を細く吐いて頭が甘く痺れるのを感じると嘔吐感は奥のほうへと引っ込んだ。
夢現のまま眺めた蛍の亡骸に、不思議と自身と重ね合わせてしまってか、崩れないように慎重に親指と人差し指の腹が触れると足がボロボロと崩れた。
僕は後ろめたさに胸が痛んだ。
人気のない空間で人がいないことを確認すると、慎重に胸ポケットへと運んだ。
崩壊していく蛍に同情してしまい、蛍だったカスをベロの先で舐めて外に出た。
すこし苦かった。
ここは、裏路地の突き当たりの廃墟らしい。
どうしてこんなところにいたのか、思い出せない。
間違いなく、僕が歩いてきたであろう道を、全くの他人の気持ちで歩いている。
不思議と新しい人生を歩むような気分だった。
しばらく殺風景な裏路地を歩いていると、建造物の隙間から、横切る人の流れが見えた。僕には、どうにもその熱に馴染めそうにもなく、人通りが少なくなったタイミングで裏路地を出た。
帰路の途中、晴天にぽつんと瞳のような雲が浮いているのが見えた。それは、空を埋め尽くす青い雲の隙間から、白い空が覗いているようだった。
「ちょっと、お聞きしたいんですけど....」
孤独に雲が流れていく。
孤独な雲が二つに分離する。
「どこかで、お会いしましたか」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
