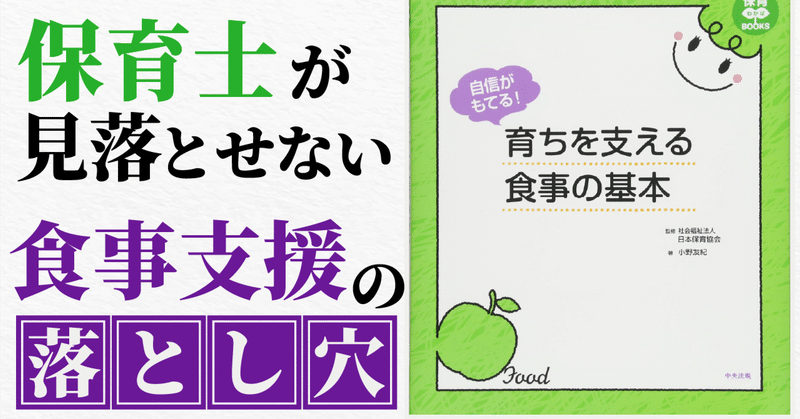
保育士が見落とせない、食事支援の落とし穴
今日は、
新年度、食事の支援について考えている方。
こんな食事提供ってどうなんだろう?と疑問を感じている方。
ずっと自分なりの食事提供をしてきたけど、一度立ち止まって考えてたい方。
保育をもっと深めていきたい方。
そんな皆さんにとって、少しでも参考になればうれしいです
(動画解説はコチラ https://youtu.be/tvUKdhU9hd4 )
①子どもたちの生活に「食事」は欠かせません

みなさん、園生活において、
子どもたちの食事とどのように向き合っていらっしゃいますか。
「先輩のやっていることを真似している」
「自分が子どもの頃に、親からされたことを思い出してやっている」
「園の方針がしっかり定まっている」などなど。
それぞれの方法で、良い保育になっているという所も、もちろんあると思います。
しかし、こどものためにと思ってやっていたことが、実はあまりためになっていなかった。
むしろ逆効果になっていたのでは?なんて事があるかもしれません。
今回はそんな「食事支援の落とし穴」にはまらないために、より良い保育につなげるために、「食事の支援」のポイントについて考えていきたいと思います
食事支援について、ポイントは3つです。
ポイント1食育の目標を知ること
ポイント2子どもの発達に合わせること
ポイント3環境を整えること
ポイント1つめ 食育の目標を知ること

食育という言葉があります。
人が生きていくための「食の能力」。これを育むことが「食育」と言われています。
では、生きていくために、どんな「食に関する力」が必要なんでしょうか。
『保育所における食育に関する指針』で厚生労働省は「食を営む力」だ、と言っています。
「食を営む力」。う~ん、ちょっと、わかりにくいですよね。
一方で「楽しく食べる子ども」に成長していくことを期待している、とも言ってます。
私には、こっちの方がわかりやすいです。
つまり厚労省は、食育を通して「楽しく食べる子ども」に成長してもらいたいと考えている。ということです。
保育の現場では、ひと昔前まで、「最後まで残さず食べること」「好き嫌いなく食べること」と言ったことが大切にされてきた時代もありました。
もちろん残さず食べることも、好き嫌いがないことも、悪いことではありません。
きっと当時の保育者も「子どもの成長のため」と考えて食事提供をしていたことでしょう。
ただ、もしそれが、「食べることの無理強い」になってしまっていたら、
食べることが、その子の「ノルマ」へと変わってしまっていたら、
きっと「給食の時間がいやだ」となるでしょう
「楽しく食べる子ども」とは反対の育ちにつながりかねません。
では、どうすれば「楽しく食べる子ども」になるのか。
どんな「食を営む力」を育てていくべきなのか。
『保育所における食育に関する指針』においては、5つの目標、と言うものが挙げられています。それがこちら。
① お腹がすくリズムのもてる子ども
② 食べたいもの、好きなものが増える子ども
③ 一緒に食べたい人がいる子ども
④ 食事づくり、準備にかかわる子ども
⑤ 食べものを話題にする子ども
こちらは、後ほど、じっくりと解説します。
ポイント2つめ こどもの発達に合わせること

食の力の育ちは、心身の発達と密接な関係があります。
心身の発達を考えずして、よりよい食事の提供は難しいんですね。
ただ、園には0歳から6歳まで、幅広い年齢の子どもがいます。
また個人差も大きいです。
保育者は子ども一人ひとりをよく見て、必要な食事支援の形を考えていく必要があります。
一概にこの年齢ではこうしましょう、と決めることはできません。
ですが、基本知識として子どもの発達を頭に入れておくと食事支援が考えやすくなることも確かです。
大まかな発達の流れでいうと、まずは栄養補給から。
0歳の子どもは消化器官が未熟なため、母乳または人工栄養を摂取します。
そして5,6ヶ月頃からは、離乳食。ゆっくりと幼児食へ近づきます。
次第に、自分で食べられるようになり、好き嫌いが出てきつつ、家族や友達、保育者と共に食べることを楽しむようになります。
幼児期になるとかんたんな調理をし、野菜の栽培に挑戦し、食文化や食の知識を得ていく。
このような流れがあります。
後ほど詳しく見ていきますが、
ポイント1つめの「楽しく食べるこども」を目指して、それぞれの発達に応じた関わり方を考えていきたいです。
ポイント3つめ 環境を整えること

一言に「環境」といっても、食事をするための環境はたくさんあります。
例えば、スプーンやお箸、おわんなどの食具、
体のサイズに合った椅子やテーブル、
適切な食事時間帯の設定、適切な分量、
配膳の位置、安全と衛生の確保、アレルギーの配慮。
それから楽しく食べられるような雰囲気づくり。
みんなが気持ちよく食べられるようマナーを伝えることも、環境を構成する要素になって来ると思います。
保育者としては、どれも気にかけておきたい要素ではあります。
しかし、この環境を構成をするのは、
ポイント1つめ「楽しく食べる子ども」の成長を支えるためです。
たとえば、楽しく食べれる子どもになるために「マナー」を伝えるのはOKですが、「マナー」を伝えるのに必死になりすぎて、毎日の食事がいつもピリピリしてしまうのはNGです。
また、ポイント2の子ども発達を考えた時、
食事の時間を守ることも重要ですが、子どもの心の育ちから見ると、実は時間を守らないことの方が大事になってくる場面もあります。
どんな環境構成が求められるのか、ポイント1、ポイント2を支える環境とは何か。
後ほど解説していきたいと思います。
今回は、栄養バランスや安全な食材選びなど、栄養士さん、調理師さんが担ってくれている部分に関しては割愛しています。実際のところ栄養バランスも、食の安全性も、非常に重要な事です。保育士も理解しておくべきことだ、とおもいます。
ただ、今回は保育者として子ども達と向き合うときに、保育者だからこそできる、保育者だからこそ理解しておきたい。そう言ったポイントを重視していこうと思います
それではよろしくお願いします〜!
②ポイント1食育の目標を知ること

農林水産省によると、人間が生きるために必要な基礎として、頭を育てる「知育」、徳を育てる「徳育」、身体を育てる「体育」に加えて、「食育」があります。
この「食育」って言葉、明治時代の医学者「石塚左玄」がはじめて提唱したと言われています。

彼は「体育も智育も才育も、すべて食育であると認識すべきだ」と言っています。
すべての道は食育に通ずる、といった感じでしょうか。
冒頭でも話した通り、
『保育所における食育に関する指針』では、「楽しく食べる子ども」に成長していくことを目指しています。
では、そんな楽しく食べる子どもとは、どんな子どもなのでしょうか。
5つの目標を順番に見ていきましょう
①「おなかがすくリズムをもてる子ども」
これは、食事の前におなかがすいていることです。
「お腹すいたー」「ごはんなにー?」こういった声が園でもよく聞かれるかもしれません
こういった食のリズムが整っている子どもたちは、就寝や起床の時間など、生活のリズムも整っていることが多いです。
ただ、保育園に入園してすぐの段階では、家庭の生活リズムと保育園の食事の時間が合っていない場合もあります。
そのため、保護者と連携して、子どもたちの空腹のリズムを把握し、調整していくことが大切です。
②「食べたいもの好きなものが増える子ども」
これは、 食べ物の好き嫌いがない子どもを目指す、と思われがちですが、実はそうではありません。
嫌いなものがあってもいい、苦手なものがあってもいいんです。
それでも徐々に好きなものを増やしていけることが大事です。
食べたいものや好きな物を増やすためには、いろいろな料理や食材との出会いが大切です。
普段の保育の中でも食材について話したり、栽培したり、調理をしたり、旬の物や行事食などなど、子ども達と食とのたくさんの出会いを考えていきたいですね。
③「一緒に食べたいひとがいる子ども」
これは、誰とでも仲良く食べるこどもが良い、ということではありません。むしろ、特定の保育者であったり仲の良い友達がいることが重要です。
親しい人と一緒に食べると、食事は楽しく、落ち着いて食べるようになります。
どんな高級フレンチでも、知らない人と一緒に食べると、あまり味わい深くなかった。そんな経験がある方もいらっしゃるかもしれません
逆に、仲の良い友達と一緒に食べると、食事は美味しく感じられ、「食べたい」という意欲も湧きます。
保育者は、子どもたちにとって「一緒に食べたい人」を目指すことが大切です。まずは、保育者自身が子どもたちとの関係性を築いていくことを目指す。
そして、食事の場では、子どもたち同士がコミュニケーションを取りやすいような環境を整えることも大切です。
④食事作り、準備に関わる子ども
クッキングや野菜栽培、収穫体験などは私たちに馴染み深い活動です。
では、なぜこう言った活動が保育では大切にされてきたのでしょうか。
その理由は、五感に働きかけるからです。
料理を食べるだけでは得られないこと。それは、食材の感触を知ること、調理前の食材を見ること、匂いを嗅ぐこと。こういった経験が子どもたちの食の知識、経験となり、食べたい、と言う意欲、さらなる食への関心へとつながっていくのではないでしょうか。
⑤ 食べものを話題にする子ども
これは、料理に使われている食材を話題にしたり、「美味しい」「いいにおい」と自分の言葉で料理の感想を話すことです。
身近な大人が料理に興味を持って、普段から食べ物について話題にしていると、子どもたちも自然と食べ物の話題に慣れてきます。
自分たちが食べているものについて話をすることで、私たちが住んでいる世界や環境の話題や、安全で健康的な食べ物を選ぶ方法についても考えるようになるかもしれません。
以上、この5つの目標が「食を営む力」となり、「楽しく食べる子ども」への成長を支えます。
③ポイント2子どもの発達に合わせる

ここでは年齢ごとに、食に関連する子どもの発達を見ていこうと思います。
まずは0歳
0歳の赤ちゃんは消化器官が未熟なため、母乳や人工栄養がとても重要です。
母乳には多くの利点があり、赤ちゃんの体を強くし、免疫力を高めると言われています。
ただし、完全母乳育児の子どもの中には、入園後に人工乳を飲むことに慣れない子もいます。保育者は無理にあげるのではなく、スプーンやコップを使ったり、周りの子が飲んでいるのを見せたりするなど、様々な方法を試してみることが大切です。保護者と連携をとりながら「どうすれば飲んでくれますかね〜」と一緒に考えてみると良いでしょう。
5〜6ヶ月頃からは、母乳や人工乳だけでは栄養が不足するため、柔らかくつぶしたかゆや野菜、果物を使った離乳食が始まります。この時期に乳汁以外の食べ物を与えると、消化酵素が活性化されます。
しかし、まだまだ消化吸収機能が未成熟なのでナマ物は避け、加熱調理したものを与えます。便に未消化の食材が混じることもありますが、機嫌が良く、便の硬さもいつも通りであれば心配ありません。1日1回1さじから。焦らず、子どもの機嫌が良い時に徐々に始めていきましょう。
離乳食開始後、月齢を重ねるにつれ、唇は上下から左右、そして左右非対称へと動かせる様になり、舌は前後から上下、そして左右へと動かせる様になります。このような口の機能の発達に合わせ、ゆっくりと食材を固く、また、さまざまな食品を用意していくことになります。
7-8ヶ月ごろには、舌が上下に動かせる様になってきます。料理は舌で潰せる豆腐ぐらいの硬さで用意。また、いろんな味や舌触りが経験できる様にします。1日2回食で食事のリズムをつけ始めます。早い子は5,6ヶ月からスプーンを使い始める子もいますが、手の発達にも個人差が大きいので、この時期だから、と無理に教え込む必要はありません。
手づかみで食べても、食べようとする意欲を見せてくれる方が素敵です。また手づかみ食べの時は、「汚れるから」という理由で保育者が手づかみを止めたり、手伝いをしすぎないようにしましょう。子どもの自分で食べようとする意欲が削がれてしまいます。
9-11ヶ月ごろは、歯茎が動かせる様になります。歯茎で潰せるバナナの様な硬さで、一口サイズの料理を用意します。1日3回食にしていきます。
牛乳や小麦粉などのアレルギーを引き起こしやすい食品に注意しながら、肉や魚などで不足しがちな鉄分を補給します。この頃、指先が器用になるので、手づかみ食べが上手になります。
1歳〜1歳6ヶ月ごろには、3回の食事とおやつから必要な栄養素を取れる様になってきます。歯茎で噛める硬さ、大人が指で潰せる硬さの料理を用意します。そして、離乳食は1歳6ヶ月でおおむね完了し幼児食へと移行していきます。
ただし、これは目安なので幼児食に移行しても、手や口の発達が伴わない場合は、前段階の離乳食に戻すことも大切です。
2歳〜4歳頃には、好き嫌いが出てくることが多くなります。この時、保育者としては、やっぱりなんでも食べてほしいな、と願うのですが、無理に食べさせるのは逆効果です。
そもそも子どもには馴染みのない食べ物を警戒する「食物新奇性恐怖」があります。これは「安全性のわからない食べ物は警戒すべきだ」という、進化上の「生き残り戦術」です。
また、乳幼児期には、耳の構造が未発達であることや、耳管が短いことから、中耳炎になりやすいです。
中耳炎になったら、味覚情報を舌から脳に伝える「神経」がダメージを受けることもあります
すると、特定の食べ物キャベツやブロッコリーなどが人並み以上に苦く感じるようになります
このような子ども達に食事の無理強いを行うと、そもそもの食事に対する嫌悪感、恐怖感を抱かせてしまいかねません。
大切なのは「楽しく食べる子ども」に育ってもらうため、食卓の楽しい雰囲気は壊さないようにすること。そして「食べたいもの、好きなものが増える子ども」に育ってもらうため、苦手なものでも「一口だけ」は食べる。食べ始める前に挑戦、食べ終わる直前に挑戦、と言ったふうに子どもにとって挑戦しやすいタイミングをはかります。
どうしても嫌がる時は無理強いをせず、少しでも食べれた時は一緒になって喜ぶ。こうやって少しずつ、ゆっくりと好きなものが増やしていければいいですね。
5歳〜6歳頃には、好き嫌いがある程度落ち着いてくることが多いため、新しい食べ物にも興味を持つようになります。
新しい食べ物に興味を持ち、栄養の大切さを理解するためには、自分たちで料理したり、野菜を栽培したりすることが有効です。
また保育者が食の話題を提供したり、食をテーマに保育で探求活動をしてみたりすることもよいのではないでしょうか。
以上が、食に関する子どもの発達でした。
最後に、食育の目標をを目指し、子ども達の食に関する発達を支えるための「環境」についてみていきたいと思います
④ポイント3環境を整えること

まずは場所作りです。
離乳食期は、子どもへの刺激が食欲や集中力を左右します。
せっかくの食事の時に、視線の先に他の子どもが遊んでいたり、おもちゃや絵が見えたりすると、それに気を取られ食事に集中できません。視線の先についたてをおいたり、にぎやかに遊んでいる子ども達から距離をおくなど、集中して食べることができる環境を作ります。
一方幼児食期になると、集中して食べるだけでなく、保育者や友達と関わることで食事が楽しく美味しく感じられる時期になります。清潔で落ち着いた環境はもちろんのこと、テーブルにクロスをかけたり、花を飾ったり、楽しい装飾が効果的です。また、たまにはテラスに出たり、園庭にシートを敷いたりして、食べる場所を変えることも、食事を楽しむことにつながります。
次に保育者が座る位置です。
離乳食期、保育者の左手側に子どもが座るようにします。
これは右利きの保育者の場合、スプーンを口に運びやすいポジションです。
また、1テーブルで複数人の対応をする場合、保育者の左手側に援助が多く必要な子、右手側に援助がほとんど必要ない子を配置すると、同じく保育者の聞き手による援助がスムーズになります。
もちろん保育者が左利きの場合は、座る位置は反転します。
離乳食期の援助の際、まだ子どもが自分で食べられない時は、介助用スプーンを使います。ここで大事なのは「自分で食べている」と感じられる様にすることです。
まずはスプーンに適量をのせ、スプーンを子どもの下唇に当てます。そのまま、子どもが自分から食べ物を取り込もうとするのを待ちます。パクリ、と食べ物を取り込み、唇が閉じるのと同時に、スプーンをゆっくり水平に引き抜きます。スプーンを口の奥に入れ込んだり、スプーンを引き抜く際に上顎に擦り付けたりしない様にしましょう。誤飲してしまったり、喉や顎を傷つけてしまったりすることがあります。
そして「はい、あーん。ぱくっ。もぐもぐ、美味しいねぇ」と声をかけたり、子どもの目をしっかりと見てたべさせることで、安心して食べられる様になります。
介助用のスプーンは、横幅が口の2/3に収まるものを用意します。口の大きさは一人一人違うので、ちょっと「パクッ」とするのが難しそうだな、と感じたら、横幅があっているかチェックしてみましょう。また、縦幅も長すぎると喉を傷つけてしまいます。ボウルの部分が全部口に入るので、ボウル部分が子どもの喉まで届かないものを選びましょう。
また、ボウル部分は深さがなく平坦な方が良いです。深いスプーンだと山盛りになりやすいので、子どもの口の中が食べ物でいっぱいになってしまいます。
そうなると子どもが口の中で食べ物をまとめる、送る、と言った摂食の基礎練習ができなくなります。
手づかみ用のお皿を用意するなら、皿の内側が少し湾曲してると使いやすいです
次は姿勢を支える椅子について。
子どもが食事中に落ち着かない時は「集中力」や「意欲」の問題と考えられがちですが、実は、座り方が原因になっていることもあります。
離乳食期の子どもは、足が床についていない椅子を使うと、姿勢が保てず不安定になります。また骨盤が傾いた姿勢で座っていると、猫背になったり、常に体が動いたりして、落ち着きがなくなります。腰を支える様に抱っこしながら食事の介助をしたり、足が床にしっかりと着く様に、マットやブロックで高さ調整すると良いでしょう。
幼児期には子どもに合うサイズのイスが用意できると一番です。
座面が高すぎると足がつかず不安定な上、膝裏が座面に圧迫されます。
逆に低すぎると、体重がお尻に集中し痛くなりやすいです。
座面の高さは座った時に踵が床につき、膝裏に指が一本入るぐらいがちょうどいいと言われています。
イスは、あらかじめいくつかのサイズのイスを用意します。そして、色のシール等で目印をつけて自分に合ったサイズのイスを選びやすくしておくと良いでしょう。
また椅子をいくつも用意できない場合は、マットやブロックで微調整することも可能です。背もたれによりかかりすぎて、姿勢が崩れているなら、マットを背もたれにはさみ、滑り止めシートを座面に置いてみることで、姿勢を崩さず自分で座れるよう促せます。
最後に食事の時間について
食事のリズムをつけることは生活のリズムをつけることです。乳児の場合、月齢が低い子や、給食中に寝てしまう子などを先に食べさせるところもあるでしょう。個人差はあっても、大事なのは毎日だいたい同じ時間帯に給食を取ることだ、とされています。そして段々とクラスでまとまって同じ時間に食べる様になり、クラス全体としての食事のリズムが作られていきます。
また「食べきる時間」を設定している園もあるのではないでしょうか。
おしゃべりに夢中になりすぎたり、うまくペースをつかめず、食事の時間がどうしても長くなってしまう子どもたちもいます。
そんな時、「長い針が12までに食べ終わろうね」といったふうに声をかけ、子ども達に見通しを持って食べる様に伝えます。
この食事を食べ切る時間ですが、小学校の給食のことを考えると、準備から食べ終わるまでおおよそ30分程度が良いとされています。
とここまで話してきたものの「食事の時間をしっかり守る」ということが常に正解というわけでもありません。
柴田愛子さんの「りんごの木保育クラブ」での事例を紹介します。

入園当初の2歳児が、持ってきたお弁当を部屋の隅や廊下で開けています。一人が食べ始めると、また一人二人とあちこちに食べる子が出てきます。「お弁当はまだだよ」「たべるなら机でね」と色々言いたくなるのを我慢して、「まだ9時半なのに、どうしてたべているのかしら?」と柴田さんは考えます。
まだお母さんと離れることに慣れていない子にとって、お母さんの手作りのお弁当を開けると心が落ち着くからじゃないか。
それに、入園したてでまだ何をして遊んでいいかわからない、手持ち無沙汰なんだろう。
きっとそんな不安な心をお弁当が支えてくれてるんだな。もちろん、単純にお腹が空いたってこともあるだろうけど。
そんな気持ちがわかってしまうと「だめ」とは言えなくなってしまう、と柴田さんは言います。もちろん葛藤はある。どこまで自由にするの?しつけは?と考える。でも、まあいいか。と力を抜いて見守ることにする。
いずれおなかがすいたことも忘れるほど遊びに夢中になる時期が来る。友達ができると「一緒に食べたい」と言い出すだろう。結局1年もすればみんなでテーブルを囲んで食べる様になる。
柴田さんは言います。
「おとなは健康のため、成長のため、と考えて食を充実させようとします。食欲はさておき食べる時間を優先します。しかし、子どもにとって食べることは気持ちや心模様と繋がっている」
今、目の前にいる子どもの気持ちに寄り添って、柔軟な関わり方ができること。
今の心を満たすことが、のちの生活の充実につながると、長い目で見ること。
食事の支援には正解がありません
それは、その子、その子にとって本当に良い支援とは何か。
こうすることが良いと言われているけど、この子にとってはどうか。
こんな問いに対する答えを、保育者が常に探し続けなければならないから、かもしれません。
今日は以上になります。どうもありがとうございました!
⑤参考文献、引用
日本保育協会監修、小野友紀著『育ちを支える食事の基本』2018
柴田愛子著『とことんあそんんででっかく育て』2019
農林水産省:全国食育推進ネットワーク「みんなの食育」「食育」とは
近畿農政局:食の安全と消費者の信頼確保 、食育「食育の歴史」
福井県ブランド課:福井の幕末明治歴史秘話47
東京都感染症センター:牛海綿状脳症(狂牛病)(第17巻、3号)
食育基本法:平成十七年法律第六十三号
厚生労働省:楽しく食べる子どもに~保育所における食育に関する指針~
ゾーイ・シュランガー「Newsweek〜未熟な腸を指導、驚きの母乳効果〜」2017
メリンダ・モイヤー「Newsweek〜偏食しない子はこうして作る〜」2017
金子芳洋著『食べる機能の障害』
田角勝著『子どもの摂食・嚥下リハビリテーション』
汐見稔幸責任編集『エデュカーレ2019年5月号』人間工学から考える園の椅子とテーブル
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
