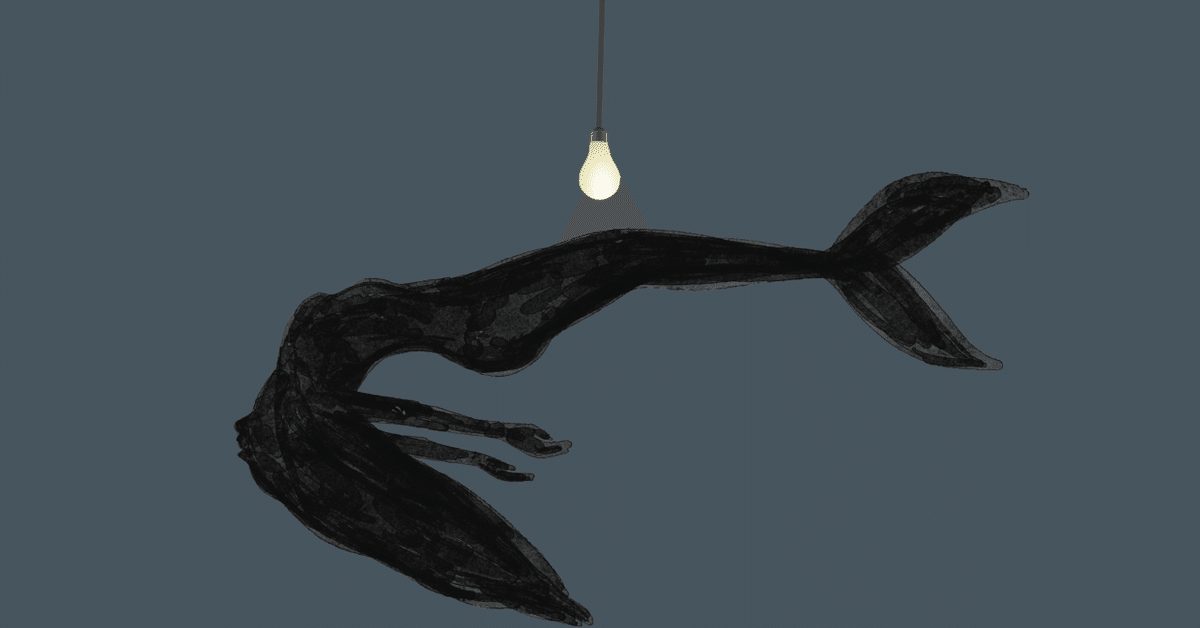
忘睡
熱がどこから生まれて伝わってくるのかわからなかった。
たぶん太陽が移動したせいだろう。
頭が故障したのかもしれない。
目を覚ましたときにはいつもよりはっきりと明るかった。
背中の下に敷き詰められている砂利も、正面から直角に降り注ぐ透明な粒子の入り混じった空気の雨も、熱を奪って私を冷たい人間に変えていきそうなものなのに、身体はどこかにある熱そのものと、さらなる熱さに対する切望のためにあえいでいた。
まるで身体が死をもとめているかのようだった。
やがて私の前に現れて、忘却の泉に浸した冷たい手で、この頬を冷やしてくれるはずの誰かのことを思いだそうとする。
もう一度その人に会えるという甘い期待は、すぐに苦々しい幻滅にかき消される。
あれは誰だったのだろう。
いまとなっては、その氷のように純然な肌の輝きも、怒りに似た熱さに融解して、永遠に取り戻すことが不可能になってしまうのではないかと私を怯えさせる。
それが誰であるかも知らないままに、先走った不安が意識の繊維を一本いっぽん脱色して細らせ、私は絡まった記憶の糸をほぐしてたぐりよせようとすることさえ放棄して、甘い諦めの温かみを下腹部に拡げていく失禁の最中に似た快楽に身を浸しつづける。
このまま眠ってしまいたい。
目を閉じたままいると、身体は暗く口を開けた深淵にどこまでも引き込まれていき、落下することによってかえって重力から自由になったかのようにしだいに軽くなっていくのを感じる。
重さはグレーターで粉末状に削られてサラダに降りそそぐ白いチーズのように、肉体を離れて暗闇のなかへ散りながらゆっくり下降していき、私は自分の重さがうしなわれていくことを肯定的にとらえて満足を覚える。
こうして私の身に訪れた充足をだれも否定することはできない。
私が味わっているのは、いっこうに思いだせず、透明なままで、その存在の落とす影すら踏めないでいることの焦慮にみちた不足状態も含めての充足なのだ。
もう一度日陰に入れば思い出せるだろうか?
あるいはこの水のない水槽のような、見えないガラスに囲まれた空間じたいから抜け出せば? ただ、それは会えるのとはちがう。
思い出だけでは、終わりのその先へ進むのに、なんの役にも立たない。
熱は太陽というより下のほうからくるのではないか。
地中の深いところに埋まっている太古の生物の骨が、何かの拍子に動きだそうとしているという可能性。
その運動が放つエネルギーがいま、分厚い土の層を通して私の背中に伝わってくるのだ。
平べったくて大きな板のような骨の周りに、たくましく伸びた強そうな骨がいくつか並んでいて、それからもっと小さく繊細な骨たちが賢いカーブを描いていくつも散らばっている。
かつて地上を跋扈した凶暴な肉食獣を、地層の牢獄へ追いやった滅びの呪文の効力が、長大な年月を経て失われようとしているのかもしれない。
この空想は私を少し楽しい気分にさせた。
だけど考えてみれば、本当の牢獄――それは時間の牢獄にほかならないだろう――の内側に閉じ込められているのは私たちのほうで、死滅することはその外側へ解放されることではないのだろうか。
そして実際に古生物が動きだす可能性はゼロだった。
まだそれが自分のものであると馴染まない体温を抱えながら半身を起こし、時間を捜し求める。
それはわれわれを閉じ込めると同時に、立ち上がって歩きだすために手で支えたり、ときどき立ち止まって身体をもたせかけ、休息したりするための壁にもなる。
壁にもたれて深く息をしてみたい。
地面についた肘の先が重たくて、不安定になった重心を予測値の内側に引き戻すために手首をひねると、そこに見慣れない腕時計が巨大な蛭のように絡みついていた。
円形のガラスを覗きこむと、私が思っていたのとは違ってそこには時間など存在せず、ただ時刻と呼ばれる図形が、数字の並んでいる円盤の上に昆虫の標本のようにピンで留められて死んでいるだけだった。
左の手首をめがけて息を吹きかければ、時刻は乾いた翅や脚のようにぱらぱらと形を崩して、どこかへ散っていってしまいそうだった。
見憶えのある時刻。
あれは、異国語で「碧い花」を意味する名前の海に浮かぶ島国を目指した旅行でのことだった。
何十種類もの花飾りに彩られた旅程と、大理石の柱が支える冷涼なホテル、青みがかった氷のようなタイル……絢爛なバスルーム。
むせ返るほど、次から次へと花が降ってくる。
花、花、花……。
ベゴニアとハイビスカスの花弁が敷きつめられた泡の中で、恋人と海辺の生き物ごっこをしているうちに、アシカとオットセイのちがいについて口論になった。
恋人は、アシカもオットセイもほとんど同じものだと主張した。
私はアシカとオットセイはまったくの別物で、鳴き声だって子育ての仕方だって父母の役割分担だって、こちらが見る目をもって見れば実態は似て非なるものであるのだと反論した。
濡れた身体にバスタオルをひっかけて、疲れ果てたカモメのようにふらふらと浴室から出ていくと、部屋の時計の針は午後の十二時十七分を指していた。
真昼の入浴タイムだったわけだ。
朝遅くまで寝ていたのかもしれないし、すでに午前の浜辺で海水浴を楽しんできたあとだったのかもしれない。
個性の乏しい絵葉書の並ぶ回転式のラックから、そのときの気分で無作為に一枚を選びとるのに似た、代り映えのしない毎日だったから、どんな日でもやっていることは大同小異だった。
浴槽の縁に手をかけて、自分の身体を水中から引き揚げようとするときに感じる名残惜しさと、のぼせてもうこれ以上は耐えられない熱さからの解放という二重の心情が、いつも誰かのもとから立ち去るときの私の気分と重なる。
頭はぼんやりとしたまま、一度は振り返ってみるものの、そこにいるのはもはや見知らぬ他人でしかなく、姿がぼやけ、遠くにかすんでしまうほどの距離まで離れてから、その場に置き去りにしたものが、ほかならぬ自分自身の抜け殻だったということに気づくのだ。
ときには、そのことを理解するのに何年もの年月を費やさねばならない。
いま私は風呂の代わりに乾いた砂のなかに浸かっている。
砂のように崩れていく時間のなかに。
地中深くからやってくるように思われるが、結局はどこからなのか判然としないこの熱の発生源は、じつのところずいぶん前から私にとり憑いているもので、いまになって急に顔を出したというような類のものではないのではないか。
私が酸素を採りいれるたび、それは燃焼速度を増して、雨すらも鎮めることができない。
いつか燃え尽きて冷めてしまうとき、そこに私はいるのだろうか。
もちろん、私どころか誰も存在しないだろう。
カメラがパンして私の死体を映しだす。
正確には死体ではなく、まるで死んだみたいに、あるいは生きていない、何か人形じみた物体として横たわっているだけの身体なのだけど。
視点は足先から、衣服越しに、舐めるように、というよりはむしろ風景写真に求められる適正な距離を保って、ゆっくりと平行移動していき、私の曲げられた左肘を折り返し地点にして、視野の左上方へある手首へと斜めに上っていく。
軍手をはめた腕の先端で停止すると、そこに巻きつけられた革のベルトの腕時計にズームし、時刻に注意が引きつけられる。
短針が十二と一の間。長針は三と四の間。
こんなワンシーンにさえ時刻があるということに驚かされる。
忘れられた合言葉を思い出させ、再び強調するかのようにカメラは時刻を刻印するのだ。
十二時十七分やその他のさまざまな個別の時刻が大事なのではなく、時刻(という制度)そのものが大事なのであり、たとえ時計自体が故障か電池切れで止まっていたとしても問題はない。
数字と数字の間で、針が形づくっている何らかの図形。そこに定着してしまう前までは、一匹の蝶だったかもしれないもの。
悪党に襲われたわけでも、落雷に撃たれたわけでもなく、私はいつの間にかこの荒野に横たわっていて、この場面で私に与えられた唯一の指示――〈半身を起こして腕時計を確かめる〉――にしたがい演技をするのだが、主体的に時計を確かめるのは結局のところ、私ではなくてカメラのほうなのだ。
私の胸より上の部分はいまだ映像の外側にいて、カメラが首を振るのを待っていた。
レンズに頭部がとらえられさえすれば、自分が何者であるのかはっきりするとでもいうような、熱に浮かされた期待とともに。
こうして映画の出演者になったという妄想も、私の気を一瞬のうち紛らわせた。
立ち入り禁止区域の向こうとこちら側を往復する密猟者ないしは案内人。
だけど、自分ではルイス・キャロルの物語に登場する白ウサギにでもなって、少女をそれとなくおびき寄せる役のほうが似合っている気がする。
穴への落下。それですべては終わる。
突然、どこからともなく聞こえてくる「止まれ、動くな!」という素っ頓狂な声に制止され、私は途方に暮れてしまう。
それまで進んでいたのが、どの方角だったのか、日の差すことのない銀幕の内側で、見極めることの不可能な、似たり寄ったりの灰色の遠景に囲まれて怯えている。
銀幕というよりは、透明なガラスの内側で。
忘れ去られた眠りそのものの内側で。
それにしても、どうしてこの場所を、内側と感じるのかはさだかでないにせよ。
誰かがあの図形を毀損しようとして、この「内側」へ足を踏み入れる。
あらゆる時間がばらばらに散らばって存在しているのだということを、いったいどうやって信じてもらえばいいのだろう。
さまざまな図形を描くところを想像してみる。
完全な円でもきれな楕円でもない歪んだ丸、正方形とか長方形や平行四辺形になれない四角形、二等辺三角形や正三角形とはいかないいびつな三角形。
それとも、ただの線。
点。
ここから遠くへ向かって移動しつづける点。
光の照射角によって、刻々と変形する影を落とす線分たちのダンス。
創造と破壊の繰り返し。
私が描いた図形を、次から次へと現れる闖入者どもが蹂躙し、私はその行為に対して異議を唱えようと口をひらくのだが、金縛りにあったかのように身体はいうことをきかない。
無声の抗議に耳を傾ける者などひとりもおらず、暗い影に満たされて身体の半分がこんどは凍えるように冷えていく。
左半身が地熱を吸収して火照っているのに対し、右半身は特大の平べったい包丁の背で撫でられたみたいに震えが止まらない。
私は眠り方を忘れた。
時間の測り方を、寝そべり方を忘れた。
しかし、自分が誰であるかを忘れきったわけではない。
いやむしろ、自分が誰であるかということについて、非常に明晰ですらあるかもしれない。
どこにもいない彼ら彼女らと、私を取り巻いてあらゆる場面においても私を一人きりにさせてくれない彼ら彼女らとのはざまで、私は孤独を奪われた一人の幽霊なのだ。
現在のところ、それがもっともらしい答えだ。
太陽が次に移動する前に、私は不動から不動へと変化を遂げるだろう。
誰かが見つける。
誰にも眠られたことのない眠りの抜け殻を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
