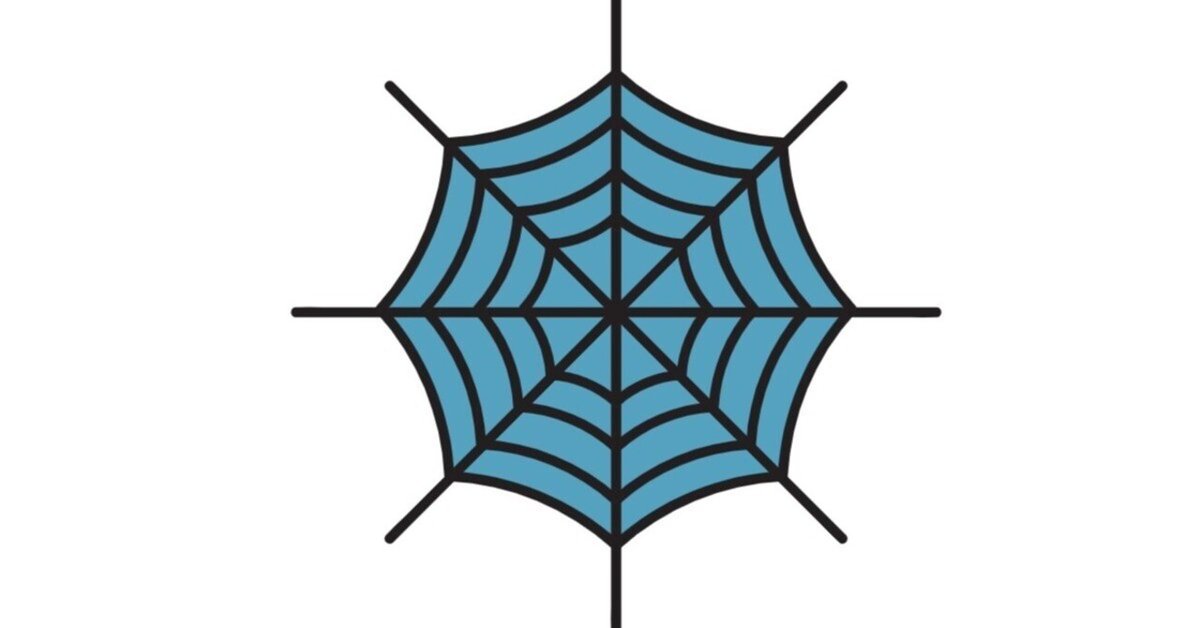
【連載小説】蜘蛛の手を掴む<第六話>
音丸慎吾の尻ぬぐい
音丸と二人、菜緒は三角ラトイと泉岳イミズの行方を捜した。当てはないが、音丸を連れてきたのは、呪現言語師を探り当てる力に秀でているからだ。特別潜入捜査員、通称・トクセンと呼ばれる部署から音丸は引き抜かれてきた。もともと、音丸はトクセンの実谷重綱が見つけてきた逸材。呪現言語師として、スカウトしてきたが、才能は開花せず。代わりに、呪現言語師に身体が反応する。目の奥にビジョンが見えると本人は言っているが、眉唾ものだ、と菜緒は疑い深い。
とにかく、音丸がいればソナーとしての役割は果たす。あとは、力でねじ伏せればいい、はずだが、いかんせん菜緒は不意打ちの呪現言語師にはこっぴどくやられた経験がある。耳栓でなんとかなると、千堂寺がよく言うが全く役には立たない。
「ねぇ、音丸、三角ラトイってどんな風貌?特徴は?」
「えっと、背は170・細身・髪の毛は前髪ぱっつんで腰まで。でも切ってる可能性ありますね。目は切れ長、鼻は高め、口角下がり気味、左頬骨あたりに豆粒大の痣、耳は見えませんでした」
音丸はスマホを見ながら答えた。
「便利ね、そのスマホなんでも書いてるの?」
菜緒の運転は荒い、助手席の音丸は右に左に揺れる。スマホ画面を見ていると、酔いそうだった。
「あと、泉岳イミズは、背が150程。髪の毛はショート、細身、目はくりくりと大きめ。左足が負傷しているのか、元からか、動きが悪かったです。両耳潰れていました、柔道かレスリングでもしてたんでしょうか」
「ホント、便利、そのスマホ。私も欲しいわ。で、三角ラトイはどこに?」
「呪現言語師の居場所しかわかりませんよ、三角ラトイかどうかは、僕もわかりませんし」
音丸が自身の能力に限りがあることを菜緒に説明する。この説明のくだりはもう何回目だろうかと、音丸は数えていた。おそらく十二回目だった。
「嵯京湾・海浜倉庫五十二区画の管理室ですね。位置ナビに繋ぎます」
「これ、三角ラトイである可能性は?」
「70%ぐらいですかね。これほどの強さはそうそういませんし」
菜緒はアクセルを押し込んだ。特別捜査室専用の車は、思いのほか小ぶりだ。軽自動車に間違われることも多い。そのため、菜緒みたいなイキった運転をしていると、無用に絡まれることは多い。
まただ、音丸は思った。前方の車が煽られていると感じ、進路を塞ぐ。煽られている、あながち勘違いでもない、菜緒はもうイライラしていた。
ハザードを付け、進路を明らかに塞ぐ前方のスポーツカー。車高が異常に低い。スピードを落とし、車道の真ん中で車を止めた。菜緒はそのまま体当たりでもして、前に進もうとしたが音丸が制止した。
「おいおい、ナンかイキった走りしてんじゃねーか」
ジャージ姿の男が運転席から降りてきた。金属バットをズリズリとアスファルトに擦り付けて菜緒たちの車に向かってくる。
「シンちゃん、やっちゃいなよ!」
助手席から金髪の若い女が降りてきた。すらっと長い脚に、ショートパンツ。上はキャミソールを重ね着したみたいな、だらしない姿だった。
「菜緒さんは、そのままで。僕が何とかします。穏便にね」
音丸は助手席から降りた。何事も穏やかに、処理する、千堂寺のバディになってからは時にそうだった。トクセンの実谷と組んでいた時も同じく。きっと菜緒も同じだろうと思っていたが、その通りで逆にホッとした。尻ぬぐい、帳尻合わせ、尻をもつ、とにかく「尻」周りは自分の仕事だと、音丸は自負があった。先輩方に思いっきり破天荒に仕事をしていただくためには、自分が中和させればと考えていたからだ。
―――「千堂寺さん、音丸ってどんな子なんですか?」
菜緒は以前、千堂寺に音丸の仕事っぷりについて飲みながら訊いていた。中野の千堂寺いきつけの小料理屋だった。手酌でビールをつぐ千堂寺に、菜緒は食い入るように見つめる。
「あんまり、見るなよ。恥ずかしいだろ、こちとら男やもめだ」
「そうじゃなくて、音丸どうなんです?」
菜緒はしつこく千堂寺に食い下がる。小鉢のほうれん草はすっかり乾いている。
「まぁ、音丸は、実谷さんが拾ってきたんだけどさ、もともとは呪現言語師の予定だったんだけど。実のところ、アイツ」
千堂寺は、言葉を選んでいた。本当のことを菜緒に言うべきか、言うとしてもこの場所でいいのかと。
「もったいぶらないでくださいよ。ここ、いきつけの店でしょ。女将さんも信用できる店ってことでしょ?ねぇ、女将さん」
小料理屋の店名は由紀子、と言った。店主の名を冠した。由紀子は小さく会釈し、カウンター越しの菜緒たちから少し離れ、煮物に火をかけ始めた。店が十坪程度、離れようにも会話は聞こえてしまう。
千堂寺は、手酌でグラスにビールを注いだ。ビール瓶の周りにびっしりと付いた水滴が、千堂寺の手の平に吸い取られていく。その手を千堂寺は、おしぼりで拭き取る。
「音丸はなぁ、制御が効かない。呪現言語師としての才能はある。だが、自分でその力をコントロールして初めて能力ってものは、安全に使えるってことだろ。止められない火炎放射器って、使いどころ難しいだろ。ガス欠まで待たなきゃならない」
千堂寺の顔が険しい。
「だから、呪現言語師の適性がないということで、サポートに回らせてるんですね」
「あぁ、でもな、呪現言語師の力自体は、実谷さんと俺で、封印している。ちょっとタネは言えないが、脳内にリミッターかけている感じだ」
菜緒は日本酒をグイッと飲み干した。
「じゃあ、それって【解除のトリガー】を設定しているってことですよね」
「あぁ、極秘だがな」
「呪現言語師が、呪現言語使えなかったら、役に立てるんですかね?」
菜緒は音丸がそのまま組織に飼われている核心に迫った。
「あいつね、もしかしたら菜緒ちゃんより強いよ。一応、実谷さんと俺で、力も制御するようにしておいたけど。これは、難しいんだよな。キレちゃうと、どうにもなんなくて」
千堂寺はメニューを見ながら、菜緒に目を合わせず言った。
「菜緒ちゃんって、千堂寺さん酔っぱらってますね。でもわかりました、音丸とバディになることはなさそうだけど、一応ね。同じチームだし、知っておかないと」
「そうだな」
千堂寺はまっすぐ前を向いている菜緒の横顔に横目で見た。相変わらず、人の懐に入るのがうまい女だ、と千堂寺は菜緒の人たらしぶりを評価していた。―――
「おらぁ!てめぇ、どういうつもりなんだよ」
男が金属バットを高く振り上げる。頭の悪そうな女はヤレヤレ!と煽る。音丸は、まっすぐ男の足もとで、膝をついた。
「どうも、すみません。ちょっと急いでまして。申し訳ございません」
男は、音丸の頭部に金属バットを押し付け、音丸は土下座の形になった。菜緒は運転席から様子を眺めている。これで丸く収めてくれるのか、それとも…。菜緒は、音丸がキレるのではと期待していた。
「おい、動画撮れ!マミ!」
女は近づいてきて、土下座の形になった音丸の動画を撮影し始めた。
「コレ、ネットにアップしてやっから。クソがよぉ」
「ネットのアップは、やめてもらえませんか?仕事柄、ちょっとまずいんで」
音丸が土下座しながら通る声で、男に頼んだ。
「バカ野郎!悪いのはテメェらだろ。晒されロ!クソが」
「頼んでも、ダメですか?」
「ダメに決まってんだろ!」
音丸は押し付けられている金属バットを後頭部で押し返した。それを見ていた菜緒は運転席から拍手喝采を送った。
「覚醒しちゃう?音丸」
「そうですか、じゃぁコレで」
音丸は財布から一万円を出し、男に手渡した。
「なんだよ、買収かよ。こんなはした金でよぉ!」
「いいじゃん、このお金でピッグバーガーバーガーに行こうよ、シンちゃん!」
女が動画を撮影しながら言った。
「ダメだね!」
男が金属バットを振り上げ、音丸の尻をめがけて振りぬいた。
「ホレェ!ヒットエンドラーン。走れ走れよてめぇ」
音丸は微動だにしなかった。
「あーあ、ごめんね。彼女さん、そこの頭悪そうな彼女さん、運転できるの?」
「何言ってんだテメェ!」
「あたし?運転できるに決まってんじゃん!ナメンナヨ!チーギュー坊や!」
音丸は尻をパンパンと払い、そのまま膝を上げ、膝から先を回転させた。ピカピカに磨いた革靴の先は男の側頭部を打ち抜いた。そのまま、曲げた膝を腹部に、さらに膝から先を左右にジャックナイフのようにパタパタと広げ閉じを繰り返す。男は立ったまま気を失い、うしろに倒れ込んだ。
「一万円、治療費にしてください」
音丸は助手席に戻って来た。
運転席で菜緒は、パチパチと手を叩いていた。
「音丸、強いねぇ。ブチ切れた?」
「あんなのでキレませんよ!一万円経費で落ちますよね」
「落ちないよ、領収書ないじゃん」
「えーーーー」
金髪の女は、倒れた男をじっと眺めていた。
菜緒は倒れた男を避けて、反対車線に車を出した。三角ラトイのいるかもしれない嵯京湾・海浜倉庫五十二区画の管理室に向かって、アクセルを思いっきり踏み込んだ。
■第七話:特別潜入捜査員、実谷重綱の耳
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
