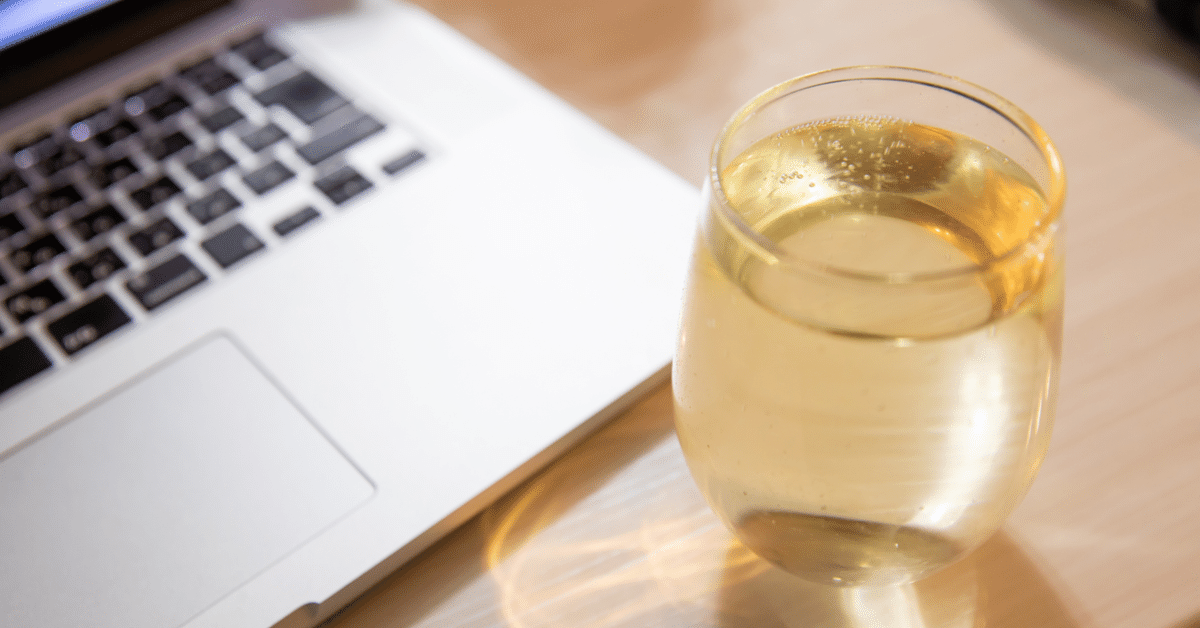
税理士試験 酒税法の選択
税理士試験の税法9科目のうち3科目を選択して受験することができます。多くの人は、ミニ税法といわれる3つ目の税法科目として、身近で実務に役立つ消費税法を選択するといわれています。
私は、既に終了した令和4年度の税理士試験で、そのミニ税法科目として酒税法を受験しました。その本試験の1年前からTAC水道橋校にて、酒税法のコースに毎週土曜日午後2時~5時まで通学していました。
1年間の受験準備期間と本試験を終えて、酒税法を選択した感想や総評価を行います。
酒税法選択の総評
① 良かった点
以下の様に、3点に纏めてよかった点を並列しました。
・最も暗記理論の範囲が少ない。
・毎年同じ出題傾向。
・各種酒類の違いに詳しくなれる。
私が酒税法を選択をした一番の理由として、簿記論と同時並行する科目として考えた際、最も出題範囲のボリュームが少ない科目であることからでした。両立することはほぼ可能でした。
酒税法の計算問題の本試験は、酒類と判定と各種酒類の税額を求めるだけの単純な計算問題から構成されています。理論も比較的基礎的な知識が問われる内容であり、出題の傾向は毎年同じようなものと言えます。
最後に、ワインとブランデーの違い、ビールと発泡酒の違い、日本酒とみりんの違いなど、酒類に対するミニ知識を身に着けられます。
私は、普段アルコールを殆ど飲まないので、酒類の判定に関しては関心の持てませんでしたが、ソムリエになることに興味がある人や、様々な酒を嗜むことが好きな方にとっては、面白い内容かもしれません。
② 悪かった点
良かった点と対比する形で酒税法を選択して良くなかったと思う点3つを選びました。
・再受験者のレベルが非常に高い。
・理屈無しの丸暗記で、内容に飽きる。
・税理士業務に役立たない。
酒税法の合格率もその他税法と同様に12%前後と狭き門です。酒税法は出題範囲が狭いので、再受験者の理解度が非常に高く、初学者であった私は予備校のテストでは全く平均点には届かず、いつも10~20点も下回るレベルでした。本試験では9割近くの正答率でないと、合格しない感じだと思います。
酒類の判定を正しく回答するのが、最も重要な事項です。ここを誤ると、絶対に税額が合致せず、5~10点近くはロストしてしまいます。
しかし、その判定するには理屈無き丸暗記しかありません。
例えば、果実酒 (ワイン) では、果実を蒸留した場合はアルコール度数が20度未満が条件ですが、清酒では22度未満、また焼酎では36度以上・・・という風に決めで定義が作られた様な規定になってます。
何とかゴロ合わせで暗記しようとしましたが、それでも対応できない箇所も多々あり、酒類の判定が合否を左右する分かれ道になります。
問題の出題構成はワンパターンで、理論2問→酒類の判定→税額計算のワンパターンで予備校の問題集もワンパターンです。似たような酒類の判定ばかりで、本試験の直前3か月前のGW頃にはもう飽きてしまいました。
消費税は税抜売上高が1,000万円を超える事業者には、必ずつきまとうものですが、酒税は酒類製造者にしか発生しない特殊な税金です。あなたが税理士になっても、酒類製造者をクライアントにすることは非常に稀なはずで、税理士として一生関わらない税金の1つかもしれません。
総合的な感想
実務に直結しない学問は、モチベーションを保って勉強に励むことが非常に困難であり、直前2か月では酒税法の勉強は殆どやらずに、簿記論だけにフォーカスする戦術に変更しました。
もし酒税法だけ受験するのであれば、酒税法の勉強を開始するのは、本試験の1年前からではなくて、年明け1月から約7か月の準備期間で対策してもよいかもしれません。高いモチベーションで勉強できるのなら、その期間でも本試験9割近くの実力を取れることはできると思います。
結局は、飽きずに試験勉強を続けられる科目を選ぶことが合格への近道ではないか思います。酒税法は理論の暗記範囲は少なく対策はできるものの、計算問題の酒類の判定に関する暗記が定着しませんでした。
それより出題範囲が広くて対策に時間を要する科目であっても、なるほどと理解できる科目の方が、継続して勉強を進められると思います。
私は、今は消費税法を学習していますが、こちらの方が理解できる・納得できるポイントがたくさんあり、昨年から王道の消費税法を選ぶべきだったと思いました。
最後に酒税法の特徴なのかもしれませんが、予備校の授業や本試験会場でも60歳を越えるようなご高齢の方を何人も見かけており、他の科目で苦労されて、酒税法を選択されてきた方がいるのではと感じました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
