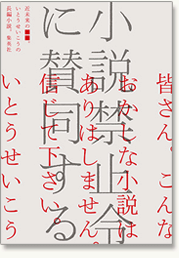いとうせいこう|小説と随筆の境界はどこにあるのか?『小説禁止令に賛同する』
随筆(エッセイ)というのは、フランスの哲学者・モンテーニュが生み出した方法です。小説でなく、詩や歌でもない、型にはまらない形式を「エッセイ」と呼びます。エッセイとは何かは、なかなか定義できないのではないか、と作家の丸谷才一は言っていますし、「定義に挑戦するものだ」という批評家もいます。
それまでは、韻文のルールに則ったり、文学の起承転結などの形式を意識しなければ、文章を書けませんでした。そういう窮屈さに困り果てたフランス人のモンテーニュが、なんとか自分の本音を吐き出すために考えだしたのが「エッセイ」という手法だったそうです。(丸谷才一『文学のレッスン』より)
もちろん、古代でもプルタルコスの『モラリア』も『枕草子』もエッセイですが、その形式を「エセー」と名付けたのがモンテーニュでした。
いまでは当たり前のエッセイですが、実は小説や詩歌のような創作物の束縛から逃れるために生まれたのでした。
◆小説と随筆のあいだで
さて、そんな発明品「エッセイ」を武器として、小説に反旗を翻した主人公がいました。それが、『小説禁止令に賛同する』(いとうせいこう著)の主人公です。
本書はいとうせいこう氏の実験小説です。
舞台は2036年の、日本ではなく「東端列島」と呼ばれる国。どうやら「小説禁止令」が施行されていて、七十五歳の語り手「わたし」はそれに賛成する人物です。反小説について弁舌を振るい、随筆を書きます。つまり、小説の中で、随筆を書いて、小説を否定する、という入れ子構造の小説になっています。
いとうせいこう氏によると、もともと「随筆」を書くつもりが、いつのまにか「小説」になったそうです。
とりわけ日本の小説において随筆と小説の境はどこにあるのかにも長く興味があった。それで小説が発生する手前のぎりぎりのところの随筆を書きたいと思ったのが、最初でしたね。(刊行記念インタビューより)
随筆を書いていたら、小説になってしまった、というわけです。さらに、この主人公「わたし」はいとうせいこう氏のような人物です。
とある集合住宅の軒下で鉢に入れた植物をちまちま育てていた手記で、出版社から賞をもらった、というエピソードも登場します。これはきっと『ボタニカル・ライフ』のことですね。講談社エッセイ賞受賞を受賞しています。
その賞で得た賞金でとある本を購入する、という風に話が展開します。事実とフィクションが入り混じりながら進みます。私小説的でもあります。
でも、単なる「私小説」にはしたくなかった。
18世紀までさかのぼれば、自由な、随筆でも小説でも私小説でもないやり方が見つかるんじゃないかという、僕の結論だったんです。(同上)
こんな風に新たな創作の方法を模索していたようです。
◆小説を否定する「わたし」
本書は、かつて小説家だった主人公が、2020年代初頭に起きた領土紛争と前後して投獄され、獄中で配られている小冊子『やすらか』に文章を寄せている、という形式で書かれています。
その内容が、「小説禁止令に賛同する」という権力側に媚を売るような体になっています。小説の卑劣さを述べながら、そんなものを読むべきじゃないと歴史的・文学論的に書き記していきます。
「練られた筋書きだの、生活の機微を活写した虚構だの、人間のありようを深く追求するだの、そんなことの一切が嘘八百だということを、わたしは平易な随筆でもってあきらかに示したい。
それが敗戦国の人間の、当然の責務だと考えるからです」
(『小説禁止令に賛同する』p.9より)
こんな風に「わたし」は小説を否定します。モンテーニュのように、随筆に可能性を求めたのです。
◆でも、小説への愛が止まらない
しかしながら、主人公の随筆からは、小説への愛を感じずにはいられません。たとえば、こういう風に小説について論じています。
多くの小説の導入が、夢から覚めたところから始まるということを「わたし」は書きます。カフカの『変身』も漱石の『三四郎』も、夢から覚めたところから始まります。(本書では実際の小説や哲学書が多数登場します。)
それを「わたし」は『夢から小説』と名付けているのですが、この方法に通底しているのは、「これから始まるのは紛れもない現実である」ということを強調するためではないか、と論じます。
しかも、小説を書きながら、作中の現実は一つ一つ決定されていきます。文章が生まれるに連れて、物語世界は現出します。三四郎は大学に行くし、恋もするし、友人と議論したりもする。「現実のようなもの」が書くことによって立ち現れていきます。
「それが『書く』という行為の基礎だとしたらどうでしょうか。無数にあり得る文からひとつだけを選び取り、そうでしかいられない不自由さを積極的に受け取ることなのだとしたら。
それは『夢から醒める』ことそのものではないでしょうか。
つまり、生きるということだとしたら。」
(『小説禁止令に賛同する』p.77より)
これはまさに「小説」を肯定しています。愛してさえいるようです。小説の可能性に最も魅了されている人の書きっぷりです。
しかし、「わたし」は監獄にいる身なので、すぐに否定します。
「・・・いやいや、小説程度のものが人生のあり方を鮮明にするとはお笑い草ですね、皆さん。」(『小説禁止令に賛同する』p.77より)
とすぐに取り繕いますが、「わたし」は明らかに小説の虜です。「わたし」にとって小説を書くということ自体が「生きる」ことそのものだったのではないでしょうか。
◆「第四の壁」と読者
「わたし」はより深く小説を理解しています。
たとえば『仮名手本忠臣蔵』、たとえば中上健次の『地の果て 至上の時』、たとえば夏目漱石『行人』。これらには共通して「立ち聞き」の手法が導入されているそうです。登場人物が「たまたま」ある事実を知ってしまう、という方法です。分かりやすく言えば、「家政婦は見た!」状態ですね。
この「立ち聞き」という方法は「読者」を前提にしているからこそ成立します。「立ち聞きしている」という状況を読者が見ているからこそ、物語の展開にハラハラするからです。市原悦子に視聴者は感情移入していきます。
そんな中で、近代の小説は「読者など存在しない」かのように展開します。小説の方から読者に語りかけるようなことはほとんどありません。「わたし」によると、二葉亭四迷の『浮雲』くらいまでは、読者に語りかける方法がしばしばあったそうです。
これは、映画や演劇でいうところの「第四の壁」と呼ばれるものです。第四の壁とは、想像上の透明な壁のことです。フィクションである演劇内の世界と観客のいる現実世界との境界を表す概念です。観客は、観客席からこの第四の壁を通して演じられる世界を見ることになります。
現代でも時おり、この第四の壁を破ることがあります。たとえば、古畑任三郎では、暗転して、古畑にピンスポットがあたり、視聴者に語りかけてきます。「えぇ〜あの方は1つの大きななミスをしています。・・・古畑任三郎でした」のアレです。マンガ『銀魂』でも坂田銀時はよく読者に語りかけます。
いずれにせよ、小説は読者を前提に成立します。読者を隠すにせよ、第四の壁を破るにせよ、読者が見ていることを意識することで物語は構築されます。
「わたし」にとって、小説は生きることでした。その生きることは、読者、つまり他者がいなければ意味がない。「わたし」の書きっぷりからは、その熱意さえも感じられます。
物語の途中では、実は他の囚人はこの冊子を読んでいないかもしれない、という事実を突きつけられます。しかし「わたし」は看守が検閲のためであっても「読者」であることを信じます。誰かが読んでいる、ということを信じ続けます。
◆虚構と現実のあいだを行ったり来たり
では、随筆はどうか?
それについては「わたし」の随筆の読者であり、冊子の編集を担当している上級官吏・梁氏から指摘を受けます。「結局は小説も随筆も同じ」というものです。むしろ、随筆のほうが、小説以上に読者が際立ちます。随筆では著者の主語が際立つがゆえに、読者を想定していることがより一層、際立つからです。(その違いについては、本書では図が書かれているので要チェックです。)
本書は、小説と随筆のあいだを行ったり来たりします。「わたし」といとうせいこう氏のあいだも行ったり来たりします。現実の日本と2036年の架空の戦後日本のあいだも行ったり来たりします。どちらかが大事なのではなく、その間を描こうとしています。「わたし」は「書けば書くほど現実は遠のいていく」とも書きます。
「書けば書くほど現実は遠のいていく。
どうしようもない感覚です。
わたしはこれを書きようがない。
過去を受け入れて見つめて言葉にしているのに、ひとことひとことが別な世界を生み出してしまう。
それは小説でも随筆でも同じ。
現実など書きようがないし、それでいいのかもしれません。」
(『小説禁止令に賛同する』p.100より)
しかし、「わたし」は書き続けます。監獄で拷問を受けながらも、「声」を失いながらも書き続けます。そして、最終的にはこの「あいだ」は融解していきます。虚実皮膜のあいだがあいまいになって、急速に物語は展開し、突然終結します。ここはぜひ本書を読んでみて下さい。
◆「現実らしきもの」を求めて"起興"する
少々ネタバレですが、最後には、作中作である『月宮殿暴走』が鍵になっていきます。「わたし」の世界で2020年ごろにヒットしたとされている小説だそうですが、「わたし」が生み出した架空の小説なのではないか、という疑惑が投げかけられます。
いとうせいこう氏/「わたし」/『月宮殿暴走』の三重構造が、現実と虚構の関係を次第に崩していきます。いとうせいこう氏が「わたし」を生み出し、「わたし」は『月宮殿暴走』を生み出す。この創作の連鎖によって、「遠のいていく現実」は少しだけ、読者に近づいてきます。「現実らしきもの」になんだか触れられそうになります。
いとうせいこう氏は現代の時代状況を受けて、本書を書いたと言います。
いまは「戦後」ではなく「戦前」であるという時代状況についてです。これから戦争が、どんなかたちかはともかく起きるのではないか。物書きの倫理として、すこし先の未来から現在を歴史的に検証したときに、作家が何を考えていたかのひとつの答えを用意しておきたい。それがこの作品になりました。(刊行記念インタビューより)
いとうせいこう氏が本書を書かずにはいられなかったこと、「わたし」が『月宮殿暴走』を書かずにはいられなかったことこそが現実です。その創作運動こそ、人間にとってやめられない行為です。小説が禁止されている時代であっても、小説を否定するという形式を取りながら、小説を書かずにはいられない。
本書を書いた理由の奥にあるものを、いとうせいこう氏は白川静の「興」に求めています。
自分がフィクションを書くことに疲れちゃった時期があったんです。そんなとき、白川静の「興(きょう)」という概念を思い出しました。古代の歌はいわば自然に対する宗教的な感情が湧いてくる際に詠まれるという考えで、興は枕詞に似た機能を持つ。だったら、かすかな興が生じることだけを随筆に書きたいと考えたんです。(同上)
「興」とは「人が神に捧げる呪的行為」と言われています。歌を詠むために「思いを興す」という意味です。超越的なる神に対して、人が向かう古代の方法です。そもそも、中国の詩経も日本の万葉集もこの「興」のために詠まれたものではないかと、白川静は言います。(『白川静—漢字の世界観』松岡 正剛著より)
この「興」を起こすことを「起興」と言うそうです。この起興はすでに失われた方法のようですが、いとうせいこう氏は、「わたし」を通して、この起興を成し遂げてみたかったのかもしれません。
現代の万葉集として『小説禁止令に賛同する』は、小説と随筆、虚構と現実のあいだで、現代の人々の思いを興しているのかもしれません。帯にもあるように、「こんなおかしな小説はありはしません」。ぜひ読んでみてください。戦前である「いま」という時代への思いを興せるかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?