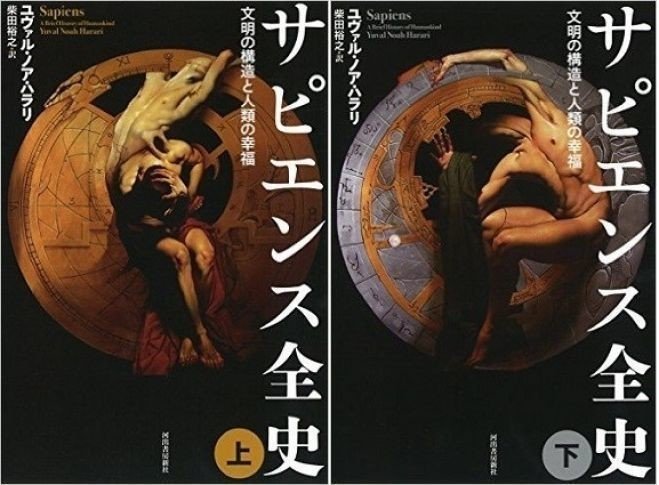ユヴァル・ノア・ハラリ|人類が「想像」するようになった日――『サピエンス全史』より
最近は、VRとかARとかで、「リアリティ」が広がりつつある。仮想なのか拡張なのかはともかく、現実が広がっているのだ。では「バーチャル」と「リアル」の境界線はどこにあるのだろうか? ネットはバーチャル?会社はリアル?ゲームはバーチャル?スポーツはリアル?じゃあ、ネットでの出会いはバーチャル?法人はリアルな存在?
もはや境界線はあいまいになってきている。そもそも、ネットによってバーチャルが肥大し、初音ミクのライブには人が集まり、テニスの王子様の舞台は「2.5次元」として享受されている。バーチャルなんてもはや現実の一部でしかない。では、これは最近のことなのだろうか?
◆サピエンス全史の秘密
そんなことを思っていたある日、店頭で気になっていた『サピエンス全史』をのぞいで見ると、こう書いてあった。
「アフリカでほそぼそと暮らしていたホモ・サピエンスが、食物連鎖の頂点に立ち、文明を築いていたのはなぜか。その答えを解く鍵は『虚構』にある」
ビジネス書コーナーで超売れているこの本は、実は「虚構」についての本だった。これは、もしかすると、「バーチャル」についての文明誌かもしれない。これはちゃんと読まなければ。ということで、読み漁ってみた。
◆直立二足歩行の弊害
本書は「革命」についての本である。人類250万年の歴史の中で、3度の大きな革命を経ていると著者のユヴァル・ノア・ハラリはいう。約7万年前の「認知革命」、約1万2000年前の「農業革命」、そして、500年ほど前の「科学革命」である。この三大革命をめぐって上下巻が進んでいくのだが、まずは、最初の「認知革命」だ。
そもそも人類は直立二足歩行をするようになって、道具を手に持ち、火を扱い、生態系の頂点を極めたと言われている。歴史の教科書の最初の方で習うことだ。しかし、実はよいことばかりではなかったというのが著者の論である。二足歩行は四足よりもはるかに遅くなってしまう。走るのが遅いライオンでさえ、ウサインボルトよりも速く走ることができる。
さらに、二足歩行のために腰回りは細くなり、出産は難しくなる。そのため、子供は幼い状態で産む必要があり、他の動物に比べ、はるかに未熟な状態で産み落とされる。そのために、産み落とされた後にさまざまな学習と適応を経ることができる。あえて幼い状態で産まれているという説だ。これを「ネオテニー戦略」という。
そのせいで、子供を長期間育てる必要があり、母親以外の助けを借りる必要が出る。そのために「社会」が生まれたと言われている。女性が閉経してもなお、生き続けるのは、社会の子供たちを育てるためだという説もある。これを「おばあさん仮説」という。
直立二足歩行によっては人類は「強み」を得たと思われてきた。しかし、著者は「弱さ」だという。いまや、生態系の王かもしれないが、数百万年の間、人類は捕食者を恐れ、植物を食し、昆虫を捕まえ、細々と暮らしてきた。初期の人類は、他の動物の食べ残しである、骨髄を啜って生きていたという記録もある。弱々しい存在だったのである。
◆われわれには昔々、兄弟がいた
しかし、40万年前になってようやく人類は大きな獲物をとるようになり、10万年前にホモ・サピエンスの台頭によってようやう生態系の頂点に登りつめることになる。
15万年前、ヒト種はわれわれ1種類ではなかった。私たちは「ホモ・サピエンス」というヒト種である。チンパンジーやオラウータンやボノボが大型類人猿という同種であるように、ヒト種にも仲間がいてもおかしくない。しかし、いないのだ。これは実は驚くべきことだ。
その理由はまだわかっていないが、ホモ・サピエンスが東アフリカからアラビア半島に行き着いた時、すでに他のヒト種がユーラシア全土を席巻していた。それが、ネアンデルタール人である。
では、なぜ、いまネアンデルタール人は存在しないのか? われわれ人類の兄弟であるネアンデルタール人はどこへいってしまったのか。
『指輪物語』には、人間以外にも、ホビットやエルフやドワーフやオークやトロールがいた。彼らは中つ国で協力したり敵対しながら旅の仲間を集め、冥王サウロンに立ち向かう。我らにもホビットやドワーフのような仲間がいたはずなのだ。しかし、いなくなってしまった。人類史というのはそんな悲劇の物語なのか?
◆2010年、世紀の大発見!
ネアンデルタール人の不在はまだ人類最大の謎だ。現在は大きく、二つの説があるらしい。「交雑説」と「交代説」である。前者はホモ・サピエンスと他の種が交雑によって一体化したというもので、後者はホモ・サピエンスが他の種を大量虐殺したという説だ。前者ではわれわれは「混血のホモ・サピエンス」であり、後者では「純血のホモ・サピエンス」となる。どちらが正しいのか? 2010年、ついに答えが出た。
ネアンデルタール人のDNAを4年かけて解析した結果、現代人特有のDNAのうち1~4%はネアンデルタール人のものだったのである。さらに、デニソワ人の化石が発見されると、現代人の6%にデニソワ人のDNAが検出された。つまり、「交雑説」が立証されたのである。
しかしながら、交代説が覆ったわけではない。約五万年前がその境界点だと言われている。ホモ・サピエンスもネアンデルタール人もデニソワ人もあと一歩でそれぞれ完全に異なる種になりそうだった。お互い、交雑しており、混ざりつつ、それぞれの道を歩む途中で、他2種は滅んでしまったのだ。
なぜ、ホモ・サピエンスだけ生き残ったのかはいまだにわかっていない。やはり、ホモ・サピエンスが滅ぼしたのだろうか? この謎はまだ解かれていない。ネアンデルタール人はホモ・サピエンスよりも脳も大きく、体も大きかった。それなのになぜ負けたのか? そこに著者は「虚構」の力を見出すのである。やっと、バーチャルの話に突入する。
◆認知革命でホモ・サピエンス勝利
約10万年前、一度、ホモ・サピエンスはネアンデルタール人に敗れている。レヴァント地方の戦いでサピエンスは引き揚げてしまい、ネアンデルタール人は中東地方に君臨し続けたという証拠があるのだ。
しかし7万年前、ホモ・サピエンスは再びネアンデルタール人に勝負を挑み、勝利したのである。中東から追い払っただけではなく、地球上から消し去ったのだ。
さらには、4万5000年前にはオーストラリアにまで渡っている。この3万年のあいだに、舟もランプも弓矢も針も発明したのだ。そして、その頃、あの有名な「シュターデルのライオン人間(通称ライオンマン)」も創作している。つまり、芸術を生み出しているのだ。これが「認知革命」と呼ばれているエポックである。

ドイツイツで発見された、後期旧石器時代のものとされる
ライオンマンの像
◆「虚構」を共有できるようになった
では、何が起こったのか?
一般的には言語を獲得したと言われている。しかし、人類の言語は世界初のものではない。ミツバチもアリもサバンナモンキーも言語はもっている。「気をつけろ!ワシがきた!」くらいのことは伝えられる。しかし、人類は「相談」もできる。川に近づくライオンと戦うかどうかを話し合えるのだ。さらに、「噂話」もできるようになる。これは敵についての会話ではなく、仲間同士のコミュニケーションを高めるための会話である。
これを著者は「虚構」の誕生だと言っている。架空の事物について語ることのできる能力である。来ないかもしれないライオンについて、嘘かもしれない噂話について、さらには、神話や伝説について語れるようになったのだ。これによって、想像できるようになっただけではない。「共通の神話」を信じられるようになったのである。これは他の動物にはありえない進化なのだ。
◆協力のための想像の秩序
共通の神話を持てることで、人類は何ができるようになったかというと、「協力」である。社会学では、噂話でまとまることができる人類の数は150人と言われている。しかし、太古の部族も古代の都市も中世の教会も近代国家も数万数十万の人々がまとまっている。それは「虚構」を共有しているからだと著者はいう。フランスの法典も法人の規約も貨幣への信用も「虚構」でしかない。しかし、人は信じることで、存在していると思い込むことができる。著者はこう述べる。
「サピエンスはこのように、認知革命以降ずっと二重の現実の中に暮らしてきた。一方には、川や木やライオンといった客観的事実が存在し、もう一方には、神や国民や法人といった想像上の現実が存在する」
◆虚構はとても役に立つ
さらに、著者は虚構の効用を強調する。普通、動物たちは莫大な年月を経て生態系に順応するために進化をする。DNAを更新していくのだ。しかし、人類は虚構をもつことで、新たな状況に即座に対応できる方法を得たのである。
ほぼ一夜で王権神授説から国民主権の神話へ乗り換えることができる。虚構を持つ前の人類は遺伝子の突然変異によって住む環境や場所を変えていた。たとえば、ホモ・エレクトスは石器を発明して以来、200万年も変わることなく住み続けた。しかし、ホモ・サピエンスは自らの振る舞いを素早く変えられるようになり、遺伝子や環境を変えずとも、新しい行動を起こせるようになった。
さらに、虚構は交易も促した。交易は単なる技術のように見えるかもしれない。しかし、交易は信頼抜きでは存在しえないのだ。信頼とは虚構なのである。認知革命によって、人類の変遷は生物学から歴史学へと大きく変化する。そこには虚構により生み出された文化が生まれたからである。
◆人類の生活が一変した日
これは『サピエンス全史』の長大な物語のほんの始まり部分にすぎない。次の農業革命でも「虚構」が活躍する。
人類は250万年もの間、植物を採集し、動物を狩って食料としてきた。これで十分だったはずである。腹も満たされ、豊かな世界だったはずである。
しかし、1万年ほど前にすべてが一変した。それは、いくつかの動植物種の生命を操作することに、サピエンスがほぼすべての時間と労力を傾け始めたころだった。人間は日の出から日の入りまで、種を蒔き、作物に水をやり、雑草を抜き、草地にヒツジを連れていった。こうして働けば、より多くの果物や穀物、肉が手に入るだろうと考えたからだ。これが農業革命である。
農耕への移行は紀元前9500~8500年ごろにトルコの南東部とイランの西部とレヴァント地方で始まった。紀元前9000年ごろまでに小麦が栽培植物化され、ヤギが家畜化された。紀元前3500年までに家畜化・栽培化のピークは過ぎていた。私たちが現在摂取する90%以上のカロリーは私たちの祖先が紀元前9500年から3500年の間にかけて栽培した、ほんの少しの植物、すなわち、小麦、稲、とうもろこし、ジャガイモ、キビ、大麦に由来する。逆いうと、それらの植物しか大量の栽培化ができなかったのである。
◆農業は人類をハッピーにしたか?
かつて研究者たちは、農業革命は人類の大躍進だと評価した。だが、実はそれは夢想にしかすぎなかったと著者は言う。農業民は狩猟採集民よりも困難であり、満足度の低い生活だったのだ。狩猟採集生活の方が、刺激的で多様な生活であり、飢えや病気の危険が少なかった。
人類は農業革命によってたしかに獲得できる食糧の総量は増やしたが、より良い生活やより長い余暇を獲得することはできなかった。むしろ、人口爆発と飽食のエリート層を生み出してしまったのだ。
では、犯人はだれか?
それは小麦、稲、ジャガイモたちだ。彼らは栽培化されたのではなく、人類を「家畜化」したのである。小麦の目線になるとわかる。小麦は中東の一部にしか生息していなかったにもかかわらず、いまでは、地球上を覆い尽くすほどの種に成長した。小麦はひ弱だった。すぐ病気になるし、草取りも必要だ。サピエンスたちは来る日も来る日も小麦のために時間を費やした。小麦たちは経済的安心は与えてくれなかった。イナゴの大群に襲われれば、そのせいで何百万という人が死んだ。小麦は戦争も生み出した。定住によって縄張りが生まれ、土地を奪い合うことになったからだ。
では、小麦は何を人類に与えてくれたのか?
◆100人の健康よりも1000人の不健康
それは、個々の人々への恩恵ではなく、サピエンス全体への利益だった。単位面積当たりの土地からはるかに多くの食物が得られ、そのおかげで、サピエンスは指数関数的に増加した。
狩猟採集時代には、健康状態の良い人々を100人抱えるのがいっぱいだったのに、農耕によって1000人規模の村がギリギリやっていけるほどになったのだ。ただし、人々は病気や栄養不良に悩まされることになったが、それは進化の歴史には関係ない。進化の鍵は二重螺旋の数が重要であって、健康状態は問題としない。
つまり、遺伝子にとっては、100人の健康な村よりも1000人の不健康な村が「善」なのである。小麦を改良したり、肥料を改良したり、土地を改良したりすることで、人類は楽になるはずだった。しかし、子供の数は増え続けた。遊牧民であったときには、3、4年周期だった出産が、農耕によって毎年のように子供を産む。人口は増える。働く、改良する、働くを繰り返し、それは、現代まできているのだと、著者はいうのだ。現代の残業社会は1万年前から続いているというのだ。(ところどころ暴論のようなものを入れるのが著者の特徴のようだ・・・。)
果たして農業革命が人類の繁栄と進歩への善行だったのか、地獄への一歩だったのかは専門家の間でも物議をかもすものになっている。とはいえ、こうして人類は増え続けた。定住によって所有も増え、“豊かな”生活へと進歩していった。
◆数年後のことまで考え始めた人類
かつて狩猟採集民は翌週や翌月のことは思考していた。来月生きていけるかな?というのは考えていた。逆にいうと、「数年後」までは思考できていなかった。それは同時に、未来への心配も少なくて済んだことを意味する。一方で、農耕民は数年先の計画を立てながら農業に勤しむ。農耕には不確実性がつきものだ。自然災害や疫病など予測不能なことが待っている。
したがって、農業革命によって、「未来への不安」という懸念事項が登場したのである。そのために、余剰食糧がつくられた。冬を乗り越えるための食糧、飢饉が来た場合の備蓄が余剰として生産されるようになった。そうすると、より強いものがより多くの余剰を抱えるために、支配するようになる。村落から町へ、そして、都市へと拡大していくのである。
◆未来という虚構を共有する
ここで虚構に戻る。
これほどの都市を維持するために「神話」という虚構が強力な絆になった。共同幻想を抱くことで、数万人単位の社会が維持されたのである。紀元前8500年ごろの世界で最大級の定住地はエリコであり、数百人が住んでいた。紀元前7000年には、アナトリアのチャタル・ヒュユクには5000から1万の人々が暮らしていたという。その後、エジプト帝国やアッシリア帝国、バビロニア帝国、ペルシア帝国が登場する。中国でも秦が統一し、ローマにより地中海が統一される。
これらは大きな「協力」の賜物である。協力の在り方はいろいろだった。ハンムラビ法典のような支配-被支配をわけるような「虚構」を生み出したものもあったし、アメリカ独立憲法のように全国民が平等であるという「虚構」を生み出したものもあった。
いずれにせよ、これらの虚構は想像上の秩序でしかない。しかし、この虚構を心から信じられる時にこそ、集団は強くなる。キリスト教の強さはイエスの存在を信じているからである。寓話や昔話としてではなく、「史実」として信じていることに強さがあることと同じである。
◆虚構は欲望を形にする
虚構は存在しないが、想像上の秩序は身の回りの物質的世界にも刻まれる。「貴族」という神話が神殿を生み出し、「個人」という神話がプライベートルームという建築を生み出す。
さらに、想像上の秩序は欲望をも生み出す。 今日の西洋人の欲望には、ロマン主義、国民主義、資本主義、人間至上主義の神話がねりこまれている。ロマン主義は消費主義に取って代わり、ダイエットコークを信じる人々になる。「新しい経験によって目を開かれ、人生が変わった」というのがロマン主義なだが、それはそのまま消費社会を意味する。
この虚構は主観でも客観でもなく「共同主観的」なものである。みんなが信じるものを信じるというループの中にある。これによって、ヒエラルキーも言語も貨幣もジェンダー価値観さえも、共有されていく。
◆虚構の矛盾が人類を前進させる
虚構には「認知的不協和」がつきまとう。認知的不協和とは、人が自身の中で矛盾する認知を同時に抱えた状態、またそのときに覚える不快感を表す社会心理学用語である。アメリカの心理学者レオン・フェスティンガーによって提唱された。人はこれを解消するために、自身の態度や行動を変更すると考えられている。
これは、喫煙者がタバコをやめない論理のときに表れる。タバコが不健康なことは知っているのにタバコを吸う。これは矛盾だ。だから、タバコを否定すれば、認知的不協和は起きない。しかし、喫煙者はタバコを吸っている長寿の人を例にし、新たな認知を用意する。「タバコを吸っても、長生きできるではないか」と主張するのだ。
たとえば、人々は自由でありながら、平等であるというのは矛盾である。自由によって結果は不平等になるはずだが、人類は平等だと主張する。また、中世の文化で騎士道とキリスト教が同時に存在したことも矛盾である。このような矛盾はいつの時代にもつきものだ。しかし、この矛盾こそが認知的不協和を生み出し、私たちは考えようとする。批判したり、再評価したりを繰り返す。
たとえば、神の子イエスと神であるイエスは矛盾する。イエスは神なのか、子なのか? そこで、人はそれを否定するのではなく、認知的不協和を解消しようとする。そこで生まれるのが「三位一体論」である。イエスは子でもあり、神でもあるのだ。
人々は虚構を生み出したことで飛躍した。なぜ虚構を生み出せるようになったかはわからないが、結果的に虚構は人類に歴史を与えたのだ。サピエンス全史とは虚構の歴史だったのである。
そして、虚構には矛盾がつきまとう。その矛盾に新たな論理を補填しようとする。その組み立てに勝利した者こそ、世界を手にれる。キリスト教も帝国主義も資本主義も矛盾だらけだ。しかし、この矛盾が認知的不協和となって、人類の行動を変化させてきたのである。新たな論理を誂(あつら)えようとするのだ。
「バーチャル」を生み出したのは、ホモ・サピエンスだった。それによって人類は進歩してきた。つまり、バーチャル・リアリティはいまに始まったことではなかったのだ。5万年前から人類はすでにバーチャル・リアリティを生きていた。そうじゃないとここまで生きてこれなかった。虚構と矛盾と新たな論理の三角関係を生み出し続けてきたのである。
虚構を手に入れたことで人類は孤独になった。ネアンデルタール人やホモ・エレクトスという兄弟を失ってしまった。その結果、『指輪物語』で仲間を得るような虚構を生み出したのは、ちょっとした悪い冗談のような気もする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?