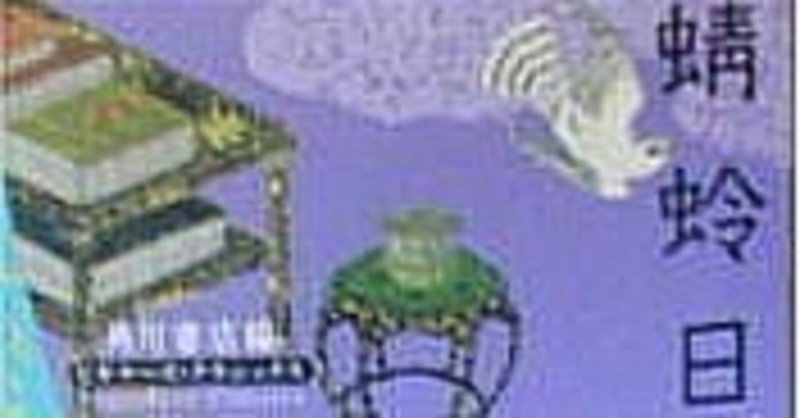
しんすけの読書日記 『蜻蛉日記』
平安時代の貴族の慣習が悲劇となった作品と云って良い。
この日記を書いた女は、裕福な家庭に生まれ、美人で、詠も優れて上手かった。そして多くの人に愛された。
これだけ書くと幸せな生涯を送った様に観えるのだが、日記からはまったく幸福感が伝わってこない。
かく年月はつもれど思ふやうにもあらぬ身をし嘆けば、声あらたまるもよろこぼしからず、なほものはかなきを思へば、あるかなきかの心地するかげろふの日記といふべし。
これは上巻の最後にあるもの。青春への告別のようにさえ観えてくる。夫を独り占めできない、貴族の女の哀しい詩だからだろう。
夫の藤原兼家には、記録に残されているだけでも他に三人の女がいた。
当時としては当たり前のことだが、人間の女としてみれば堪えられることではない。
兼家のもう一人の妻、時姫は五人の子を産んだが、作者には道綱一人だけしかいない。それも作者の寂しさを募らせたのでないだろうか。
成長した道綱が、賭弓や舞で帝の称賛を得て喜ぶ作者の筆さえ、読むものには悲しい。
その夜も、後の二、三日まで、知りと知りたる人、法師にいたるまで、「若君の御よろこび聞こえに聞こえに」と、おこせ言ふを聞くにも、あやしきまでうれし。
いなづまの光だに来ぬ屋隠れは 軒端の苗も物おもふらし
日の光や稲妻の光が届かない軒端の稲を、夫が訪れない自分に託してしまうのだった。
後日、紫式部と謂われた女もこの日記を読み涙したに違いない。式部も藤原宣孝の複数の妻の一人に過ぎなかったからだ。
その涙が『源氏物語』を産んだと想うのは間違いだろうか。
岩木のごとして明かしつれば つとめてもの言はで帰りぬ
貴族であるがゆえの気位の高さが、甘える知恵が出ないのも悲しすぎないか。
かって『豊饒の海』を読み終えたとき。こんなことを思い浮かべてた。

『蜻蛉日記』なかりせば、『源氏物語』も『浜松中納言物語』も生まれ得ず。『豊饒の海』をも。

京のはてなれば 夜いたう更けてぞ たたき来なる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
